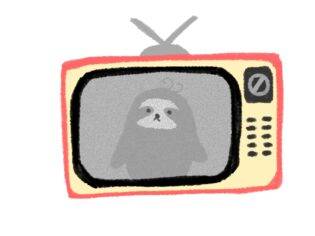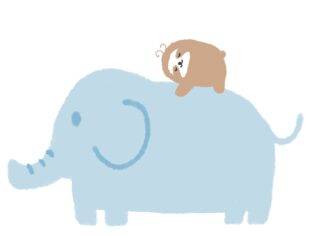8月23日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本初の量産ポテチ「のり塩」発売記念日: 湖池屋ポテトチップスの日
株式会社湖池屋が制定。1962年(昭和37年)のこの日、オリジナルのポテトチップスである「湖池屋ポテトチップス のり塩」が発売された。

Q: なぜ「湖池屋ポテトチップス のり塩」が日本初の量産ポテトチップスなのですか?
A: 湖池屋の創業者である小池和夫氏が、飲み屋で出会ったアメリカ人が食べていたポテトチップスに感銘を受け、日本人の口に合うポテトチップスを作ろうと開発に着手しました。試行錯誤の末、日本で初めてポテトチップスの量産化に成功し、1962年8月23日に「湖池屋ポテトチップス のり塩」として発売しました。これが日本のポテトチップス市場の幕開けとなりました。
Q: なぜ最初の味が「のり塩」だったのですか?
A: 当時、アメリカのポテトチップスは塩味が主流でしたが、そのままでは日本人には物足りないと考えた小池氏が、日本の食卓に馴染み深い「のり」と「塩」を組み合わせることを思いつきました。この和風の味付けが、日本人の味覚にマッチし、大ヒットにつながりました。
Q: 湖池屋という社名の由来は何ですか?
A: 創業者・小池和夫氏の姓「小池(こいけ)」に由来します。当初は個人商店でしたが、事業拡大に伴い株式会社化し、現在の「株式会社湖池屋」となりました。
日本の製油発祥にちなむ記念日: 油の日
カネダ株式会社が共同で制定。日付は、859年(貞観元年)8月23日に清和天皇の勅命により九州にあった宇佐八幡宮が大山崎に遷宮されたことから。
Q: なぜ大山崎への遷宮が「油の日」の由来なのですか?
A: 859年(貞観元年)8月23日、清和天皇の勅命により、九州の宇佐八幡宮から現在の京都府大山崎町にある離宮八幡宮へ遷宮が行われました。この離宮八幡宮が、神官が荏胡麻(えごま)を絞って灯明油を製造したことから「日本の製油発祥の地」とされているため、この遷宮の日が「油の日」として、油の専門商社であるカネダ株式会社などによって制定されました。
Q: 当時の油は何に使われていましたか?
A: 主に神仏に捧げる灯り(灯明)を灯すために使われていました。荏胡麻油は比較的安価で手に入りやすかったため、広く普及しました。食用として油が使われるようになるのは、もう少し後の時代になります。
Q: 離宮八幡宮と油の関係は現在どうなっていますか?
A: 離宮八幡宮は現在も「油祖」として製油業者からの信仰を集めており、境内には油祖像や油祖に関する資料を展示する油祖資料館があります。毎年油の日の前後には油に関する神事も行われます。
戊辰戦争の悲劇、若き武士たちの集団自決: 白虎隊自刃の日
1868年(慶応4年)のこの日、戊辰戦争(新政府軍と旧幕府側との戦い)で会津藩最年少の部隊「白虎隊」が城下の飯盛山で自刃した。
Q: 白虎隊とはどのような部隊でしたか?
A: 戊辰戦争の際に、旧幕府側についた会津藩(現在の福島県西部)が編成した少年兵部隊の一つです。藩士の子弟のうち、主に16歳から17歳の少年たちで構成されていました(最年少グループ)。他にも年齢別に玄武隊、朱雀隊、青龍隊がありました。
Q: なぜ彼らは飯盛山で自刃したのですか?
A: 新政府軍との戦いに敗れて飯盛山へ退却した際、城下町が燃えているのを見て、本拠地である鶴ヶ城(若松城)が落城したものと誤認しました。「城が落ちては生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けられぬ」として、集団で自決(自刃)を選んだと伝えられています。実際には城はまだ落城していませんでした。
Q: この出来事はどのように語り継がれていますか?
A: 白虎隊の悲劇は、会津藩の忠義や武士道精神の象徴として、また戦争の悲惨さを伝える物語として、後世に語り継がれています。自刃の地となった飯盛山には墓や記念碑が建てられ、多くの人が訪れています。映画やドラマ、小説などの題材にもなっています。
人権侵害の歴史を記憶し教訓とする国際デー: 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー
ユネスコ(国連教育科学文化機関)が1998年に制定した国際デー。日付は、1791年8月22日から23日にかけての夜、現在のハイチとドミニカ共和国にあたるサント・ドミンゴで、大西洋奴隷貿易廃止の重要なきっかけとなった奴隷蜂起(ハイチ革命の始まり)が起こったことに由来します。
Q: この国際デーの目的は何ですか?
A: 数世紀にわたって続いた大西洋奴隷貿易という、人類史上最大級の人権侵害の悲劇を記憶し、その原因と結果について考察し、現代社会における人種差別や偏見、不寛容と闘うための教訓とすることを目的としています。
Q: 大西洋奴隷貿易とはどのようなものでしたか?
A: 16世紀から19世紀にかけて、主にヨーロッパの国々がアフリカ大陸から多数の人々を強制的に連れ去り、南北アメリカ大陸やカリブ海の植民地へ奴隷として輸送・売買した貿易のことです。過酷な労働や非人道的な扱いにより、多くの命が失われました。
Q: ハイチ革命はなぜ重要だったのですか?
A: フランスの植民地だったサント・ドミンゴで起こった奴隷たちの蜂起は、長期にわたる闘争の末、世界初の黒人による共和国(ハイチ)の独立につながりました。これは奴隷制度廃止運動に大きな影響を与え、奴隷貿易とその制度そのものの終焉に向けた重要な転換点となりました。
夏の暑さが峠を越える頃: 処暑(二十四節気)
二十四節気の一つ。暦の上では、この頃から暑さが和らぎ始めるとされています(ただし実際にはまだ残暑が厳しいことが多いです)。「処」は「止まる」「終わる」などの意味があり、「暑さが止む」頃という意味合いです。通常、8月23日頃ですが、年によって日付が変わることがあります(2024年は8月22日)。
Q: 処暑の頃にはどのような自然の変化が見られますか?
A: 厳しい暑さは続くものの、朝晩にはわずかに涼しい風が感じられたり、コオロギなどの虫の声が聞こえ始めたりするなど、少しずつ秋の気配が兆し始めるとされています。台風が多く発生する時期でもあります。
Q: この時期の食べ物や行事にはどんなものがありますか?
A: スダチやカボスといった柑橘類、ナスやカボチャなどの夏野菜が旬を迎えます。また、お盆が過ぎ、地蔵盆などの行事が行われる地域もあります。