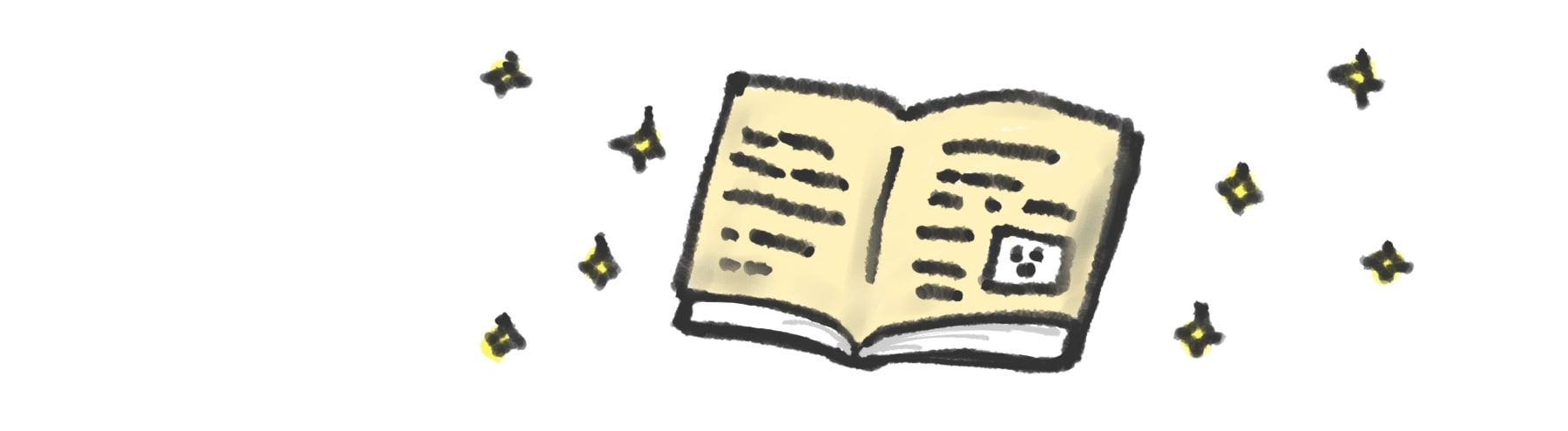
投稿日: 2020.03.27 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)食べ物188 - おでんの語源は田楽!関西と関東の違い
関西で関東焚きとも呼ばれているおでんは、田楽が語源といわれ、「おでんがく」が略されて「おでん」になったといわれている
「関東煮(かんとうだき)」とも呼ばれるおでんですが、その語源は意外にも田楽(でんがく)なんです。
室町時代から江戸時代にかけて、豆腐を串に刺して味噌を塗って焼いた田楽が庶民の間で大人気でした。この田楽を指す言葉として「おでんがく」という丁寧な言い方が使われていました。
やがて、この「おでんがく」が省略され、「おでん」として広まっていったというのが有力な説です。
おでんが、味噌田楽から進化したとは驚きですよね。
ちなみに、地域によっておでんの具材や味付けは大きく異なります。
関西では、牛すじやタコが入っていたり、出汁も昆布や薄口醤油をベースにした上品な味わいが特徴です。
一方、関東では、ちくわぶやはんぺんなど練り物が多く、濃口醤油を使った濃いめの味付けが一般的です。
おでん一つとっても、地域ごとの文化の違いが感じられて面白いですね。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 動物・植物95
- イルカを漢字で「海豚」と書くの…
- 日本の地域62
- 91都道府県にはそれぞれ代表す…
- 動物・植物21
- ミツバチが一生かけて集める蜂蜜…
- アニメ・マンガ11
- 「サザエさん」の原作では、イク…
- 人物・人名151
- 「田中実」の同姓同名は 約5,…
- 歴史109
- 『アーサー王物語』の作者は婦女…
- 日本の地域285
- 岡山県と四国の香川県を結ぶ瀬戸…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















