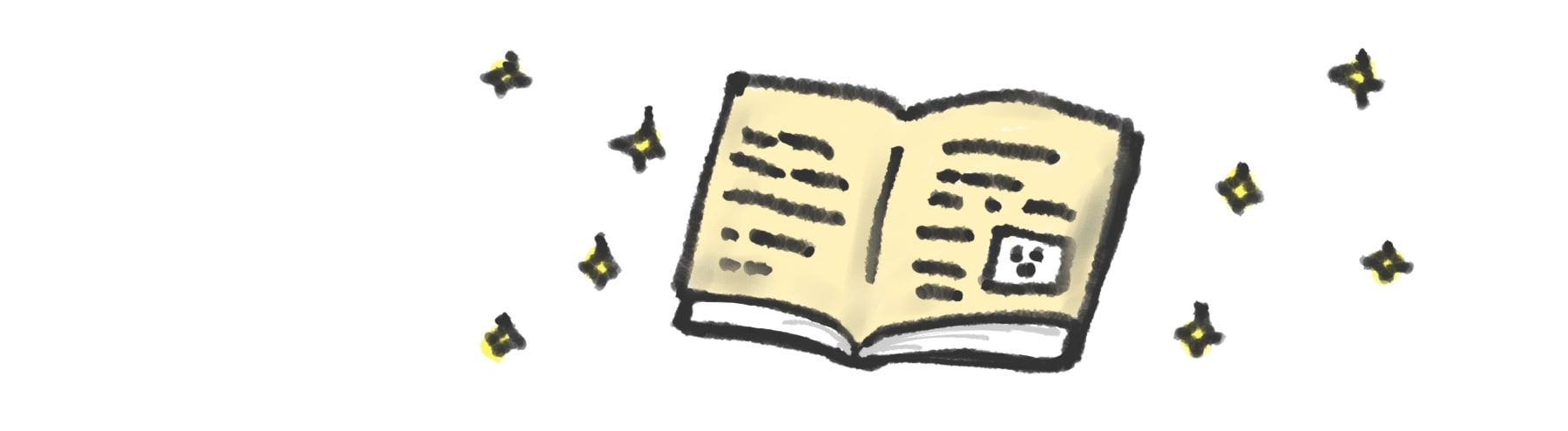
投稿日: 2020.05.08 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)歴史23 - 江戸時代は一日二食が常識?
江戸時代の中期までは「朝夕のおもの」といって食事は一日に2回だけだった。
一日二食の習慣は、武士階級から広まったと言われています。彼らは質素倹約を旨とし、無駄を省く生活を心がけていました。また、農民も日の出から日没まで働くため、朝と夕にしっかりと食事を摂ることで、十分なエネルギーを確保していました。
当時の人々の生活リズムも、一日二食に合っていました。夜明けと共に起床し、日中は仕事、そして日が暮れる頃には就寝するという生活を送っていたため、現代のように夜遅くまで活動することは稀でした。
しかし、江戸時代後期になると、都市部を中心に一日三食の習慣が広まり始めます。経済の発展とともに、夜間の活動時間が増え、間食をする習慣も生まれたことが要因と考えられています。また、料理の種類が増え、外食文化が発達したことも影響しています。
このように、江戸時代の食生活は、時代の変化と共に徐々に変化していきました。一日二食から三食への移行は、社会の変化を反映する興味深い現象と言えるでしょう。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 人物・人名232
- 日本人からすると変わった名前「…
- 食べ物146
- 濃口醤油より、薄口醤油の方が塩…
- 日本の地域270
- 鳥取県にある鳥取砂丘は、日本最…
- 日本の地域356
- 大分県の保育園や小学校では春に…
- 日本の地域75
- 全国各都道府県のシンボル。埼玉…
- 文学48
- 祇園精舎は京都どころか日本にも…
- スポーツ9
- ゴルフボールが凸凹なのは、ボー…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















