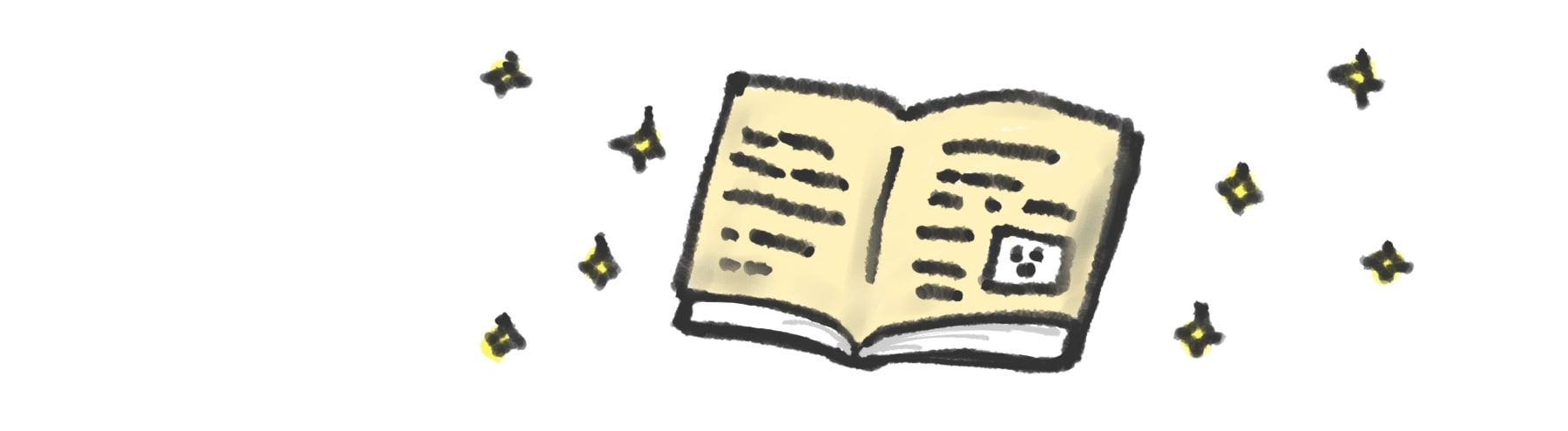
投稿日: 2020.05.08 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)文学42 - 新田次郎は山岳小説家?本人は否定?
山岳小説家の代表、新田次郎は自分の作品が山岳小説と呼ばれることを嫌っていた 「平地を書けば平地小説でしょうか」と言ってさえいる”
新田次郎の本名は藤原寛人。中央気象台(現在の気象庁)に長年勤務し、気象予報官として手腕を発揮しました。その傍ら、気象や山岳に関する知識、そして何よりも山を愛する心を活かして小説を執筆しました。
代表作には、明治時代の測量隊を描いた『孤高の人』、木曽駒ヶ岳を舞台にした『強力伝』、八甲田山雪中行軍遭難事件を題材にした『八甲田山死の彷徨』などがあります。これらの作品は、自然の厳しさ、人間の極限状態、そしてそこに垣間見える人間ドラマを鮮やかに描き出し、多くの読者を魅了しました。
しかし、彼は「平地を書けば平地小説でしょうか」と述べているように、自身の作品が山岳という特定のジャンルに限定されることを避けようとしました。彼の小説は、単に山を舞台にした物語ではなく、人間そのものを深く掘り下げた普遍的なテーマを描いているという自負があったのかもしれません。山はあくまで舞台設定の一つであり、そこで生きる人々の葛藤や成長こそが、彼の作品の本質だったと言えるでしょう。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 食べ物28
- たい焼きは昔、亀の形だった
- ゲーム16
- カセットにフーフー息を吹きかけ…
- アニメ・マンガ146
- 「あたしンち」の母は身長約16…
- 歴史55
- タイタニック号事件を14年前に…
- 日本の地域153
- 山形県のお通夜は鈴や鐘が鳴らさ…
- アニメ・マンガ124
- 「地獄先生ぬ〜べ〜」はは、女性…
- 日本の地域262
- 奈良県民はお腹が痛い時に正露丸…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















