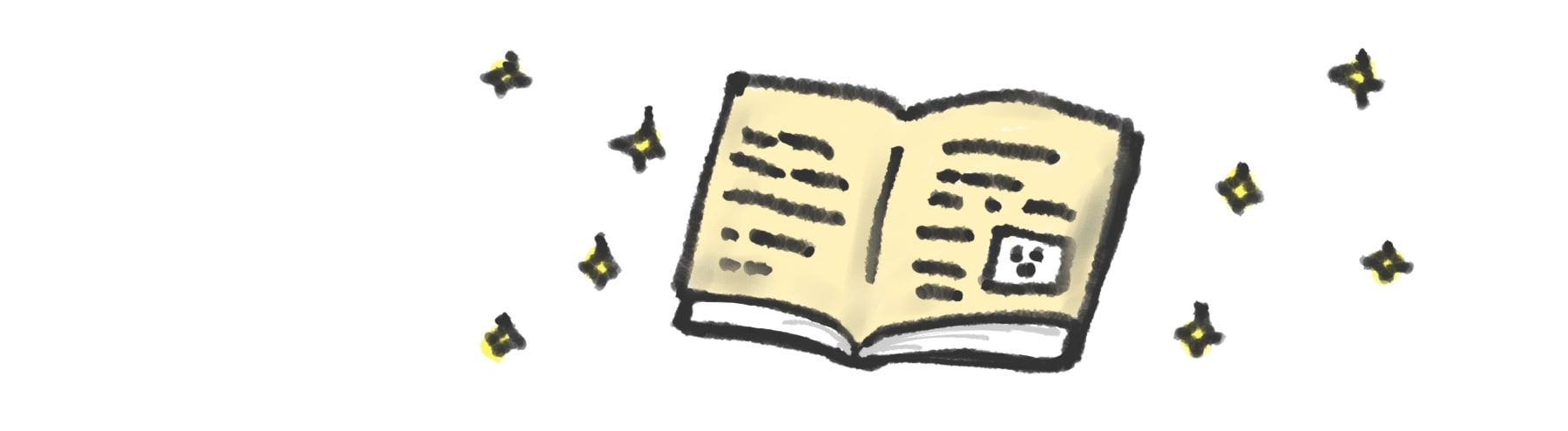
投稿日: 2020.05.14 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)日本の地域133 - 北海道トリビア!ザンギは唐揚げ?
北海道では唐揚げのことを「ザンギ」と言う。
ザンギは、一般的に鶏肉に下味をつけ、小麦粉や片栗粉などをまぶして揚げた料理を指します。唐揚げとの明確な区別は難しいですが、ザンギの方が下味が濃い、骨付き肉を使うことが多い、といった傾向が見られます。
ザンギの発祥には諸説ありますが、有力なのは、昭和30年代に釧路市の鳥料理店「鳥松」で生まれたという説です。店主が中国の揚げ物をヒントに、鶏肉を醤油や生姜などで漬け込んだものを揚げて提供したのが始まりとされています。当初は「骨付き唐揚げ」として提供されていましたが、「いろいろな材料を“残技(ザンギ)”を駆使して作った」という洒落から「ザンギ」と呼ばれるようになったと言われています。
ザンギは、北海道内の飲食店を中心に広がり、家庭料理としても定着しました。現在では、鶏肉だけでなく、タコやイカなど、様々な食材を使ったザンギも存在します。また、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでも手軽に購入できる惣菜として親しまれています。
北海道を訪れた際には、ぜひ本場のザンギを味わってみてください。きっと、その奥深い味わいに驚かれることでしょう。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 動物・植物78
- ココという名前のゴリラは、手話…
- ゲーム52
- シュタインズゲートのシステムは…
- 文学21
- 『もっと光を』と言い残して死ん…
- 日本の地域104
- 全国各都道府県のシンボル。福岡…
- 日本の地域159
- 茨城県では、語尾に「だっぺ」を…
- ゲーム78
- 『ギターヒーロー エアロスミス…
- 人物・人名2
- 世界一長い名前はフィラデルフィ…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















