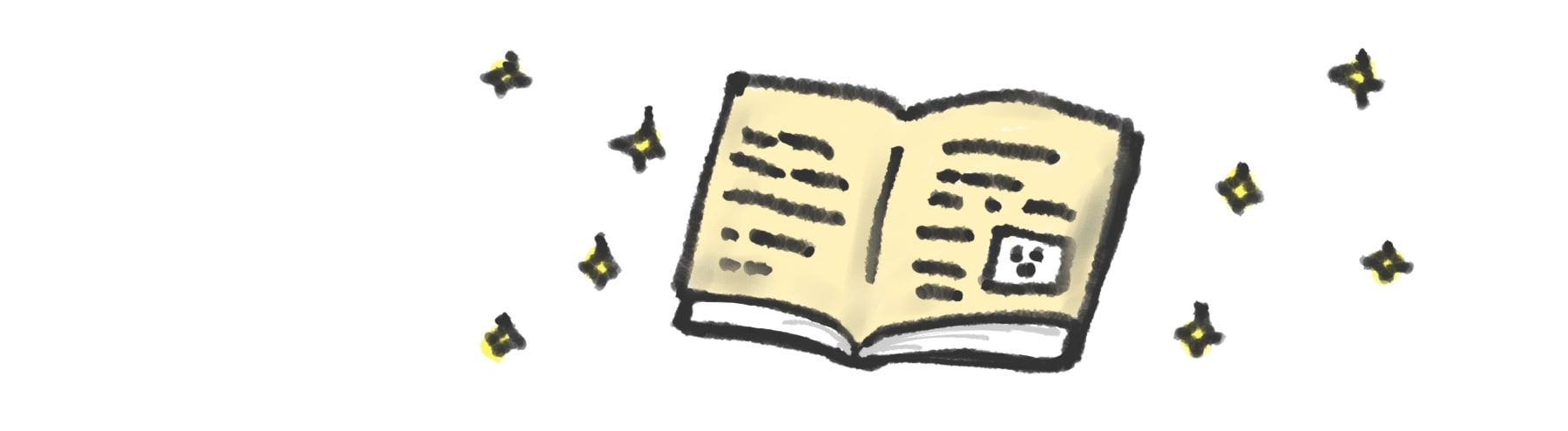
投稿日: 2020.05.14 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)日本の地域229 - 可睡斎 トイレの神様【静岡 袋井】
静岡県袋井市にある可睡斎には「トイレの神様」が実在する。
静岡県袋井市にある可睡斎は、禅宗の一派である曹洞宗の寺院として知られています。この可睡斎には、ちょっと変わった存在、「東司(とうす)の神様」、つまりトイレの神様が祀られています。
その起源は、室町時代に遡ります。可睡斎の住職であった禅師が、徳川家康をもてなす際、便所で食事を出したという逸話が残っています。家康はそれを快く受け入れ、「禅僧は便所においても修行の場とする」という禅の精神に感銘を受けました。以来、可睡斎では東司(トイレ)を清浄な場所として大切にし、そこに神様を祀るようになったのです。
可睡斎の東司は、「東司(とうす)」または「洗頭(せんず)」と呼ばれ、実際に使用されていた古い便所をそのまま保存・公開しています。中には烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)という神様が祀られており、火の神であり、不浄を清める力を持つとされています。
この烏枢沙摩明王は、トイレの守護神として信仰されており、可睡斎では、毎年1月には「御手洗祭」という特別な祭りが行われ、多くの参拝客が訪れます。トイレの神様にお参りすることで、健康長寿や厄除け、さらには家内安全のご利益があると信じられています。トイレを大切にする心、清浄を保つことの重要性を教えてくれる、ちょっとユニークな場所です。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 食べ物178
- 椎茸は1時間天日干しをするだけ…
- アニメ・マンガ100
- 「千と千尋の神隠し」の、銭婆と…
- 日本の地域365
- 鹿児島はかき氷の「白熊」が有名…
- 食べ物121
- 2015年にアメリカのシアトル…
- 食べ物15
- ビスケットの語源は、ラテン語の…
- 日本の地域317
- 高知県の観光で有名なはりまや橋…
- 日本の地域320
- よさこいの発祥は高知県である。
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















