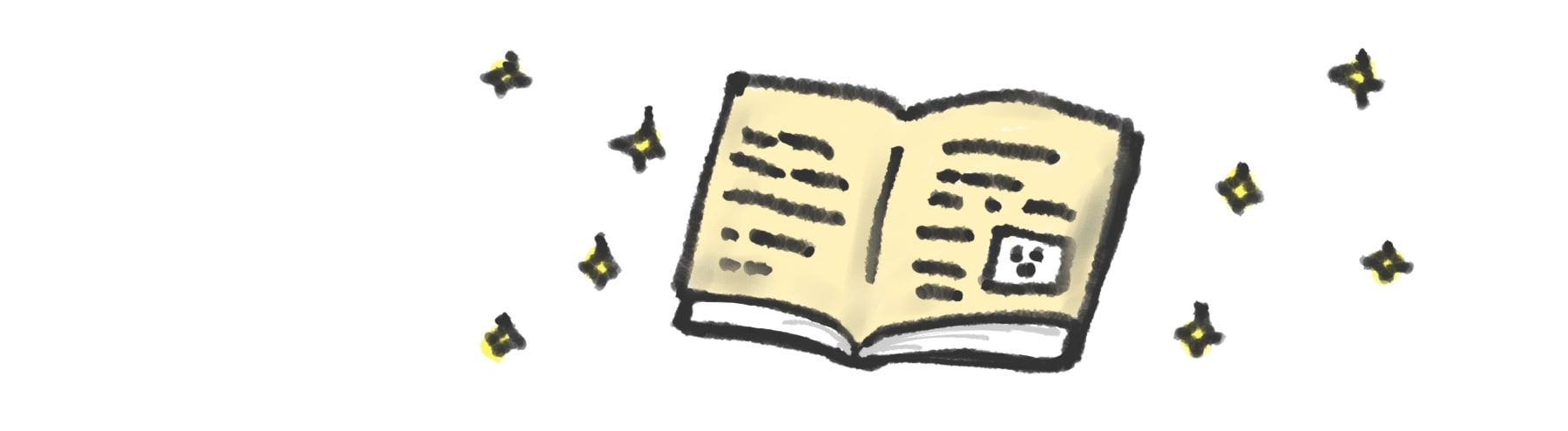
投稿日: 2020.05.14 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)日本の地域263 - 醤油は和歌山発祥のトリビア
日本の食に欠かすことができない「醤油」は、和歌山県発祥である。
そのルーツは鎌倉時代に遡ります。
覚心という僧侶が中国から持ち帰った金山寺味噌の製法にあります。
この味噌の製造過程で、桶の底に溜まった液体が偶然発見されたのが、醤油の原型である「溜(たまり)」と言われています。
この溜まりを改良し、製造方法を確立したのが湯浅の人々でした。
彼らは、大豆、麦、塩といった原料を使い、独自の製法を編み出しました。
これが全国へと広まり、日本の食文化に欠かせない調味料、醤油として定着していったのです。
湯浅町には、現在も江戸時代から続く醤油醸造元が残っており、伝統的な製法を守り続けています。
これらの醸造元では、木桶仕込みなど、手間暇かけた製法で、風味豊かな醤油を生産しています。
湯浅はまさに、日本の醤油の故郷と言えるでしょう。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 歴史112
- 「漢方」は日本のもの。本場では…
- ゲーム116
- ドンキーコングはマリオのペット…
- 動物・植物78
- ココという名前のゴリラは、手話…
- 日本の地域295
- 徳島県は全国の都道府県で唯一電…
- 歴史152
- チュッパチャプスの包み紙のロゴ…
- 動物・植物32
- ハチドリは体長6センチ程度しか…
- 日本の地域375
- 恐怖心などでゾクッとしたときに…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















