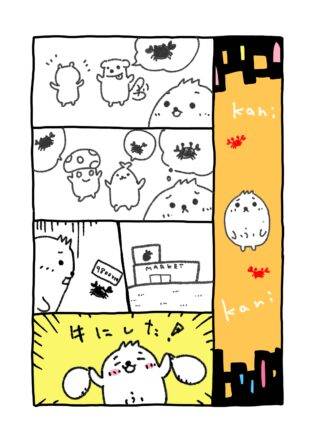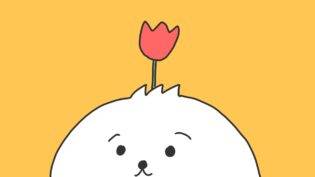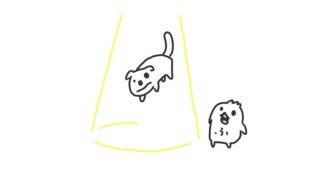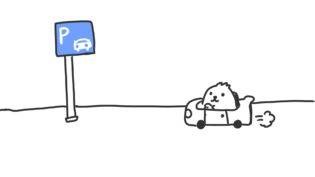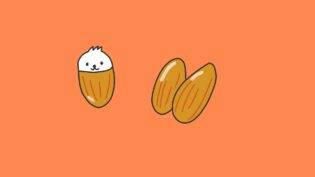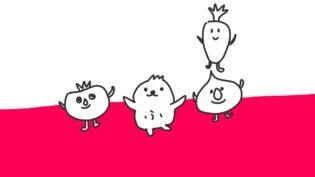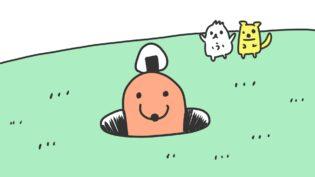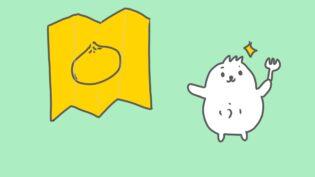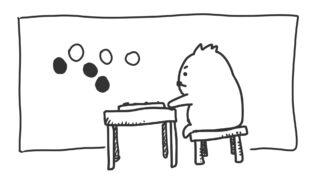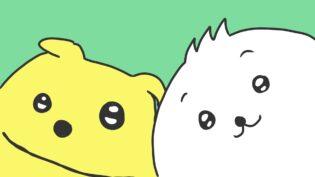1月2日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
一年の吉凶を占う?: 初夢の日
現代では元日から2日までの3日間で見る夢を「初夢」としていますが、江戸時代前期は12月31日~1月1日は眠らない風習があったため、新年初めて寝る1月2日に設定されたと伝えられています。初夢で「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」を見ると縁起が良いと言われ、富士は「無事」、鷹は「高い」、茄子は「成す」という言葉にかけらているそうで、どれも徳川家康が好んだものを順に並べたという由来という説が有力。
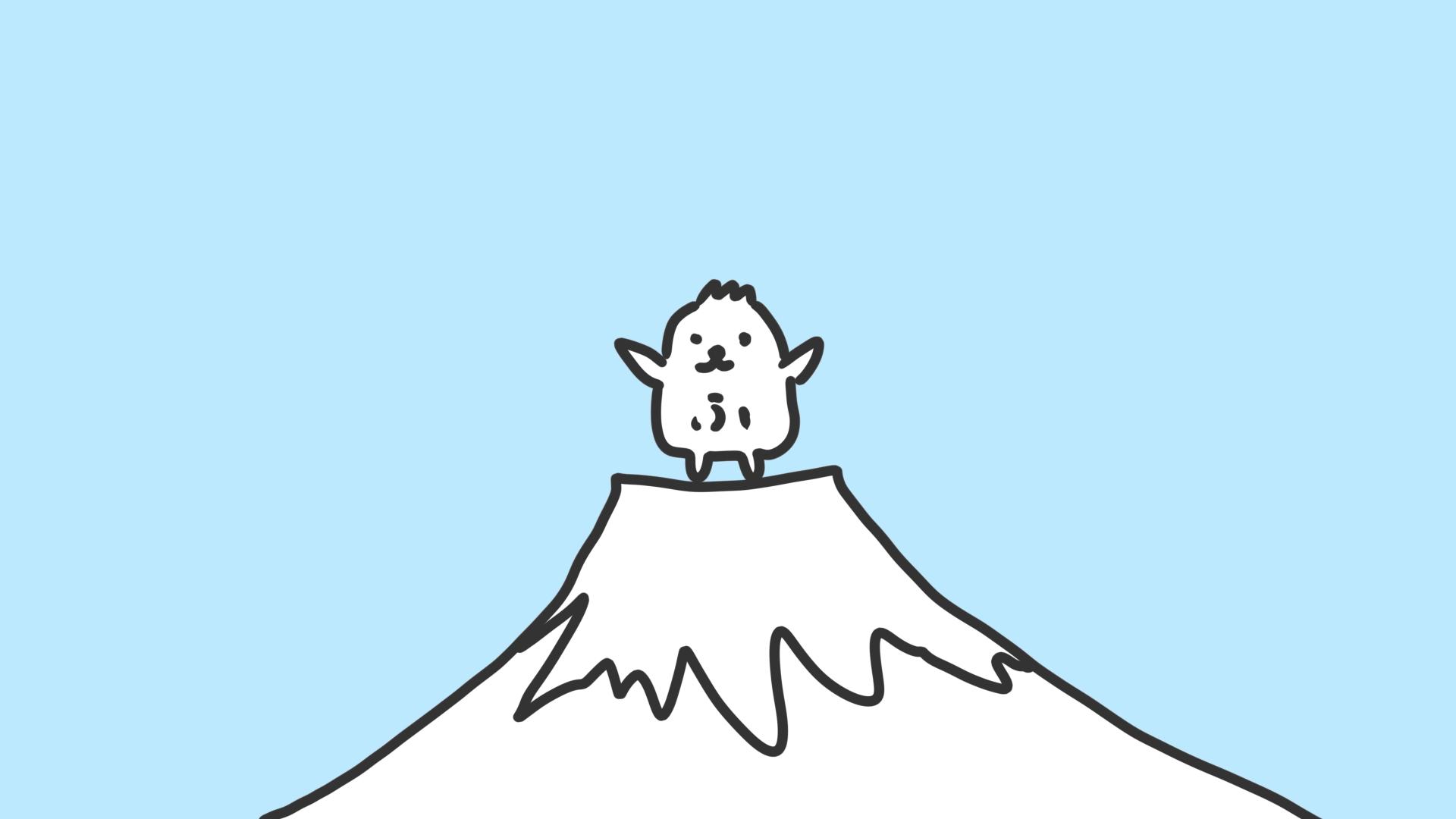
Q: なぜ初夢は縁起が良いとされるのですか?
A: 新年を迎えて最初に見る夢は、その年の運勢を暗示したり、神様からのお告げであったりすると古くから信じられていたためです。特に縁起の良い夢は、一年間の幸運の兆しと考えられました。いつ見る夢を初夢とするかは時代によって異なり、元日の夜、あるいは提供情報にあるように2日の夜に見る夢とされることがありました。
Q: 「一富士二鷹三茄子」には続きがあるのですか?
A: 一般的には「一富士二鷹三茄子」までが有名ですが、「四扇(しおうぎ)、五煙草(ごたばこ)、六座頭(ろくざとう)」と続くとも言われています。扇は末広がりで子孫繁栄や商売繁盛、煙草は煙が上に昇ることから運気上昇、座頭(剃髪した盲目の僧侶)は「毛がない」=「怪我ない」として家内安全に通じるといった解釈があります。ただし、四以降はあまり一般的ではありません。
Q: 良い初夢を見るためのおまじないはありますか?
A: 昔からの言い伝えとして、枕の下に七福神や宝船が描かれた絵を敷いて寝ると良い夢が見られるとされています。また、「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな(長き夜の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな)」という上から読んでも下から読んでも同じ回文を紙に書き、枕の下に入れて寝ると悪夢を見ずに済むとも言われています。
新年の抱負を筆に込めて: 書き初め
日本の年中行事の一つで、新年になって初めて毛筆で字や絵を書くという行為。元々は宮中で行われていた儀式が、江戸時代以降は庶民にも広まっていったそうです。
Q: なぜ新年には書き初めをするのですか?
A: 新年に初めて毛筆で文字を書くことで、字の上達を祈願したり、その年の目標や抱負を記して決意を新たにしたりする目的があります。元々は、年の初めに吉とされる方角(恵方)に向かい、新年に初めて汲んだ水(若水)で墨をすって詩歌などを書くという、やや儀式的な意味合いもありました。
Q: 書き初めはいつ、どのように行うのが一般的ですか?
A: 年が明けてから行うもので、特に1月2日に行われることが多いとされています。伝統的には、その年の恵方に向かって座り、めでたい言葉や詩歌、あるいは一年の目標などを書きます。学校の冬休みの宿題として書かれることも多いですね。
Q: 書き初めで書かれたものはどうするのですか?
A: 伝統的には、小正月(1月15日頃)に行われる「どんど焼き(左義長)」という行事で、門松やしめ縄などと一緒に燃やすのが習わしです。書き初めを燃やした炎が高く上がるほど字が上達すると言われています。地域によっては神社に納めることもあります。
国民と皇室を結ぶ新年の挨拶: 皇居一般参賀
新年を迎えた1月2日に、皇居で天皇皇后両陛下はじめ皇族方が国民からの祝賀をお受けになる行事です。多くの国民が皇居を訪れ、新年の挨拶を交わす貴重な機会となっています。
Q: 皇居一般参賀ではどのようなことが行われますか?
A: 天皇皇后両陛下と成年皇族の方々が、宮殿・長和殿のベランダに数回お出ましになり、集まった人々からの祝賀に応えられます。天皇陛下から新年のご挨拶(おことば)があるのが通例です。多くの人々が日の丸の小旗を振って新年のお祝いをします。
Q: いつからこの行事は始まったのですか?
A: 現在の形での新年一般参賀は、戦後の1948年(昭和23年)1月1日に始まりました。それ以前にも類似の行事はありましたが、より国民に開かれた皇室を象徴する行事として定着しました。
商売繁盛を願う年の初荷: 初荷
新年になって、問屋や商店などが初めて商品を車や船に積んで送り出すこと、またはその荷物のことを指します。年の初めの景気づけとして、縁起の良い飾り付けをしたトラックなどで行われることもありました。
Q: 初荷はなぜ縁起が良いとされたのですか?
A: 新年最初の出荷が無事に行われ、荷物が順調に届けられることは、その年の商売が繁盛することにつながると考えられたためです。そのため、大漁旗やのぼり、しめ飾りなどで華やかに飾り付けたトラックで配送し、景気づけをする習慣がありました。
Q: 現在でも初荷の習慣は見られますか?
A: 物流システムの変化などにより、かつてのような派手な飾り付けをしたトラックによる初荷の光景は少なくなりました。しかし、新年最初の業務開始という意味での「初荷」の概念や、取引先への年始挨拶を兼ねた配送などは行われています。
福を求めて賑わう: 初売り
デパートやスーパー、商店などが新年になって最初に営業を開始し、商品を売り出すことです。多くは1月2日や3日に行われ、福袋の販売などで多くの買い物客で賑わいます。
Q: 初売りの目玉である「福袋」はいつ頃から始まったのですか?
A: その起源は江戸時代の呉服店「越後屋」(現在の三越)が始めた「恵比寿袋」や、明治時代の「多可良袋(たからぶくろ)」など諸説ありますが、様々な商品を袋に詰めてお得な価格で販売するというアイデアは古くから存在しました。現在のような形での福袋が正月の初売りの定番となったのは、大正時代以降と考えられています。
Q: 初売りはなぜこんなに賑わうのでしょうか?
A: 新年のお祝いムードの中、お得な価格で商品が手に入るという期待感(特に福袋)や、新年の運試しといった要素が人々を引きつけます。また、年末年始の休業期間を経て、購買意欲が高まっていることも理由の一つと考えられます。
新春の襷リレーがスタート: 箱根駅伝(往路)
毎年1月2日・3日に行われる「東京箱根間往復大学駅伝競走」、通称「箱根駅伝」の往路(行き)のレースが1月2日に行われます。東京・大手町から神奈川・箱根町の芦ノ湖畔までの約107.5kmを5人のランナーが襷で繋ぎます。
Q: 箱根駅伝の往路にはどのような特徴がありますか?
A: 平坦な区間が多い序盤から、徐々にアップダウンが増え、最終5区では標高差800m以上を一気に駆け上がる過酷な「山登り」が待ち受けます。各大学のエースが集う「花の2区」や、山登りのスペシャリストが競う5区など、見どころの多いコースです。
Q: 箱根駅伝の正式名称と主催団体は?
A: 正式名称は「東京箱根間往復大学駅伝競走」です。主催は関東学生陸上競技連盟で、読売新聞社が共催しています。関東の大学が参加するローカルな大会ですが、テレビ中継などを通じて全国的な人気を誇る、お正月の風物詩となっています。