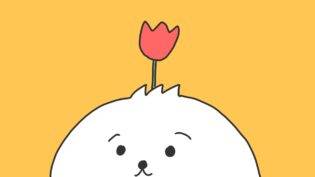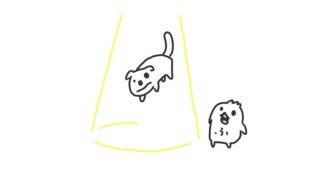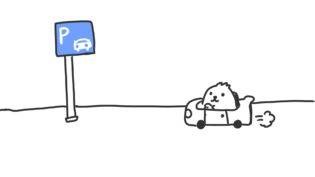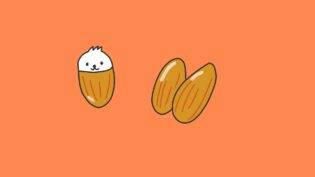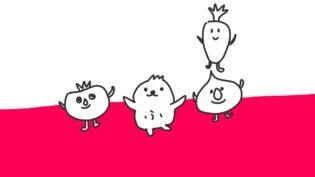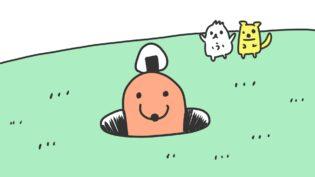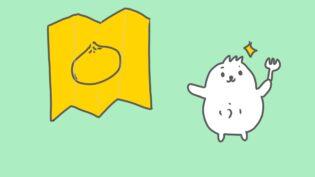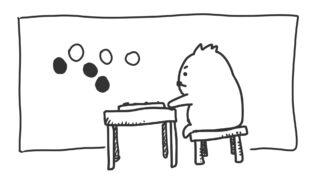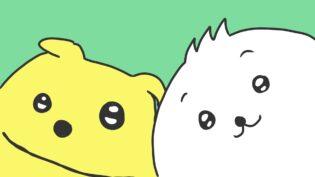1月7日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
七草粥で無病息災を願う: 人日(じんじつ)の節句
五節句の一つ。「七日正月」は「七草粥」を食べることから「七草の節句」ともいいます。
Q: 五節句とは何ですか?
A: 五節句(ごせっく)は、日本の伝統的な年中行事を行う季節の節目となる日のことで、江戸幕府によって公的な祝日として定められました。人日(じんじつ、1月7日)、上巳(じょうし/じょうみ、3月3日)、端午(たんご、5月5日)、七夕(しちせき/たなばた、7月7日)、重陽(ちょうよう、9月9日)の五つを指します。それぞれ季節の植物などを用いた行事が行われます。
Q: なぜ1月7日に七草粥を食べるのですか?
A: 正月の祝膳や祝酒で疲れた胃腸を休ませ、冬場に不足しがちな青菜の栄養を摂るため、また、七草の若芽の生命力にあやかって一年の無病息災を願うためと言われています。古代中国の風習が日本に伝わり、日本の文化と融合して定着しました。
Q: 七草粥に入れる七草とは具体的に何ですか?
A: 春の七草として一般的に知られているのは、芹(せり)、薺(なずな、ぺんぺん草)、御形(ごぎょう、母子草)、繁縷(はこべら、はこべ)、仏の座(ほとけのざ、田平子)、菘(すずな、かぶ)、蘿蔔(すずしろ、だいこん)の7種類です。これらを刻んでお粥に入れて食べます。
七草の力で健康祈願?: 爪切りの日
新年になって初めて爪を切る日。七草をゆでた汁に爪をつけ、柔らかくしてから切ると、その年は風邪を引かないと言われている。
Q: なぜ新年に初めて爪を切る日として1月7日が意識されるのですか?
A: 正月三が日などの間は、縁起を担いで刃物を使うことを避ける風習がありました。また、「夜に爪を切ると親の死に目に会えない」といった迷信もあり、年の初めに日中の明るい時間を選んで、縁起の良い七草にちなんで爪を切るという習慣が生まれたと考えられます。
Q: 七草をゆでた汁に爪をつけるのはなぜですか?
A: 七草には邪気を払い、万病を防ぐ力があると信じられていました。その七草を浸した神聖な汁に爪をつけることで、爪を清め、さらに柔らかくして切りやすくするという実用的な面と、七草の持つとされる霊験にあやかって一年の健康を願うという、おまじない的な意味合いが込められていると考えられます。
Q: この言い伝えは現在でも広く行われていますか?
A: 現代では、このような言い伝えを意識して爪を切る人は少なくなっていますが、新年の節目に行われる日本の伝統的な風習の一つとして知られています。一種の生活の知恵や、健康への願いが込められた習慣と言えるでしょう。
戦後復興期の象徴?聖徳太子千円札登場: 千円札発行の日
1950年(昭和25年)のこの日、1946年(昭和21年)の新円切替後、初の1000円札が発行された。絵柄は表が聖徳太子、裏が法隆寺の夢殿。
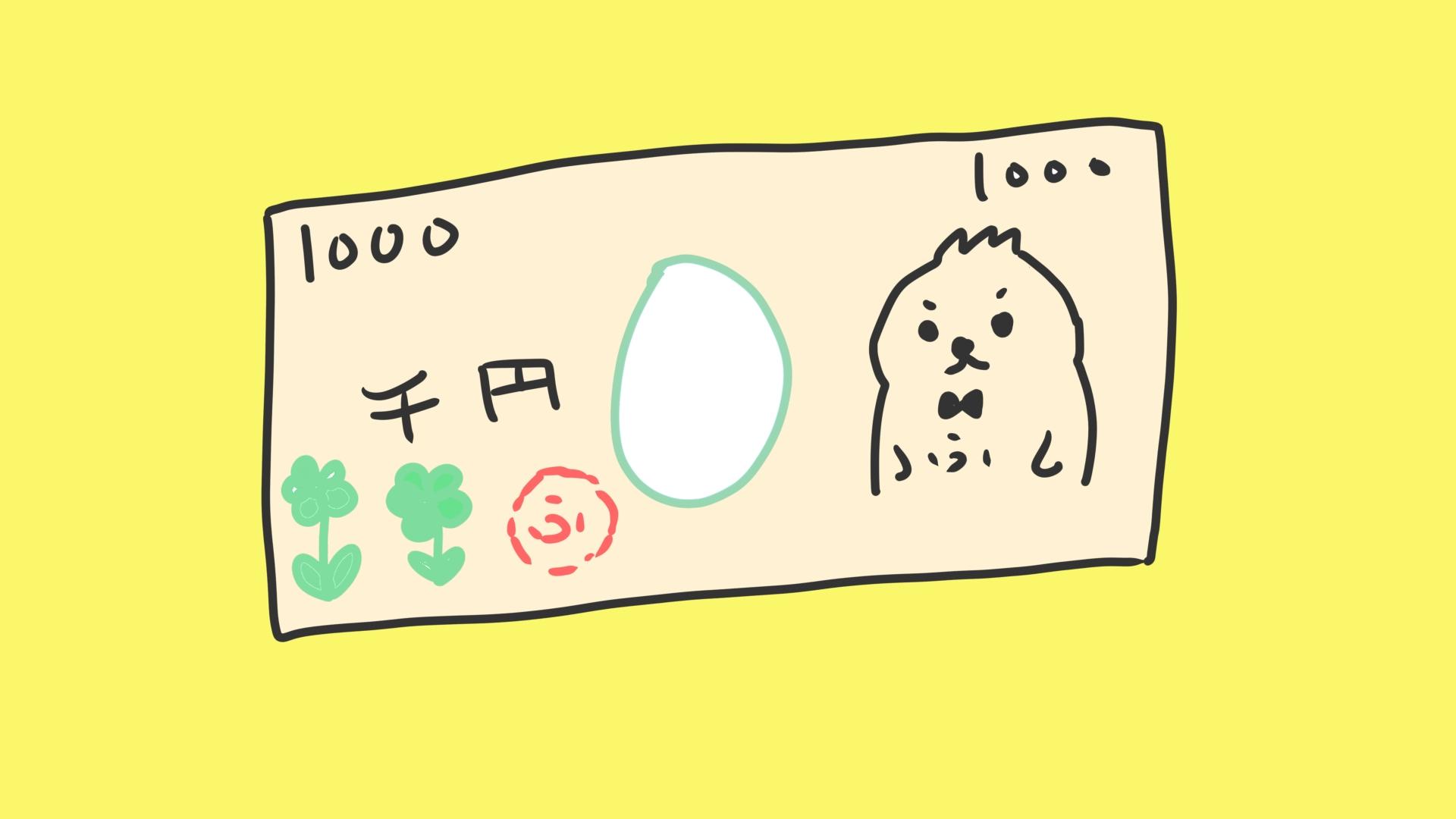
Q: なぜこの千円札に聖徳太子が描かれたのですか?
A: 聖徳太子は、十七条憲法の制定や冠位十二階の導入など、古代日本の国家体制の基礎を築いた人物として、また仏教を篤く信仰し文化の発展に貢献した人物として、戦後の新しい国づくりや文化国家を目指す日本の象徴としてふさわしいと考えられたためです。お札の肖像としては非常に人気が高く、その後も五千円札や一万円札にも登場しました。
Q: 「新円切替」とは何ですか?
A: 第二次世界大戦後の激しいインフレーションを抑制するため、1946年(昭和21年)に日本政府が実施した金融政策です。旧紙幣(旧円)の流通を停止し、預金を封鎖した上で、限られた額だけ新しい紙幣(新円)との交換を認めるというものでした。この1950年に発行された千円札は、この新円体制下で初めて発行された千円額面の紙幣でした。
Q: この聖徳太子の千円札はいつまで使われていましたか?
A: この千円札(日本銀行券B千円券)は、1963年(昭和38年)に伊藤博文の肖像を用いた新しい千円札(C千円券)が発行されるまで主に流通しました。支払い停止(法的に通用しなくなる)となったのは1965年(昭和40年)です。
宮中の新年儀式、邪気払い: 白馬節会(あおうまのせちえ)
年の初めに白馬(古くは青馬)を見ると一年の邪気が祓われるという中国の故事に由来し、日本の宮中で行われた年中行事の一つです。天皇が庭に引き出された白馬をご覧になり、宴を催す儀式で、人日の節句(1月7日)に行われました。
Q: なぜ「あおうま」と読むのに「白馬」なのですか?
A: 元々は「あお」という言葉が緑色だけでなく、灰色や黒みがかった色も含む広い意味で使われており、年の初めには青馬(黒みがかった馬)を見るのが良いとされていました。しかし、後に陰陽五行説の影響などから白馬が用いられるようになり、儀式の名称の読み方「あおうま」だけが残ったとされています。
Q: この儀式は現在も行われていますか?
A: 古代から続く宮中行事でしたが、時代の変化とともに儀式の形式は簡略化されたり、中断されたりしました。現在では、京都の上賀茂神社などで、白馬節会神事としてその名残を伝える行事が行われています。
Q: 白馬節会はどのような目的で行われたのですか?
A: 天皇が年の初めに縁起の良いとされる白馬(または青馬)をご覧になることで、その年の邪気を払い、国家の安泰や五穀豊穣を祈願する目的がありました。貴族たちが集う宴も催され、新年の重要な儀式の一つとされていました。