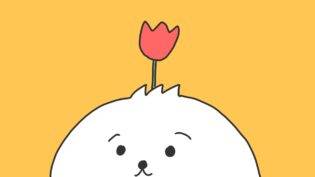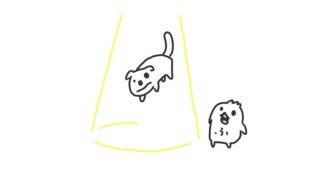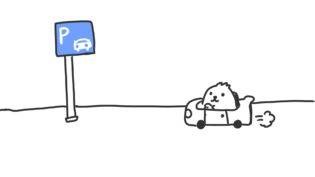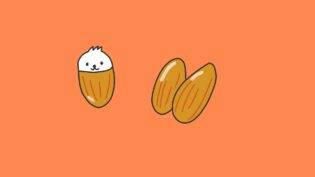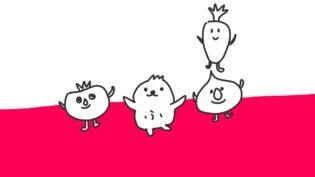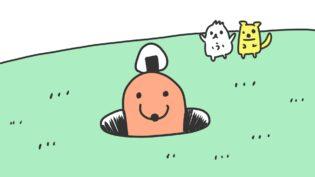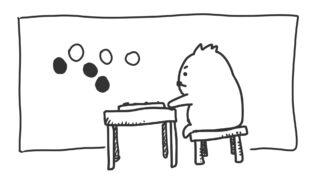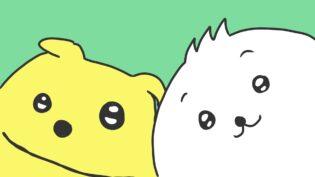1月9日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
一休さんの機転にちなんで: とんちの日・クイズの日
「いっ(1)きゅう(9)」(一休)の語呂に合わせて。室町時代の臨済宗の僧で、頓知(とんち)話など説話で有名な一休宗純(いっきゅうそうじゅん)の愛称「一休さん」から。
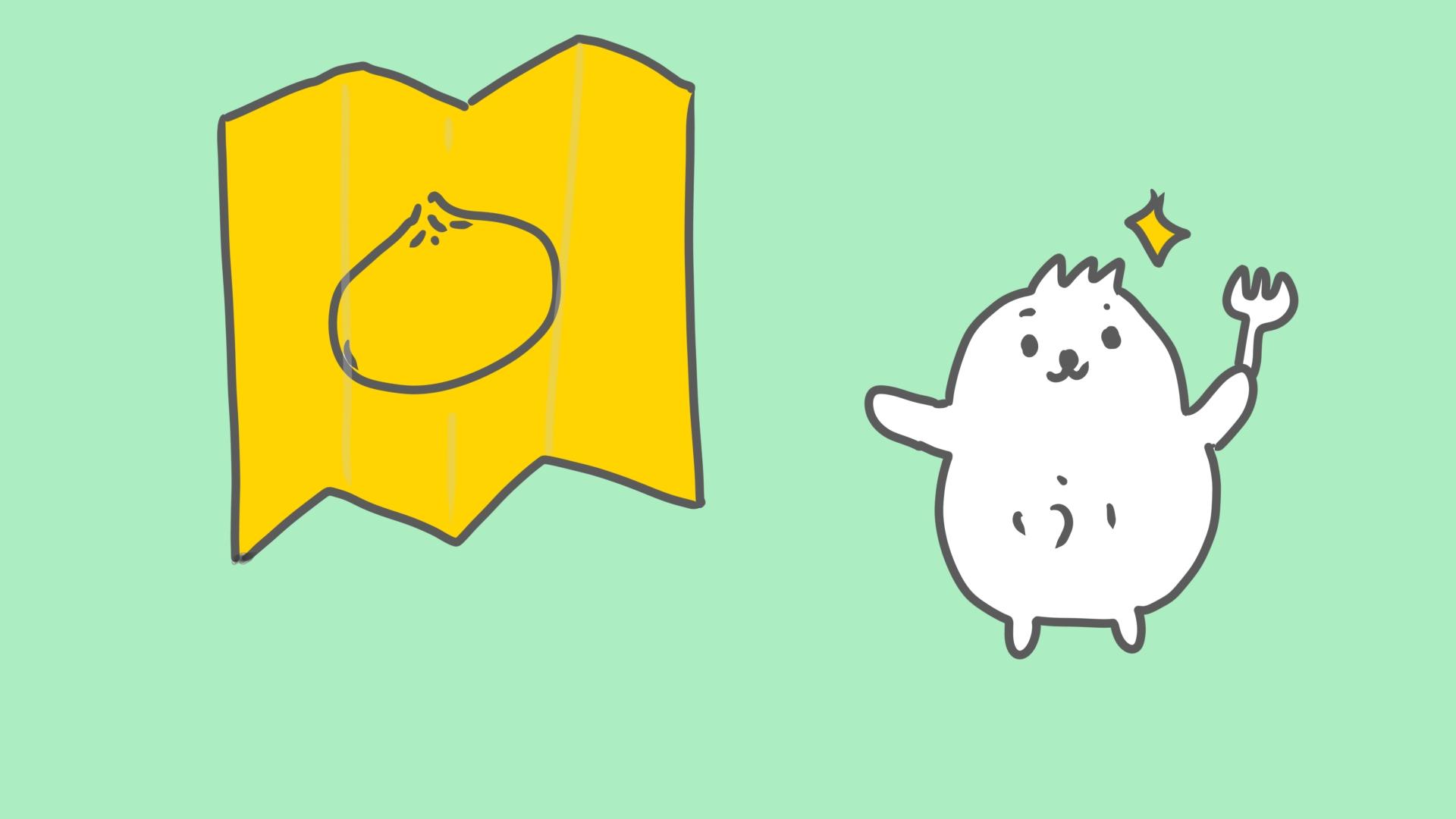
Q: なぜ1月9日が「とんちの日」や「クイズの日」なのですか?
A: 日付の「1(いっ)9(きゅう)」が、とんち話で有名な室町時代の僧侶「一休(いっきゅう)さん」を連想させる語呂合わせから来ています。一休さんの機転の利いた話が「とんち」や「クイズ」に通じることから、このように呼ばれるようになりました。
Q: 一休さんとはどのような人物ですか?
A: 一休宗純(いっきゅうそうじゅん)は、室町時代に活躍した臨済宗大徳寺派の僧侶であり、詩人としても知られています。後小松天皇の皇子とも言われ、権威に屈せず自由奔放な生き方をしたと伝えられています。屏風の虎退治や「このはしわたるべからず」など、彼の頓知話は江戸時代に作られた説話集『一休咄』によって広く知られるようになりました。
Q: 「とんち」とは具体的にどのような意味ですか?
A: その場に応じて即座に働く機転や知恵のことを指します。特に、難しい状況や問いに対して、ユーモアや意表を突くような発想で切り抜ける賢さを意味することが多いです。一休さんの話は、この「とんち」の良い例とされています。
名力士谷風の死を悼む: 風邪の日
江戸全域で猛威を奮ったインフルエンザによって、35連勝で現役のまま没した大相撲で活躍した谷風梶之助から。当時インフルエンザは「流行性感冒(りゅうこうせいかんぼう)」を略して「流感(りゅうかん)」と呼ばれてれていました。
Q: なぜ1月9日が「風邪の日」と言われるようになったのですか?
A: 1795年(寛政7年)の1月9日に、江戸時代の名横綱である谷風梶之助(二代目)が、当時流行していたインフルエンザ(流感)によって現役のまま亡くなったとされることに由来します。この出来事から、この日が俗に「風邪の日」と呼ばれることがあります。
Q: 谷風梶之助とはどのような力士でしたか?
A: 谷風梶之助は江戸時代中期に活躍した伝説的な力士で、初代横綱の一人とされています(ただし、公式な横綱制度は後の時代に確立)。小野川喜三郎と共に相撲人気を高め、63連勝という不滅の記録も打ち立てました。亡くなる直前まで35連勝中だったことからも、その強さがうかがえます。
Q: 当時の「流感」はどのような病気だったと考えられますか?
A: 現在でいうインフルエンザに相当する感染症と考えられています。江戸時代にもインフルエンザの流行はたびたび記録されており、「お駒風」「谷風邪」など、その時の流行状況や著名な罹患者の名前を冠して呼ばれることもありました。谷風が亡くなった際の流行も、江戸中で猛威をふるったと記録されています。
高級コーヒーの記念出荷日: ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒーの日
ジャマイカ産コーヒーが日本向けに初めて1400袋もの大型出荷をした1967年(昭和42年)1月9日にちなんで。
Q: なぜ1月9日が「ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒーの日」なのですか?
A: 1967年(昭和42年)1月9日に、ジャマイカにあるブルーマウンテン山脈で栽培されたコーヒー豆が、初めて日本へ向けて1400袋という大規模なロットで船積み出荷された歴史的な日であることに由来します。ジャマイカコーヒー輸入協議会などが制定しました。
Q: ブルーマウンテンコーヒーはなぜ「コーヒーの王様」と呼ばれるのですか?
A: ジャマイカのブルーマウンテン山脈のごく限られた地域で栽培され、厳しい品質基準(スクリーンサイズや欠点豆の混入率など)をクリアしたものだけが「ブルーマウンテン」として認定されます。独特の香り高くバランスの取れた上品な味わいと、その希少性から「コーヒーの王様」と称され、高値で取引されています。
Q: 日本はブルーマウンテンコーヒーの主要な輸入国なのですか?
A: はい、日本は長年にわたりブルーマウンテンコーヒーの最大の輸入国です。全生産量の多くが日本向けに出荷されており、日本のコーヒー愛好家にとって非常に馴染み深い高級コーヒーの一つとなっています。
商売繁盛の前夜祭: 宵戎(よいえびす)
関西地方を中心に、商売繁盛の神様「えびす様」を祀る十日戎(とおかえびす)の前日にあたるのが1月9日の「宵戎」です。多くの神社ではこの日から祭りが始まり、縁起物の笹を求める人々で賑わいます。
Q: 宵戎とはどのような意味を持つ日ですか?
A: 「宵」は祭りの本番(本戎)の前夜を意味します。1月10日の「本戎」、11日の「残り福」と合わせて三日間行われる十日戎祭りの初日にあたり、この日から福を授かろうと多くの参拝者が訪れます。本戎に向けて祭りの雰囲気が盛り上がり始める日です。
Q: 十日戎のお祭りでは、どのような縁起物が授与されますか?
A: 「福笹(ふくざさ)」と呼ばれる、縁起の良い笹が代表的です。参拝者はこの笹に、鯛、小判、米俵、大福帳、打ち出の小槌などの様々な飾り物(吉兆と呼ばれる)を福娘と呼ばれる巫女さんなどに付けてもらい、一年間の商売繁盛や家内安全を祈願します。
Q: えびす様は漁業の神様でもあるのですか?
A: はい、えびす様(戎様、恵比寿様)は、七福神の一柱として広く知られ、主に商売繁盛の神様として信仰されていますが、元々は漁業の神様としても厚く信仰されてきました。手に釣り竿と鯛を持っている姿が一般的であることからも、そのルーツがうかがえます。