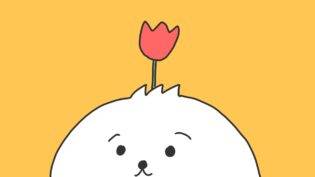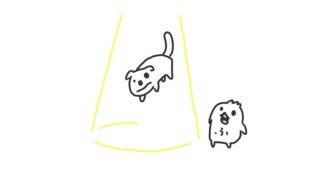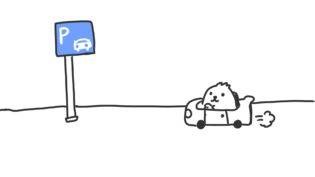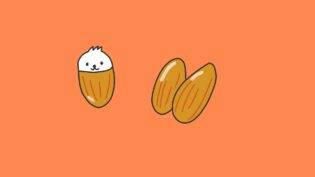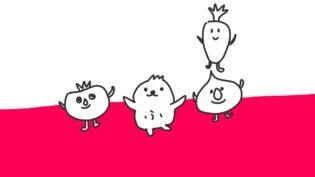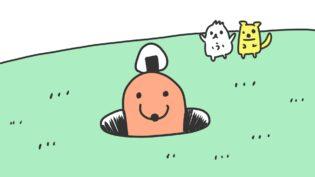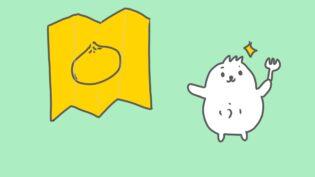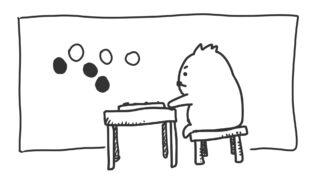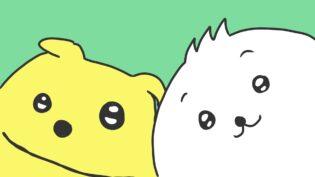1月11日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
年神様への感謝と無病息災祈願: 鏡開き
正月に神(年神)や仏に供えた鏡餅を下げて食べる日。

Q: なぜ1月11日に鏡開きを行うのが一般的なのですか?
A: 正月の間、年神様が宿っていたとされる鏡餅を、神様がお帰りになる松の内(一般的に関東では1月7日まで、関西では1月15日までとされることが多い)が明けた後にお下げしていただく行事です。地域によって日は異なりますが、徳川幕府が1月11日を蔵開きの日に定めたことなどから、全国的に1月11日に行われることが多くなりました。
Q: なぜ鏡餅を「割る」ではなく「開く」と表現するのですか?
A: 武家社会では「割る」や「切る」という言葉が縁起が悪いとされていたため、末広がりで縁起の良い「開く」という言葉を使うようになったのが由来とされています。神様にお供えした縁起の良い食べ物ですので、良い言葉を使うのですね。
Q: 鏡開きで下げたお餅はどのようにして食べるのが良いですか?
A: 包丁で切ることは武士の切腹を連想させ縁起が悪いとされるため、手で割ったり、木槌などで叩いて砕いたりするのが伝統的です。砕いたお餅は、お汁粉やお雑煮などに入れて食べるのが一般的で、神様にお供えしたものをいただくことで、その年の無病息災を願います。(補足:蔵開き、樽酒の日も、商家などで新年最初の蔵を開き、商売繁盛を祈る行事として、鏡開きと近い日に行われることがあります。)
マカロニの形が「1」に見える?: マカロニサラダの日
デリア食品株式会社が制定。「マカロニサラダ」入っているマカロニの形が数字の1に似ていることから。
Q: マカロニサラダの日はなぜ1月11日なのですか?
A: 日付の「1月11日」が数字の「1」が3つ並ぶことに着目し、マカロニの細長い形状が「1」に似ていることから、惣菜などを製造販売するデリア食品株式会社が制定しました。
Q: マカロニサラダはいつ頃から日本で親しまれるようになりましたか?
A: マカロニ自体は明治時代に日本に伝わりましたが、現在のようなマヨネーズと和えたサラダとして一般家庭や惣菜店で広く普及したのは、食生活が洋風化し、マヨネーズが普及した昭和中期(1950年代~)以降と考えられます。今では定番の家庭料理、お惣菜の一つですね。
Q: この記念日にはどのような願いが込められていますか?
A: 多くの人に愛されているマカロニサラダを、この日をきっかけにさらに多くの人に食べてもらい、その美味しさを再認識してほしいという願いが込められていると考えられます。
スペイン語・イタリア語で「1」: UNO(ウノ)の日
「UNO(ウノ)」を販売するマテル・インターナショナル株式会社が制定。日付はスペイン語やイタリア語で「UNO(ウノ)」は数字の1を意味することから、1が重なる1月11日に。
Q: なぜ「UNO」は1月11日を記念日にしたのですか?
A: カードゲーム「UNO(ウノ)」の名前は、スペイン語やイタリア語で数字の「1」を意味します。そのため、数字の「1」が3つ並ぶ1月11日を、ゲームの名前と関連付けて記念日として制定しました。制定したのは、UNOの販売元であるマテル・インターナショナル株式会社です。
Q: UNOはどのようなルールで遊ぶゲームですか?
A: 手持ちのカードを誰よりも早くなくすことを目指すゲームです。場に出ているカードと同じ色、数字、または記号のカードを順番に出していきます。特殊な効果を持つ「ワイルドカード」や「ドローカード」などもあり、戦略性が求められます。手札が残り1枚になったら「UNO!」と宣言するルールが特徴的です。
Q: UNOはいつ、どこで生まれたゲームですか?
A: 1971年にアメリカ・オハイオ州の理髪店主マール・ロビンス氏によって考案されました。家族や友人と遊ぶために作られたものが評判を呼び、商品化され、世界中で人気のカードゲームとなりました。
お菓子の形が「1」にそっくり?: アスパラガスビスケットの日
株式会社ギンビスが制定。アスパラガスビスケットの形が1に似ているから1月11日とした。
Q: アスパラガスビスケットのどこが「1」に似ているのですか?
A: 株式会社ギンビスが製造・販売する「アスパラガスビスケット」は、細長いスティック状の形をしています。この形状が数字の「1」に似ていることから、1が3つ並ぶ1月11日を記念日として制定しました。
Q: なぜ「アスパラガス」という名前なのにアスパラガスは入っていないのですか?
A: 諸説ありますが、ビスケットの形状が野菜のアスパラガスに似ていることや、開発された1968年当時、アスパラガスが西洋野菜として健康的でおしゃれなイメージがあったため、そのイメージにあやかって名付けられたと言われています。黒ゴマの風味が香ばしい、ロングセラーのビスケットです。
Q: この記念日を制定した目的は何でしょうか?
A: 長年親しまれてきた自社製品「アスパラガスビスケット」の更なる認知度向上と販売促進、そしてこのお菓子を通じて楽しい時間を過ごしてほしいという願いが込められていると考えられます。
Ill=111?: イラストレーションの日
日本イラストレーション協会が制定。日付「Illustration」(イラストレーション)の頭3文字「Ill」(アイエルエル)の形が1が3つ並んでいるように見えることから1月11日としたもの。
Q: なぜ「Illustration」の頭文字から1月11日が記念日になったのですか?
A: 英単語「Illustration」の最初の3文字「Ill」が、大文字の「I」と小文字の「l」(エル)2つで構成されており、これが数字の「1」が3つ並んでいる「111」に見えることにちなんで、日本イラストレーション協会(JIA)が1月11日を「イラストレーションの日」として制定しました。
Q: この記念日はどのような活動を推奨していますか?
A: イラストレーションの魅力や役割を社会に広く伝え、イラストレーション文化の普及と発展を目指す日とされています。イラストレーターの活動を応援したり、人々がイラストに親しむきっかけを作ったりすることを目的としています。
Q: 日本イラストレーション協会とはどのような団体ですか?
A: プロのイラストレーターを中心に構成され、イラストレーションの著作権保護や普及活動、イラストレーターの交流促進などを行っている職能団体です。
敵に塩を送った日?: 塩の日
戦国時代、甲斐の武田信玄が今川氏・北条氏によって塩の供給を絶たれた際、ライバルであった越後の上杉謙信が塩を送ったという「敵に塩を送る」の故事に由来するとされる日です。その塩が信濃国松本(現在の長野県松本市)に到着したのが1月11日だったという説があります。
Q: 「敵に塩を送る」という故事は本当にあったのですか?
A: 歴史的な事実として確定しているわけではなく、後世の創作であるという説も有力です。しかし、上杉謙信の義理堅さや人情深さを象徴するエピソードとして、また「困難な状況にある敵であっても、その弱みにつけこまずに助ける」という意味の故事成語として広く知られています。
Q: なぜ塩の供給を止めることが重要だったのですか?
A: 塩は人間の生命維持に不可欠なだけでなく、食料の保存(漬物、味噌など)や武具の手入れなどにも用いられる重要な物資でした。特に山国である甲斐(山梨県)は塩の生産ができず、海に面した地域からの供給に頼っていたため、「塩止め」は深刻な打撃を与える戦略でした。
Q: この「塩の日」は一般的に行事などが行われますか?
A: 長野県松本市には、この故事にちなんだ塩市(あめ市)というお祭りが1月に行われるなど、地域によっては関連する行事がありますが、全国的に統一された記念日として広く認知されているわけではありません。