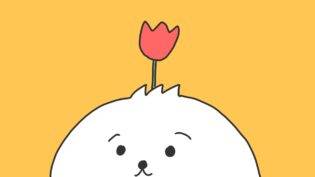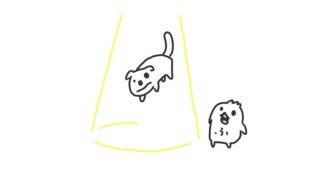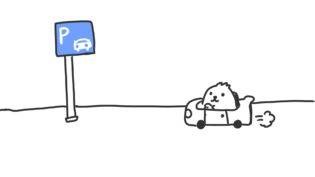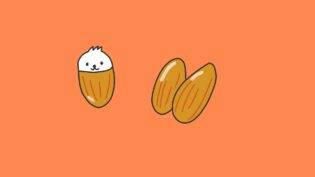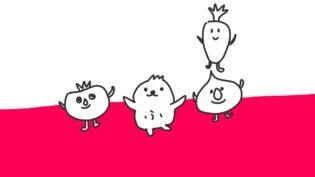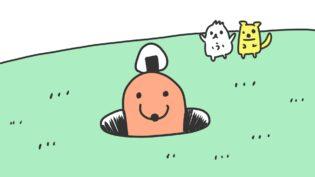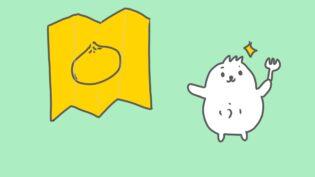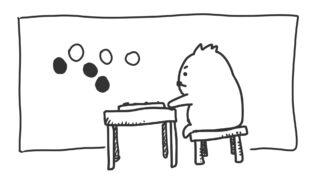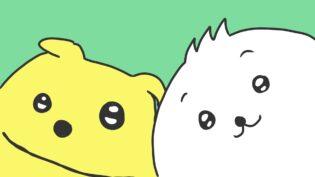1月12日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本のスキー文化の原点: スキーの日
1911年(明治44年)、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人レルヒ少佐が、日本で初めての本格的なスキー指導をした日。 この日を全日本スキー連盟など全国のスキー関係団体が、平成14年に「スキーの日」と制定しました。
Q: なぜ1月12日が「スキーの日」なのですか?
A: 1911年(明治44年)1月12日に、当時のオーストリア=ハンガリー帝国(現オーストリア)の軍人であったテオドール・フォン・レルヒ少佐が、新潟県高田(現・上越市)の陸軍歩兵連隊の将校たちに対して、日本で初めてとなる本格的なスキー技術の指導を行った歴史的な日にちなんでいます。
Q: レルヒ少佐はなぜ日本でスキーを教えることになったのですか?
A: 日露戦争後、日本の陸軍は寒冷地での作戦能力向上の必要性を感じていました。そこで、雪国での軍事活動にスキーが有効であると考え、アルペンスキーの先進国であったオーストリアから専門家としてレルヒ少佐を招聘し、その指導を仰ぐことになったのです。
Q: この記念日はいつ、誰によって制定されましたか?
A: 日本におけるスキー発祥100周年を前にした2002年(平成14年)に、全日本スキー連盟(SAJ)をはじめとするスキー関連団体によって制定されました。スキー文化の普及と発展を願う目的があります。
大正の大噴火を伝える: 桜島の日
1914年(大正3年)のこの日、鹿児島県の桜島で、史上最大の大噴火(大正大噴火)が始まったことから。この噴火は約1ヵ月間にわたって頻繁に爆発が繰り返され、多量の溶岩が流出。
Q: なぜ1月12日が「桜島の日」なのですか?
A: 1914年(大正3年)1月12日に、鹿児島県の桜島で有史以来最大規模とされる「大正大噴火」が始まったことに由来します。この噴火による教訓を忘れず、防災意識を高めるために、鹿児島市などによって制定されました。
Q: 大正大噴火はどのような被害をもたらしましたか?
A: 噴火は約1ヶ月続き、大量の火山灰や軽石を噴出し、大規模な溶岩流が発生しました。この溶岩流によって、それまで島だった桜島と対岸の大隅半島が陸続きになりました。多くの集落が埋没し、死者・行方不明者58名を出す大きな被害となりました。
Q: 現在の桜島はどのような状況ですか?
A: 桜島は現在も活動を続ける活火山であり、日常的に小規模な噴火を繰り返しています。噴火警戒レベルが設定され、常時観測体制が敷かれています。周辺地域では、火山灰への対策(克灰袋など)が日常の一部となっています。
SNS時代の肯定感を象徴: いいねの日
「い(1)い(1)ね(2)」と読む語呂合わせから。2021年(令和3年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録。
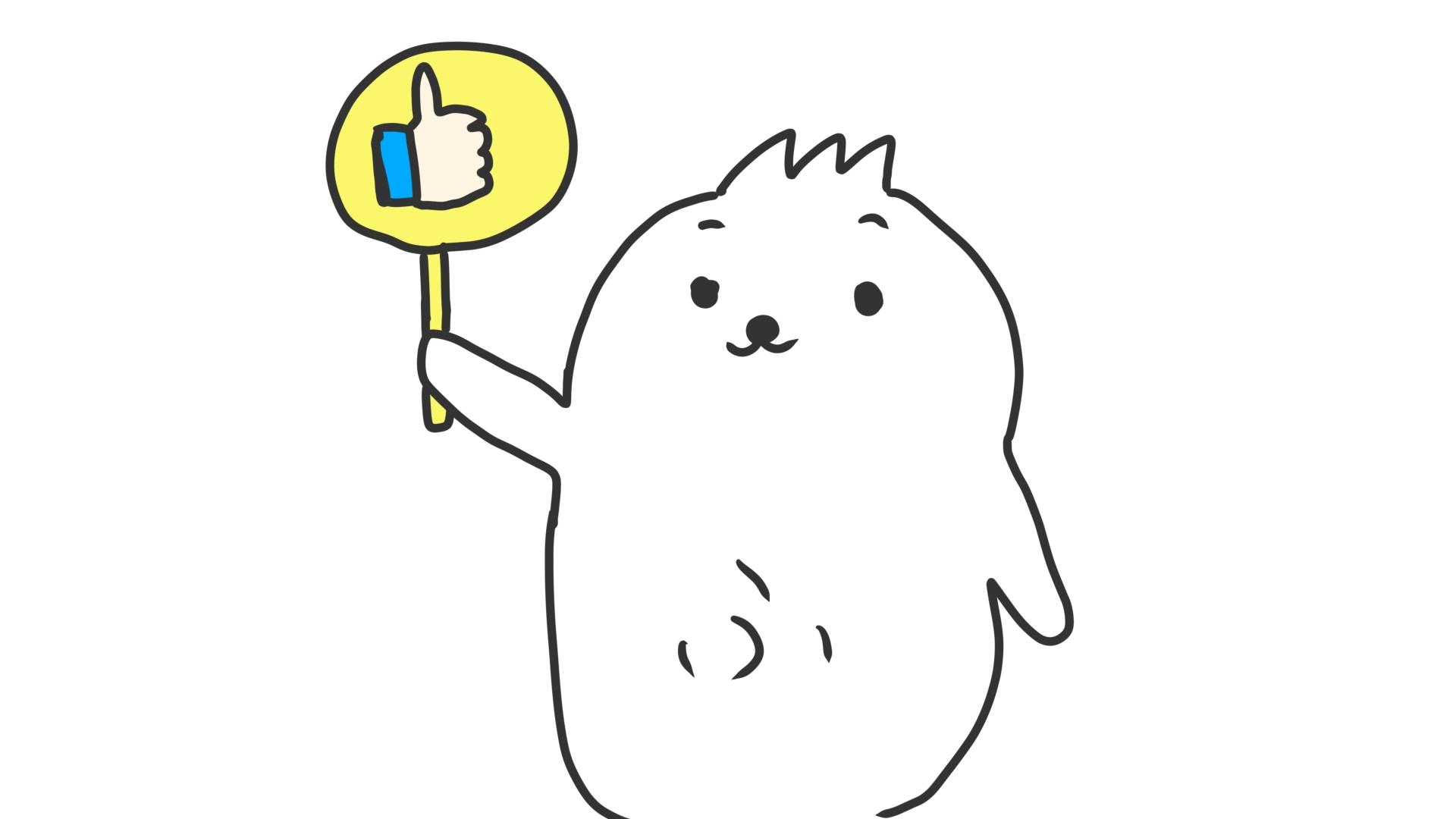
Q: 「いいねの日」の由来は何ですか?
A: 日付の「1(い)1(い)2(ね)」を「いいね」と読む語呂合わせから制定されました。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: (制定者は明記されていませんが) SNSなどで広く使われる「いいね!」のように、気軽に相手を肯定したり、ポジティブな気持ちを伝え合ったりすることの素晴らしさを再認識し、世の中に「いいね!」があふれることを願う目的があると考えられます。2021年に一般社団法人日本記念日協会によって認定・登録されています。
Q: 「いいね!」はどのような場面で使われますか?
A: FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などのSNS投稿に対する共感や賛同、応援の意思を示す機能として広く使われています。また、オンラインだけでなく、日常会話やジェスチャーでも、相手への肯定や賞賛を表す際に用いられます。
栄養満点な根菜に注目: いいにんじんの日
日付を「い(1)い(1)にん(2)じん」と読む語呂合わせから、JA全農などが中心となって制定したとされる記念日です。栄養豊富なにんじんを食べて健康になってもらうことを目的としています。
Q: なぜ1月12日が「いいにんじんの日」なのですか?
A: 日付の「1(い)1(い)2(にん)」で「いいにんじん」と読む語呂合わせが由来です。
Q: にんじんにはどのような栄養が含まれていますか?
A: にんじんの鮮やかなオレンジ色は、β-カロテンという色素によるものです。β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、目や皮膚の健康維持、免疫機能の向上などに役立ちます。その他にも食物繊維やカリウムなどが含まれています。
Q: この記念日はどのようなことを推奨していますか?
A: 正式な制定団体や活動は明確ではありませんが、この日をきっかけに、栄養価の高いにんじんを食卓に取り入れ、その美味しさや健康効果を再認識し、消費を促進することを目的としていると考えられます。