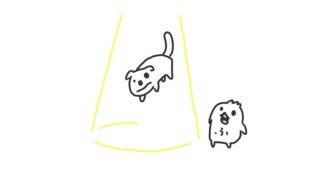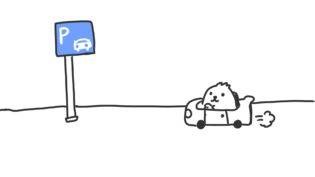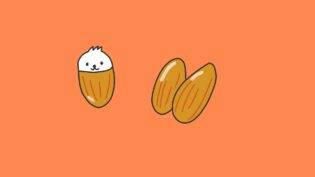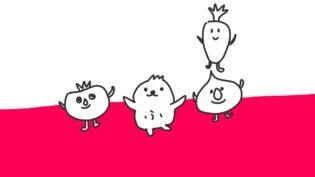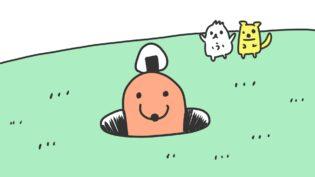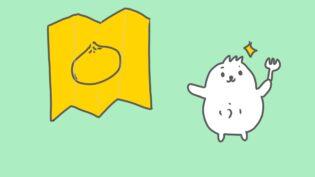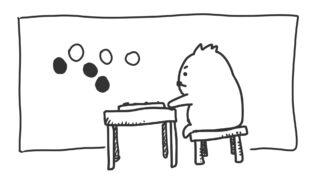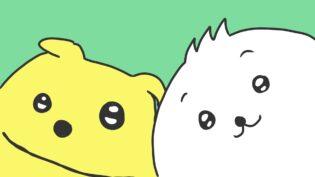1月31日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
正月の締めくくりと年始挨拶の機会: 晦日正月・晦日節
中部地方を中心に各地で行われている風習で、お正月の最後の日として祝う日。また「晦日節」の日でもあり、年始に挨拶ができなかった家を訪ねる日でもあります。
Q: 晦日正月とは具体的にどのようなことをする日ですか?
A: 地域によって異なりますが、お正月飾りを片付けたり、お供えした餅などを食べたりして、一連の正月行事を締めくくる日とされています。松の内にできなかった挨拶回りをする「晦日節」としての側面も持ちます。
Q: なぜお正月の最後の日を特に祝うのですか?
A: 正月行事の終わりを一つの区切りとし、無事に新年を迎えられたことへの感謝や、通常の生活への移行を意識する意味合いがあると考えられます。また、忙しい松の内が過ぎ、落ち着いて過ごせるこの日に改めて祝うという側面もあるようです。
Q: 年始に挨拶ができなかった家を訪ねるのはなぜですか?
A: 松の内(一般的には1月7日または15日まで)に年始の挨拶に行けなかった場合に、この晦日正月の日に改めて訪問する風習が一部地域にあります。新年の挨拶を欠かさないという礼儀を重んじる気持ちの表れと言えるでしょう。
語呂合わせで伝える感謝の気持ち: 愛妻の日・愛妻感謝の日
「愛(I=1)妻(31)」と読む語呂合わせから。
Q: 「愛妻の日」の由来は何ですか?
A: 日付の1月31日を英語の「I(アイ=1)」と「31(サイ)」にかけて「愛妻」と読む語呂合わせから来ています。日本愛妻家協会が、妻への感謝の気持ちを形にするきっかけの日にしようと提唱しました。
Q: この日はどのように過ごすことが推奨されていますか?
A: 夫から妻へ感謝の気持ちを伝えたり、プレゼントを贈ったり、二人で過ごす時間を作るなど、夫婦の絆を深める日にすることが推奨されています。例えば、「午後8時(愛妻の時間)に帰宅する」「感謝の言葉を伝える」「花を贈る」などが提案されています。
Q: 日本愛妻家協会とはどのような団体ですか?
A: 「妻というもっとも身近な赤の他人を大切にする人が増えると、世界はもう少し豊かで平和になるかもしれない」という理念のもと、群馬県嬬恋村を拠点に活動している団体です。「キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ(キャベチュー)」などのユニークなイベントでも知られています。
愛情を込めて贈る春の花: チューリップを贈る日
愛妻の日に合わせて、大切なパートナー(愛妻)にチューリップを贈ってほしいとの思いを込めて砺波切花研究会が制定。
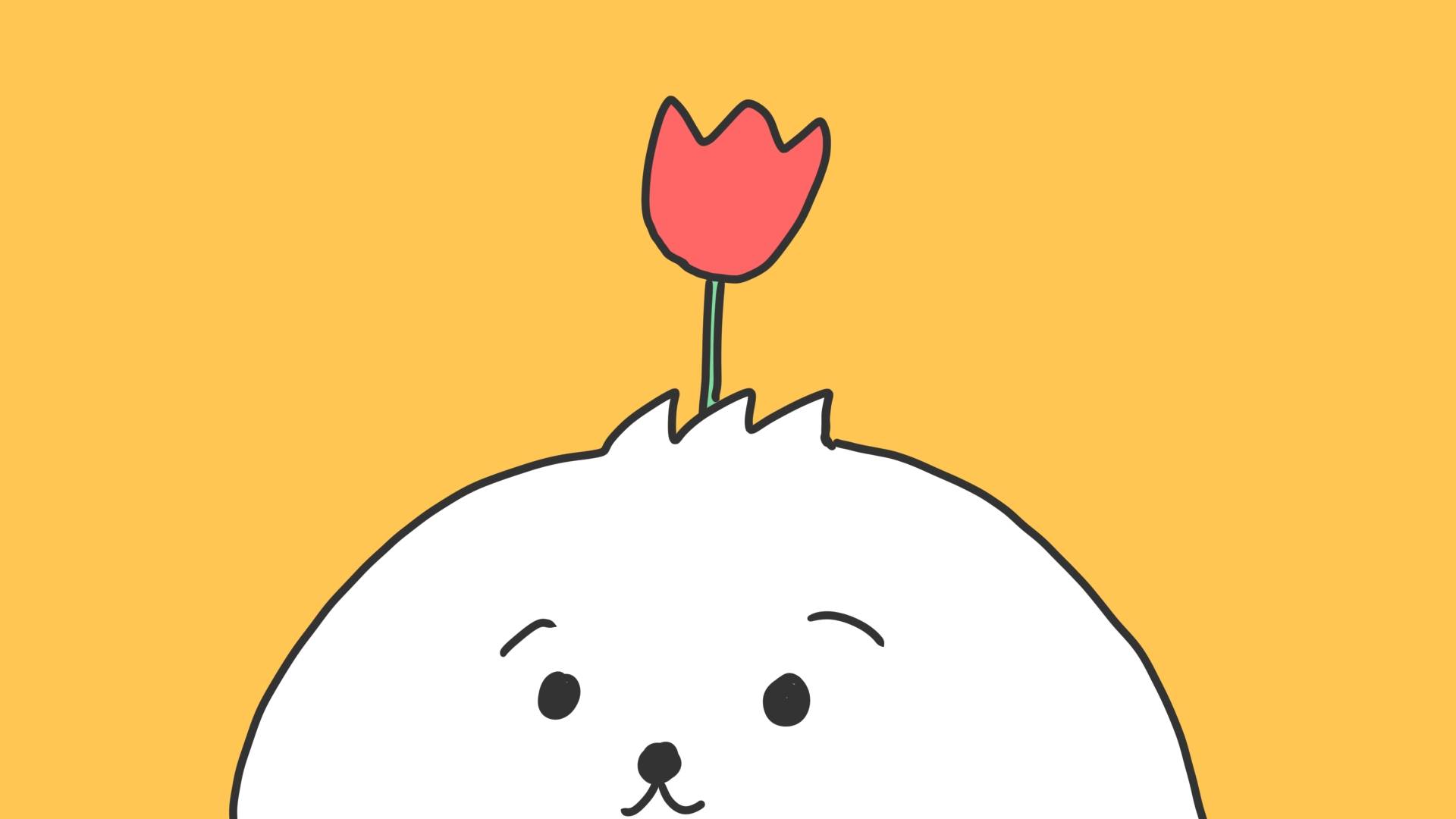
Q: なぜ「愛妻の日」に合わせてチューリップを贈るのですか?
A: チューリップは春を象徴する明るい花であり、色によって様々な愛の花言葉を持つことから、愛妻への感謝と愛情を表現するのにふさわしい花と考えられたためです。1月はチューリップの出荷が増える時期でもあります。
Q: チューリップにはどのような花言葉がありますか?
A: チューリップ全般の花言葉は「思いやり」「博愛」などですが、色によって異なります。例えば、赤色は「愛の告白」、ピンク色は「誠実な愛」、黄色は「希望のない恋」(※近年は「明るさ」などポジティブな意味も)、紫色は「不滅の愛」などがあります。贈る相手や気持ちに合わせて色を選ぶのも素敵です。
Q: 制定した砺波切花研究会はどのような団体ですか?
A: 富山県砺波市は日本有数のチューリップ球根の産地として有名です。砺波切花研究会は、その砺波市でチューリップをはじめとする切り花の品質向上や生産振興に取り組んでいる生産者の団体です。チューリップの魅力を広める活動の一環としてこの記念日を制定しました。
日本初の保険金支払いが行われた日: 生命保険の日
1882年(明治15年)のこの日、日本で最初の生命保険会社である明治生命(現:明治安田生命)が、創立から1年4ヶ月後に初めての保険金支払いをしました。受取人は警察官で、保険金は1000円だったとされています。
Q: なぜ1月31日が「生命保険の日」なのですか?
A: 1882年(明治15年)のこの日に、日本で初めて生命保険金が支払われたことに由来します。これは、万が一の際に遺された家族の生活を支えるという生命保険の役割が、日本で初めて果たされた日として記念されています。
Q: 日本初の生命保険会社はいつ設立されたのですか?
A: 福沢諭吉らの尽力により、1881年(明治14年)7月に日本初の生命保険会社として「明治生命保険会社」が設立されました。近代的な相互扶助の仕組みとして、生命保険制度が日本に導入されたのです。
災害に備える農地の役割を考える日: 防災農地の日
都市農地の保全活動などを行うNPO法人「畑と田んぼ環境再生会」が制定。日付は1月31日を「131」と見立て、「い(1)ざ、さ(3)いがい(1)」(いざ、災害)と読む語呂合わせから。
Q: 「防災農地の日」の由来を教えてください。
A: 日付の「131」を「い(1)ざ、さ(3)いがい(1)」と読み、「いざ、災害」の時に農地が役立つことを想起させる語呂合わせから来ています。
Q: 農地は災害時にどのように役立つのでしょうか?
A: 都市部にある農地は、地震などの災害時に、火災の延焼を防ぐ空間となったり、避難場所や仮設住宅の建設地になったりする可能性があります。また、食料生産の場としての機能はもちろん、井戸水が生活用水として活用できる場合もあります。このように、農地が持つ多面的な防災機能に注目が集まっています。