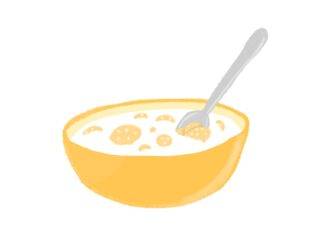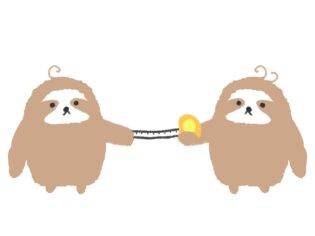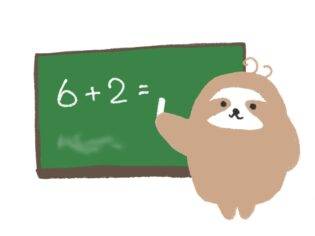5月1日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
新しい時代の幕開け: 「令和」改元の日
2019年(令和元年)5月1日に、日本の元号が「平成」から「令和(れいわ)」へと改められました。これは、前日の4月30日に第125代天皇・明仁(あきひと)陛下が退位され、5月1日に皇太子・徳仁(なるひと)親王殿下が第126代天皇に即位されたことに伴うものです。憲政史上初の天皇退位による改元となりました。
Q: 「令和」改元の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の法律で定められた記念日ではありませんが、天皇の退位と即位に伴って新しい元号「令和」が始まった、日本の歴史における極めて重要な節目として国民に記憶される日です。平成という一つの時代が終わり、令和という新しい時代への希望や決意を新たにする象徴的な日と言えます。
Q: なぜ5月1日が「令和」改元の日なのですか?
A: 2019年4月30日をもって第125代天皇・明仁陛下が退位され、その翌日である5月1日の午前0時に、皇太子・徳仁親王殿下が第126代天皇に即位されました。これに伴い、元号法に基づき、同日から新しい元号として「令和」が施行されたためです。
Q: 「令和」という元号にはどのような意味が込められていますか?
A: 日本の古典である『万葉集』の梅花の歌の序文「初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(きよ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かほら)す」から引用されました。「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められています。厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりの日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いが込められていると説明されています。
恋心と雅を伝える「こ(5)い(1)」の風: 扇の日
扇子(せんす)や団扇(うちわ)の製造・販売業者で構成される京都扇子団扇商工協同組合が1990年(平成2年)に制定。日付は、日本を代表する古典文学『源氏物語』の中で、光源氏が女性に扇(おうぎ)を贈って愛を伝える場面があることと、「こ(5)い(1)」(恋)と読む語呂合わせにちなんでいます。

Q: 扇の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 日本の伝統工芸品であり、夏の風物詩でもある扇子や団扇の文化的な価値、美しさ、そして実用性(涼をとる、儀礼用、装飾用など)を広くPRし、その需要を喚起することを目的としています。特に、扇が古来より贈答品やコミュニケーションツールとしても用いられてきた歴史を踏まえ、その魅力を伝える狙いがあります。
Q: なぜ5月1日が「扇の日」なのですか?
A: 『源氏物語』という古典文学の代表作において、扇が恋愛の場面で重要な小道具として登場することと、日付の「5(こ)1(い)」が「恋」に通じるという風雅な語呂合わせから、この日が選ばれました。これから暑くなる季節に向けて、扇子や団扇への関心を高める時期でもあります。
Q: 扇子と団扇の違いは何ですか?
A: 扇子は、骨組み(竹や木など)に紙や布を貼り、折りたたむことができるのが特徴です。携帯に便利で、儀礼的な場面でも用いられます。一方、団扇は、竹などの骨に紙や布を貼ったもので、折りたたむことはできません。扇子よりも大きな風を送ることができ、主に涼をとるためや、広告媒体としても使われます。
幸福を願って贈る白い花: スズランの日 (Jour de Muguet)
フランスで古くから続く習慣で、毎年5月1日に、愛する人や大切な人(家族、友人、恋人など)にスズラン(鈴蘭、ミュゲ:Muguet)の花を贈ると、贈られた人に幸運が訪れると言われています。この風習にちなんで、日本でも「スズランの日」として知られ、花屋さんなどでスズランが販売されます。
Q: スズランの日は、どのような目的で広まったのですか?
A: 特定の団体が日本で制定したものではありませんが、フランスの美しく心温まる伝統的な風習を日本でも紹介し、春の訪れとともに、大切な人の幸福を願って花を贈るという素敵な習慣を広めることを目的として、花業界などを中心に提唱されています。
Q: なぜ5月1日が「スズランの日」なのですか?
A: フランスにおける長年の伝統に基づいています。その起源には諸説ありますが、有力な説の一つとして、16世紀のフランス国王シャルル9世が、5月1日に भेंटされたスズランの花の可憐さに感銘を受け、宮廷の女性たちに毎年スズランを贈るようになったことが始まりとされています。また、古代ケルト人の春の祭りに由来するという説もあります。春の到来と幸福の訪れを象徴する日として、5月1日にスズランを贈る風習が定着しました。
Q: スズランはどのような花ですか?花言葉は?
A: 春に、鈴のような形をした可憐な白い小花を、一つの花茎に複数咲かせます。甘く清らかな香りが特徴です。花言葉は「再び幸せが訪れる」「純粋」「純潔」「謙遜」などで、その花姿や香りにふさわしい、幸福や清らかさを連想させる言葉が多くあります。(ただし、スズランには毒性があるので注意が必要です)
縁起の良い出世魚「こ(5)い(1)」: 鯉の日
鯉(こい)の生産者団体である全国養鯉振興協議会などが制定。日付は「こ(5)い(1)」(鯉)と読む語呂合わせからです。
Q: 鯉の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 日本で古くから観賞魚(錦鯉など)や食用魚として親しまれ、また、滝を登る鯉の伝説から立身出世の象徴(鯉のぼりなど)とされるなど、文化的に深い関わりを持つ鯉の魅力を再認識し、鯉に関する文化や産業の振興を図ることを目的としています。
Q: なぜ5月1日が「鯉の日」なのですか?
A: 「5(こ)1(い)」という、日本語で「鯉(こい)」と読む際の音に合わせた、覚えやすく直接的な語呂合わせからこの日が選ばれました。5月5日の「端午の節句」も近く、鯉のぼりが飾られるなど、鯉に親しみを感じる機会が多い時期でもあります。
Q: 鯉はなぜ「出世魚」として縁起が良いのですか?
A: 中国の故事「登竜門」に由来します。黄河の急流にある竜門という滝を登りきった鯉は竜になるという伝説から、鯉は困難を乗り越えて立身出世する象徴とされました。このため、男の子の健やかな成長と将来の成功を願って、端午の節句に鯉のぼりを飾る習慣が生まれました。
労働者の祭典、権利と連帯を確認する日: メーデー (May Day)
世界各地で毎年5月1日に行われる、労働者の祭典です。その起源は、1886年5月1日にアメリカのシカゴで行われた、労働者が8時間労働制を求めて行ったゼネスト(統一ストライキ)と、その後の労働運動(ヘイマーケット事件など)にあります。この出来事を記念し、1889年の第二インターナショナル創立大会で、5月1日を労働者の権利要求と国際的な連帯を示す日とすることが決定されました。
Q: メーデーはどのような目的で行われますか?
A: 労働者の権利(団結権、団体交渉権、ストライキ権など)の確認、労働条件の改善要求(賃上げ、労働時間短縮、安全な労働環境など)、そして世界中の労働者の連帯を示すことを目的としています。デモ行進や集会、講演会、文化イベントなどが開催されます。
Q: 日本のメーデーはいつから始まりましたか?
A: 日本では、1920年(大正9年)5月2日に東京の上野公園で第1回のメーデーが開催されたのが始まりです。戦時中の中断を経て、戦後1946年に復活し、現在も多くの労働組合が中心となって、全国各地で様々な取り組みが行われています。
Q: メーデーは祝日ですか?
A: 世界の多くの国(約80カ国以上)で、メーデー(またはその付近の日)は「労働者の日」などとして祝日(メーデーホリデー)になっていますが、日本では国民の祝日ではありません。ただし、企業によっては慣例的に休日としている場合があります。
赤十字の精神を普及する日: 日本赤十字社創立記念日
1877年(明治10年)5月1日に、佐野常民(さの つねたみ)らが、西南戦争の負傷者救護のために、日本赤十字社の前身である「博愛社(はくあいしゃ)」を設立したことを記念する日です。
Q: 日本赤十字社創立記念日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の制定団体があるわけではありませんが、紛争や災害時における人道支援、医療活動、血液事業、社会福祉活動など、多岐にわたる活動を通じて国内外で貢献している日本赤十字社の創設を記念し、その活動理念である「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」という赤十字精神への理解と支援を広める日として認識されています。
Q: なぜ5月1日が「日本赤十字社創立記念日」なのですか?
A: 1877年(明治10年)5月1日に、佐野常民らが西南戦争の負傷者を敵味方の区別なく救護するために、日本で初めての戦時救護団体「博愛社」を設立した、まさにその日付に基づいています。博愛社は、後に国際赤十字に加盟し、1887年に「日本赤十字社」と改称しました。
Q: 日本赤十字社はどのような活動を行っていますか?
A: 国内外での災害救護活動、医療事業(赤十字病院の運営など)、血液事業(献血の推進)、救急法などの講習普及、青少年赤十字活動、国際的な人道支援活動など、非常に幅広い分野で人道的活動を展開しています。その活動は多くのボランティアや寄付によって支えられています。