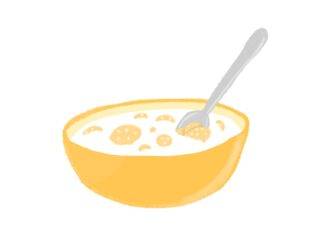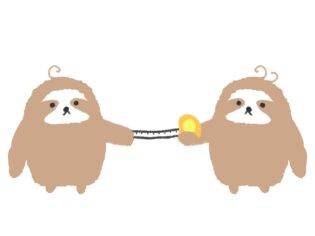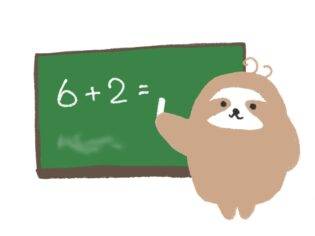5月2日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
海の恵みと資源を守る意識を世界へ: 世界まぐろデー (World Tuna Day)
2016年(平成28年)12月の国連総会で制定され、翌2017年から実施されている国際デーの一つです。マグロ類が世界的な食料源として、また多くの国々の経済にとって重要な水産資源である一方、一部の種では乱獲による資源枯渇が懸念されていることから、マグロ資源の持続可能な管理と保全の重要性に対する国際社会の意識を高めることを目的としています。
Q: 世界まぐろデーは、どのような目的で制定されましたか?
A: マグロ類が持つ食料安全保障や経済発展、文化における重要な役割を認識し、その資源を持続可能な形で管理・利用していくことの重要性について、国際社会全体の意識を高めることを目的として国連によって制定されました。科学的根拠に基づいた漁業管理の推進や、違法・無報告・無規制(IUU)漁業の撲滅も目指しています。
Q: なぜ5月2日が「世界まぐろデー」なのですか?
A: この日付は、2016年12月の国連総会で「世界まぐろデー」を制定する決議が採択された際に定められました。特定の歴史的な出来事に由来するというよりは、マグロ資源の保全について世界的に考える日として、この日が選ばれたと考えられます。(日付選定の具体的な理由は公表されていないようです。太平洋の島嶼国などが強く推進しました。)
Q: マグロ資源を守るためにどのような取り組みが行われていますか?
A: 各国の漁獲量制限(漁獲枠の設定)、漁具や漁法の規制、産卵期や稚魚の保護、養殖技術の開発、そして違法漁業の取り締まりなど、国際的な協力のもとで様々な資源管理措置が取られています。消費者の側でも、持続可能な漁業で獲られたマグロを選ぶなどの意識が求められています。
国民の貯蓄を支えた身近な金融機関: 郵便貯金の日
1875年(明治8年)5月2日に、国民の貯蓄奨励と国家資金の安定供給を目的として、東京府下18箇所と横浜1箇所の郵便局に「貯金預所」が設けられ、日本の近代的な郵便貯金制度が始まったことを記念して、1950年(昭和25年)に当時の郵政省(現在の日本郵政グループ)が制定しました。「郵便貯金創業記念日」とも呼ばれます。

Q: 郵便貯金の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 日本の近代的な郵便貯金制度の創設を記念し、国民生活に最も身近な金融機関として、貯蓄の奨励や国民経済の安定に貢献してきた郵便貯金事業の意義と役割を広くPRし、貯蓄の大切さを再認識してもらうことを目的として制定されました。
Q: なぜ5月2日が「郵便貯金の日」なのですか?
A: 1875年(明治8年)5月2日に、明治政府によって郵便貯金業務が正式に開始された、まさにその歴史的な日付に基づいています。全国の郵便局ネットワークを通じて、誰でも少額から安全に貯蓄できるこの制度は、国民の資産形成に大きく貢献しました。(現在は「ゆうちょ銀行」として民営化されています)
Q: 郵便貯金はなぜ「安全」と言われたのですか?
A: 国(政府)が運営する事業であったため、元本保証の信頼性が非常に高く、預け入れ限度額はあったものの、破綻のリスクが極めて低いと考えられていました。そのため、庶民にとって最も安心できる貯蓄手段として広く利用されました。
街を彩る情報メディア「こ(5)うつう(2)」: 交通広告の日
JR東日本グループの広告会社である株式会社JR東日本メディア(旧:関東交通広告協議会など)が1993年(平成5年)に制定。日付は「こ(5)うつう(2)」(交通)と読む語呂合わせからです。
Q: 交通広告の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 電車の中吊り、駅貼りポスター、車体ラッピング、駅構内のデジタルサイネージなど、公共交通機関のスペースを活用した「交通広告」が持つ、多くの人々の目に触れるという特性や、地域に密着した情報発信力、多様な表現方法といった媒体価値を広く社会にアピールし、その利用促進と広告業界の活性化を図ることを目的としています。
Q: なぜ5月2日が「交通広告の日」なのですか?
A: 「交(5)通(2)」という、覚えやすく直接的な語呂合わせから、多くの人に交通広告に関心を持ってもらうきっかけとなるように、この日が選ばれました。ゴールデンウィーク期間中で、交通機関の利用者が増える時期であることも理由の一つと考えられます。
Q: 交通広告にはどのような種類や特徴がありますか?
A: 車内広告(中吊り、窓上ポスター、ドア横ステッカー、車内ビジョンなど)、駅広告(駅貼りポスター、駅看板、柱巻き広告、フロア広告、デジタルサイネージなど)、車体広告(ラッピングバス・電車など)があります。通勤・通学などで日常的に繰り返し接触するため反復効果が高い、特定の路線や駅周辺のターゲットに訴求しやすい、公共空間での掲出のため信頼性が比較的高い、といった特徴があります。
国産鉛筆、工場生産の始まり: えんぴつ記念日
1886年(明治19年)5月2日に、眞崎仁六(まさき にろく)が東京・新宿に設立した眞崎鉛筆製造所(後の三菱鉛筆株式会社)において、日本で初めてとなる鉛筆の工場生産が本格的に開始されたとされることを記念する日です。
Q: えんぴつ記念日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の制定団体があるわけではありませんが、それまで輸入や手工業に頼っていた鉛筆が、日本国内で初めて工場で大量生産されるようになったという、日本の文房具史および産業史における重要な出来事を記念する日として認識されています。学用品や筆記具として欠かせない鉛筆の歴史や技術に思いを馳せる日です。
Q: なぜ5月2日が「えんぴつ記念日」なのですか?
A: 1886年(明治19年)5月2日に、眞崎鉛筆製造所が日本で初めて鉛筆の工場生産を開始したとされる日付に基づいています。(ただし、工場の設立日や生産開始の正確な日付については諸説あるようです。)これにより、国産鉛筆の安定供給が可能となりました。
Q: 鉛筆の芯は何でできていますか?HBや2Bの違いは何ですか?
A: 鉛筆の芯は、鉛(なまり)ではなく、黒鉛(こくえん、グラファイト)と粘土を混ぜて焼き固めたものです。HBや2Bといった記号は芯の硬さと濃さを表しています。HはHard(硬い)、BはBlack(黒い)、FはFirm(しっかりした)の頭文字です。Hの前の数字が大きいほど硬く薄い芯、Bの前の数字が大きいほど柔らかく濃い芯になります。HBはその中間、FはHBとHの中間の硬さです。
緑が輝く季節に感謝: 緑のおばさんの日
1959年(昭和34年)5月2日に、通学途中の児童を交通事故から守るための「学童擁護員」(緑のおばさん)の制度が東京都でスタートしたことを記念する日とされています。
Q: 緑のおばさんの日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の制定団体があるわけではありませんが、子どもたちの登下校時の安全を見守り、交通安全指導を行う「学童擁護員」(通称:緑のおばさん、近年は性別に関わらず緑の帽子とベストを着用することから「緑のボランティア」などとも呼ばれる)の活動に感謝し、その重要性を再認識する日として語られています。地域ぐるみでの子どもの安全確保への意識を高めるきっかけの日です。
Q: なぜ「緑のおばさん」と呼ばれるようになったのですか?
A: 制度発足当初、交通安全のシンボルカラーである緑色の制服(帽子やベスト、手旗など)を着用し、主に地域の女性(主婦など)がボランティアとして活動に参加していたことから、親しみを込めて「緑のおばさん」という愛称で呼ばれるようになりました。
Q: 学童擁護員の活動はなぜ重要なのでしょうか?
A: 交通量の多い横断歩道や見通しの悪い交差点などで、子どもたちが安全に道路を横断できるよう誘導したり、交通ルールを守るよう指導したりすることで、痛ましい交通事故を未然に防ぐ重要な役割を担っています。また、地域の大人が子どもたちを見守っているという安心感を子どもたちや保護者に与え、地域の防犯意識向上にも貢献しています。