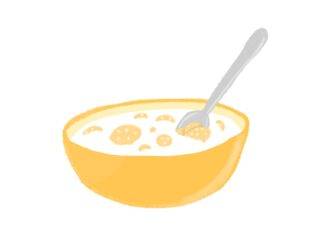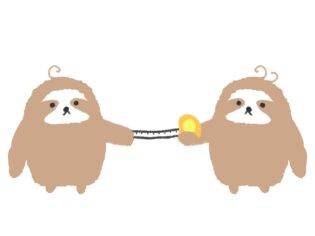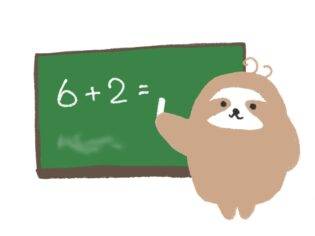5月8日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本の伝統発酵食を家庭の食卓へ: ぬか漬けの日
5月8日は「ぬか漬けの日」です。ぬか漬けの普及活動を行う業界団体「日本いりぬか工業会」が制定しました。日本の伝統的な発酵食品である「ぬか漬け」の文化を次世代へ伝え、健康的な食生活の普及と食文化の継承を目的としています。日付は、ぬか床の発酵が安定する季節であり、旬の野菜も多く出回り始める5月と、米ぬかの「米」の下半分が漢数字の八に似ている8日、また「ご(5)は(8)ん」の語呂合わせで「ごはんにぬか漬け」というキャッチフレーズを通じて、家庭の食卓でぬか漬けを楽しんでほしいという想いが込められています。2015年に制定され、日本記念日協会にも登録されています。
Q: ぬか漬けとはどんな食品ですか?
A: ぬか漬けは、米ぬか・塩・水などを混ぜて発酵させた「ぬか床」に野菜(きゅうり、なす、かぶなど)を漬け込んで作る日本の伝統的な漬物です。乳酸菌による発酵で独特の風味と旨味が生まれ、ビタミンB群や食物繊維が豊富で、健康効果が高いとされています。
Q: ぬか漬けの魅力や効果は何ですか?
A: ぬか漬けは乳酸菌が豊富で腸内環境を整え、免疫力アップや美肌効果が期待できます。また、野菜の栄養を効率的に摂取でき、低カロリーでご飯のお供にぴったり。家庭で毎日かき混ぜる手間が愛着を生み、食文化として長く親しまれています。
Q: 「ぬか漬けの日」はなぜ5月8日なのですか?
A: 春から夏にかけて旬の野菜が多くなり、ぬか床の発酵が安定しやすい5月と、米ぬかの「米」の下部が「八」に似ている8日を組み合わせ、さらに「ご(5)は(8)ん」の語呂で「ごはんにぬか漬け」を連想させるためです。家庭でぬか漬けを始めて、ご飯と一緒に楽しむきっかけにしたいという願いが込められています。
沖縄の夏野菜「ゴー(5)ヤー(8)」で元気に: ゴーヤーの日
JA沖縄経済連(現:JAおきなわ)と沖縄県が1997年(平成9年)に制定。日付は「ゴー(5)ヤー(8)」と読む語呂合わせと、沖縄で5月頃からゴーヤー(和名:ツルレイシ、通称:ニガウリ)の出荷が増え、夏に向けて旬を迎えることにちなんでいます。
Q: なぜ5月8日が「ゴーヤーの日」なのですか?
A: 沖縄の方言である「ゴーヤー」という呼び名が、数字の「5(ゴー)8(ヤー)」という語呂合わせにぴったり合うことから、覚えやすく親しみやすいこの日が選ばれました。また、沖縄では5月頃からゴーヤーが市場に多く出回り始め、夏の食卓に欠かせない食材となる時期にあたります。
Q: ゴーヤーは沖縄でどのように親しまれていますか?
A: 沖縄料理を代表する野菜の一つであり、特に豆腐や豚肉、卵と一緒に炒めた「ゴーヤーチャンプルー」は、家庭料理としても、観光客向けのメニューとしても非常に有名です。独特の強い苦みがありますが、ビタミンC(加熱しても壊れにくい)やミネラル、食物繊維が豊富で、夏バテ防止や健康維持に役立つ食材として、古くから沖縄の人々の健康を支えてきました。
Q: ゴーヤーの苦味を和らげる方法は?
A: 苦味の原因は、種とワタの部分に多く含まれるため、これらをきれいに取り除くことがポイントです。また、薄切りにして塩もみしたり、さっと下茹でしたり、油で炒めたりすることでも苦味は和らぎます。ただし、苦味成分にも健康効果があると言われています。
日本の風景と文化を守り育てる: 松の日
松くい虫などの病害虫から日本の松を守る活動を行う社団法人「日本の松の緑を守る会」が1989年(平成元年)に制定。日付は、1981年(昭和56年)5月8日に同会の全国大会が奈良市で初めて開催されたことと、5月4日が「みどりの日」であることに続き、松の緑が一年で最も輝く時期であることにちなんでいます。

Q: 「松の日」は何を目的として制定されましたか?
A: 日本の風景を象徴する樹木であり、古くから文化や芸術、信仰の対象ともなってきた「松」を、松くい虫などの病害や環境変化から守り、その美しい緑を後世に引き継いでいくことの大切さを広く国民に訴え、松の保護活動への関心を高めることを目的としています。
Q: なぜ5月8日が「松の日」に選ばれたのですか?
A: 「日本の松の緑を守る会」の第一回全国大会が開催された記念すべき日であることと、新緑が目に鮮やかで、松の緑も特に美しく見える時期であり、「みどりの日」との連動性も考慮されたことから、この日付が選ばれました。
Q: 日本において松はどのような存在ですか?
A: 常緑樹であることから、古来より不老長寿や繁栄、吉祥の象徴とされ、門松などお正月の飾りにも用いられます。また、海岸線の「白砂青松」の景観や、日本庭園、盆栽、水墨画、能楽の舞台(松羽目)など、日本の自然景観や伝統文化・芸術に欠かせない存在です。建材や燃料としても利用されてきました。
米粉のもっちり感?「ご(5)はんパ(8)ン」: ごはんパンの日
長野県茅野市のパン店、有限会社「高原のパンやさん」が制定。日付は「ご(5)はんパ(8)ン」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ5月8日が「ごはんパンの日」なのですか?
A: 「ご(5)はん パン(≒8)」という語呂合わせから、この日が記念日として制定されました。「は」の音を数字の「8」に当てはめた、ユニークな発想です。
Q: 「ごはんパン」とは、どのようなパンですか?
A: 一般的には、小麦粉の代わりに米粉を主原料として使ったり、炊いたご飯を生地に練り込んだりして作られたパンを指すことが多いです。小麦粉のパンとは異なる、もっちりとした食感や、お米由来のほのかな甘みが特徴です。制定者である「高原のパンやさん」が具体的にどのようなパンを指しているかは不明ですが、お米を使ったパンの美味しさや可能性を広める日と言えるでしょう。
Q: 米粉パンにはどのようなメリットがありますか?
A: 小麦アレルギーの人でも食べられるグルテンフリーのパンを作ることができます(ただし製造工程での混入がないか確認が必要)。また、小麦粉パンに比べて水分量が多く、もっちり・しっとりとした食感が楽しめます。日本の米の消費拡大に貢献するという側面もあります。
許さない!「御用(58)だ!」: 万引き防止の日
万引き防止システムなどを開発・販売するセーフティ&セキュリティ株式会社(旧:株式会社ジェイエヌシー)が2009年(平成21年)に制定。日付は、江戸時代の捕物帳などで悪人を捕らえる際に発せられる言葉「御用(ごよう)だ!」と、「ご(5)よう(8)」と読む語呂合せから。
Q: なぜ5月8日が「万引き防止の日」なのですか?
A: 犯罪者を捕まえる際の掛け声「御用(ごよう)だ!」を、数字の「5(ご)8(よう)」という語呂合わせに掛け、万引きという犯罪行為を許さず、防止するという強い意志を表す日として、この日付が選ばれました。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: 小売店にとって深刻な損害となるだけでなく、社会全体の安全やモラルにも関わる「万引き」という犯罪の防止を、店舗関係者だけでなく、社会全体で考え、取り組む意識を高めることを目的としています。万引きは軽い気持ちで行われることもありますが、窃盗というれっきとした犯罪であることを啓発する日です。
Q: 万引きを防止するためにどのような対策がありますか?
A: 店舗側では、防犯カメラや防犯ゲート(万引き防止タグ)の設置、警備員の配置、従業員による声かけの徹底、見通しの良い店内レイアウトなどが有効です。地域社会としては、万引きは犯罪であるという意識の共有や、学校での規範教育、そして万引きをしてしまう背景にある問題(貧困、精神疾患、認知症など)への支援体制を考えることも重要です。
世界で最も飲まれている炭酸飲料?: コカ・コーラの日 (Coca-Cola Day)
1886年5月8日に、アメリカ・ジョージア州アトランタの薬剤師ジョン・S・ペンバートン博士によって、現在「コカ・コーラ」として知られる飲料が初めて調合され、近くの薬局でグラス1杯5セントで販売され始めたことを記念する日です。(※コカ・コーラ社が公式に制定した記念日ではありませんが、ファンの間などで祝われます)
Q: コカ・コーラはどのようにして生まれたのですか?
A: 薬剤師であったペンバートン博士が、コカの葉の抽出物やコーラの実(カフェインを含む)などを原料に、当初は頭痛や疲労回復に効く新しいシロップ(薬用酒のようなもの)として開発しました。偶然、助手がこのシロップを炭酸水で割ったところ非常に美味しかったため、ノンアルコールの炭酸飲料として販売されるようになったと言われています。
Q: 「コカ・コーラ」という名前の由来は?
A: 主な原料であった「コカ(Coca)の葉」と「コーラ(Kola)の実」から名付けられました。特徴的なロゴタイプは、ペンバートン博士の経理担当者であったフランク・M・ロビンソン氏が考案したと言われています。
Q: コカ・コーラはどのように世界的なブランドになったのですか?
A: 巧みな広告戦略、独特のボトルデザイン(コンツアーボトル)、フランチャイズシステムによる世界的な販売網の構築、そしてオリンピックやワールドカップなどの国際的なイベントへのスポンサー活動などを通じて、アメリカ文化の象徴として、また世界中の人々に愛される炭酸飲料としての地位を確立しました。