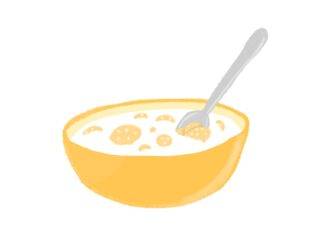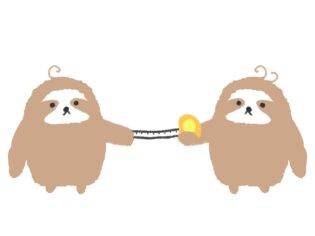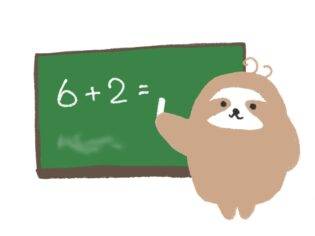5月15日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
家族の絆と大切さを世界で考える日: 国際家族デー (International Day of Families)
1993年(平成5年)9月の国連総会で制定され、翌1994年の「国際家族年」から実施されている国際デーの一つです。社会の基本的な単位である「家族」の重要性に対する国際社会の認識を高め、家族に関連する問題(貧困、教育、健康、ジェンダー平等、ワークライフバランスなど)への取り組みを促進することを目的としています。
Q: なぜ「国際家族デー」が国連によって制定されたのですか?
A: 家族は、個人の成長と幸福の基盤であり、社会の安定と発展にとっても不可欠な存在です。しかし、世界中で家族は様々な課題や変化に直面しています。国連は、こうした状況を踏まえ、家族の持つ多様な形態や機能を尊重し、家族を支援する政策やプログラムの重要性を各国政府や国際社会に訴えるために、この国際デーを制定しました。
Q: なぜ5月15日が選ばれたのですか?
A: 1993年の国連総会で、翌1994年を「国際家族年」とすることが決定された際、その年の中間点に近い5月15日を「国際家族デー」とすることが定められました。春の季節であり、家族で過ごすのに適した時期であることも考慮された可能性があります。
Q: この日にはどのようなことが行われますか?
A: 世界各地で、家族の重要性や直面する課題をテーマにしたセミナー、ワークショップ、写真展、地域イベントなどが開催されます。また、国連や各国政府、NGOなどが、家族支援政策に関する議論や提言を行います。家族の絆を深め、感謝の気持ちを伝え合う良い機会ともされています。
27年間の米国統治から祖国復帰へ: 沖縄本土復帰記念日
1972年(昭和47年)5月15日に、第二次世界大戦後27年間にわたってアメリカ合衆国の施政権下に置かれていた沖縄県(琉球諸島及び大東諸島)が、日本国に復帰したことを記念する日です。これは、1971年6月17日に調印された「沖縄返還協定」の発効によるものです。
Q: なぜ沖縄はアメリカの統治下に置かれていたのですか?
A: 第二次世界大戦における沖縄戦の後、日本の敗戦に伴い、沖縄はアメリカ軍の占領下に置かれました。その後、1952年のサンフランシスコ平和条約発効により日本は独立を回復しましたが、沖縄は日本の潜在主権下にあるものの、引き続きアメリカの施政権下に置かれることになりました。これは、冷戦下の東アジアにおけるアメリカの軍事戦略上の重要性などが理由でした。
Q: 沖縄の本土復帰はどのように実現したのですか?
A: アメリカの統治下で、沖縄県民は日本国民としての権利が制限されるなど多くの困難を経験しました。そのため、祖国である日本への復帰を求める県民運動がねばり強く展開されました。日本政府もアメリカ政府との間で返還交渉を続け、ベトナム戦争などを背景とした国際情勢の変化や、日米関係の進展などを経て、1971年に返還協定が調印され、翌1972年5月15日に復帰が実現しました。
Q: この日は沖縄にとってどのような意味を持ちますか?
A: 27年ぶりに日本国民としての権利を回復し、祖国に復帰した歴史的な日であり、平和への強い願いを再確認する重要な節目です。沖縄県では、この日を記念する式典や関連イベントが開催されますが、同時に、復帰後も残る米軍基地問題など、沖縄が抱える課題について考える日ともなっています。
乳酸菌研究のパイオニア生誕: ヨーグルトの日
ヨーグルトをはじめとする乳製品メーカーである明治乳業株式会社(現:株式会社 明治)が制定。日付は、ヨーグルトに含まれる乳酸菌(特にブルガリア菌)が健康や長寿に貢献する可能性を示唆し、その価値を世界に広めたロシア(現ウクライナ)出身の微生物学者・免疫学者イリヤ・メチニコフ(Ilya Mechnikov)博士の誕生日(1845年5月15日)にちなんでいます。
Q: なぜ5月15日が「ヨーグルトの日」なのですか?
A: ヨーグルトの健康効果、特に長寿との関連性を科学的に研究し、世界的にヨーグルトへの関心を高めるきっかけを作ったイリヤ・メチニコフ博士の誕生日(1845年5月15日)を記念して、この日が選ばれました。
Q: メチニコフ博士はヨーグルトに関してどのような発見をしましたか?
A: メチニコフ博士は、ブルガリアなどの地域に長寿者が多いことに注目し、彼らが日常的に摂取している発酵乳(ヨーグルト)に含まれる乳酸菌が、腸内で有害な腐敗菌の増殖を抑え、自家中毒(腸内腐敗による毒素)を防ぐことで老化を遅らせ、長寿に貢献するのではないかという「不老長寿説」を提唱しました。この説は、その後の腸内細菌研究や発酵乳製品の普及に大きな影響を与えました。(メチニコフ博士は食細胞の研究による免疫機構の解明で1908年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています)
Q: この記念日は誰が制定したのですか?
A: 日本でヨーグルト製品を長年にわたり製造・販売してきた大手企業である明治乳業株式会社(現:株式会社 明治)が、ヨーグルトの普及と、その健康価値や食文化への貢献を広く啓発する目的で制定しました。
女性の脚を美しく見せた革命的素材: ストッキングの日
1940年(昭和15年)5月15日に、アメリカの大手化学メーカーであるデュポン社が、世界で初めて開発した完全な合成繊維「ナイロン」で作られたストッキングを、全米のデパートなどで一斉に発売したことを記念する日です。
Q: なぜ5月15日が「ストッキングの日」なのですか?
A: 1940年(昭和15年)の5月15日に、デュポン社が「鋼鉄よりも強く、クモの糸より細い」と宣伝された画期的な新素材ナイロンを使ったストッキングを全米で発売開始した、まさにその歴史的な日付に由来しています。(特定の制定団体はありません)
Q: ナイロンストッキングの登場は、なぜ画期的だったのですか?
A: それまでのストッキングは、主に高価で繊細な天然素材である絹(シルク)で作られていました。ナイロンは、シルクに似た光沢や滑らかさを持ちながら、はるかに丈夫で伝線しにくく、価格も手頃でした。また、薄手で透明感があり、脚を美しく見せる効果も高かったため、発売と同時に女性たちの間で爆発的な人気となり、ファッションに革命をもたらしました。「ナイロン(Nylons)」という言葉がストッキングの代名詞になるほどでした。
Q: その後ストッキングはどうなりましたか?
A: 第二次世界大戦中はナイロンが軍需物資(パラシュートなど)に転用されたため生産が中止されましたが、戦後復活し、さらにパンティーストッキング(パンスト)が登場するなど進化を続け、女性のファッションに欠かせないアイテムとして定着しました。素材もポリウレタンなどが加わり、機能性(着圧、保温、伝線しにくいなど)も多様化しています。
日本サッカー新時代のキックオフ!: Jリーグの日
日本のプロサッカーリーグである「Jリーグ」を運営する公益社団法人 日本プロサッカーリーグが、リーグ開幕20周年を記念して2013年(平成25年)に制定。日付は、1993年(平成5年)5月15日に、国立競技場でJリーグの開幕戦(ヴェルディ川崎 vs 横浜マリノス)が華々しく行われたことに由来します。

Q: なぜ5月15日が「Jリーグの日」なのですか?
A: 1993年(平成5年)の5月15日に、日本初のプロサッカーリーグである「Jリーグ」が、多くの注目と期待を集めて国立競技場で開幕したことを記念しています。この日は日本のサッカー界にとって、新たな時代の幕開けとなった歴史的な一日です。
Q: Jリーグの開幕は、日本サッカーにどのような影響を与えましたか?
A: Jリーグの開幕は、それまでアマチュアが主体だった日本サッカー界にプロフェッショナリズムをもたらし、競技レベルの向上、選手の待遇改善、スタジアム環境の整備などを大きく進展させました。また、ジーコ、ラモス瑠偉、三浦知良といったスター選手の活躍や、華やかな演出も相まって、空前のサッカーブームを巻き起こし、サッカーを国民的な人気スポーツへと押し上げました。地域に根ざしたクラブ運営も、スポーツを通じた地域貢献のモデルとなりました。
Q: 開幕戦はどのような試合でしたか?
A: 開幕戦は、ヴェルディ川崎(現:東京ヴェルディ)と横浜マリノス(現:横浜F・マリノス)という、当時の人気・実力を兼ね備えたチーム同士の対戦となりました。試合は1-2で横浜マリノスが勝利しましたが、華やかなオープニングセレモニーや、高いレベルのプレー、そして満員の観衆の熱気は、Jリーグの輝かしいスタートを象徴するものでした。
手作りお菓子の定番を祝う?: 青春七五三
制定した団体や明確な由来は不明ですが、5月15日を「青春七五三」と呼ぶ動きがあるようです。これは、15歳(中学3年生頃)を、子どもから大人へと成長していく過程における一つの節目と捉え、その成長を祝い、将来への希望や決意を新たにする日、といった意味合いが込められていると考えられます。(※広く認知された記念日ではありません)
Q: なぜ「青春七五三」と呼ばれるのですか?
A: 7歳、5歳、3歳で行う伝統的な「七五三」になぞらえて、15歳という思春期・青年期の入り口にあたる年齢を、人生の新たな節目として祝おうという発想から生まれた造語と考えられます。「青春」という言葉が、この時期特有の多感さやエネルギーを表しています。
Q: この日にはどのようなことをするのが良いでしょうか?
A: 公式な行事などはありませんが、15歳を迎える(または迎えた)本人が、これまでの成長を振り返り、将来の夢や目標について考えたり、家族や友人、恩師などに感謝の気持ちを伝えたりする機会とするのは良いかもしれません。周りの大人も、その成長を温かく見守り、応援する気持ちを示す日と捉えることができます。