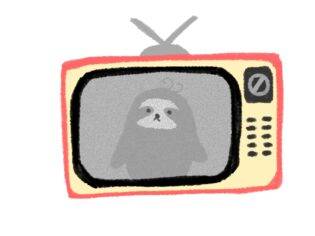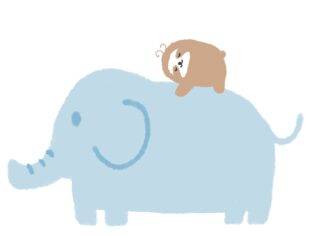8月20日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
道路交通安全の礎、日本初の自動信号機設置: 交通信号設置記念日
1931年(昭和6年)のこの日、東京・銀座の尾張町交差点(現在の銀座4丁目交差点)・京橋交差点などに、日本初の3色灯の自動交通信号機が設置された。

Q: なぜこの日に自動信号機が設置されたのですか?
A: 1931年(昭和6年)8月20日に、当時の東京市の主要な交差点であった銀座尾張町(現:銀座4丁目)や京橋などに、初めて3色灯(赤・黄・青)を用いた自動交通信号機が設置・稼働を開始した歴史的な出来事に由来します。
Q: 設置された信号機はどのようなものでしたか?
A: アメリカから輸入されたもので、現在のものと同様に赤・黄・青の3色が順番に点灯する仕組みでした。ただし、当時はまだ左側通行だったため、色の配置が現在とは逆(右から赤・黄・青)だったと言われています。
Q: 信号機が設置される前はどのように交通整理をしていたのですか?
A: 交通量の多い交差点では、警察官が手信号で車両や歩行者の整理を行っていました。自動車の増加に伴い、より効率的で安全な交通整理方法として自動信号機が導入されました。
マラリア媒介蚊発見、感染症研究の転換点: 蚊の日・モスキートデー
1897年(明治30年)のこの日、イギリスの細菌学者ロナルド・ロスが、羽斑蚊(ハマダラカ)類の蚊の胃の中からマラリアの原虫を発見した。
Q: ロナルド・ロスの発見は何が重要だったのですか?
A: この発見により、マラリアが蚊によって媒介されることが科学的に証明されました。それまで原因不明とされていたマラリアの感染経路が解明されたことで、蚊の駆除や予防策の開発につながり、感染症対策に大きな進歩をもたらしました。ロスはこの功績により1902年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。
Q: なぜ「蚊の日」または「モスキートデー」と呼ばれるのですか?
A: マラリアという病気の原因解明において「蚊(Mosquito)」が決定的な役割を果たした、ロナルド・ロスの歴史的な発見があった日であることから、この名前で呼ばれています。
Q: マラリアはどのような病気ですか?
A: マラリア原虫を持つハマダラカに刺されることで感染する病気で、高熱、悪寒、頭痛、嘔吐などの症状を引き起こします。主に熱帯・亜熱帯地域で流行しており、現在でも世界的に重要な感染症の一つです。適切な予防と治療が必要です。
語呂合わせで祝う、父親への感謝の日: 親父の日
株式会社トップコーチングスタジアムが制定。日付は8月20日を「0820」として「親父(オヤジ)」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月20日が「親父の日」なのですか?
A: 日付の「0820」を「お(0)や(8)じ(20)」と読む語呂合わせから、人材育成コンサルティングなどを行う株式会社トップコーチングスタジアムが制定しました。
Q: 制定した会社の目的は何ですか?
A: 同社は父親の生き方や子育てへの関わり方を支援する活動も行っており、世の中の「親父(父親)」にエールを送り、その存在の大きさや大切さを再認識するきっかけの日とすることを目的としています。
Q: 「父の日」や「パパの日」との違いは何ですか?
A: 6月の「父の日」は商業的な起源を持ち広く定着しています。8月8日の「パパの日」は現代的な父親像を応援する意味合いがあります。「親父の日」は、より日本的な父親像(親父)に焦点を当て、その生き方や役割を考える日、というニュアンスがあるかもしれません。
北九州発祥の味、総料理長の誕生日を記念: 瑠璃カレーの日
新九協同株式会社が制定。北九州発祥の元祖生カレーを生んだ同社の総料理長の名を冠した「瑠璃カレー」を多くの人に食べてもらい、まちおこしやボランティア支援に活かすことが目的。日付は敬意を表して総料理長の誕生日である8月20日から。
Q: なぜ総料理長の誕生日が記念日になったのですか?
A: 「元祖生カレー」という独自のカレーを開発し、その名を冠した「瑠璃カレー」を生み出した総料理長への敬意を表し、その功績を称えるために、彼の誕生日である8月20日を記念日として新九協同株式会社が制定しました。
Q: 「元祖生カレー」とはどのようなカレーですか?
A: 一般的な情報からは詳細不明ですが、「生」という言葉から、加熱処理を最小限に抑えたり、フレッシュな素材やスパイス感を重視したりした、独特の製法や風味を持つカレーと推測されます。北九州発祥のご当地グルメの一つとしてPRされています。
Q: この記念日の目的は何ですか?
A: 地域(北九州)発祥のユニークなカレー「瑠璃カレー」の知名度を高め、より多くの人にその味を知ってもらうこと、そしてその売上などを通じて、地域の活性化(まちおこし)やボランティア活動の支援につなげることを目的としています。
情報の普及を支える協会の設立記念日: 日本放送協会 (NHK) 設立記念日
1926年(大正15年)8月20日、社団法人日本放送協会(NHK)が設立されました。これは、前年に東京・大阪・名古屋でそれぞれ開始されたラジオ放送事業を全国的に統合・運営するための組織として設立されたものです。
Q: なぜ日本放送協会(NHK)が設立されたのですか?
A: ラジオ放送という新しいメディアを、公共的な目的のために全国規模で普及・発展させる必要があったためです。各地に設立されていた放送局を一つにまとめることで、より効率的で安定した放送網の構築を目指しました。
Q: NHKの役割は何ですか?
A: 公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、豊かで良い番組を制作・放送することを使命としています。ニュース報道、教育番組、文化・教養番組、福祉番組、災害情報など、国民生活に不可欠な情報を公平・公正に提供する役割を担っています。
Q: NHKはどのように運営されているのですか?
A: 主な財源は、視聴者から公平に負担される受信料です。国からの交付金や広告収入に頼らないことで、特定のスポンサーや政府の意向に左右されず、自主・自律性を保つ仕組みになっています。