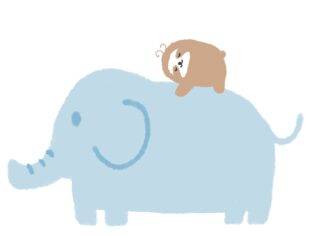8月28日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本のテレビ放送新時代の幕開け: 民放テレビスタートの日
1953年(昭和28年)8月28日午前11時20分、日本テレビ(JOAX-TV)が民間放送として初のテレビ放送を正式に開始。
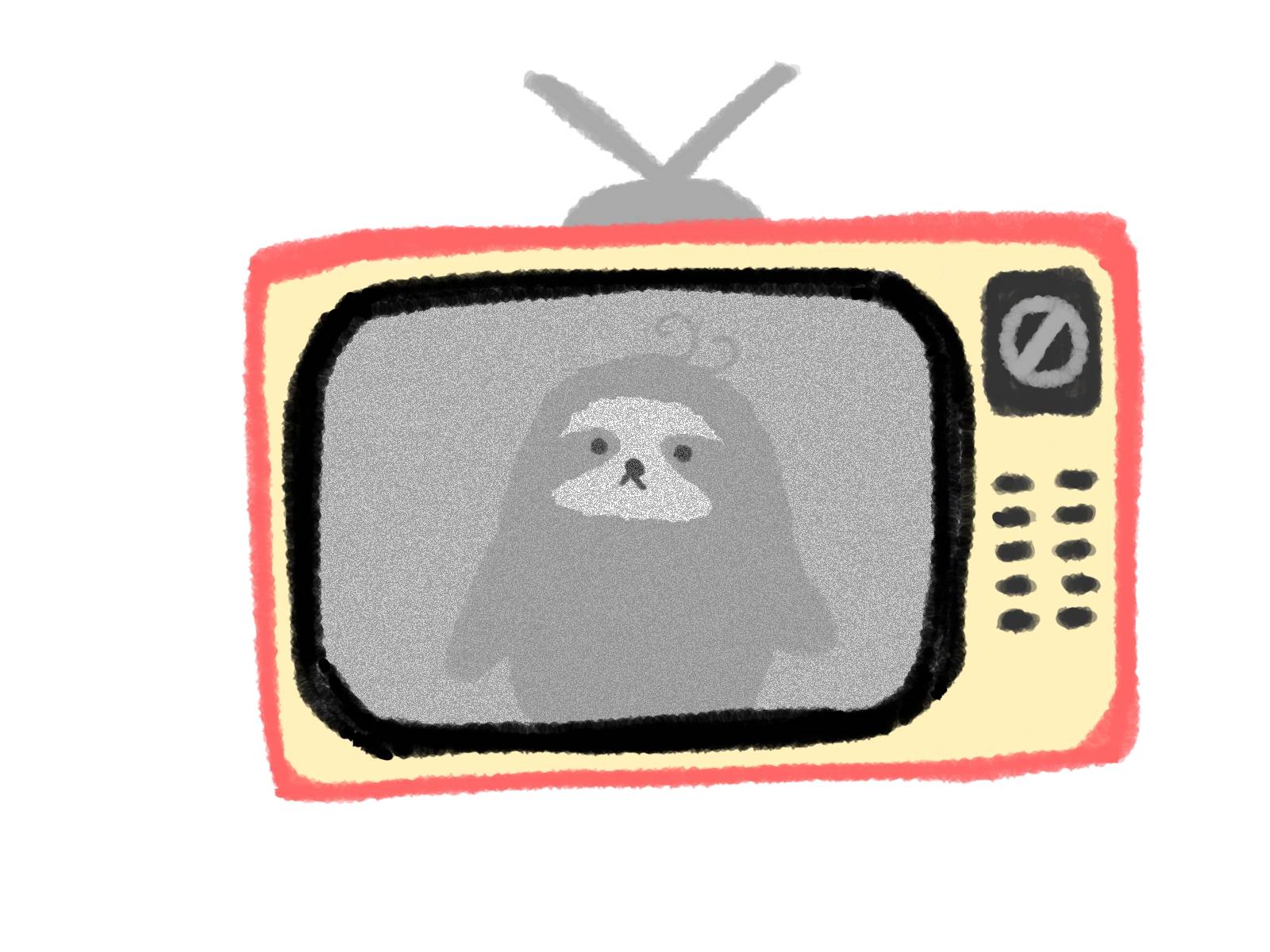
Q: なぜこの日が「民放テレビスタートの日」なのですか?
A: 1953年(昭和28年)8月28日に、日本で初めての民間放送によるテレビ局である「日本テレビ放送網(NTV)」が、本放送を開始した歴史的な日であるためです。これにより、NHK(公共放送)に加えて、広告収入で運営されるテレビ放送が始まりました。
Q: 最初に放送された番組は何でしたか?
A: 開局を告げるアナウンスに続き、アメリカから提供された短編映画などが放送された後、開局記念式典の中継などが行われました。当時のテレビは非常に高価で、一般家庭への普及はまだ先でしたが、街頭テレビには多くの人が集まったと言われています。
Q: 民放テレビの開始は社会にどのような影響を与えましたか?
A: 娯楽番組やスポーツ中継、そしてコマーシャル(CM)など、NHKとは異なる多様なコンテンツが登場し、テレビがお茶の間の中心となる時代へと導きました。広告を通じて新しい商品やライフスタイルが紹介され、消費文化の発展にも大きな影響を与えました。
テレビ広告の誕生、CM文化の始まり: テレビCMの日
一般社団法人・日本民間放送連盟(民放連)が2005年(平成17年)に制定。1953年(昭和28年)のこの日に開始された民放の日本テレビ(JOAX-TV)で、日本初のテレビCMが放送された。
Q: 日本初のテレビCMはどのようなものでしたか?
A: 1953年8月28日、日本テレビの本放送開始日の正午の時報の際に放送された、精工舎(現在のセイコーグループ)の時計のCMでした。「精工舎の時計が正午をお知らせします」というアナウンスと共に、時計の文字盤と商品ロゴが映し出される、わずか30秒ほどのシンプルなものでした。
Q: なぜ「テレビCMの日」が制定されたのですか?
A: 日本民間放送連盟が、民放テレビがスタートし、同時に日本初のテレビCMが放送されたこの日を記念し、テレビCMが持つ情報伝達力や文化的な役割、経済への貢献などを再認識してもらうために2005年に制定しました。
Q: テレビCMはどのように変化してきましたか?
A: 当初の生CMや静止画中心のものから、フィルム、VTR、そしてCG技術の発展に伴い、映像表現は格段に進化しました。時代ごとの流行や社会情勢を反映し、単なる商品紹介にとどまらず、ユーモアや感動、話題性を呼ぶエンターテインメントとしても楽しまれるようになっています。
和の職人技が洋の楽器を生んだ日: バイオリンの日
1880年(明治13年)のこの日、国産バイオリンがはじめて完成された日。日本初のバイオリン第1号を完成させたのは、三味線職人の松永定次郎氏。
Q: なぜ三味線職人がバイオリンを作ったのですか?
A: 明治維新後の文明開化の流れの中で、西洋音楽が日本にもたらされました。当時、輸入されたバイオリンの修理依頼を受けた三味線職人の松永定次郎氏が、その構造に興味を持ち、見よう見まねで製作を試みました。三味線製作で培った木工技術や勘を活かし、1880年8月28日に日本で初めてとなる国産バイオリンを完成させたとされています。
Q: 国産バイオリンの誕生はどのような意味がありましたか?
A: それまで高価な輸入品に頼るしかなかったバイオリンが国内で製作できるようになったことは、日本における西洋音楽の普及にとって大きな一歩でした。松永氏の成功は、他の楽器職人にも影響を与え、日本の楽器製造業の発展の礎となりました。
Q: 松永定次郎氏はその後どうなりましたか?
A: 彼はその後、名古屋でバイオリン製造の会社を設立し、弟子の育成にも力を注ぎました。その弟子の中から、後の日本の弦楽器製作をリードする人材(現在のスズキバイオリンの創業者・鈴木政吉など)が育っていきました。
専門知識で天気を伝えるプロフェッショナルの誕生: 気象予報士の日
1994年(平成6年)のこの日、第1回の気象予報士国家試験が行われた。
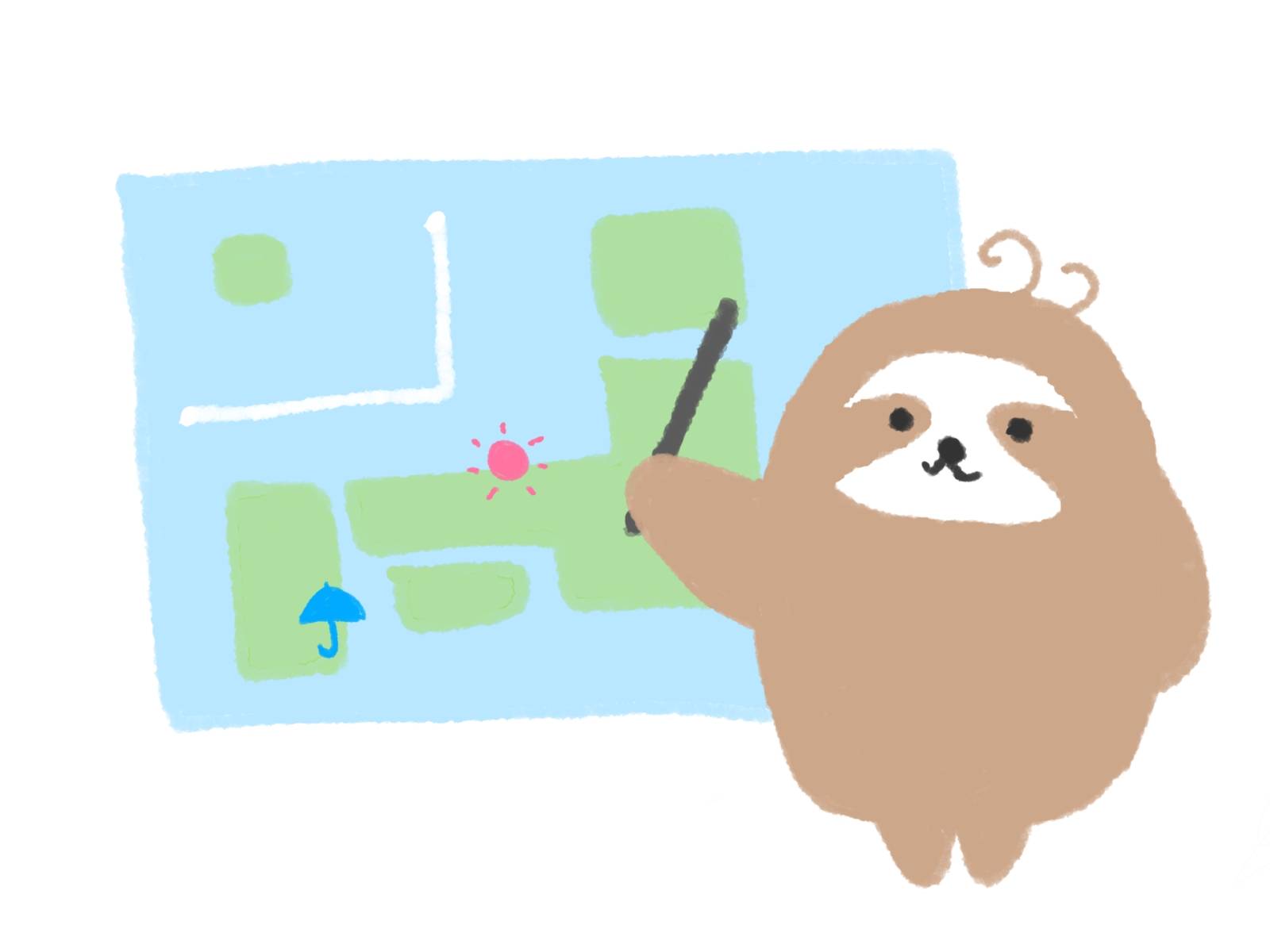
Q: なぜこの日が「気象予報士の日」なのですか?
A: 1993年の気象業務法改正により創設された国家資格「気象予報士」の、第1回目となる資格試験が1994年8月28日に実施されたことに由来します。
Q: 気象予報士制度はなぜ導入されたのですか?
A: それまでは気象庁だけが一般向けの天気予報を発表することができましたが、多様化する社会のニーズに応え、より詳細で地域に密着した気象情報を提供できるようにするため、一定の知識と技術を持つ専門家として気象予報士に予報業務を許可する制度が導入されました。これにより、民間気象会社などが独自の予報を発表できるようになりました。
Q: 気象予報士の試験は難しいのですか?
A: はい、合格率が平均して5%程度と、非常に難易度の高い国家資格の一つとされています。気象に関する幅広い専門知識(気象学、予報技術、関連法規など)が問われます。
触れずに奏でる不思議な電子楽器の発明者を記念: テルミンの日
テルミン奏者である川口淳史氏が制定。日付はテルミンの発明者であるロシアの物理学者レフ・セルゲイビッチ・テルミン博士の誕生日から。
Q: テルミンとはどのような楽器ですか?
A: 世界初の電子楽器の一つとされています。最大の特徴は、楽器本体に直接触れることなく、本体から伸びる2本のアンテナに奏者が手を近づけたり遠ざけたりすることで、音の高さ(ピッチ)と音量(ボリューム)をコントロールして演奏する点です。独特の浮遊感のある音色を持っています。
Q: なぜ発明者の誕生日が記念日になったのですか?
A: このユニークな楽器「テルミン」を発明したロシアの物理学者であり音楽家でもあるレフ・テルミン博士(1896年8月28日生まれ)の功績を称え、テルミンという楽器の魅力を広めるために、日本のテルミン奏者・川口淳史氏が博士の誕生日にちなんで制定しました。
Q: テルミンはどのような音楽で使われていますか?
A: その独特な音色から、クラシック音楽、現代音楽、実験音楽、ポップス、映画音楽(特にSF映画やホラー映画の効果音など)といった幅広いジャンルで使われています。また、楽器自体のパフォーマンス性も注目されています。
キャラディネートを提唱、ファッションの楽しみ方を広める: キャラディネートの日
株式会社グレイスが制定。「ファッションの中にキャラクターを自然に取り入れ、自分だけの個性を楽しむ」という「キャラディネート」を多くの人に知ってもらい、楽しんでもらうことが目的。日付は8月28日を「828」として「洋服(ようふく)」と読み、さらに英語の「fashion(ファッション)」の頭文字「Fa」を「8」と見立てて。
Q: 「キャラディネート」とは何ですか?
A: 「キャラクター」と「コーディネート」を組み合わせた造語です。アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターがデザインされた服やアクセサリー、小物を、日常のファッションの中に自然に取り入れて楽しむスタイルのことを指します。
Q: なぜ8月28日が「キャラディネートの日」なのですか?
A: 複数の語呂合わせ・見立てが組み合わされています。まず「828」を「洋服(ようふく)」と読みます。さらに、英語の「fashion」の頭文字「Fa」をアルファベットの順番(F=6, a=1)ではなく、形状が似ている数字の「8」に見立てています。このユニークな発想から、キャラクターアパレルなどを企画・販売する株式会社グレイスが制定しました。
Q: キャラディネートを楽しむポイントは何ですか?
A: キャラクターが大きくプリントされたものだけでなく、ワンポイントのデザインやモチーフを取り入れたアイテム、キャラクターをイメージした色使いなどで、さりげなく「好き」を表現できるのが魅力です。子供だけでなく、大人の間でもファッションの楽しみ方の一つとして広がっています。