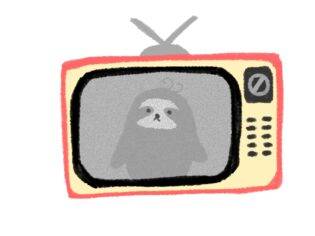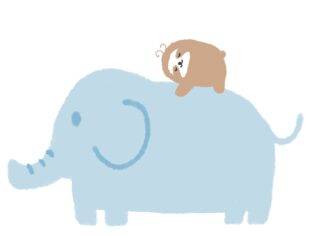8月29日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
国宝や重要文化財を守る礎、法律施行を記念: 文化財保護法施行記念日
1950年(昭和25年)のこの日、国宝・重要文化財などを保護・活用するための基本となる法律「文化財保護法」が施行された。
Q: なぜ文化財保護法が必要だったのですか?
A: 第二次世界大戦後の社会混乱や、開発による文化財の破壊・消失が懸念されたためです。特に、1949年の法隆寺金堂壁画の焼損事故は、国民に大きな衝撃を与え、文化財保護の機運を高める直接的な契機となりました。この法律により、文化財を国民全体の財産として体系的に保護・活用する仕組みが整えられました。
Q: 文化財保護法ではどのようなものが「文化財」として定義されていますか?
A: 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書などの「有形文化財」、演劇、音楽、工芸技術などの「無形文化財」、衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などの「民俗文化財」、史跡、名勝、天然記念物などの「記念物」、周囲の環境と一体となって歴史的風致を形成している「文化的景観」、城下町、宿場町、門前町などの「伝統的建造物群」などが含まれます。
Q: この法律によって、文化財の扱いはどう変わりましたか?
A: 国宝や重要文化財などの指定制度が整備され、保存のための調査や修理に対する国庫補助が行われるようになりました。また、文化財の公開や活用も促進され、博物館や美術館での展示、史跡公園の整備などを通じて、多くの人々が文化財に触れる機会が増えました。
急勾配を力強く登る、日本初の鋼索鉄道開業: ケーブルカーの日
1918年(大正7年)のこの日、大阪電気軌道(現:近畿日本鉄道(近鉄))の子会社・生駒鋼索鉄道が、日本初のケーブルカー(現:近鉄生駒ケーブル)を開業させた。
Q: 日本で最初のケーブルカーはなぜ生駒山に作られたのですか?
A: 生駒山の山上には、古くから信仰を集める宝山寺(生駒聖天)があり、多くの参拝者が訪れていました。しかし、麓からの道のりは急峻で険しかったため、参拝客の輸送手段として、また、生駒山上遊園地(当時)へのアクセス手段として、急勾配を登ることができるケーブルカーが建設されました。
Q: ケーブルカーはどのような仕組みで動いているのですか?
A: 車両自体には動力エンジンは搭載されていません。線路の間に敷設された太い鋼索(ケーブル)に車両が取り付けられており、山の上にある強力なモーターを備えた巻上所(機械室)でケーブルを巻き上げたり、送り出したりすることで車両を動かします。多くの場合、2台の車両がケーブルで結ばれ、互いが重りとなって昇り降りする「つるべ式」が採用されています。
Q: 現在、日本でケーブルカーはどのような場所で見られますか?
A: 主に山岳地帯の観光地や、山腹・山頂にある寺社への参拝路線として運行されています。例えば、東京の高尾山、神奈川の大山、兵庫の六甲山、富山の立山黒部アルペンルートなど、多くの場所で活躍しており、景色を楽しむ乗り物としても人気があります。
廃藩置県を経て誕生、県の始まりを祝う郷土の日: 秋田県の記念日
秋田県が1965年(昭和40年)に制定。明治4年7月14日(新暦1871年8月29日)、廃藩置県により「秋田県」という名前が初めて使われた。
Q: なぜこの日が「秋田県の記念日」とされているのですか?
A: 明治政府による廃藩置県(藩を廃止して府や県を置く政策)によって、1871年(明治4年)の旧暦7月14日(新暦の8月29日)に、それまでの秋田藩などが統合され、初めて「秋田県」という名称の行政区画が設置された歴史的な日に由来します。
Q: 廃藩置県は日本にとってどのような意味がありましたか?
A: 江戸時代の藩を中心とした地方分権的な体制から、明治政府による中央集権的な統一国家へと移行するための重要な改革でした。これにより、全国的な行政制度や税制、軍制の整備などが可能になりました。
Q: 秋田県ではこの記念日にどのようなことが行われますか?
A: 県民が郷土秋田への関心と理解を深め、愛着と誇りを持ってより豊かな県を築くことを目指す日とされています。県有施設の無料開放や割引、記念イベントなどが実施されることがあります。
夏のスタミナ補給!語呂合わせで楽しむ食文化: 焼肉の日
「全国焼肉協会」(JY)が1993年(平成5年)に制定。日付は「や(8)きに(2)く(9)」と読む語呂合わせから。

Q: なぜ8月29日が「焼肉の日」なのですか?
A: 日付の「8(や)き2(に)9(く)」と読む語呂合わせから、全国焼肉協会が1993年に制定しました。夏の暑さで体力が落ちやすい時期に、焼肉を食べてスタミナをつけてもらいたいという願いも込められています。
Q: 全国焼肉協会はどのような団体ですか?
A: 焼肉店経営者や関連企業などが加盟する業界団体です。焼肉業界の健全な発展、焼肉文化の普及・啓発、衛生管理や経営に関する情報提供などを行っています。
Q: 日本で焼肉が広まったのはいつ頃からですか?
A: 肉食文化自体は古くからありましたが、現在のようなスタイル(薄切り肉を網や鉄板で焼き、タレをつけて食べる)の焼肉が広く普及したのは、戦後の食糧事情の改善や、在日コリアンの食文化の影響などが大きいと言われています。高度経済成長期以降、外食産業の発展とともに、家族や仲間と楽しむ人気の食事スタイルとして定着しました。
低カロリー高タンパク、語呂合わせで魅力をPR: 馬肉を愛する日
株式会社若丸が制定。日付は「ば(8)にく(29)」(馬肉)と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月29日が「馬肉を愛する日」なのですか?
A: 「ば(8)にく(29)」と読む語呂合わせから、馬肉専門の食品加工・販売会社である株式会社若丸が制定しました。馬肉の美味しさや魅力をより多くの人に知ってもらうことが目的です。
Q: 馬肉にはどのような栄養的な特徴がありますか?
A: 牛肉や豚肉に比べて、高タンパク質でありながら、低カロリー・低脂肪であるのが大きな特徴です。また、疲労回復に役立つグリコーゲンや、貧血予防に効果的な鉄分も豊富に含まれています。ヘルシーな食肉として注目されています。
Q: 馬肉はどのように食べられていますか?
A: 新鮮な馬肉を生で食べる「馬刺し」が有名で、特に熊本県や長野県、福島県会津地方などで郷土料理として親しまれています。部位によって赤身、霜降り、タテガミ(コウネ)などがあり、それぞれ異なる味わいを楽しめます。他にも、加熱して食べる「桜鍋」(すき焼き風の鍋)などもあります。
高級食材フグの新たな楽しみ方、語呂合わせでPR: 焼きふぐの日
料理店「心・技・体 うるふ」が制定。日付は「や(8)きふ(2)ぐ(9)」(焼きふぐ)と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月29日が「焼きふぐの日」なのですか?
A: 「や(8)きふ(2)ぐ(9)」と読む語呂合わせから、焼きふぐ料理を提供することで知られる料理店「心・技・体 うるふ」(元横綱・千代の富士(九重親方)が監修)が制定しました。
Q: 「焼きふぐ」とはどのような料理ですか?
A: ふぐの身を、網や鉄板で焼いて食べる料理スタイルです。一般的にふぐ料理というと、刺身(てっさ)や鍋(てっちり)が有名ですが、焼くことでふぐの旨味が凝縮され、香ばしさやプリプリとした食感を楽しめるのが特徴です。タレや塩など、店によって様々な味付けで提供されます。
Q: ふぐ料理はなぜ特別な調理が必要なのですか?
A: ふぐの種類によっては、内臓(特に肝臓や卵巣)や皮などに猛毒であるテトロドトキシンが含まれているためです。安全に食べるためには、専門的な知識と技術を持った「ふぐ調理師(ふぐ取扱者)」が、有毒部位を正確に除去する調理を行う必要があります。
宝塚歌劇の不朽の名作、初演日を記念: ベルばらの日
1974年(昭和49年)のこの日、宝塚歌劇で『ベルサイユのばら』(通称:ベルばら)が初演された。『ベルサイユのばら』は池田理代子原作の漫画で、フランス革命前から革命前期を舞台に、男装の麗人オスカルとフランス王妃マリー・アントワネットらの人生を描く、史実を基にしたフィクション作品。
Q: なぜ『ベルサイユのばら』の宝塚初演が記念日となっているのですか?
A: 1974年8月29日に初演された宝塚歌劇版『ベルサイユのばら』は、空前の大ヒットとなり、社会現象とも言えるほどのブームを巻き起こしました。宝塚歌劇団の歴史においても、新たなファン層を開拓し、その後の公演スタイルにも大きな影響を与えた、画期的な作品であったためです。
Q: 宝塚版『ベルばら』の成功の要因は何だったと考えられますか?
A: 池田理代子氏による原作漫画の絶大な人気に加え、男装の麗人オスカルという宝塚の男役スターにぴったりのキャラクター、マリー・アントワネットやフェルゼンといった華やかな登場人物、フランス革命というドラマチックな歴史背景、豪華絢爛な衣装や舞台装置などが、観客を強く魅了したと考えられます。
Q: 『ベルサイユのばら』はどのような物語ですか?
A: 18世紀後半のフランス、革命前夜のベルサイユ宮殿を主な舞台としています。王妃マリー・アントワネットやスウェーデン貴族フェルゼン、そして架空の人物でありながら物語の中心となる男装の近衛隊長オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェと、彼女を支える幼馴染アンドレ・グランディエの、激動の時代における愛と人生、そして革命へと向かう歴史の流れを描いた壮大な物語です。
核兵器なき世界への願い、実験場閉鎖を記憶する国際デー: 核実験に反対する国際デー
2009年12月の国連総会で制定された国際デー。日付は、1991年8月29日に、旧ソ連最大の核実験場であったカザフスタンのセミパラチンスク核実験場が閉鎖されたことにちなみます。核兵器の実験がもたらす壊滅的な影響(環境破壊、健康被害など)への認識を高め、核実験の全面禁止と核兵器廃絶の必要性を国際社会に訴える日です。
Q: なぜセミパラチンスク核実験場の閉鎖が重要なのですか?
A: セミパラチンスク核実験場では、ソ連時代に40年以上にわたり数百回もの核実験(大気圏内・地下)が行われ、周辺住民や環境に甚大な被害をもたらしました。その閉鎖は、冷戦終結後の核軍縮への動きを象徴する出来事であり、核実験による悲劇を繰り返さないという国際的な決意を示す上で重要な意味を持ちました。
Q: 核実験は現在も行われているのですか?
A: 多くの国が核実験を停止していますが、包括的核実験禁止条約(CTBT)はまだ発効しておらず、一部の国では核実験が続けられています。核兵器が存在する限り、その使用や実験のリスクはなくならず、完全な禁止と廃絶が求められています。
Q: この国際デーに私たちにできることはありますか?
A: 核兵器や核実験がもたらす非人道的な結果について学び、関心を持つことが第一歩です。関連するニュースやドキュメンタリーを見たり、被爆者や被害者の声に耳を傾けたりすること、そして核兵器廃絶を訴える世論を高めるために、自分の考えを周りの人と共有することなどが考えられます。
ゆでたまご先生公認!友情パワーで戦う超人ヒーローの日: キン肉マンの日
人気漫画『キン肉マン』の記念日。作者であるゆでたまご(嶋田隆司氏、中井義則氏)によって公認されています。日付は「キン(曜日)」と「肉(29)」の語呂合わせから。1979年に『週刊少年ジャンプ』で連載が開始されたのが金曜日であったことも由来の一つとされています。
Q: 『キン肉マン』はどのような漫画ですか?
A: 地球を守るヒーロー(超人)でありながら、ドジでマヌケなキン肉星の王子キン肉マン(本名:キン肉スグル)が、仲間たちとの友情パワーを武器に、次々と現れる強敵超人たちとリング上で戦い、成長していく物語です。プロレスをモチーフにした熱いバトルと、個性豊かな超人たち、随所に散りばめられたギャグが特徴です。
Q: なぜ「キン肉マンの日」が制定されたのですか?
A: 長年にわたり多くのファンに愛され続けている作品『キン肉マン』を、作者とファンが一緒になって祝い、盛り上げるための記念日として制定されました。この日には、関連イベントやキャンペーン、新情報の発表などが行われることがあります。
Q: 『キン肉マン』の人気を支える魅力は何でしょうか?
A: 主人公キン肉マンの人間味あふれる(超人ですが)キャラクター、ロビンマスク、テリーマン、ラーメンマン、ウォーズマンといった魅力的な仲間やライバル超人たち、「火事場のクソ力」に代表される逆境からの大逆転劇、そして何よりも「友情」というテーマが一貫して描かれている点が、世代を超えて読者の心を掴む理由と考えられます。