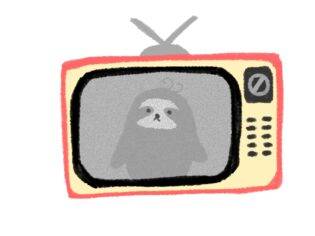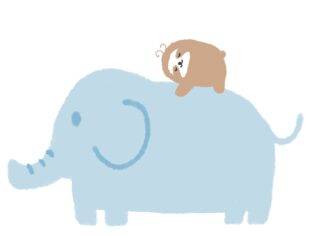8月27日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
国民的映画シリーズの幕開け、フーテンの寅さん誕生: 『男はつらいよ』の日
1969年(昭和44年)のこの日、監督・山田洋次、主演・渥美清の映画『男はつらいよ』シリーズの第1作が公開。
Q: なぜこの日が『男はつらいよ』の日なのですか?
A: 1969年8月27日に、国民的人気映画シリーズ『男はつらいよ』の記念すべき第1作目が公開されたことに由来します。ここから約27年間、全48作(+特別編)にわたる長寿シリーズが始まりました。
Q: 『男はつらいよ』シリーズはなぜこれほど長く愛されたのですか?
A: 主人公・車寅次郎(寅さん)の破天荒ながらも憎めない人柄、日本各地を旅する中で出会う人々との人情味あふれる交流、毎回登場するマドンナとの成就しない恋模様などが、多くの日本人の共感を呼び、時代を超えて愛される理由となりました。
Q: 寅さんを演じた渥美清さんはどのような俳優でしたか?
A: 渥美清さんは、第1作から亡くなる直前の特別編まで、寅さん役を一貫して演じ続けました。その卓越した演技力と独特のユーモア、温かい人柄によって、寅さんという唯一無二のキャラクターを作り上げ、「寅さん=渥美清」として国民に深く記憶される俳優となりました。
ローマの休日の名シーンにちなむ、冷たいデザートの日: ジェラートの日
日本ジェラート協会が制定。映画『ローマの休日』(Roman Holiday)がアメリカで公開された1953年(昭和28年)8月27日にちなんで。オードリー・ヘプバーン演じるアン王女がジェラートを食べるシーンが話題となり、ローマを観光する人々が憧れるデザートとして人気を博しました。
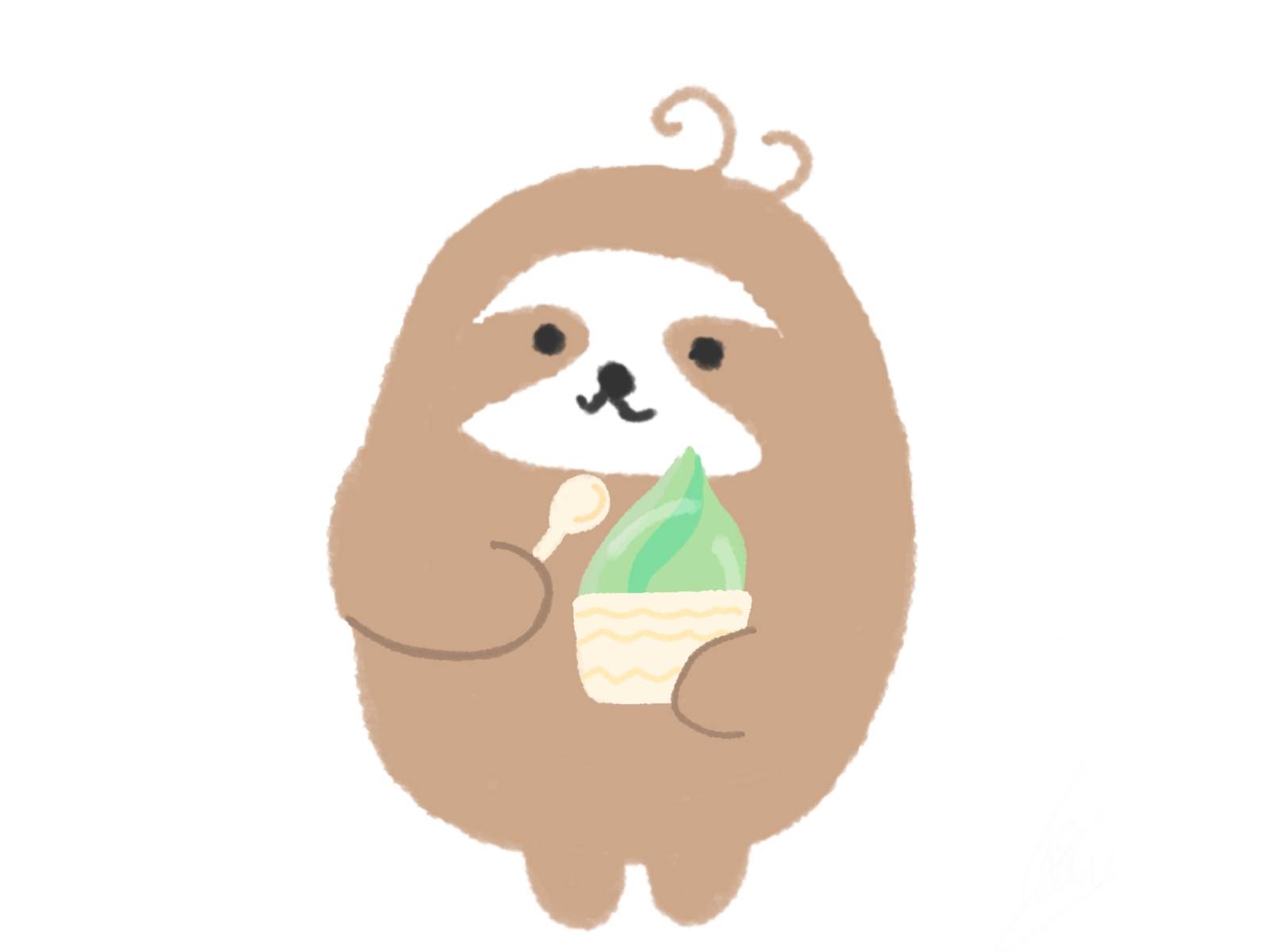
Q: なぜ映画『ローマの休日』の公開日が「ジェラートの日」になったのですか?
A: 1953年8月27日にアメリカで公開された映画『ローマの休日』の中で、主演のオードリー・ヘプバーンが演じるアン王女が、ローマのスペイン広場の階段で美味しそうにジェラートを食べるシーンが非常に有名になりました。このシーンがきっかけでジェラートの人気が高まったことから、日本ジェラート協会がこの日を記念日として制定しました。
Q: ジェラートとアイスクリームの違いは何ですか?
A: ジェラートはイタリア語でアイスクリーム全般を指しますが、一般的に日本の「アイスクリーム」に比べて乳脂肪分が少なく(通常4~8%程度)、空気含有量も低めです。そのため、素材本来の風味が濃厚で、より滑らかな口どけとさっぱりとした後味が特徴とされています。
Q: 日本ジェラート協会はどのような活動をしていますか?
A: ジェラートの品質向上、製造技術の研究開発、消費の普及、関連情報の提供などを目的とした団体です。ジェラートに関するイベントの開催や、ジェラートマエストロなどの資格認定なども行っています。
日本の原子力研究開発の始まり: 日本に原子の火がともった日
1957年(昭和32)のこの日、茨城県・東海村の日本原子力研究所に設置されたウォーターボイラー型炉1号が臨界実験に成功して日本最初の「原子の火」がともる。これによりインドに次いでアジアで2番目の原子炉稼働国となる。
Q: なぜこの出来事が「原子の火がともった日」と呼ばれるのですか?
A: 1957年8月27日に、茨城県東海村にある日本原子力研究所(現:日本原子力研究開発機構 JAEA)の実験用原子炉「JRR-1」が、核分裂の連鎖反応が持続的に起こる「臨界」状態に日本で初めて到達したことを指します。「原子の火」とは、この制御された核分裂エネルギーのことを象徴的に表現した言葉です。
Q: この原子炉(JRR-1)の目的は何でしたか?
A: アメリカから導入された小型のウォーターボイラー型研究炉で、主な目的は原子炉の物理的・工学的な基礎研究、技術者の養成訓練、そしてラジオアイソトープ(放射性同位体)の生産など、原子力の平和利用に関する研究開発の第一歩と位置づけられていました。
Q: この出来事は日本の科学技術にとってどのような意味を持ちましたか?
A: 日本が自国で原子炉を運転し、原子力の制御に成功したことは、戦後の科学技術復興の象徴的な出来事であり、その後の原子力発電開発へとつながる重要な一歩となりました。アジアではインドに次ぐ原子炉稼働国となったことも、当時の技術水準を示す出来事でした。