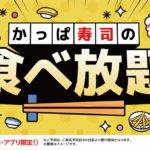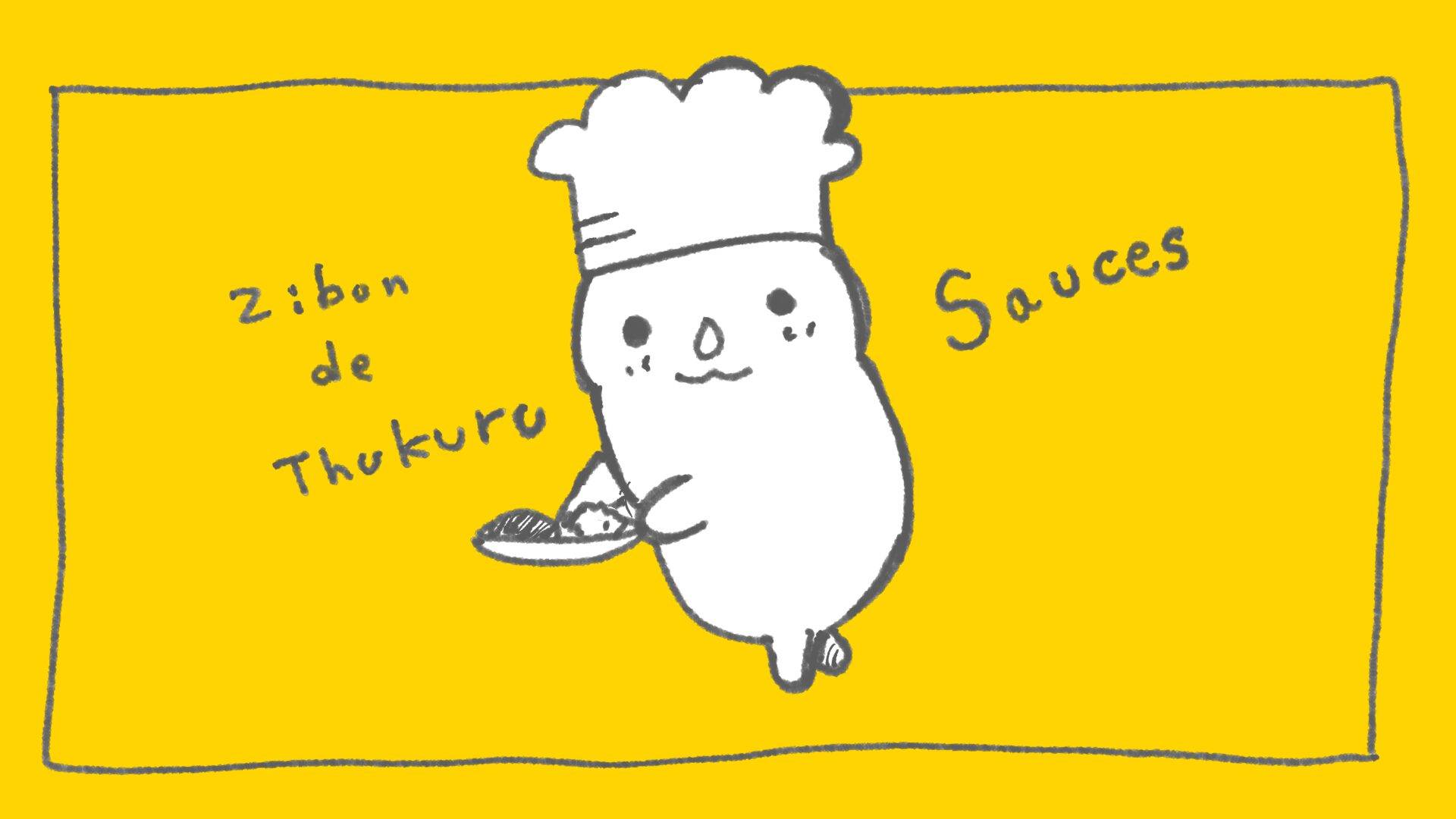お米がぐんぐん値上がり!ご飯一杯で家計はどれだけピンチ?

暮らしと食
最近、お米の値段がずいぶん上がってきましたね。気づけば、5kgのお米が4,000円を超えるのが当たり前になっています。
この値上がりが私たちの家計にどれくらい影響するのか、4人家族を例に2025年の春の状況を具体的な数字で見てみましょう。その後、国産米の価格がこの秋以降もさらに上昇する可能性を見ながら、将来の食費のイメージをつかみます。
お米の代わりにパンや麺類で済ませた場合の費用も比べ、「毎日のご飯茶碗一杯にかかるお金」を改めて感じてみましょう。
2025年春のお米の値段:5kgで4,300円ほどに
少し前の2020年頃、お米5kgの値段は2,100円くらいでした。1kgあたりにすると420円ほどです。
それが今、2025年の春には、お米5kgが4,300円くらい、1kgあたり860円ほどになっています。スーパーの棚に並んでいるお米の値段は、この5年ほどで約2倍になったことになります。
都会の大きなスーパー(例えばイオンや西友など)では4,200円くらいで見かけることもありますが、地方のお店や、人気の高いコシヒカリなどのブランド米になると、5,500円から6,000円もする場合があります。
この値上がりは、家計にじわじわと響いてきます。SNS(Xなど)でも、「お米5kgで5,000円は高すぎる!」「田舎ではもう6,000円もする」といった、値上がりを実感している声が多く見られます。
2025年春の家計負担:年間9万円の増加に
総務省のデータなどによると、4人家族が1年間に食べるお米の量は、平均で約204kgと言われています。これは、5kgのお米の袋に換算すると約40袋分、月に3~4袋消費する計算になります。
現在(2025年春)のお米の値段(5kg約4,300円、1kg約860円)で、年間204kgのお米を購入すると、かかる費用はこうなります:
- 2020年(1kg=420円の場合):年間約8.6万円
- 2025年春(1kg=860円の場合):年間約17.5万円
2020年と比べると、2025年春の米代は年間で約9万円近くも増えていることになります。
毎月3~4袋(1袋4,300円として)購入している家庭では、月に約7,000円から8,000円ほど、以前より余分な出費が増えている計算です。家庭によっては、お米代だけで食費全体の3割から4割を占めるようになっています。
SNSでは「食費が月に2.5万円も増えた」「お米代が家計を圧迫している」といった悲鳴にも似た声が目立ちます。都市部では、少しでも値段の安いブレンド米を選ぶ家庭が増えている一方、地方では地元のブランド米を高くても購入するケースも見られます。
どちらにしても、お米代の増加は、どの地域でも避けられない共通の課題となっています。
お米の代わりにパンや麺を使ったら?
食費を抑えるために、お米を食べる量を少し減らし、その分を食パンやうどんなどの別の主食で補うことを考える家庭もあるでしょう。
ここで、お米を1割減らした場合に、他の主食で補うと費用がどうなるか、2025年春の価格で比べてみましょう。お米の消費量を1割減らすと、年間204kgから183.6kgになります。
この減らした分を食パンやうどんで補った場合の費用を、2025年春の価格(お米1kg約860円、5kg約4,300円)で計算してみました。
食パンとうどんの場合の年間費用
図:2025年春における4人家族の年間主食費比較。お米のみの場合(約15.8万円)と、お米の消費量を10%減らし、その代わりを食パン(約17.3万円)またはうどん(約18万円)で補った場合の年間費用を示します。
試算の結果、お米を1割減らした分の費用は以下のようになります:
- お米だけ(1割減らした場合):年間約15.8万円(通常のお米代より1.7万円ほど少ない)。
- 減らした分を食パンで補う:お米代約15.8万円に食パン代1.5万円を足して、年間合計約17.3万円。お米だけの場合より約2,000円ほど少ない費用で済みます。
- 減らした分をうどんで補う:お米代約15.8万円にうどん代2.2万円を足して、年間合計約18万円。お米だけの場合より約4,000円ほど費用が多くなります。
食パンを選ぶと年間で少し(2,000円ほど)費用を抑えられますが、うどんで補うとむしろ費用が増える計算になります。パンや麺類も最近値上がりしているため、主食を変えても劇的に節約するのは難しいのが現状です。

2025年秋以降の見通し:もし国産米が高騰し続けたら?
2025年春のお米の価格(1kg約860円、5kg約4,300円)が続いた場合、年間のお米代は2020年より約9万円多くなるとお伝えしました。
しかし、もし国産米の価格がこの秋以降もさらに上昇が続いた場合、家計への負担は一層増大すると予想されます。
なぜ価格が上がりそうなのか、少し詳しく見てみましょう。農林水産省のデータによると、2024年に収穫されたお米の量は679万トンでした。ところが、このお米が市場に出回る「集荷量」が、前の年から21万~23万トンも減っています。
この結果、国内のお米の「在庫」が177万トンとなり、過去10年で最も少ない量になっています。つまり、市場に出回るお米が足りない状況が生まれているのです。
政府は市場の品薄感を和らげるために、国が備蓄しているお米21万トンを放出しましたが、これは市場全体の需要(年間約674万トン)に比べるとわずかです。そのため、2025年4月時点でも、お米5kgの価格は4,214円と高い状態が続いており、政府の対応だけでは価格を十分に抑えきれていません。
こうしたお米が足りない状況が秋以降も続くと、国産米の価格はさらに上がる可能性が高いと考えられています。例えば、秋には5kgあたり4,500円~5,000円が普通になり、地域や銘柄によっては6,000円に達することも十分に考えられます。
仮に、秋以降のお米の価格が1kgあたり1,000円になったと想定して、年間のお米代を計算してみましょう:
- 2025年秋(1kg=1,000円で計算した場合):年間204kgで約20.4万円。
- これは、2020年(1kg=420円)と比べると年間約11.8万円多くなります。
- また、2025年春(1kg=860円)と比べても年間約2.9万円多くなる計算です。
お米の消費を1割減らしてパンや麺で補う場合でも、食パン代を足すと年間約19.9万円(お米だけより約1,000円少ない)、うどん代を足すと年間約20.7万円(お米だけより約3,000円多い)となり、やはり高額な出費になります。
秋に国産米の価格がさらに上昇した場合、4人家族のお米代は年間で約12万円近くも増える可能性があります。お米代が家計の食費の大きな部分を占めている家庭では、食費全体の見直しがさらに必要になるかもしれません。

外国産米(アメリカ、タイ、ベトナムなど)の影響は?
国産米の価格が高騰し、手に入りにくい状況が続く中で、外国から輸入されるお米が日本の市場にどう影響するかも注目されています。
日本はアメリカ、タイ、ベトナムといった国々からお米を輸入しています。これらの外国産米は、以前は主に業務用や加工用として使われることが多かったのですが、国産米の品薄や価格高騰を受けて、2025年春(4月時点)では、スーパーなどでも一般の消費者向けに販売されるケースが増えています。例えば、米国産の米が8割と国産米が2割のブレンド米がスーパーで売られたり、コンビニのおにぎりの一部に外国産米が使われたりしているといった例が見られます。
民間による外国産米の輸入量は、高い関税(1kgあたり341円)がかかるにも関わらず、国産米の価格が高いために採算が取れることから増加傾向にあります。これにより、特に外食産業や食品加工分野では、国産米の不足を補い、材料コストの急激な上昇を一部抑える助けになる可能性があります。
また、スーパーなどで外国産米やそのブレンド米が手頃な価格帯で提供されることで、価格を重視する消費者にとっては、お米選びの選択肢が少し増えることになります。
しかしながら、多くの日本の消費者は、食味や品質の面で国産米を長年好む傾向にあります。外国産米は品種によって食感や風味が異なり、炊き方に工夫が必要な場合もあります。
そのため、外国産米の輸入が増えたり、スーパーでの扱いが増えたりしたとしても、日本国内で主流となっている、品質の良い国産主食用米(いわゆる「ごはん」として食べられるお米)全体の価格が大幅に下がる、あるいは高騰が劇的に抑えられるといった可能性は低いと考えられています。外国産米はあくまで一部の需要を補う役割が中心であり、秋以降の国産米の価格は、依然として日本国内での収穫量や在庫、市場への出回り具合といった要因が最も大きく影響すると見られます。
まとめると、2025年春の時点で、4人家族のお米代は2020年より年間で約9万円近く増えています。もしこの秋、国産米の価格がさらに上がり、5kgのお米が5,000円が普通になるような事態になれば、年間のお米代は12万円近くも多くなる可能性があります。
お米以外のパンや麺類で代用しても、大きな節約にはつながりにくいのが現状です。外国産米も以前より手に入りやすくなっていますが、これは主に業務用や一部小売での選択肢を増やすものであり、広く流通している国産米全体の価格動向を大きく変えるほどの力はまだないと考えられます。
こうしてみると、毎日の食卓に欠かせない「ご飯一杯」にかかるお金の重さを、数字の上で改めて感じざるを得ません。

データ出典:総務省(2025年3月家計調査より:お米5kg平均約4,378円など)、農林水産省(お米の消費量、2024年産米の生産量679万トン、集荷量減少、在庫177万トンなど)、NHK報道(2025年4月時点の価格4,214円、備蓄米放出効果の限定性など)、ウェブ検索(代替品の価格:食パン1斤270~290円、うどん250g270~290円などを参照)。2025年秋の価格(5kgで4,500~5,000円、最大6,000円)は、集荷不足や在庫減少といった需給状況に基づいた高騰シナリオでの予測値です。SNS(Xなど)での投稿内容(月2~3万円負担増、地域差など)を参考に、実感についての記述を補足しました。試算は地域による価格差を考慮し、平均的な値を用いて計算しています。外国産米に関する記述は、2025年4月時点での各種報道や流通状況、一般的な市場構造、影響の可能性に基づいています。
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
「暮らしと食 」に関する記事
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
「暮らしと食」人気記事
カテゴリー
一部記事及び画像はPRタイムスのプレスリリースから引用しています。