12月3日は何の日?何の記念日?簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
明治の改暦、新時代への一歩: カレンダーの日
全国団扇扇子カレンダー協議会と全国カレンダー出版協同組合連合会が1988年(昭和63年)に制定。1872年(明治5年)11月9日の太政官布告により、それまでの太陰太陽暦(旧暦)から太陽暦(新暦、グレゴリオ暦)への改暦が決定され、明治5年12月3日(旧暦)が、翌日の1873年(明治6年)1月1日(新暦)となったことに由来します。
Q: なぜ「カレンダーの日」が12月3日なのですか?
A: 1872年(明治5年)の旧暦12月3日が、太陽暦(現在のカレンダー)が公式に採用される前の最後の日付であったことを記念しています。この改暦は、日本の近代化において重要な出来事でした。
Q: なぜ明治政府は太陽暦を採用したのですか?
A: 西洋諸国との国際的な時間感覚の統一を図り、近代国家としての体裁を整えること、また、旧暦の閏月(うるうづき)による月ごとの給与支払いの煩雑さを解消する(財政的な理由もあったとされる)ことなどが目的でした。
Q: 改暦はスムーズに行われたのですか?
A: 発表から実施までの期間が非常に短かったため、社会的な混乱もあったようです。特に旧暦に基づいていた年中行事や生活習慣との調整が必要となりました。しかし、これにより日本は国際標準の暦を採用することになりました。
不思議と驚き「ワン(1)ツー(2)スリー(3)」: 奇術の日
公益社団法人・日本奇術協会が1990年(平成2年)に制定。日付は、奇術(手品・マジック)を演じる際の代表的な掛け声である「ワン(1)ツー(2)スリー(3)」と読む語呂合わせから。

Q: 奇術の日はどんなイベントが行われますか?
A: 日本奇術協会や各地のマジック愛好家団体などが中心となり、マジックショー、発表会、コンテスト、レクチャー、ワークショップなどが開催されることがあります。マジックの楽しさや不思議さに触れる機会となっています。
Q: 誰が「奇術の日」を制定したのですか?
A: 日本のプロマジシャンの団体である公益社団法人・日本奇術協会が1990年に制定しました。
Q: 奇術(マジック)の魅力は何ですか?
A: 不可能を可能に見せる驚きや不思議さ、観客を楽しませるエンターテイメント性、そして巧みなテクニックや演出による芸術性などが魅力です。言葉が通じなくても楽しめる、世界共通のエンターテイメントでもあります。
日頃の感謝を「サン(3)クス」で伝える: 妻の日
印刷会社である凸版印刷株式会社(現:TOPPAN株式会社)が1995年(平成7年)に制定。日付は、年末の時期である12月の最初(月初)に、1年間の妻の労をねぎらい感謝する日として、感謝を表す「サン(3)クス」(Thanks)と読む語呂合わせから。
Q: 妻の日には何をすれば良いですか?
A: 日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを、言葉や手紙、プレゼントなどで伝える良い機会です。花束やちょっとしたギフトを贈ったり、家事を手伝ったり、二人で食事に出かけたりするのも良いでしょう。大切なのは感謝の気持ちを伝えることです。
Q: 妻の日が生まれた理由は何ですか?
A: 年末の忙しい時期を前に、1年間家庭を支えてくれた妻へ感謝の気持ちを表すきっかけの日として、覚えやすい「サン(3)クス」という語呂合わせから制定されました。
Q: 「いい夫婦の日」(11月22日)との違いは何ですか?
A: 「いい夫婦の日」は夫婦がお互いに感謝し合う日ですが、「妻の日」は特に夫から妻へ感謝を伝えることに焦点を当てていると言えるでしょう。どちらも夫婦間のコミュニケーションを深める良い機会です。
冬のビタミン補給!「いい(11)みか(3)ん」: みかんの日
全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が制定。日付は「いい(11)みか(3日)ん」と読む語呂合わせで、11月3日と12月3日を「みかんの日」としています。(語呂合わせは3日(みっか)の「みか」と「みかん」を掛けています)
Q: みかんの日に特別なイベントはありますか?
A: 全国的・統一的なイベントは少ないかもしれませんが、みかんの産地や、スーパーマーケット、JAなどでは、この日に合わせて販売促進キャンペーンや試食会、みかん狩りイベントなどが行われることがあります。
Q: なぜ11月3日と12月3日の2日間が「みかんの日」なのですか?
A: 「いい(11)みか(3日)ん」という覚えやすい語呂合わせと、11月から12月にかけて温州みかんが旬を迎え、最も美味しくなる時期であることを記念して、2つの日が制定されました。
Q: みかんの皮をむく以外での活用法はありますか?
A: みかんの皮(陳皮:ちんぴ)は、よく洗って乾燥させれば、入浴剤としてお風呂に入れたり(体を温める効果)、細かく刻んで料理やお菓子の香り付けに使ったりすることができます。漢方薬としても利用されます。
個人タクシー誕生の歴史: 個人タクシーの日
一般社団法人・全国個人タクシー協会が制定。1959年(昭和34年)12月3日に、日本で初めて個人タクシー事業者の営業許可が下りたことを記念しています。
Q: なぜ「個人タクシーの日」が12月3日なのですか?
A: 1959年(昭和34年)のこの日に、それまで法人タクシーしかなかった日本において、初めて個人によるタクシー営業が許可された、歴史的な日であることに由来します。
Q: 個人タクシーと法人タクシーの違いは何ですか?
A: 法人タクシーはタクシー会社に雇用された運転手が乗務しますが、個人タクシーは、タクシー会社での一定期間以上の乗務経験など、厳しい資格要件を満たした運転手自身が、個人事業主として営業許可を取得して運営しています。車両の選択やサービス内容に個性が反映されやすいのが特徴です。
Q: 個人タクシーを利用するメリットは何ですか?
A: 長年の経験を持つベテランドライバーが多く、質の高い接客や地理への詳しさなどが期待できます。車両も比較的グレードの高いものが使われていることが多いです。一方で、流し営業が主体で、配車アプリなどに対応していない場合もあります。
障がいのある人もない人も共に生きる社会へ: 国際障害者デー (International Day of Persons with Disabilities)
1992年(平成4年)の国連総会で制定された国際デーです。障害者の権利擁護と福祉の向上、そして障害のある人々が社会のあらゆる分野(政治、経済、社会、文化など)へ完全かつ平等に参加できる社会の実現を目指し、国際社会全体の意識を高めることを目的としています。
Q: なぜ国際障害者デーが制定されたのですか?
A: 障害のある人々が直面する様々な障壁(物理的なバリア、制度的なバリア、情報・コミュニケーションのバリア、そして人々の意識の中にあるバリア)を取り除き、誰もが尊厳を持って、その能力を発揮できるインクルーシブ(包括的)な社会を築くことの重要性を訴えるために制定されました。
Q: この日にはどのような取り組みが行われますか?
A: 世界各地で、障害者の権利やインクルージョンに関するセミナーやシンポジウム、バリアフリー体験イベント、障害者アートの展示会、パラスポーツの体験会などが開催されます。障害のある人々の声に耳を傾け、理解を深める機会となっています。
Q: 私たちにできることは何ですか?
A: まず、障害や障害のある人々に対する正しい知識を学び、偏見や固定観念を持たないことが大切です。街中で困っている様子の障害のある人を見かけたら、勇気を出して声をかけ、必要なサポートを申し出ることも重要です(ただし、一方的な手助けではなく、相手の意向を確認することが基本です)。誰もが暮らしやすい社会環境づくりに関心を持つことも求められます。















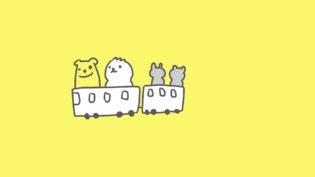

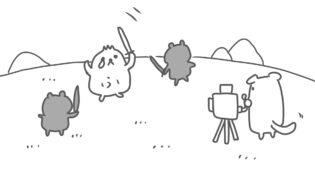
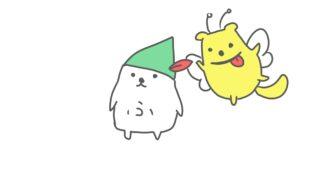



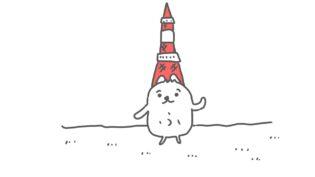
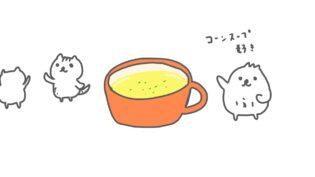

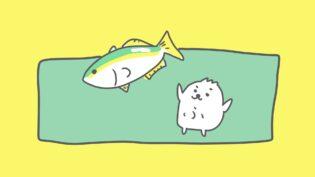
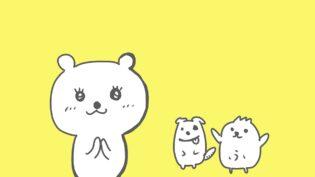
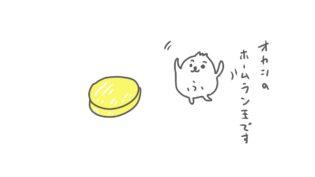


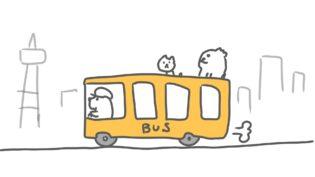


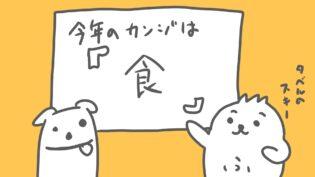
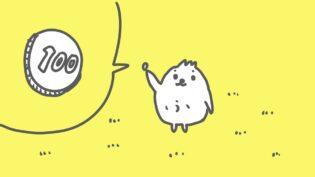

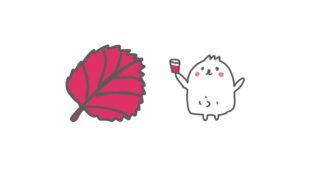
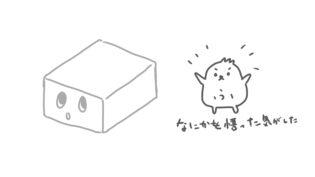
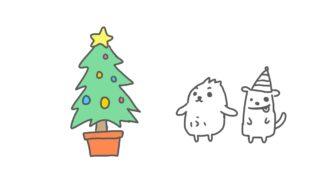

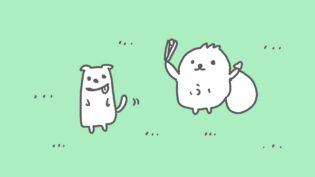
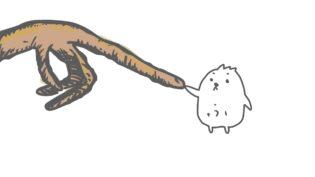





コメント
今日は色んな日なんですね!特に奇術の日、マジックの掛け声が由来っていうのが面白い!妻の日は忘れずに感謝しないと…😅
今日は色んな記念日があるんですね!奇術の日の「ワンツースリー」の語呂合わせ、覚えやすくて面白いです🤣