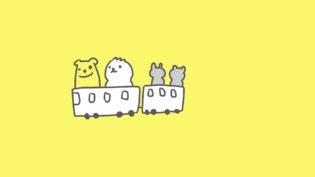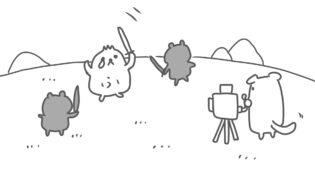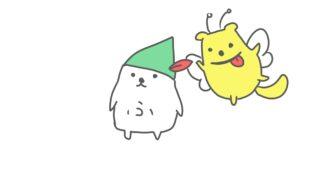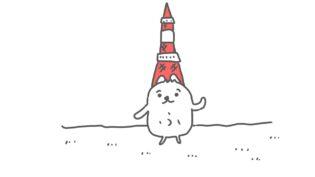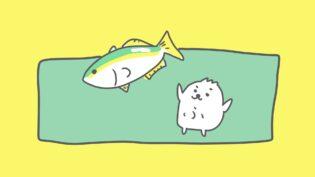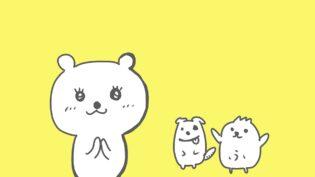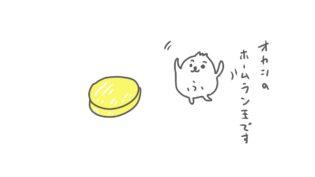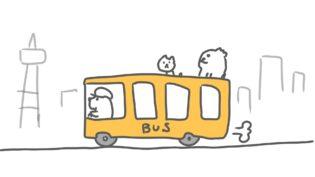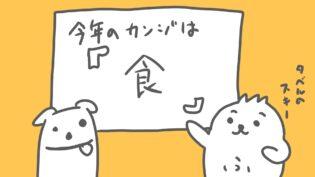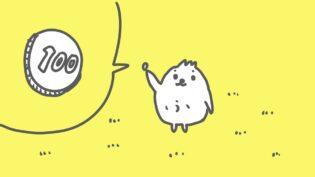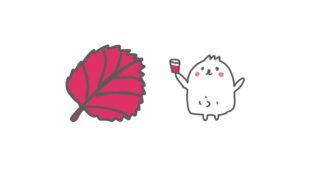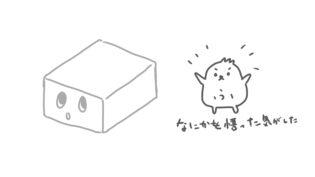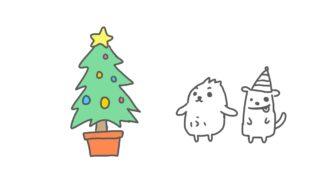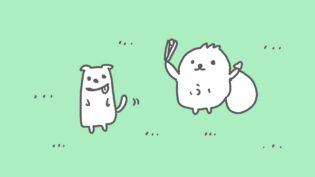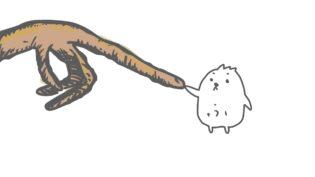12月22日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
「いつ(12)もフーフー(22)」温まる一杯: スープの日
スープの製造・販売業者などで構成される日本スープ協会が、1980年(昭和55年)の設立総会に合わせて制定。日付は「いつ(12)もフーフー(22)とスープをいただく」という、温かいスープを飲む様子を表した語呂合わせと、冬の寒い時期に温かいスープが恋しくなることから。
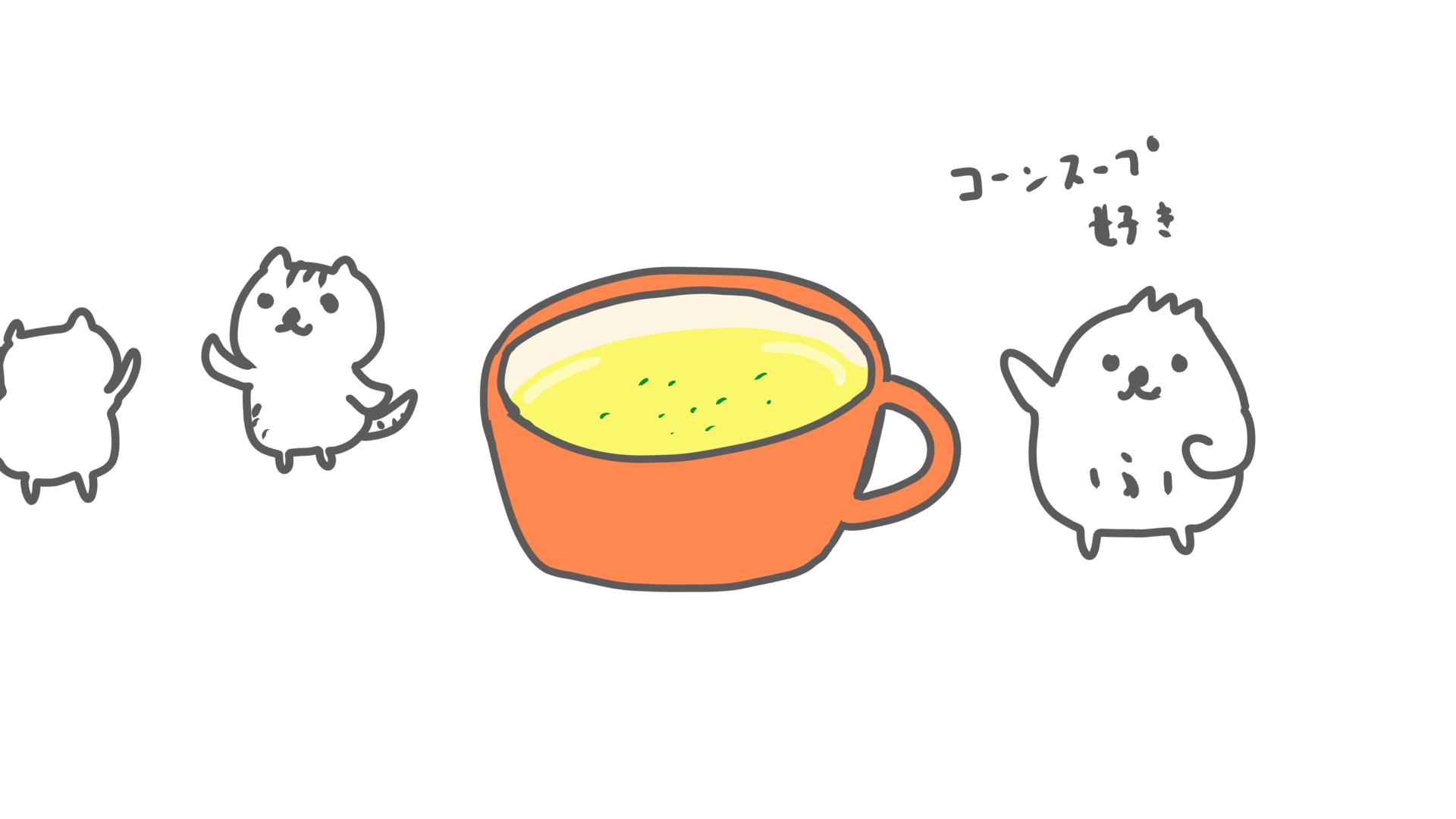
Q: スープの日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 体を温め、手軽に栄養も摂れるスープの魅力を広く伝え、家庭や外食でのスープの消費を促進することを目的としています。また、スープに関する様々な情報を発信する日でもあります。
Q: なぜ12月22日が「スープの日」なのですか?
A: 「いつ(12)もフーフー(22)とスープをいただく」という、温かいスープを飲む情景が目に浮かぶような語呂合わせと、寒さが本格化し温かいスープが特に美味しく感じられる12月下旬という時期から、この日が選ばれました。
Q: 世界にはどのようなスープがありますか?
A: フランスの「オニオングラタンスープ」や「ブイヤベース」、ロシアの「ボルシチ」、中国の「フカヒレスープ」、タイの「トムヤムクン」、スペインの「ガスパチョ」(冷製スープ)、日本の「味噌汁」や「お吸い物」など、各国の食文化を反映した多種多様なスープが存在します。
テレビ番組の人気を測る指標の始まり: 視聴率の日
テレビ番組の視聴率調査などを行う株式会社ビデオリサーチが制定。1962年(昭和37年)12月22日に、同社が関東地区において、日本で初めて機械式(オンラインメーターシステム)によるテレビ視聴率調査を開始し、その調査結果レポート第一号を発行したことにちなんでいます。
Q: 視聴率の日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 日本において、機械を用いた客観的なテレビ視聴率調査が始まり、そのデータが定期的に提供されるようになったことを記念しています。
Q: テレビ視聴率調査は、どのような目的で行われていますか?
A: どの時間帯に、どのような層(性別、年齢など)の人々が、どのテレビ番組をどれくらい見ているかを把握するために行われます。このデータは、テレビ局にとっては番組編成や制作の参考に、広告主や広告会社にとっては広告出稿の効果測定や媒体価値判断の重要な指標として活用されています。
Q: 視聴率はどのように調査されているのですか?
A: 全国の世帯の中から統計的に無作為に選ばれた調査協力世帯に、専用の測定器(ピープルメーター)を設置し、「誰が」「いつ」「どのチャンネル」を視聴したかを自動的に記録・集計しています。近年では、録画再生視聴やタイムシフト視聴のデータも測定されています。
働く人々の権利を守る法律の誕生: 労働組合法制定記念日
1945年(昭和20年)12月22日に、戦後の日本の民主化政策の一環として、「労働組合法」が公布されたことを記念する日です。この法律は、労働者が使用者と対等な立場で交渉できるように、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)という「労働三権」を保障した画期的な法律でした。
Q: 労働組合法制定記念日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 1945年(昭和20年)に、労働者の基本的な権利(労働三権)を保障し、労働組合の結成と活動を法的に認めた「労働組合法」が公布されたことを記念しています。
Q: 労働組合法は、どのような目的で制定されましたか?
A: 戦前の日本では労働者の権利が十分に保障されていなかった反省から、労働者が団結して使用者と交渉し、労働条件(賃金、労働時間、労働環境など)の維持・改善を図る権利を法的に保障することで、労働者の地位向上と、労使関係の安定化、そして民主的な経済社会の発展を目指して制定されました。
Q: 労働組合にはどのような役割がありますか?
A: 労働者の代表として、会社(使用者)と労働条件などについて交渉(団体交渉)を行ったり、労働協約を締結したりします。また、職場環境の改善を求めたり、不当な解雇や差別などから労働者を守ったりする役割も担っています。ストライキなどの団体行動(争議行為)を行う権利も認められています。
一年で最も夜が長い日: 冬至(とうじ) (※年によって12月21日か22日)
二十四節気の一つで、例年12月21日または22日頃にあたります。北半球において、太陽の位置が一年で最も南に寄り、昼(日の出から日の入りまで)の時間が最も短く、夜が最も長くなる日です。この日を境に、徐々に日が長くなっていきます。(※12月21日の場合もあります)
Q: 冬至とはどのような意味を持つ日ですか?
A: 太陽の力が最も弱まる日であり、この日を境に再び太陽の力が強まっていく(日が長くなっていく)ことから、古くから「一陽来復(いちようらいふく)」といって、悪いことが去り良い方向へ向かう転換点と考えられてきました。世界各地で、冬至に関連する祭りや習慣があります。
Q: 冬至にかぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりするのはなぜですか?
A: 冬至にかぼちゃ(南瓜=なんきん)のように「ん」のつくものを食べると「運」が呼び込めると言われています。また、かぼちゃは栄養価が高く、長期保存も可能なため、冬にビタミンなどを補給する目的もあったとされます。ゆず湯に入るのは、強い香りで邪気を払い、体を温めて血行を促進し、風邪を予防するためと言われています。「冬至」と「湯治(とうじ)」をかけた語呂合わせでもあります。
Q: 二十四節気とは何ですか?
A: 太陽の黄道上の位置に基づいて1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。古代中国で考案され、日本では農作業の目安などに使われてきました。立春、春分、夏至、秋分、冬至などが有名です。