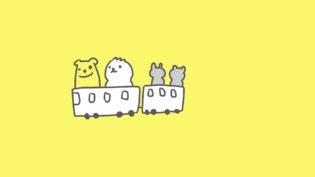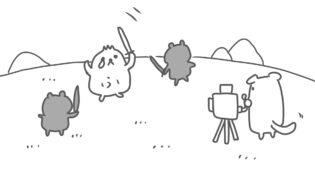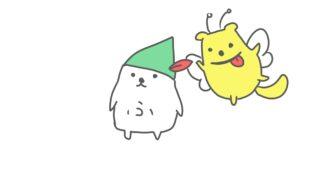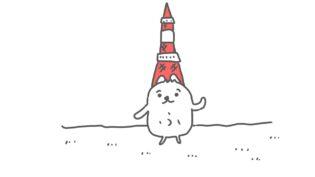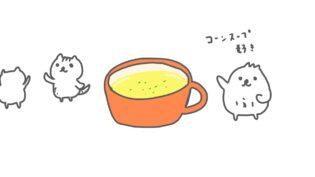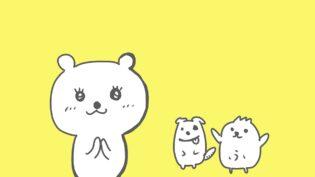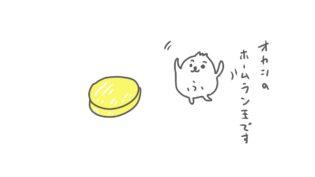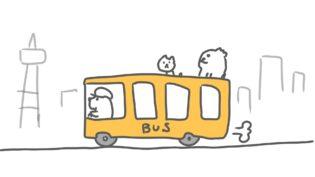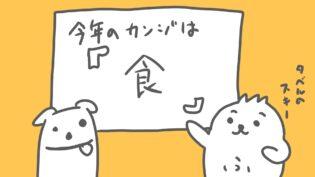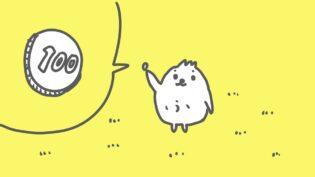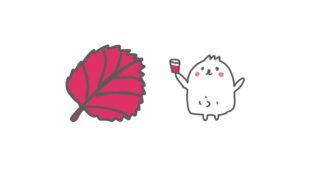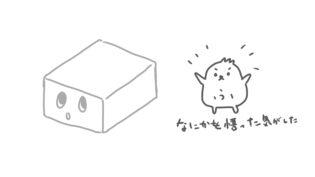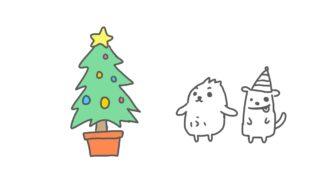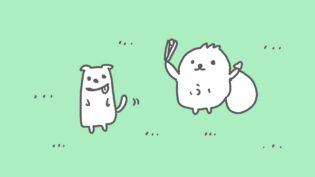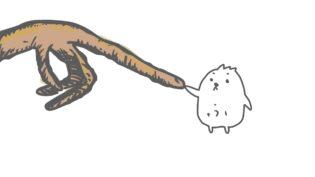12月20日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
安全で円滑な交通社会の礎: 道路交通法施行記念日
1960年(昭和35年)12月20日に、現在の日本の交通ルールの基本となる「道路交通法」(道交法)が施行されたことを記念する日です。
Q: 道路交通法施行記念日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 1960年(昭和35年)に、車両(自動車、バイク、自転車など)や歩行者が道路を通行する際のルール、運転免許制度、交通違反に対する罰則などを定めた「道路交通法」が施行されたことを記念しています。
Q: 道路交通法は、どのような目的で施行されたのですか?
A: モータリゼーション(自動車社会)の進展に伴い増加する交通事故を防止し、道路における交通の安全と円滑を図ることを目的として施行されました。時代に合わせて改正が重ねられ、現在に至っています。
Q: 私たちが安全のために心がけるべきことは?
A: 運転者はもちろん、歩行者や自転車利用者も、交通ルールを正しく理解し、遵守することが基本です。互いに譲り合いの気持ちを持ち、思いやりをもった行動を心がけることが、交通事故を防ぎ、誰もが安全・安心に道路を利用できる社会につながります。
魚へんに師走の「鰤」!「ぶ(2)り(0)」で縁起良く: ブリの日
12月(師走)は「鰤(ブリ)」という漢字に「師」が含まれること、そして「ぶ(2)り(輪=0)」(鰤)と読む語呂合わせから、12月20日が記念日とされています。(制定団体は不明瞭です)
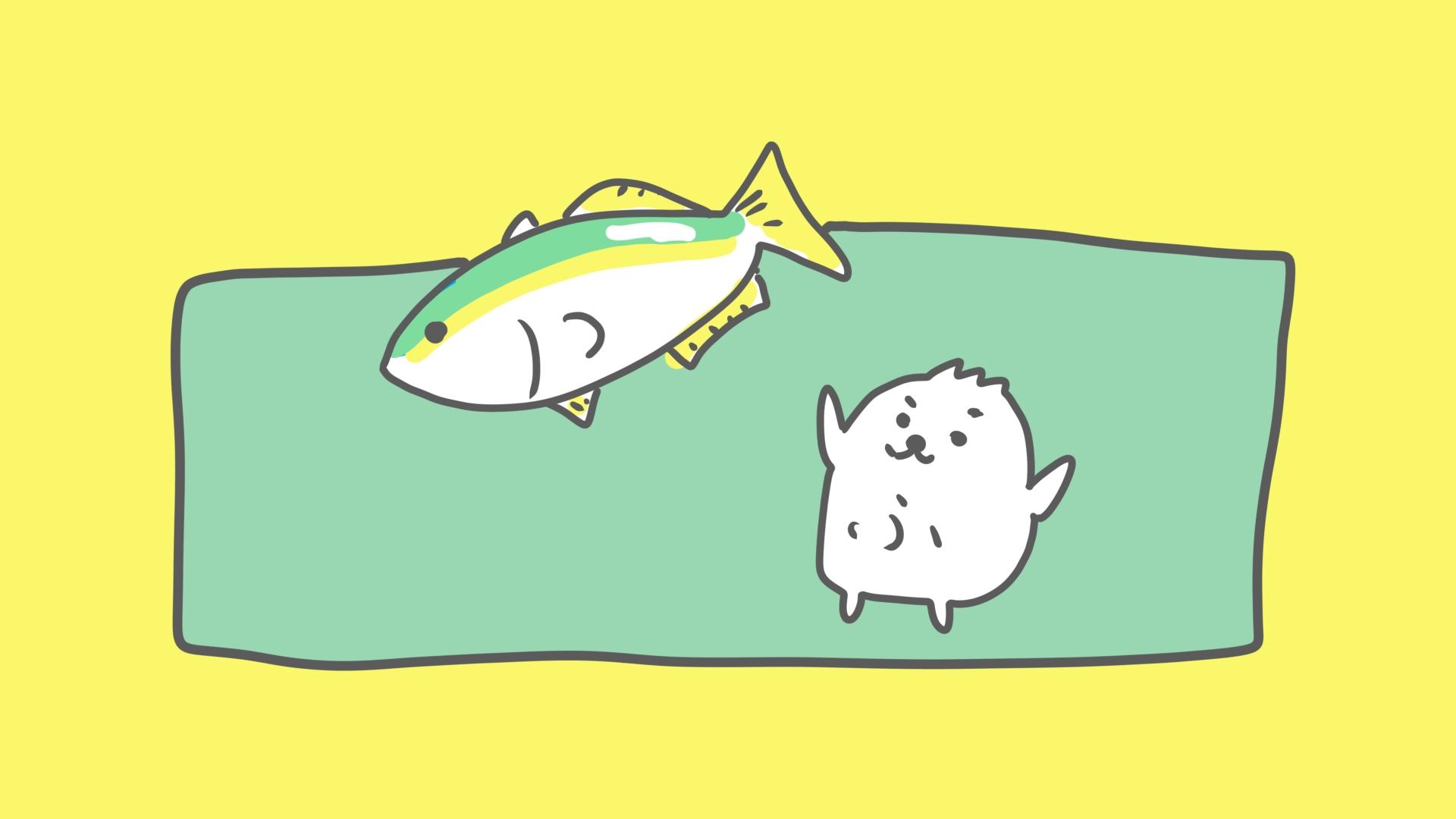
Q: ブリの日は、どのような理由で12月20日に制定されましたか?
A: 12月(師走)の「師」が魚へんにつくと「鰤」になることと、「ぶ(2)り(輪=0)」という語呂合わせから、この日が選ばれました。「輪(わ)」を数字の「0」に見立てています。
Q: ブリは、なぜ縁起の良い魚とされていますか?
A: ブリは成長するにつれて呼び名が変わる「出世魚」(例:ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ ※関東での呼び名)であることから、立身出世を願う縁起物とされ、お正月のおせち料理や祝いの席で用いられることが多いです。特に冬に脂がのって美味しくなるため、「寒ブリ」として珍重されます。
Q: ブリにはどのような栄養がありますか?
A: 良質なたんぱく質に加え、血液をサラサラにする効果が期待されるEPA(エイコサペンタエン酸)や、脳機能に関わるDHA(ドコサヘキサエン酸)などの不飽和脂肪酸を豊富に含んでいます。また、ビタミンDやビタミンB群も含まれています。
生きた化石、学術調査開始: シーラカンスの日
1952年(昭和27年)12月20日に、アフリカ東海岸のコモロ諸島沖でシーラカンス(Coelacanth)が捕獲され、初めて本格的な学術調査が行われたことを記念する日です。シーラカンスは、約6500万年前に絶滅したと考えられていましたが、1938年に南アフリカで生存が確認され、「生きた化石」として世界を驚かせました。
Q: シーラカンスの日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 「生きた化石」と呼ばれる古代魚シーラカンスが、1938年の発見後、初めて学術的な調査対象として捕獲された日を記念しています。これにより、その形態や生態に関する研究が大きく進展しました。
Q: シーラカンスは、どのような特徴を持つ魚ですか?
A: 約4億年前(デボン紀)に出現し、恐竜が絶滅した白亜紀末まで生存していたと考えられていた古代魚の仲間です。現代の魚とは異なり、胸ビレや腹ビレに骨格があり、陸上脊椎動物の四肢への進化の過程をうかがわせる特徴を持つことから、「生きた化石」と呼ばれています。深海に生息しています。
Q: なぜ1938年の発見日ではなく、1952年の学術調査の日が記念日なのですか?
A: 1938年の発見は非常に衝撃的でしたが、標本が十分に研究される前に腐敗が進んでしまいました。1952年の捕獲によって、初めて詳細な解剖学的調査や組織の研究が可能となり、シーラカンスの生物学的価値が科学的に確立されたため、この日が記念日として重視されていると考えられます。
百貨店、新しい商業形態の誕生: デパート開業の日
1904年(明治37年)12月20日に、東京・日本橋の「三井呉服店」が、「デパートメントストア宣言」を行い、従来の呉服店から、様々な商品を部門別に陳列・販売する欧米型の百貨店(デパートメントストア)へと業態を転換し、「三越呉服店」(現在の三越百貨店)として営業を開始したことを記念する日です。
Q: デパート開業の日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 日本橋の老舗「三井呉服店」が、伝統的な呉服商から近代的な「百貨店(デパート)」へと生まれ変わり、日本における百貨店の歴史が始まった日を記念しています。
Q: 日本初のデパートは、どのようにして誕生しましたか?
A: 東京・日本橋の「三井呉服店」が、呉服商から百貨店へと業態を変更し、欧米スタイルのデパート形式(陳列販売、正札販売、現金販売など)を採用することで誕生しました。「三越呉服店」と改称し、1904年(明治37年)12月20日に営業を開始しました。
Q: デパートの登場は社会にどのような影響を与えましたか?
A: 多種多様な商品が一堂に揃い、自由に見て選べるという新しい買い物体験を提供し、消費文化の発展を促しました。また、エレベーターやエスカレーター、食堂、催事場などを備えた豪華な建物は、単なる買い物だけでなく、娯楽や文化の発信地としても機能し、都市のランドマークとなりました。
人間の連帯と共生の促進: 人間の連帯国際デー (International Human Solidarity Day)
2005年の国連総会で制定された国際デーです。貧困の撲滅や持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、国家間および個人間の「連帯(Solidarity)」、つまり互いに助け合い、支え合う精神の重要性を認識し、国際的な協力と行動を促進することを目的としています。
Q: なぜ「人間の連帯」が重要なのでしょうか?
A: グローバル化が進む現代社会において、貧困、飢餓、紛争、気候変動、感染症といった課題は、一国だけでは解決できない地球規模の問題となっています。これらの課題を克服し、すべての人々が平和で尊厳ある生活を送れるようにするためには、国境を越え、人々が互いに協力し、連帯して取り組むことが不可欠です。
Q: この記念日の由来は何ですか?
A: 特定の歴史的出来事に直接由来するわけではありませんが、国連憲章にも謳われている国際協力と連帯の精神を改めて強調し、21世紀におけるその重要性を訴えるために制定されました。
Q: 私たちにできる連帯とは?
A: 開発途上国への支援活動(寄付やボランティアなど)に参加すること、フェアトレード製品を購入すること、環境問題に関心を持ち行動すること、国内外の様々な課題について学び、周りの人と話し合うこと、そして何よりも、身近な人々を含め、困難な状況にある人々への共感と思いやりの心を持つことが、連帯への第一歩となります。