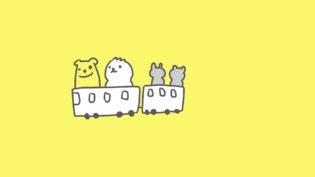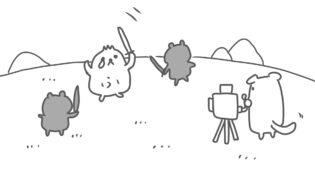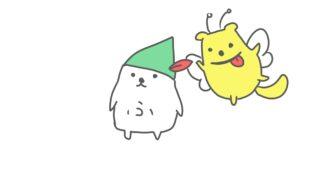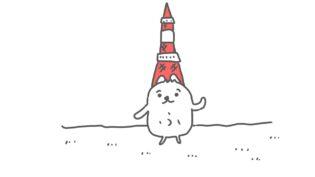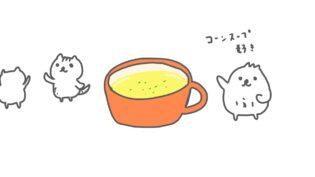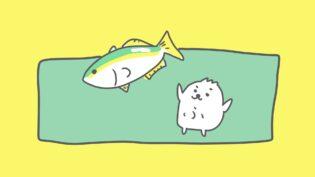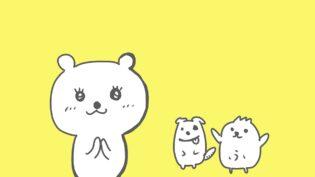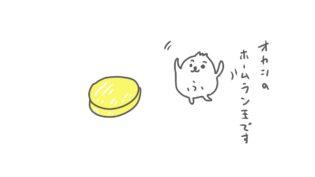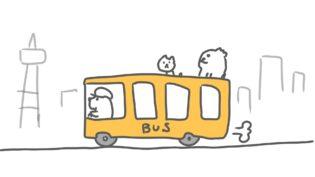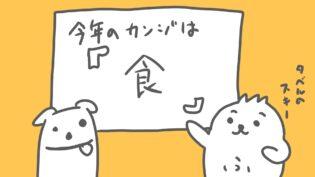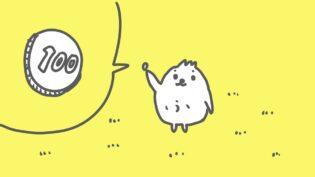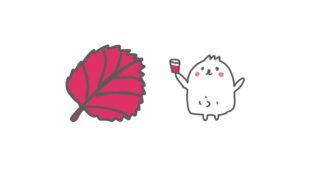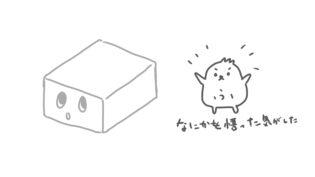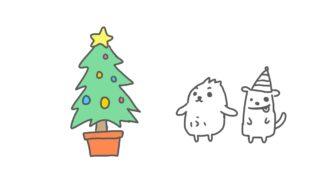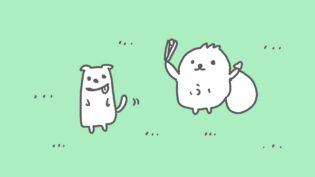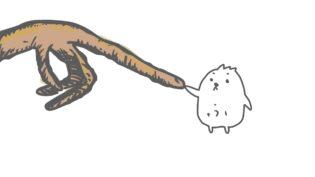12月6日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
エジソンの発明で音が記録された日: 音の日
一般社団法人 日本オーディオ協会が1994年(平成6年)に制定。1877年(明治10年)12月6日に、アメリカの発明家トーマス・アルバ・エジソンが、自ら発明した蓄音機(フォノグラフ)で「メリーさんのひつじ」の歌を録音・再生することに成功したことを記念しています。
Q: 音の日は、どのような出来事を記念していますか?
A: トーマス・エジソンが発明した蓄音機(フォノグラフ)で、世界で初めて音の録音・再生に成功したという、音響技術史上における画期的な出来事を記念しています。
Q: 音の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: オーディオ(音響機器)や音楽文化・産業のさらなる発展を図り、多くの人に「音」そのものの大切さや、良い音で聴くことの素晴らしさを再認識してもらうことを目的としています。
Q: エジソンの蓄音機はどのような仕組みでしたか?
A: 音の振動を針に伝え、その針で回転する円筒(シリンダー)に巻き付けた錫箔(すずはく)に溝を刻んで音を記録しました。再生する時は、逆にその溝を針でなぞり、振動を増幅させて音を出す仕組みでした。この発明が、後のレコードやCD、デジタルオーディオへと繋がる音響記録・再生技術の原点となりました。
優しいお姉さんに感謝を込めて: 姉の日
兄弟・姉妹の性格や関係性を研究していた漫画家・著述家の畑田国男(はただ くにお)氏が1992年(平成4年)に提唱した記念日。日付は、キリスト教の聖人であり、サンタクロースのモデルともされる聖ニコラウス(St. Nicholas)にまつわる「三姉妹伝説」に由来しています。この日は聖ニコラウスの記念日(命日)です。
Q: 「三姉妹伝説」とはどのようなお話ですか?
A: 貧しさのために身売りをしなければならなくなった三姉妹の家に、聖ニコラウスが夜中に窓から金貨を投げ入れ、長女が結婚資金を得て幸せになったという伝説です。彼はその後、次女、三女のためにも同様に金貨を投げ入れたと言われています。この伝説から、聖ニコラウスは子どもたちや弱い立場の人々を守る聖人として崇敬され、サンタクロースの起源ともなりました。
Q: なぜこの伝説から「姉の日」が生まれたのですか?
A: 畑田国男氏は、三姉妹の中でも最初に救われたのが「長女」であったことに着目し、妹たちの面倒を見たり、家族を支えたりすることの多い「姉」という存在に感謝し、その労をねぎらう日として、聖ニコラウスの記念日である12月6日を提唱しました。
Q: 姉の日には何をすると良いですか?
A: 姉がいる人は、日頃の感謝の気持ちを伝えたり、ちょっとしたプレゼントを贈ったりするのが良いでしょう。姉妹で一緒に過ごす時間を作るのも素敵ですね。
山田耕筰による日本初の交響曲初演: シンフォニー記念日
1914年(大正3年)12月6日に、日本の作曲家・指揮者である山田耕筰(やまだ こうさく)が作曲した、日本人による初めての本格的な交響曲『かちどきと平和』が、東京の帝国劇場で初演されたことを記念する日です。(制定団体は特定されていません)
Q: シンフォニー記念日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 日本人が初めて作曲した本格的な交響曲である、山田耕筰の『かちどきと平和』が初演されたという、日本の西洋音楽史における重要な出来事を記念しています。
Q: 山田耕筰とはどのような人物ですか?
A: 日本の近代音楽(西洋音楽)の基礎を築いた、最も重要な作曲家・指揮者の一人です。ドイツ留学で作曲と指揮を学び、帰国後は日本初の本格的な管弦楽団(後のNHK交響楽団の前身の一つ)を組織するなど、日本の音楽界の発展に多大な貢献をしました。童謡『赤とんぼ』『この道』などの作曲者としても広く知られています。
Q: 交響曲『かちどきと平和』はどのような作品ですか?
A: 第一次世界大戦が勃発した年に作曲され、戦争の勝利(かちどき)と平和への願いが込められた作品とされています。ドイツ留学で学んだ後期ロマン派の影響を受けた、壮大で色彩感豊かな音楽です。現在では演奏される機会は多くありませんが、日本の交響曲創作の幕開けを告げる記念碑的な作品です。