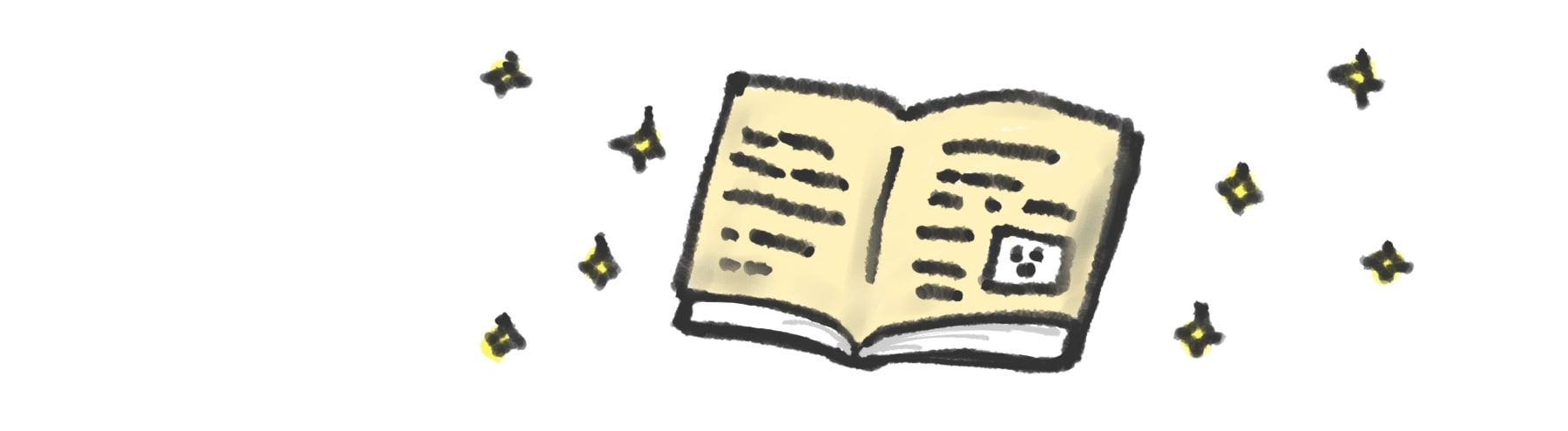
投稿日: 2020.05.14 最終更新日: 2024.05.18
トリビア(雑学)日本の地域117 - 御堂筋は昔、細道だった!?
大阪の御堂筋は、昔は幅6mくらいの細道だった。
現在の大阪のメインストリート、御堂筋。その堂々たる姿からは想像もできませんが、かつては幅わずか6メートルほどの細道でした。
時は明治時代。大阪の経済発展に伴い、南北を結ぶ幹線道路の必要性が高まりました。しかし、当時の御堂筋は道幅が狭く、交通のボトルネックとなっていたのです。
そこで、大阪市は1926年(大正15年)から大規模な道路拡幅工事に着手。沿道の建物を立ち退かせ、道路幅を現在の約44メートルまで広げるという、大胆な都市計画を実行しました。
この工事は、当時の大阪市長、関一(せき はじめ)の強いリーダーシップのもとで進められました。関市長は、「将来の大阪のためには、多少の犠牲はやむを得ない」という信念のもと、反対意見を押し切って工事を強行したと言われています。
工事は難航を極めましたが、1937年(昭和12年)に完成。現在の御堂筋が誕生しました。その結果、大阪の交通事情は劇的に改善され、御堂筋は大阪を代表するシンボルロードとして、今もなお多くの人々に利用されています。
ちなみに、御堂筋という名前は、沿道にある北御堂(本願寺津村別院)と南御堂(真宗大谷派難波別院)という二つの寺院に由来します。
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
こちらのトリビアもいかがですか?
- 人物・人名147
- 日本に実在する珍しい名前、野風…
- 食べ物96
- カニ缶の中に入ってる紙は「ステ…
- 動物・植物143
- 麦は、世界で一番多く作られてい…
- 動物・植物115
- カラスは賢いとよく言われるが、…
- ゲーム71
- 『ファイナルファンタジーIX』…
- 歴史115
- 世界最初のカフェは、16世紀の…
- 人物・人名235
- 日本人からすると変わった名前「…
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
雑学一覧
トリビア的雑学を不定期で更新予定。何か面白いトリビアあったら教えてくださいね。




















