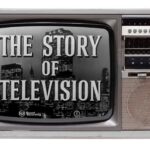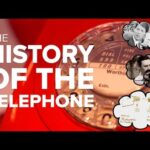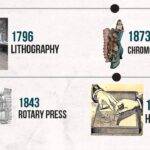AIに「なんでやねん!」思わずツッコミたくなる瞬間と、深いため息を減らす対話術

テクノロジー
私たちの日常にすっかり溶け込んできたAIツール。
文章作成、調べ物、アイデア出し…「もうAIなしでは考えられない!」なんて日も近いのかもしれません。
でも、便利なだけじゃないんですよね。
AIとの会話中に、思わず心の中で「なんでやねん!」と関西弁でツッコミを入れてしまったり、深〜いため息をついてしまったり…。「あぁ、この感じ、わかってくれる?」と、AI相手なのに誰かに共感を求めたくなる瞬間って、ありませんか?
AIは感情を持たない冷静沈着な存在ですが、対する私たちは生身の人間。
期待通りにいかないと、やっぱりモヤモヤしたり、イライラしたりしてしまうんです。
今日は、多くのAIユーザーが経験したであろう、あの「もう!」となる瞬間を、具体例を交えながらもっと詳しく掘り下げてみたいと思います。
そして、少しでもAIとの対話がラクになるようなヒントも探していきましょう。
「私の言葉、届いてる?」AIに「伝わらない」時のイライラ
私たちが感じるイライラの根源は、やはり「言葉が通じない」と感じる瞬間にあります。
人間同士なら当たり前に通じるはずのことが、AI相手だとどうしてこうも難しいのでしょうか。
言っていることを理解してもらえず、同じ説明を何度も繰り返す必要がある時
例えば、「さっき提示したこのデータ(表A)と、別のデータ(表B)を比較して、違いを分析してほしい」とお願いしたとします。
AIは「承知しました」と答えたのに、出てきたのは表Aだけの分析だったり、全く関係ないデータを持ち出したり…。
そこで「いいえ、表Bも一緒に比較してほしいんです」と丁寧に言い直しても、また同じような回答が…。
これを3回、4回と繰り返すうちに、どんどん疲弊してしまいます。
「もう、日本語が通じないのか!?」と、AI相手なのに本気で言語の壁を感じる瞬間です。
指示した内容が反映されず、期待と異なる応答が返ってくる時
「ブログ記事のタイトル案を10個、ターゲット層である30代女性向けに、親しみやすいトーンで考えてください。
キーワードは『時短』『レシピ』『一人暮らし』です。」と、かなり具体的に指示を出したとします。
すると、返ってきたのは20代男性向けの専門用語ばかりのタイトル案だったり、キーワードが全く含まれていなかったり…。
こちらの要望をまるで聞いていなかったかのような回答に、ガックリ肩を落とします。
「私の指示、複雑すぎた?」「それとも、どこか言葉が足りなかった?」と、自分を責めてしまうことも。
「さっき『分かった』って…」同じミスを繰り返すAIへの不信感
一度は「理解しました」と答えたはずなのに、すぐに同じ過ちを繰り返されると、私たちはAIの言葉を信じられなくなってしまいます。
「分かりました」と言ったにも関わらず、次に同じミスを繰り返す時
前のターンで「〇〇という表現は避けてください」と修正をお願いし、AIも「はい、今後はその表現は使用しません」と明確に答えたとします。
なのに、次の応答でサラッとその避けてほしい表現がまた登場する…。
この時感じるのは、イライラというよりも、もはや「不信感」です。
「私の言葉、一時的に記憶してるだけ?」「本当に内容を理解して修正しているわけじゃないんだな…」と、AIの知性そのものに疑問を感じてしまいます。
過去のやり取りを忘れてしまい、状況を最初から説明し直さなければならない時
これは特に、複雑なタスクを依頼している時や、複数の指示を順番に進めている時に起こりがちです。
AIが途中で会話の文脈を見失い、「申し訳ありません、もう一度最初から状況を説明していただけますか?」と言われた瞬間、「え、さっきまで話してたじゃん!」となります。
これまでの会話の積み重ねが全て無駄になったかのような感覚に、深い疲労を感じます。
まるで、記憶喪失になってしまった相手と話しているかのようです。
「それ、知ってるし…」見当違いなAIの回答への徒労感
知りたい情報や解決策を求めているのに、AIから的外れな回答が返ってくると、私たちは無駄な時間を使ったことへの徒労感を感じます。
当たり前のことをもっともらしく説明されたり、頓珍丈な回答をされたりする時
例えば、「ウェブサイトのSEOを改善する方法について、初心者向けに教えてください」と質問したとします。
すると、「キーワードは重要です」「高品質なコンテンツを作成しましょう」といった、SEOについて少しでもかじったことがある人なら誰でも知っているような、あまりにも基本的な回答が返ってくることがあります。
「それはそうだけど…! もっと具体的に!」と思ってしまいます。
あるいは、「〇〇という現象について科学的に説明してください」と質問したのに、なぜか料理のレシピが返ってきた…など、全く意図しないトンチンカンな回答が来た時の衝撃と徒労感は相当なものです。
見当違いな提案や質問をしてくる時
「このブログ記事の構成案を考えてください」と依頼した後に、「ところで、この記事のターゲット読者の年齢層は?」と、既に冒頭で伝えていたはずの情報を質問し返されたり。
あるいは、「この商品のキャッチコピーを考えてください」という依頼に対して、「この商品の価格帯を教えていただけますか?」と、キャッチコピー作成には通常不要な情報を求めてきたり。
こちらの状況や既出の情報を把握しきれていない様を見ると、「私の説明が下手なのかな…」と自己嫌悪に陥ることもあります。

曖昧な表現と、分かりきった説明へのもどかしさ
AIの回答の質に関するイライラもあります。
「〜だと思います」「〜かもしれません」など、断定を避ける曖昧な表現が多い時
これはAIの性質上、学習データに基づいた確率的な応答をするため仕方ない部分ですが、特に事実確認や明確な判断を求めている場面で、「〜の可能性が考えられます」「〜と言えるかもしれません」といった曖昧な表現ばかりだと、結局自分で調べ直さなければならず、二度手間になります。
もう少し自信を持って答えてほしい、と思ってしまいます。
自分の処理能力や限界について、分かりきった説明をされる時
「私は大量のデータに基づいて学習していますが、感情を持つことはありません。」
「私は2023年までのデータで学習しているため、それ以降の情報については正確性が保証できません。」といった、AIの能力に関する一般的な説明を、必要ない場面で挿入される時。
「それはもう知ってるよ!」と思ってしまい、会話のテンポが悪くなるもどかしさを感じます。
求めているのはAIの自己紹介ではなく、課題解決の糸口なんです。
「感情がない」からこそ生まれる、一方通行なフラストレーション
結局のところ、これらのイライラの多くの根源は、AIが感情を持たないことに起因しているのかもしれません。
私たちは、相手の表情や声のトーン、言葉の選び方から感情や真意を汲み取ろうとしますが、AIにはそれがありません。
だからこそ、私たちのフラストレーションや「こうしたい!」という強い気持ちが、AIには「単なるテキスト情報」としてしか認識されず、一方通行なコミュニケーションになってしまうのかもしれません。
「このタスクがいかに重要か」「なぜこの部分の修正にこだわっているのか」といった、感情や背景にある文脈を理解してもらえない時、私たちは「理解してもらえない」という孤独感やフラストレーションを感じてしまうのです。
AIとの付き合い方をアップデート!イライラを減らす実践ヒント
AIとの対話で「もう!」となる瞬間をゼロにするのは難しいかもしれません。
でも、ちょっとしたコツや心構えで、イライラを減らし、AIをもっと上手に活用できるようになるはずです。
私も、試行錯誤しながら以下のことを意識するようになりました。
ヒント1:AIは「完璧な人間」ではなく「高性能な道具」と割り切る
AIに人間のような柔軟性や共感性を期待しすぎないことが大切です。
「完璧な回答が得られなくても当然」と割り切ることで、期待外れだった時のショックを減らせます。
あくまで、私たちの作業を効率化してくれる「高性能な道具」として捉えましょう。
ヒント2:指示は箇条書きで「分解」して与える
複雑な指示や複数の要望がある場合は、一度に投げかけず、箇条書きで項目を分け、一つずつ順番に指示を与えてみてください。
AIが一度に処理できる情報量には限りがあります。
ステップごとに確認しながら進めることで、ミスを防ぎやすくなります。
ヒント3:欲しい回答の「型」を示す
「〜の視点で」「〜の形式で」「〜を含めて」など、具体的な型を示すことで、AIが期待する回答に近いものを生成しやすくなります。
「例えば、こんな感じで」と例を出すのも効果的です。
ヒント4:イライラしたら「休憩」、そして「リセット」
何度かやり取りしても上手くいかない時は、一度会話を中断しましょう。
時間を置くことで冷静になれます。
そして、可能であればチャットを一度閉じ、新しいチャットで最初からやり直してみてください。
AIによっては、新しい会話の方が過去の文脈に引きずられず、より正確な応答をする場合があります。
ヒント5:時には別のAIやツールも試してみる
一つのAIで上手くいかなくても、別のAIツールや、そもそもAIを使わない別の方法の方が効率的な場合もあります。
固執せず、目的に合わせて最適なツールを選択する柔軟性も大切です。
AIとの対話は、新しいコミュニケーションのかたち

AIとの対話は、人間同士のコミュニケーションとは全く異なる、新しい形です。
戸惑いやイライラを感じるのは当然のこと。
でも、この新しいコミュニケーションの「クセ」を理解し、私たちの側が少しだけアプローチを変えることで、AIはもっと強力な味方になってくれます。
完璧ではないからこそ、試行錯誤する面白さもあるのかもしれません。
この記事を読んで、「そうそう!あるある!」と共感してくれたり、AIとの付き合い方を見直すヒントになったりすれば嬉しいです。
AIと私たちの、ちょっと不器用だけど、きっと面白い対話はこれからも続いていきます。
【2コマ漫画】おいしいご飯
最新の投稿
「テクノロジー 」に関する記事
Skebでイラストリクエスト受付中:こちら
note: https://note.com/poo_pon
無料のKindle版「ぽんぷーまんが」。毎週更新中!
ぽんぷーまんがを読むAmazonでお買い物はこちらから!
※このリンク経由での購入はPON-POOの収益となる場合があります。
「テクノロジーエンタメ」人気記事
カテゴリー
一部記事及び画像はPRタイムスのプレスリリースから引用しています。