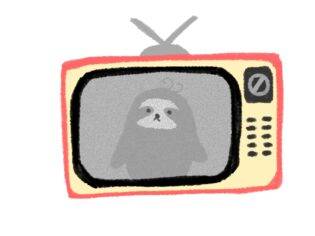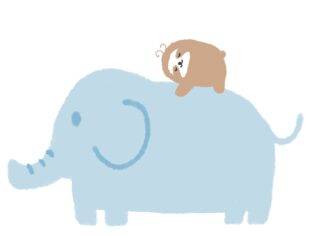8月4日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
食文化の象徴、語呂合わせで制定: 箸の日
わりばし組合が1975年(昭和50年)に制定。日付は「は(8)し(4)」(箸)と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月4日が「箸の日」なのですか?
A: 日付の「は(8)し(4)」が「箸」と読める語呂合わせにちなんで、わりばし組合によって1975年に制定されました。日本の食文化に欠かせない箸への感謝の気持ちを表す日とされています。
Q: 「箸の日」にはどのような行事が行われますか?
A: 特定の大きなイベントは少ないですが、箸への感謝を込めて古い箸を供養する「箸供養」を行う神社やお寺があります。また、箸の正しい持ち方やマナーを改めて考えるきっかけの日ともされています。
宮崎発祥、地域振興の願いも込めて: 橋の日
宮崎「橋の日」実行委員会が制定。日付は「は(8)し(4)」(橋)と読む語呂合わせから。

Q: 「橋の日」はどのようにして始まったのですか?
A: 宮崎県にある「橋の日」実行委員会が、「は(8)し(4)」の語呂合わせから提唱し、制定されました。人々の生活に不可欠な橋の重要性を再認識し、感謝することを目的としています。
Q: 宮崎県では「橋の日」に何かイベントがありますか?
A: 制定地である宮崎県では、橋の清掃活動や、橋に親しむためのウォーキングイベントなどが開催されることがあります。地域のシンボルとしての橋への関心を高める取り組みが行われています。
スリルと絶景の象徴、奈良県十津川村が制定: 吊り橋の日
奈良県吉野郡十津川村が制定。日付は「は(8)し(4)」(橋)と読む語呂合わせから。

Q: なぜ十津川村が「吊り橋の日」を制定したのですか?
A: 十津川村には、生活用鉄線橋としては日本一の長さを誇る「谷瀬の吊り橋」をはじめ、多くの吊り橋があります。これらの吊り橋が村のシンボルであり、観光資源でもあることから、その魅力をPRするために「は(8)し(4)」の語呂合わせで制定しました。
Q: 「橋の日」と「吊り橋の日」の違いは何ですか?
A: どちらも「は(8)し(4)」の語呂合わせですが、「橋の日」は宮崎県で広く橋全般を対象としているのに対し、「吊り橋の日」は特に吊り橋に焦点を当て、奈良県十津川村が制定した点に違いがあります。
Q: 十津川村の吊り橋はどのような特徴がありますか?
A: 「谷瀬の吊り橋」は長さ297メートル、高さ54メートルもあり、歩くと揺れるスリルと周囲の美しい自然景観を楽しめることで有名です。元々は地元住民の生活道として架けられましたが、現在では人気の観光スポットとなっています。
日本初のビアホール開店を記念: ビヤホールの日
株式会社サッポロライオンが1998年(平成10年)に制定。1899年(明治32年)のこの日、東京・銀座の新橋際(現:銀座八丁目)に、日本初のビアホール「恵比壽(ヱビス)ビヤホール」(銀座ライオンの前身)一号店が開店した。
Q: 「ビヤホールの日」の由来は何ですか?
A: 1899年8月4日に、現在のサッポロライオンの前身である「恵比壽ビヤホール」が東京・銀座に開店したことを記念して制定されました。これが日本におけるビヤホールの始まりとされています。
Q: なぜサッポロライオンがこの日を制定したのですか?
A: 「恵比壽ビヤホール」を開店したのがサッポロライオン(当時の日本麦酒醸造会社)であり、日本のビヤホール文化の草分けとしての歴史を記念し、さらなる発展を願って制定しました。
Q: 開店当時のビヤホールはどのような様子でしたか?
A: 開店当時は大変な人気で、ハイカラな西洋文化の象徴として多くの人で賑わったと言われています。ビールは500mlで10銭と、当時としては比較的高価でしたが、モダンな雰囲気と美味しいビールを求めて人々が集まりました。
温泉街の風情とPRを込めて: ゆかたの日
兵庫県城崎町の城崎温泉観光協会が制定。日付は「城崎ふるさと祭り」の開催される日に因む。「ゆかたの似合うまち」城崎温泉を広くPRすることが目的。
Q: なぜ8月4日が「ゆかたの日」なのですか?
A: この日は、城崎温泉で「城崎ふるさと祭り」が開催される日であり、多くの人が浴衣を着て温泉街を楽しむことにちなんで制定されました。語呂合わせではなく、地域のイベントに合わせた日付設定です。
Q: 「ゆかたの日」の目的は何ですか?
A: 「ゆかたの似合うまち」として知られる城崎温泉の魅力を、浴衣を通じて広くアピールすることが目的です。浴衣を着て外湯めぐりや散策を楽しむ文化を奨励しています。
Q: 城崎温泉以外でも「ゆかたの日」はあるのですか?
A: はい、日本ゆかた連合会が7月7日を「ゆかたの日」として制定しています。これは七夕に浴衣を着る習慣があったことや、織姫が機織り(=布)に関係することなどに由来するそうです。城崎温泉の「ゆかたの日」は地域独自の記念日と言えます。
わさビーフでお馴染み、語呂合わせで制定: ヤマヨシの日
山芳製菓株式会社が制定。日付は「や(8)まよ(4)し」(山芳)と読む語呂合わせから。
Q: 「ヤマヨシの日」は何の記念日ですか?
A: 「わさビーフ」などのポテトチップスで知られる山芳製菓株式会社が、自社の名前「やまよし」の語呂合わせ「や(8)まよ(4)し」から8月4日を記念日として制定しました。
Q: この記念日の目的は何ですか?
A: 自社ブランドや商品への関心を高め、顧客への感謝を示すことを目的としていると考えられます。記念日に合わせたキャンペーンなどが行われることもあります。
健康増進と走る楽しさを広める: 走ろうの日
熊本県熊本市の「熊本走ろう会」が制定。日付は「は(8)し(4)ろう」(走ろう)と読む語呂合わせから。

Q: 「走ろうの日」は誰が制定したのですか?
A: 熊本県熊本市を拠点に活動するランニング愛好家グループ「熊本走ろう会」が制定しました。日付は「は(8)し(4)ろう」の語呂合わせです。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: ランニングやジョギングを通じて健康増進を図り、走ることの楽しさを多くの人に広めることを目的としています。仲間と一緒に走る喜びを共有する日でもあります。
Q: 「熊本走ろう会」はどのような活動をしていますか?
A: 定期的な練習会やランニングイベントの開催、地域のマラソン大会への参加などを通じて、メンバー同士の交流や市民の健康づくりに貢献する活動を行っています。
一粒万倍日と天赦日が重なる最強開運日 (2024年): 開運の日
暦の上で縁起が良いとされる「一粒万倍日(いちりゅう まんばいび)」と、日本の暦の上で最上の吉日とされる「天赦日(てんしゃにち/てんしゃび)」が重なる日は、年に数回しかない非常に縁起の良い日とされています。2024年の8月4日はそのうちの一日です。
Q: 「一粒万倍日」とは何ですか?
A: 「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味があり、何かを始めるのに最適な日とされています。特に、仕事始め、開店、種まき、お金を出すこと(投資など)が良いとされますが、借金や人から物を借りることは苦労の種が万倍になるとされ、避けるべきと言われています。
Q: 「天赦日」とはどのような日ですか?
A: 「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、暦の上で最高の吉日と言われています。この日に始めたことは何事も成功するとされ、特に結婚、結納、入籍、出生届、引っ越し、開業、財布の新調などが推奨されます。他の凶日と重なっても、天赦日が打ち消すとも言われています。
Q: この二つが重なると、なぜ「最強開運日」なのですか?
A: 最上の吉日である天赦日と、始めたことが万倍になって返ってくる一粒万倍日が重なることで、その縁起の良さがさらに増幅されると考えられているためです。何か新しいことを始めたり、大きな決断をしたりするのに、これ以上ないほど適した日とされています。