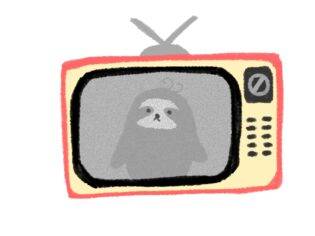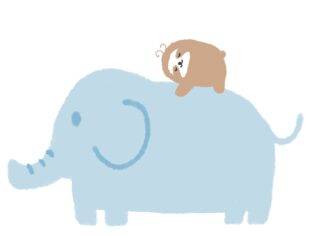8月13日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本三大夜景の一つ、ユニークな語呂合わせで制定: 函館夜景の日
函館夜景の日実行委員会が1991年(平成3年)から実施。日付は「8(や)」と「13(トランプのK)」で「やけい」(夜景)と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月13日が「函館夜景の日」なのですか?
A: 日付の「8」を「や」、「13」をトランプのキング(K)に見立てて「やK = やけい(夜景)」と読むユニークな語呂合わせから、函館夜景の日実行委員会によって制定されました。
Q: 函館の夜景はなぜ有名で美しいのですか?
A: 函館山から見下ろす夜景は、市街地が津軽海峡と函館湾に挟まれた独特のくびれた地形をしており、扇形に広がる街の灯りと、それを縁取る暗い海とのコントラストが非常に美しいとされています。ナポリ、香港と並んで「世界三大夜景」と称されたこともあり、現在でも「日本三大夜景」の一つとして人気です。
Q: この記念日には何かイベントがありますか?
A: 制定された当初は、函館山ロープウェイの割引や関連イベントなどが実施されていました。現在も、この日に合わせて夜景を楽しむ企画が行われることがあります。
夏の夜を涼しく? 稲川淳二が制定したエンタメ記念日: 怪談の日
稲川淳二氏が制定。自身の「MYSTERY NIGHT TOUR 稲川淳二の怪談ナイト」20周年連続公演を記念して記念日とした。

Q: なぜ稲川淳二氏が「怪談の日」を制定したのですか?
A: タレントであり、怪談の語り部としても有名な稲川淳二氏が、自身のライフワークである「稲川淳二の怪談ナイト」が2012年に20周年連続公演を迎えたことを記念して、怪談文化の振興とファンへの感謝を込めて制定しました。日付の由来は特に定められていないようです。
Q: 「稲川淳二の怪談ナイト」とはどのようなイベントですか?
A: 稲川淳二氏が自ら収集した不思議な話や怖い話を、独特の語り口と演出で披露するライブツアーです。夏の風物詩として長年人気を博しており、全国各地で開催されています。
Q: なぜ夏に怪談が語られることが多いのですか?
A: 諸説ありますが、お盆の時期に先祖の霊が帰ってくるという信仰と結びつき、霊的な話への関心が高まることや、怖い話を聞いて背筋が寒くなることで夏の暑さをしのぐ「納涼」の効果を期待することなどが理由として挙げられます。また、江戸時代の歌舞伎や落語で夏向けの演目として怪談物が人気だったことも影響していると言われています。
左利きの暮らしやすさを考える国際デー: 左利きの日 (International Lefthanders Day)
イギリスにある「Lefthanders Club」が、左利きの人々の権利擁護と、日常生活における様々な不便(ハサミ、缶切り、改札など)についての認知向上、そして左利きであることのユニークさを祝うために提唱した記念日。1992年に正式に制定されました。
Q: なぜ8月13日が「左利きの日」になったのですか?
A: 提唱者であるイギリスの「Lefthanders Club」の設立者ディーン・R・キャンベル氏の誕生日という説もありますが、明確な理由は公式には発表されていません。1992年からこの日に祝われるようになりました。
Q: 左利きの人は世界にどれくらいいるのですか?
A: 全人口の約10%程度が左利きであると言われています。割合は地域や文化によって多少異なります。
Q: この日にはどのような活動が行われますか?
A: 世界各地で、左利きの人々が日常生活で感じる不便さや、それを解消するための工夫について共有したり、左利き用の道具を紹介したりするイベントが行われます。また、SNSなどを通じて左利きであることの経験や誇りを語り合う動きも見られます。
ご先祖様をお迎えする日本の伝統行事: お盆(迎え盆)
多くの地域で8月13日は「迎え盆」にあたり、お盆の期間が始まります(地域によっては旧暦7月13日や新暦7月13日など異なります)。この日は、ご先祖様の霊が自宅に帰ってくるとされ、家の門口や仏壇の前で「迎え火」を焚いてお迎えする風習があります。
Q: 「迎え火」にはどのような意味があるのですか?
A: ご先祖様の霊が、あの世から自宅へ帰ってくる際に道に迷わないように、目印として火を焚くという意味合いがあります。麻の茎を乾燥させた「おがら」を燃やすのが一般的ですが、地域や家庭によっては提灯を灯す場合もあります。
Q: お盆には他にどのようなことをしますか?
A: 仏壇にお供え物をしたり、お墓参りに行ったり、僧侶にお経をあげてもらったりします。家族や親戚が集まり、ご先祖様を供養するとともに、故人を偲び、家族の絆を確認する大切な期間とされています。ナスやキュウリで作る「精霊馬(しょうりょううま)」を飾る風習も有名です。
Q: お盆の期間はいつまでですか?
A: 迎え盆の対として、通常は8月15日または16日に「送り盆」があり、ご先祖様の霊を再びあの世へ送るための「送り火」を焚きます。京都の「五山の送り火(大文字焼き)」などが有名です。お盆の期間や風習は地域によって多様性があります。