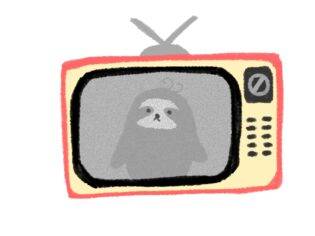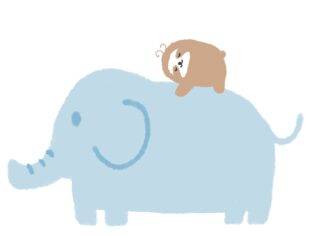8月16日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
サービス開始記念、手軽な読書体験を広めた日: 電子コミックの日
NTTソルマーレ株式会社が制定。電子コミックサイトのサービス開始10周年を記念して記念日とし、日付はサービスを開始した2004年(平成16年)8月16日から。

Q: なぜ8月16日が「電子コミックの日」なのですか?
A: NTTソルマーレ株式会社が運営する大手電子コミックサイト「コミックシーモア」が、2004年8月16日にサービスを開始したことを記念して制定されました。日本の電子書籍市場の発展に貢献してきた日と言えます。
Q: 電子コミックを利用するメリットは何ですか?
A: スマートフォンやタブレットがあれば、いつでもどこでも好きな漫画を手軽に購入して読むことができます。また、紙の単行本のように保管場所を取らず、多数の作品を持ち運べる点も大きなメリットです。検索機能で読みたい作品をすぐに見つけられる利便性もあります。
Q: NTTソルマーレはどのような事業を行っていますか?
A: 「コミックシーモア」をはじめとする電子書籍ストア事業を中核に、モバイルゲームや健康情報サービスなど、多様なデジタルコンテンツサービスを提供するNTT西日本グループの企業です。
家庭の常備薬、語呂合わせで制定された製品記念日: キップ パイロールの日
キップ薬品株式会社が制定。日付は同社の軟膏剤「キップ パイロール」の「パ(8)イロ(16)ール」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ8月16日が「キップ パイロールの日」なのですか?
A: 家庭用軟膏剤「キップ パイロール-Hi」などの製品名にある「パイロール」を「パ(8)イロ(16)ール」と読む語呂合わせから、製造元のキップ薬品株式会社が制定しました。
Q: 「キップ パイロール」はどのような時に使う薬ですか?
A: 軽度のやけど、切り傷、すり傷、ひび、あかぎれ、かみそりまけ、日やけ、雪やけによる炎症などに効能があるとされる非ステロイド系の皮膚治療薬です。殺菌作用を持つ成分も配合されており、家庭の常備薬として長年使われています。
Q: この記念日の目的は何ですか?
A: 自社のロングセラー製品である「キップ パイロール」への関心を高め、その効能や正しい使い方を改めて知ってもらい、ブランドへの親しみを深めてもらうことを目的としています。
古都の夜空を焦がす荘厳な盆行事: 五山の送り火
毎年8月16日の夜に、京都を囲む山々に「大」「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」の文字や形が次々と点火される、お盆の伝統行事です。お盆に迎えた先祖の霊(精霊)を再びあの世へ送り出すための「送り火」とされています。
Q: なぜこの行事が「五山」と呼ばれるのですか?
A: 送り火が焚かれる五つの山、すなわち東山如意ヶ嶽(大文字)、松ヶ崎西山・東山(妙法)、西賀茂船山(船形)、大北山(左大文字)、嵯峨鳥居本曼荼羅山(鳥居形)を指して「五山」と総称するためです。
Q: 送り火はどのようにして準備・実行されるのですか?
A: 各山の保存会の人々が中心となり、数ヶ月前から準備を進めます。当日は、護摩木(願い事が書かれた薪木)を集め、日没後に各山の定められた時刻に一斉に点火されます。火床の配置や薪の組み方には、それぞれの山に伝わる独特の方法があります。
Q: この行事の起源はいつ頃ですか?
A: 起源については諸説あり、正確なことは分かっていませんが、室町時代や江戸時代初期には既に行われていたと考えられています。弘法大師空海や足利義政に由来するという伝説もありますが、庶民の間の祖霊信仰や疫病退散の祈りが結びついて発展してきたと考えられています。
女性の高等教育への道を開いた日: 女子大生の日
1913年(大正2年)のこの日、東北帝国大学(現在の東北大学)が、官立大学として日本で初めて女子学生3名の入学を許可し、合格を発表したことを記念する日です。合格したのは黒田チカ(化学)、丹下ウメ(応用化学)、牧田らく(数学)の3名でした。
Q: なぜ東北帝国大学が最初に女子学生を受け入れたのですか?
A: 当時の初代総長であった澤柳政太郎が「門戸開放」という理念を強く掲げ、性別による入学資格の制限を設けなかったためです。これは、当時の「良妻賢母」を理想とする女子教育観や、文部省の方針とは異なる画期的な判断でした。
Q: 当時の社会の反応はどうでしたか?
A: 女子が帝大で男子と共に学ぶことに対しては、社会的な偏見や批判も少なくありませんでした。しかし、彼女たちの入学は、女性の知的好奇心や学ぶ権利を象徴する出来事として、後の女性の社会進出に大きな勇気と影響を与えました。
Q: 合格した3名はその後どのような道を歩みましたか?
A: 3名とも優秀な成績で卒業し、黒田チカと丹下ウメは日本人女性初の理学士となりました。それぞれが研究者や教育者として活躍し、日本の女性科学者の草分け的存在として大きな足跡を残しました。
ご先祖様を見送る、お盆期間の終わり: 月遅れ盆送り火
多くの地域(特に月遅れ盆を行う地域)で、8月16日はお盆の期間中に自宅に迎えていたご先祖様の霊を、再びあの世へ送り出す「送り盆」の日とされています。玄関先などで「送り火」を焚いて、霊が無事に帰れるように道しるべとします。
Q: 「送り火」にはどのような意味が込められていますか?
A: ご先祖様の霊が無事にあの世へ戻れるように帰り道を照らすという意味合いのほか、お盆の間一緒に過ごせたことへの感謝の気持ちや、また来年も無事に戻ってきてほしいという願いが込められているとも言われます。
Q: 送り火はどのように行うのが一般的ですか?
A: 迎え火と同様に、麻の茎を乾燥させた「おがら」を焙烙(ほうろく)という素焼きの皿の上などで燃やすのが一般的です。地域によっては提灯を灯したり、川や海に灯籠を流す「精霊流し」を行ったりするなど、様々な形で見送りが行われます。
Q: お盆の行事は全国で同じですか?
A: お盆の時期(新暦7月、旧暦7月、月遅れ8月)や期間、迎え火・送り火の形式、お供え物、精霊馬の風習など、地域や宗派、各家庭によって多様な違いが見られます。それぞれの地域の文化や歴史を反映した大切な伝統行事です。