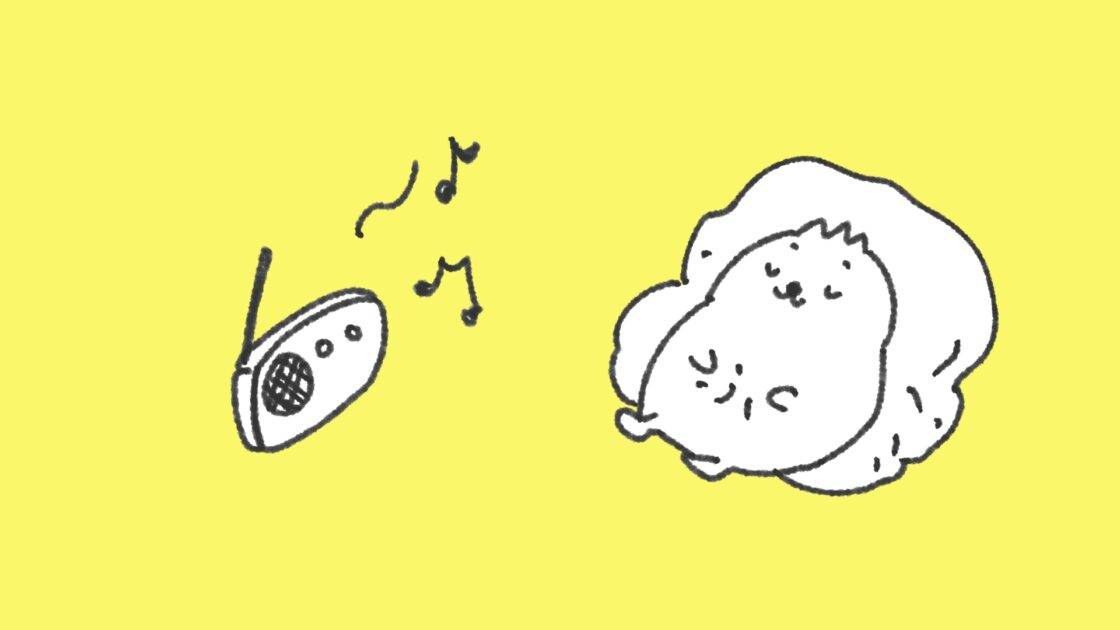
今日は何の日「2月13日」
投稿日 : 2024.02.13
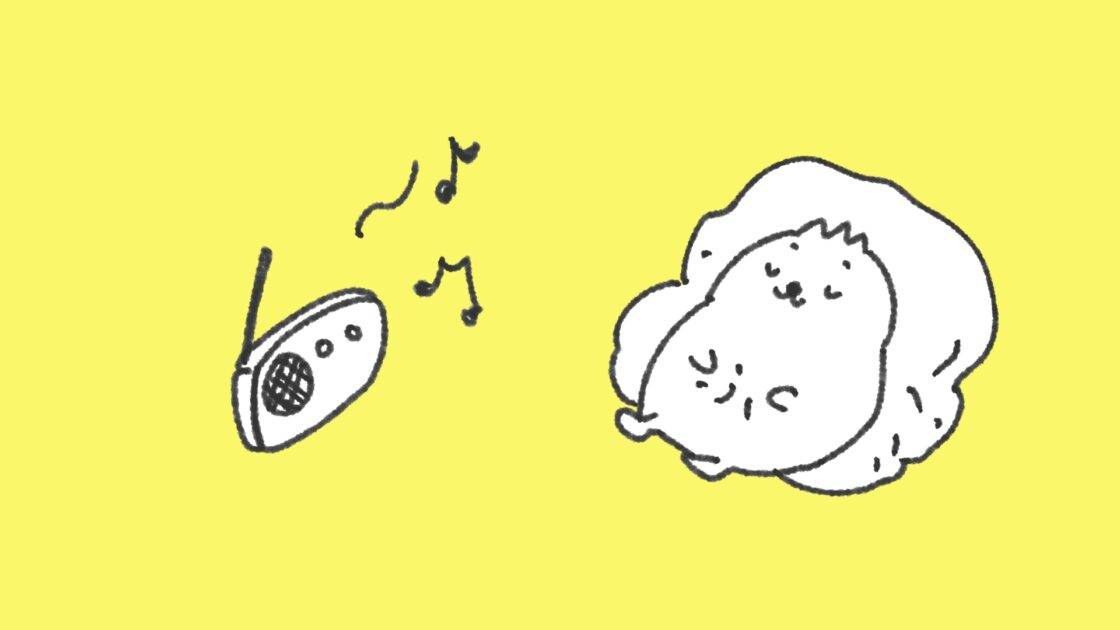
投稿日 : 2024.02.13
2月13日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
1946年(昭和21年)のこの日、国連により国際連合放送(United Nations Radio)が開設されたことにちなんで。
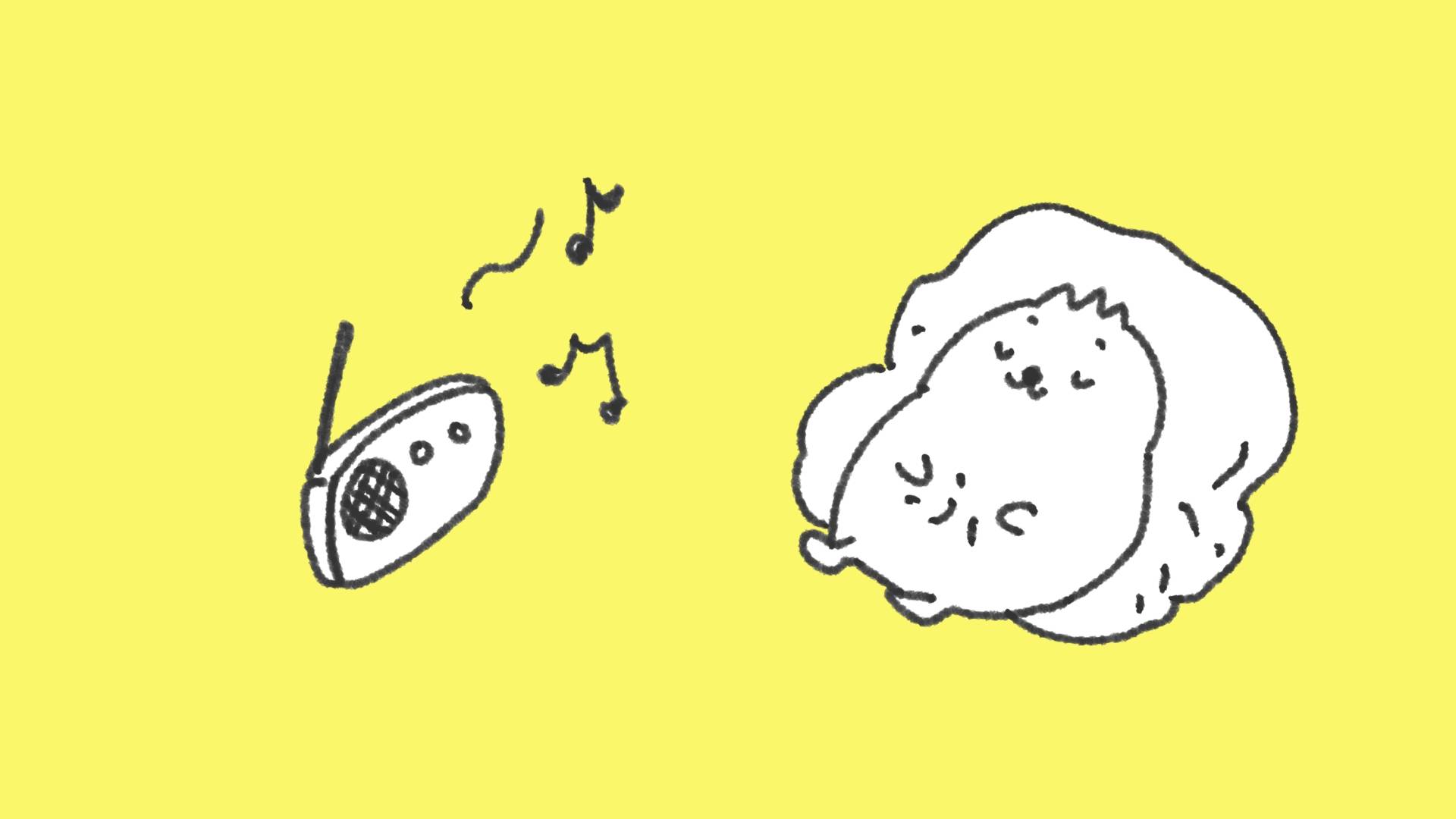
1875年(明治8年)に、苗字を名乗ることを義務づける「平民苗字必称義務令」という太政官布告が出された日にちなんで。
苗字を使っていたのは貴族と武士だけだった苗字を平民でも名乗ることを許可する「平民苗字許可令」は1870年(明治3年)。
「ニーサ(213)」と読む語呂合わせから。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は2014年(平成26年)から開始されました。
高知県の特産果樹「土佐文旦(とさぶんたん)」の生産者・農協・県などで組織する土佐文旦振興対策協議会が制定。
この記事をシェアする