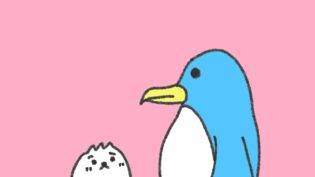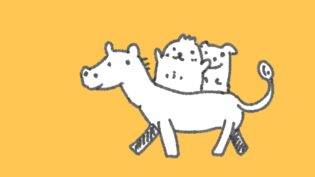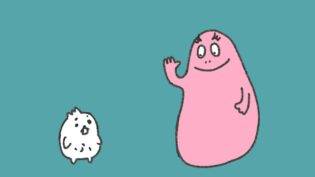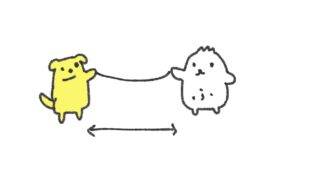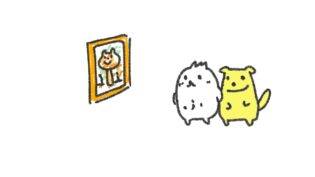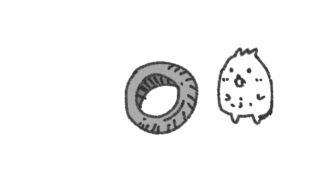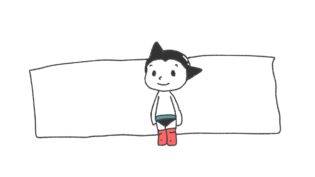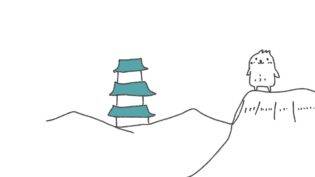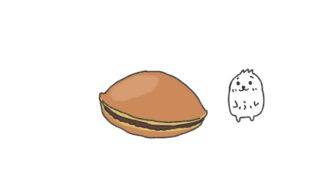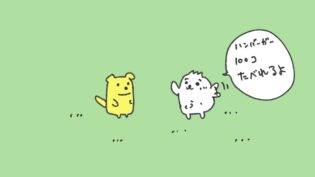4月19日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
みずみずしい旬の味「よ(4)い(1)きゅう(9)り」: 良いきゅうりの日
愛知県西三河地区のJA(農業協同組合)で構成される「西三河冬春きゅうり部会」が制定。日付は「よ(4)い(1)きゅう(9)り」(良いきゅうり)と読む語呂合わせから。新鮮で美味しい、高品質な地元産きゅうりをPRする日です。
Q: 良いきゅうりの日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 西三河地域で生産される、特に冬から春にかけて旬を迎える高品質なきゅうりの消費拡大とPRを目的として、生産者団体である西三河冬春きゅうり部会によって制定されました。きゅうりの栄養価(カリウム、ビタミンK、水分など)や、サラダ、漬物、炒め物など様々な料理に使える versatility を再認識してもらい、日々の食卓に取り入れてもらうことを目指しています。
Q: なぜ4月19日が「良いきゅうりの日」なのですか?
A: 「4(よ)1(い)9(きゅう)り」という、覚えやすく、きゅうりの品質の良さを連想させる語呂合わせから、この日が選ばれました。春になり、きゅうりの出荷量が増え、美味しくなる時期に合わせて、消費者にアピールする狙いもあります。
Q: 美味しいきゅうりの見分け方は?
A: 色が濃く、全体にハリとツヤがあり、表面のイボ(突起)がチクチクと尖っているものが新鮮で美味しいとされています。太さが均一で、持った時に重みを感じるものを選びましょう。曲がっていても味に大きな違いはありません。
身分を超えた移動の自由へ: 乗馬許可記念日
1871年(明治4年)4月19日(旧暦3月1日)に、明治政府が出した太政官布告により、それまで身分制度のもとで武士階級や一部の特権階級に限られていた「乗馬」が、一般庶民にも許可されたことを記念する日です。
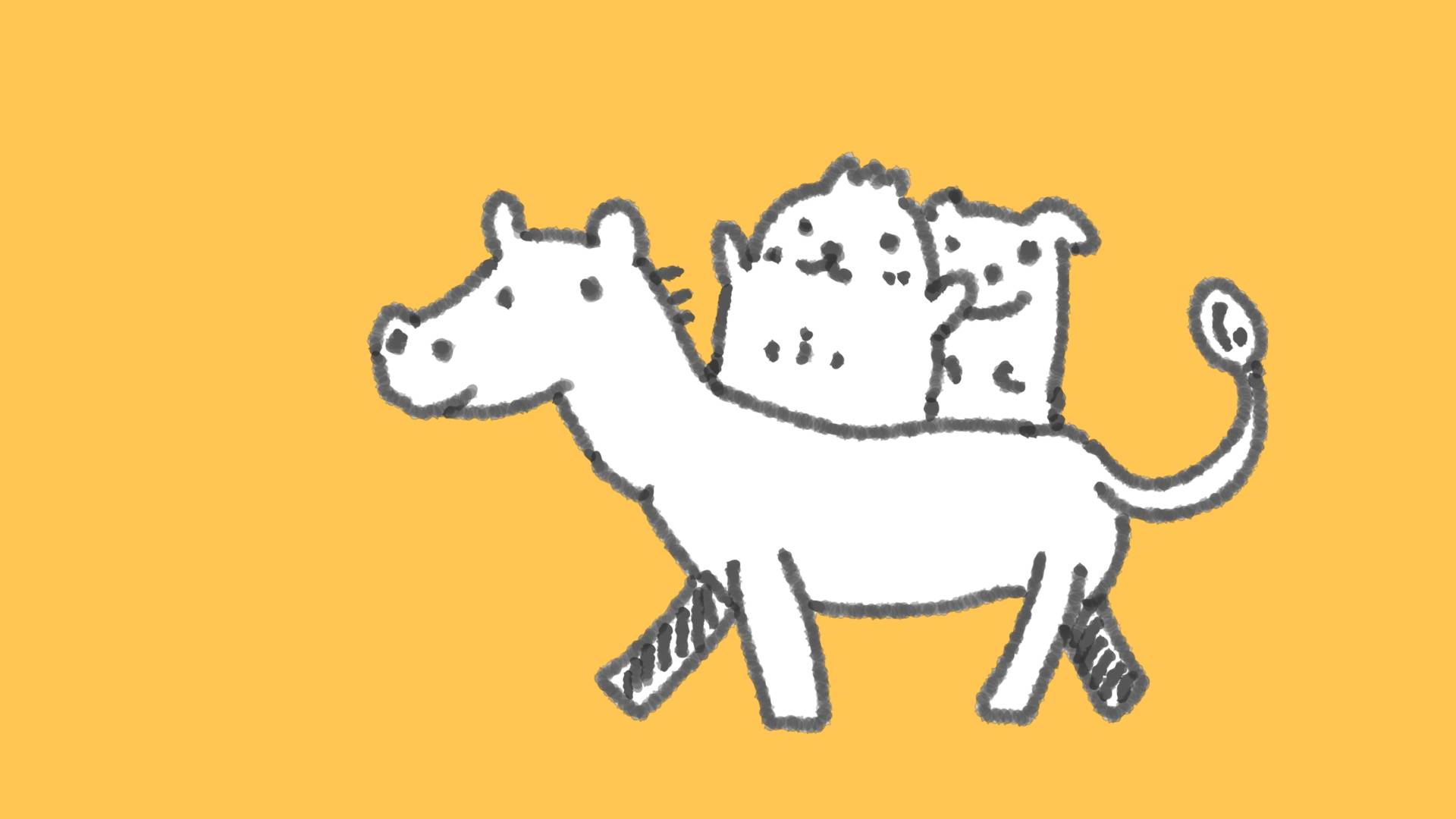
Q: なぜ明治政府は庶民に乗馬を許可したのですか?
A: 明治維新による四民平等(士農工商の身分制廃止)の理念に基づき、旧来の身分による特権や制限を撤廃していく流れの一環でした。また、交通手段としての馬の利用をより広く認めることで、物流や人の移動を円滑にし、近代化を促進する狙いもあったと考えられます。
Q: 江戸時代は庶民は馬に乗れなかったのですか?
A: 原則として、武士以外の身分(農民、町人など)が公の場で乗馬することは禁じられていました。馬は軍事力や権威の象徴であり、重要な交通・輸送手段でもあったため、厳しく管理されていました。ただし、荷物を運ぶ駄馬(だば)や、特別な許可を得た場合などは例外もありました。
Q: この許可は社会にどのような影響を与えましたか?
A: すぐに庶民の間で乗馬が広まったわけではありませんが、身分による制約が取り払われたことを示す象徴的な出来事の一つでした。移動や輸送の自由度が高まるきっかけとなり、その後の交通網の発達にも繋がっていきました。
動物園・水族館の舞台裏を知る「し(4)い(1)く(9)」: 飼育の日
全国の動物園や水族館が加盟する公益社団法人 日本動物園水族館協会(JAZA)が、協会の創立70周年を記念して2009年(平成21年)に制定。日付は「し(4)い(1)く(9)」(飼育)と読む語呂合わせから。
Q: 飼育の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 動物園や水族館の重要な使命である「種の保存」「教育・環境教育」「調査・研究」そして「レクリエーション」の提供を支える根幹となる「飼育」という仕事に光を当て、その専門性や、動物福祉への配慮、飼育下での繁殖への努力などを広く一般の人々に伝え、動物園・水族館への理解と関心を深めてもらうことを目的としています。
Q: なぜ4月19日が「飼育の日」なのですか?
A: 「飼育(しいく)」という言葉の響きが、「し(4)い(1)く(9)」という数字の語呂合わせによく合うことから、覚えやすく親しみやすいこの日が選ばれました。
Q: 飼育員さんはどのような仕事をしているのですか?
A: 担当する動物たちの日々の健康管理(給餌、清掃、観察、体調チェック)、飼育環境の整備、繁殖への取り組み、動物の生態や魅力をお客さんに伝えるためのガイドや解説、そして動物に関する調査・研究など、非常に多岐にわたる専門的な仕事をしています。動物への深い愛情と知識、そして体力や忍耐力が求められる仕事です。
地図で世界と未来を測る: 地図の日(最初の一歩の日)
1800年(寛政12年)旧暦閏4月19日(新暦では6月11日頃)に、江戸時代の測量家・伊能忠敬(いのう ただたか)が、蝦夷地(えぞち、現在の北海道)南東部の測量に出発した日です。これが、後に日本全国の詳細な地図『大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)』作成へと繋がる、測量の第一歩となったことを記念する日です。「最初の一歩の日」とも呼ばれます。
Q: なぜ伊能忠敬は全国の測量を始めたのですか?
A: 彼は50歳を過ぎてから天文学と測量学を学び、当初は個人的な興味や学術的な目的で、自費で蝦夷地の測量を行いました。その成果が幕府に認められ、その後、幕府の事業として日本全国の沿岸測量を命じられることになりました。正確な地図を作成することで、国防や行政に役立てる目的もありました。
Q: 伊能忠敬の測量はどのように行われたのですか?
A: 非常に精密な測量器具(方位盤、半円方位盤、量程車など)を用い、実際に自分の足で海岸線などを歩きながら、距離と方位を測定していく「導線法」という方法で測量を進めました。約17年間にわたり、延べ4万キロ近くを測量したと言われています。彼の没後、弟子たちによって地図は完成しました。
Q: 伊能図(大日本沿海輿地全図)の価値は何ですか?
A: 江戸時代に、一個人の情熱と努力、そして幕府の支援によって作られた、驚くほど正確で詳細な日本地図です。当時の日本の海岸線や地形を正確に記録しており、地理学的な価値はもちろん、歴史資料としても極めて高い価値を持っています。近代的な地図作成技術の礎となりました。