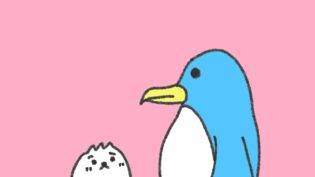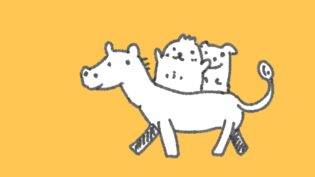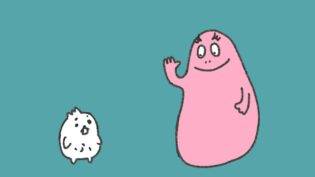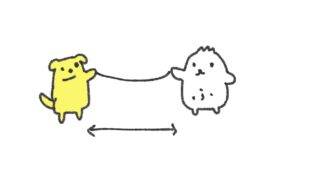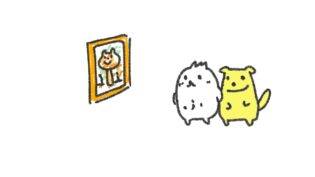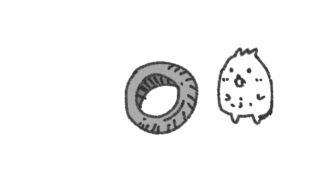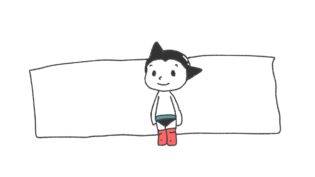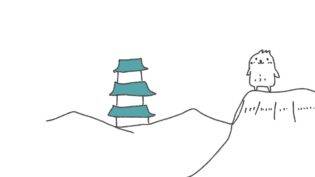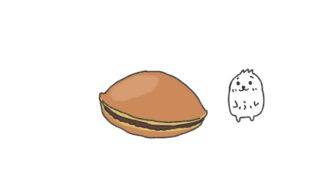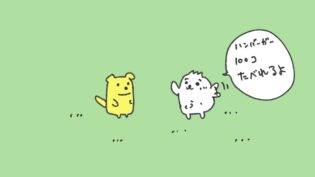4月28日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
江戸時代の人気者、天皇に拝謁: 象の日
1729年(享保14年)旧暦3月28日(新暦では4月28日頃とされる)に、現在のベトナム中部(交趾:こうち)から江戸幕府への献上品として清(当時の中国)の商人が長崎に連れてきた象が、江戸へ向かう途中で京都に立ち寄り、中御門(なかみかど)天皇と霊元(れいげん)上皇の御前にて披露されたという記録にちなむ記念日です。(※新暦換算には諸説あり、6月7日などとも言われます)
Q: 象の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の団体によって制定された記念日ではありませんが、江戸時代中期に、遠い異国から生きた象が日本へもたらされ、当時の最高権威である天皇にまでお披露目されたという、非常に珍しく、人々の関心を集めた歴史的な出来事を記念する日として語られています。動物への好奇心や、当時の世相、異文化交流の歴史に思いを馳せる日です。
Q: なぜ4月28日が「象の日」なのですか?
A: 1729年(享保14年)の旧暦3月28日に、ベトナムから来た象が京都で中御門天皇に拝謁したという記録に基づいており、その旧暦の日付を新暦に換算したものが4月28日頃にあたるとされているためです。(ただし、旧暦と新暦の換算は単純ではなく、他の日付とする説もあります。)
Q: この象はその後どうなりましたか?
A: この象(広南従四位白象と名付けられた)は、無事に江戸へ到着し、8代将軍・徳川吉宗にも披露され、浜御殿(現在の浜離宮恩賜庭園)で飼育されました。当時の江戸では大変な人気者となり、多くの見物人が訪れたり、絵画や工芸品の題材になったりしたと言われています。しかし、日本の気候や餌に慣れず、約10年後に死んでしまったと伝えられています。
占領終結、日本の独立回復: 主権回復の日・サンフランシスコ平和条約発効記念日
1952年(昭和27年)4月28日に、前年9月に調印された「日本国との平和条約」(通称:サンフランシスコ平和条約)が発効したことを記念する日です。この条約の発効により、第二次世界大戦後7年近くにわたった連合国(主にアメリカ)による日本の占領状態が終結し、日本は独立国としての主権を完全に回復しました。2013年には、日本政府によってこの日を「主権回復の日」とすることが閣議決定されました。
Q: 主権回復の日・サンフランシスコ平和条約発効記念日は、どのような目的で定められましたか?
A: 日本が第二次世界大戦後の占領期を終え、国際社会において独立した主権国家として新たなスタートを切ったという、戦後日本の歴史における極めて重要な節目を国民全体で認識し、その意義を次世代に伝えていくことを目的としています。日本の独立と発展の歴史を振り返り、未来について考える契機とする日です。
Q: なぜ4月28日が「主権回復の日・サンフランシスコ平和条約発効記念日」なのですか?
A: 1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約が、1952年4月28日の午後10時30分(日本時間)をもって正式に発効した、まさにその歴史的な日付に基づいています。この瞬間をもって、日本は連合国による占領から解放され、独立国としての地位を取り戻しました。
Q: サンフランシスコ平和条約にはどのような内容が含まれていますか?
A: 日本と連合国との間の戦争状態の終結、日本の主権の承認、領土の範囲(沖縄、小笠原などの分離)、賠償問題、安全保障に関する条項などが定められました。ただし、ソビエト連邦や中華人民共和国などは署名に参加せず、その後の領土問題などに影響を残しています。
リースリングからシュペートブルグンダーまで多様な魅力: ドイツワインの日
日本におけるドイツワインの輸入・販売業者やレストラン、愛好家などで構成される日本ドイツワイン協会連合会が、ドイツワインのさらなる普及を目指して2012年(平成24年)に制定しました。日付は「4」と「28」をドイツ語読みし、「フィア・ツヴァイ・アハト」の響きが「ドイツワイン(Deutscher Wein)」に似ている、という語呂合わせから。(※この語呂合わせの解釈はやや無理があるかもしれません)

Q: ドイツワインの日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 日本市場におけるドイツワインの認知度向上と消費拡大を目的としています。ドイツワインというと甘口の白ワインのイメージが強いかもしれませんが、近年は高品質な辛口のリースリングや、赤ワイン(シュペートブルグンダー=ピノ・ノワールなど)、スパークリングワイン(ゼクト)など、非常に多様なワインが生産されていることを広く知ってもらい、その魅力をPRする機会とされています。
Q: なぜ4月28日が「ドイツワインの日」なのですか?
A: 日本ドイツワイン協会連合会によると、数字の「428」をドイツ語で「フィア・ツヴァイ・アハト」と読み、その響きが「ドイツワイン」に似ている(?)という語呂合わせから、この日が選ばれたとされています。(※この語呂合わせは一般的ではないかもしれません)
Q: ドイツワインの主な特徴や産地は?
A: 冷涼な気候を反映した、繊細な酸味と果実味、比較的低いアルコール度数が特徴です。代表的な白ぶどう品種はリースリングで、モーゼル地方やラインガウ地方などが銘醸地として知られています。赤ワインでは、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)が主に栽培されており、アール地方やバーデン地方が有名です。糖度に基づく独自の品質等級(QmP:クーエムペー)があることも特徴です。
手軽な果汁飲料、缶で登場: 缶ジュース発売記念日
1954年(昭和29年)4月28日に、明治製菓株式会社(現:株式会社 明治)が、日本で初めてとなる缶入りのジュース「明治天然オレンジジュース」を発売したことを記念する日です。
Q: 缶ジュース発売記念日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 特定の制定団体があるわけではありませんが、それまでガラス瓶が主流だった飲料容器に、軽量で持ち運びやすく、密封性が高い「缶」という新しい形態が登場し、飲料市場や消費者のライフスタイルに変化をもたらした画期的な出来事を記念する日として認識されています。飲料業界における技術革新と商品開発の歴史を示す日と言えます。
Q: なぜ4月28日が「缶ジュース発売記念日」なのですか?
A: 1954年(昭和29年)4月28日に、明治製菓が日本初の缶入り飲料として「明治天然オレンジジュース」の販売を開始した、まさにその歴史的な発売日に由来しています。
Q: 日本初の缶ジュースはどのようなものでしたか?
A: 「明治天然オレンジジュース」は、当時のアメリカで普及し始めていた缶詰技術を応用して開発されました。スチール缶(鉄製)で、缶切りを使って開けるタイプでした。果汁100%ではなく、甘味料などが加えられた果汁飲料だったようです。当時はまだ珍しく、高級な飲み物というイメージでした。
労働者の安全と健康を守る国際的な取り組み: 労働安全衛生世界デー (World Day for Safety and Health at Work)
国際労働機関(ILO)が2003年に制定した国際デーです。世界中の職場における労働災害や職業性疾病の予防を推進し、安全で健康的な労働環境の実現に向けた国際社会の意識向上と行動を促すことを目的としています。
Q: なぜ労働安全衛生の世界デーが必要なのですか?
A: 世界では、今なお多くの労働者が、労働災害や職業に関連する病気によって命を落としたり、健康を損なったりしています。安全でない、あるいは不健康な労働環境は、労働者個人の問題だけでなく、企業の生産性や社会全体の持続可能性にも影響を及ぼします。この記念日は、すべての働く人々の安全と健康を守ることの重要性を国際的に訴えるものです。
Q: この日にはどのようなことが行われますか?
A: ILOや各国政府、労働組合、使用者団体などが連携し、労働安全衛生に関するセミナーやワークショップ、キャンペーン、優良事例の表彰、安全点検活動などを実施します。毎年特定のテーマが設定され、そのテーマに沿った啓発活動や議論が行われます。
Q: 職場での安全と健康のために重要なことは何ですか?
A: 危険箇所の特定と改善、安全な作業手順の確立と遵守、保護具の適切な使用、定期的な安全衛生教育の実施、健康診断の実施、長時間労働の抑制、ハラスメントのない職場環境づくりなどが重要です。労働者自身が安全意識を高め、危険を感じたら声を上げること、そして経営者や管理者が安全衛生への取り組みを最優先課題とすることが求められます。