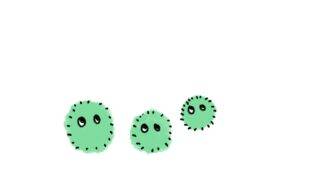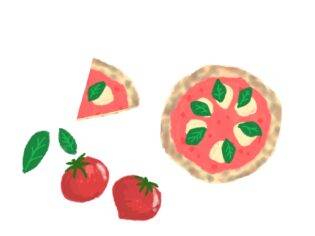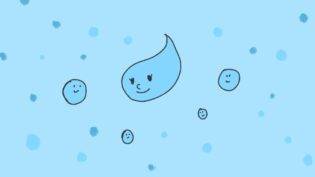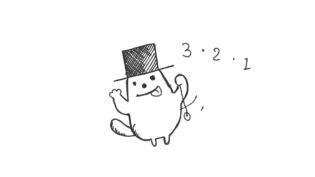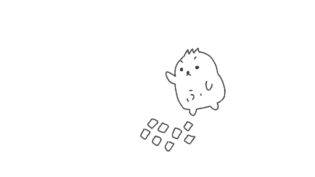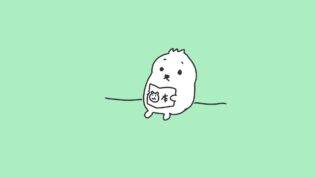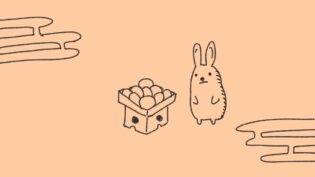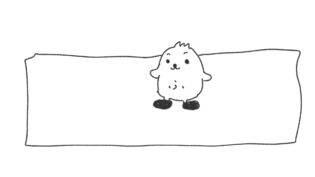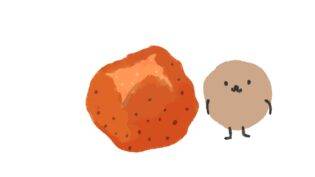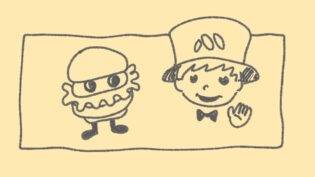3月3日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
語呂合わせと健康啓発: 耳の日
「み(3)み(3)」(耳)と読む語呂合わせから。日本耳鼻咽喉科学会が1956年(昭和31年)に制定。
Q: なぜ3月3日が「耳の日」なのですか?
A: 日付の「み(3)み(3)」という語呂合わせが由来です。覚えやすく、耳への関心を高めるきっかけとなることから、1956年に日本耳鼻咽喉科学会によって制定されました。
Q: この日はどのような目的で制定されましたか?
A: 難聴や耳鳴り、中耳炎といった耳の病気に関する悩みを持つ人々への社会的な関心を喚起し、耳の衛生や健康についての正しい知識の普及、早期発見・早期治療の重要性を啓発することを目的としています。また、聴覚障害を持つ人々への理解を深める意味合いも含まれています。
Q: 耳の健康のために普段からできることはありますか?
A: 大音量で長時間音楽を聴かない、耳掃除はやりすぎず優しく行う(または専門医に相談する)、耳に水が入ったらしっかり乾燥させる、などが挙げられます。また、めまいや聞こえにくさなど、少しでも異常を感じたら早めに耳鼻咽喉科を受診することが大切です。
岡山の名園を祝う: 後楽園開園記念日
岡山県岡山市にある「後楽園」が開園し、一般に公開。記念式典が行われた3月2日を岡山県が「開園記念日」に制定。
Q: なぜ3月3日が「後楽園開園記念日」とされているのですか?(※ユーザー提供情報ママ)
A: 提供された情報によると、岡山後楽園が一般公開された際に記念式典が行われた3月2日を、岡山県が「開園記念日」として制定したとされています。(一般的に岡山後楽園の開園記念日は3月2日と認識されています)
Q: 岡山後楽園はどのような特徴を持つ庭園ですか?
A: 江戸時代を代表する回遊式大名庭園の一つで、広々とした芝生、園内を巡る水路、池、築山、茶室などが巧みに配置されています。国の特別名勝に指定されており、金沢の兼六園、水戸の偕楽園と並び「日本三名園」の一つに数えられています。四季折々の自然の美しさを楽しむことができます。
Q: 「後楽園」という名前にはどのような意味が込められていますか?
A: 中国・北宋時代の政治家であり文人でもある范仲淹(はんちゅうえん)の著書『岳陽楼記』にある「先憂後楽」(為政者は民に先立って国のことを心配し、民が楽しんだ後に自分が楽しむべきである)という一節から、庭園を築いた岡山藩主・池田綱政が命名したと伝えられています。民とともに楽しむ庭園、という思いが込められていると考えられます。
女の子の成長を願う伝統行事: 雛祭り(桃の節句)
女の子の健やかな成長を願う伝統行事。女の子のいる家庭では、雛人形を飾り、桃の花・菱餅・雛あられを供えて祀り、白酒や寿司などの飲食を楽しむ節句祭りが行われる。
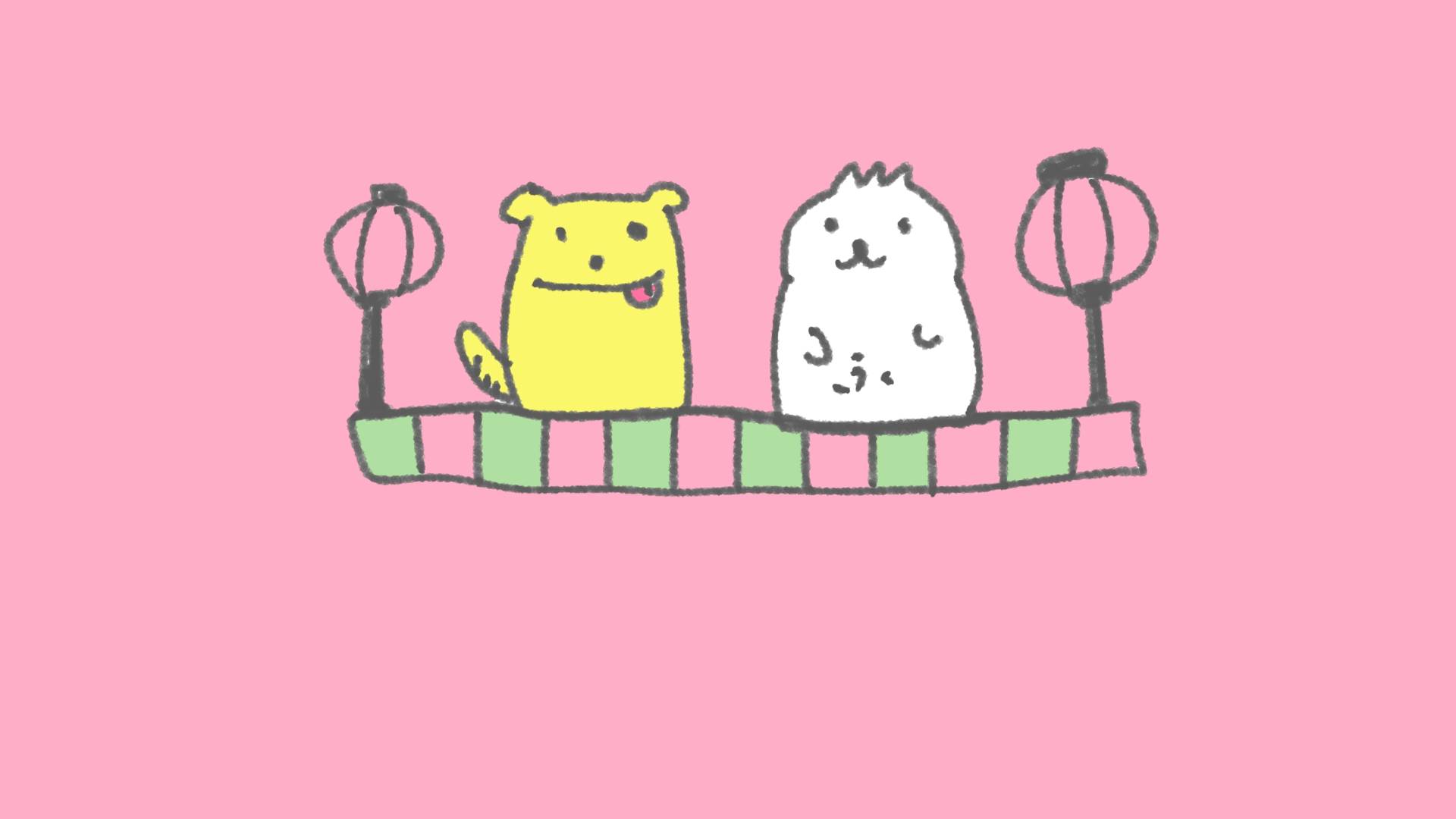
Q: 雛祭りはどのような由来を持つ行事ですか?
A: 元々は古代中国から伝わった「上巳(じょうし/じょうみ)の節句」の風習に由来します。この日、水辺で身を清めて穢れを祓う習慣が、平安時代の貴族の間で行われていた紙の人形(ひとがた)に穢れを移して川に流す「流し雛」と結びつきました。さらに、貴族の子女の間で流行した「ひいな遊び」(人形を使ったおままごと)が組み合わさり、江戸時代には現在のような雛人形を飾って女の子の健やかな成長と幸せを願う形へと発展しました。
Q: なぜ「桃の節句」とも呼ばれるのですか?
A: 旧暦の3月3日の頃は桃の花が咲く季節であったこと、そして桃には古来より邪気を祓う力があると信じられていたことから、「桃の節句」という別名がつきました。雛飾りに桃の花を添えるのもそのためです。
Q: 菱餅や雛あられにはどのような意味があるのですか?
A: 菱餅の三色(緑・白・桃色)には、緑は「健康・長寿(草萌える大地)」、白は「清浄・純潔(雪)」、桃色は「魔除け(桃の花)」といった意味が込められているとされます。菱形は心臓を表すとも、繁殖力の象徴とも言われます。雛あられは、菱餅を砕いて作られたという説や、四季(緑・桃・黄・白)を表し一年を通じて女の子が健やかであるようにとの願いが込められているなど、諸説あります。