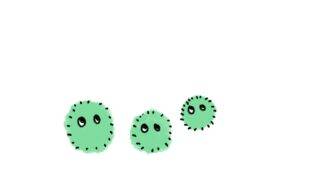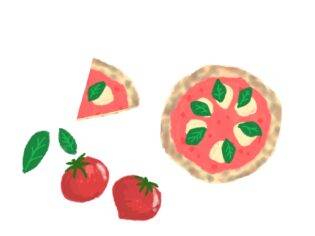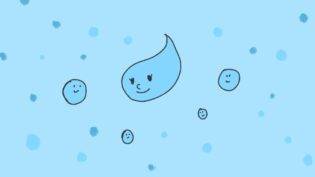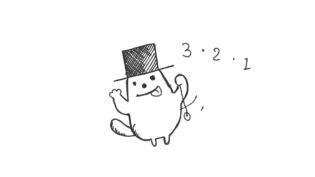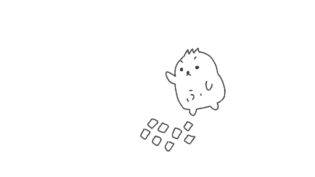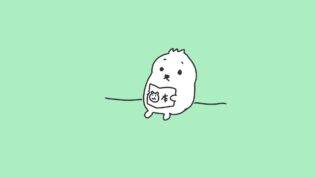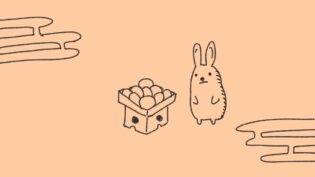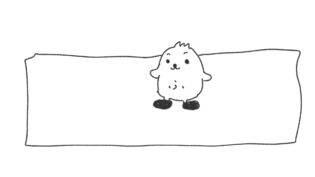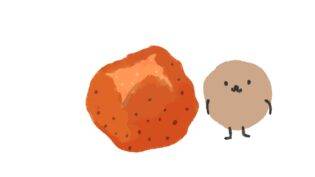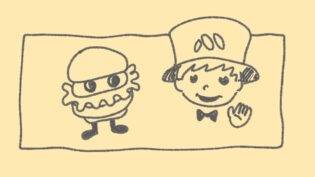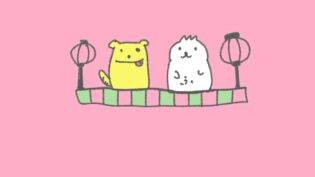3月4日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
語呂合わせと発明記念: ミシンの日
「ミ(3)シ(4)ン」と読む語呂合わせから。ミシン発明200年を記念して日本家庭用ミシン工業会が制定。
Q: なぜ3月4日が「ミシンの日」なのですか?
A: 日付の「ミ(3)シ(4)ン」という語呂合わせが由来です。親しみやすく、ミシンという道具への関心を高めることを意図しています。
Q: この記念日はいつ、なぜ制定されましたか?
A: 1990年(平成2年)に、日本家庭用ミシン工業会(現:日本縫製機械工業会)が制定しました。制定の背景には、1790年にイギリスのトーマス・セントが世界で初めてミシンの特許を取得してから200年という節目を記念する意味合いもありました。
Q: ミシンは私たちの生活にどう役立っていますか?
A: 衣類の製作や補修、カーテンやバッグなどの布製品作りを効率的に行うことを可能にします。手縫いに比べて格段に速く、丈夫に縫い上げることができるため、アパレル産業から家庭での手芸まで、幅広く活用されています。近年では高機能なコンピューターミシンも登場し、より複雑な縫製や刺繍も可能になっています。
窓の快適性と語呂合わせ: サッシの日
「サッ(3)シ(4)」と読む語呂合わせから。YKK AP株式会社が制定。
Q: 「サッシの日」の由来は何ですか?
A: 日付の「サッ(3)シ(4)」と読む語呂合わせが直接の由来です。窓サッシの重要性や役割について、より多くの人に知ってもらうことを目的としています。
Q: この記念日は誰が制定したのですか?
A: 大手建材メーカーであるYKK AP株式会社が制定しました。同社は窓やサッシなどの製品を製造・販売しており、この記念日を通じて製品のPRや住環境における窓の重要性を啓発しています。
Q: サッシは住まいでどのような役割を果たしていますか?
A: 窓ガラスを支える枠としての役割はもちろん、断熱性や気密性を高めて冷暖房効率を向上させたり、遮音性を高めて外部の騒音を軽減したり、防犯性を高めたりするなど、快適で安全な住環境を実現するために非常に重要な役割を担っています。材質や構造も進化しており、省エネ性能の高いサッシなどが注目されています。
沖縄の伝統楽器を祝う: 三線の日
三線(さんしん)は、三味線のもとになった楽器。沖縄県と沖縄県の琉球放送が制定。

Q: なぜ3月4日が「三線の日」なのですか?
A: 沖縄の伝統楽器である「三線(さんしん)」の音を「さん(3)し(4)ん」と読む語呂合わせにちなんで、琉球放送(RBC)が1993年に提唱・制定しました。
Q: 三線とはどのような楽器ですか?
A: 蛇の皮を張った胴に棹(さお)が取り付けられ、3本の弦を持つ弦楽器です。中国の三弦が原型とされ、14世紀末から15世紀頃に琉球王国(現在の沖縄県)に伝わり、独自の発展を遂げました。琉球古典音楽や沖縄民謡に欠かせない楽器であり、その独特の温かく哀愁のある音色は多くの人々を魅了しています。
Q: 「三線の日」にはどのようなことが行われますか?
A: 提唱者である琉球放送が中心となり、毎年この日の正午からラジオの特別番組が放送され、時報に合わせて沖縄県内外、さらには海外の三線愛好家も参加して、古典音楽の代表曲「かぎやで風(かじゃでぃふう)」を演奏するイベントが行われます。沖縄の文化としての三線の魅力を再認識し、継承していくことを目的としています。
情報メディアの魅力を再発見: 雑誌の日
「ざっ(3)し(4)」と読む語呂合わせから。株式会社富士山マガジンサービスが2008年に制定。
Q: 「雑誌の日」の由来は何ですか?
A: 日付の「ざっ(3)し(4)」と読む語呂合わせが由来です。雑誌の魅力や価値を再認識してもらうことを目的としています。
Q: この記念日は誰によって制定されましたか?
A: オンライン書店や雑誌の定期購読サービスなどを提供する株式会社富士山マガジンサービスが2008年(平成20年)に制定しました。同社は雑誌文化の振興に力を入れています。
Q: デジタルメディアが普及する中で、雑誌ならではの魅力は何だと思いますか?
A: 特定のテーマや分野について深く掘り下げた専門性の高い情報、編集者の視点やセンスによって選び抜かれた記事や写真の構成、手元に残して何度も読み返せる物理的な存在感、ページをめくる楽しさなどが挙げられます。また、美しい写真やデザインは、コレクションとしての価値も持ち得ます。
日本での歴史の始まり: バウムクーヘンの日
1919年(大正8年)のこの日、広島県物産陳列館(後の原爆ドーム)で行われたドイツ俘虜展示即売会で、同社を創業したドイツ人のカール・ユーハイムがドイツの伝統菓子「バウムクーヘン」を出品した。これが日本におけるバウムクーヘンの始まりであったことから、ドイツ菓子製菓会社の株式会社ユーハイムが2010年(平成22年)に制定。
Q: なぜ3月4日が「バウムクーヘンの日」なのですか?
A: 1919年3月4日に、広島で開催されたドイツ俘虜(ふりょ)による作品展示即売会で、ドイツ人菓子職人カール・ユーハイム氏が日本で初めてバウムクーヘンを製造・販売した歴史的な出来事に由来します。これを記念して、ユーハイム氏が創業した株式会社ユーハイムが2010年に制定しました。
Q: バウムクーヘンはどのようなお菓子ですか?
A: ドイツ語で「木(Baum)のお菓子(Kuchen)」という意味を持つ焼き菓子です。専用のオーブンで、回転する芯に生地を薄くかけながら、一層一層焼き重ねて作られるのが特徴です。断面が木の年輪のように見えることから、日本では長寿や繁栄を象徴する縁起の良いお菓子として、結婚式の引き出物などにもよく用いられます。
Q: カール・ユーハイム氏はどのような経緯で日本に来たのですか?
A: 第一次世界大戦中に、当時ドイツの租借地だった中国の青島(チンタオ)で菓子店を営んでいましたが、日本軍の捕虜となり、日本へ移送されました。収容所生活の後、上記の展示即売会での成功をきっかけに日本に留まり、横浜、そして後に神戸で自身の店を開き、日本におけるドイツ菓子の普及に貢献しました。