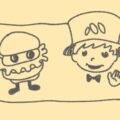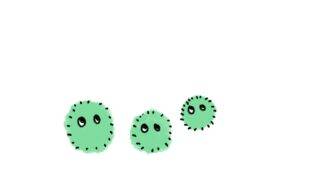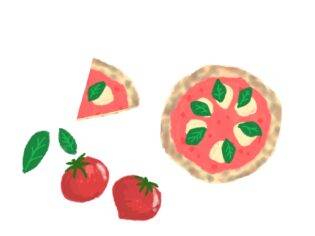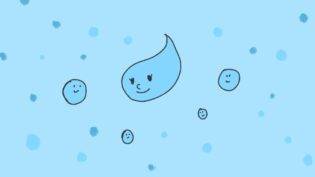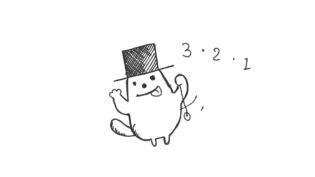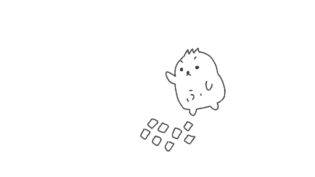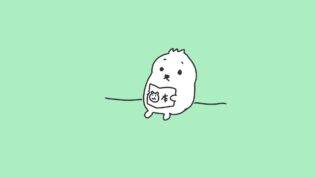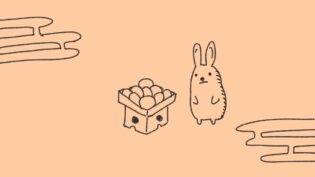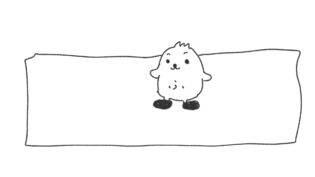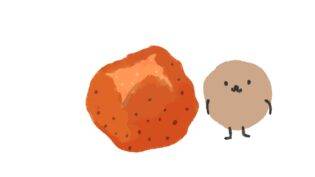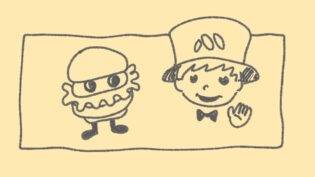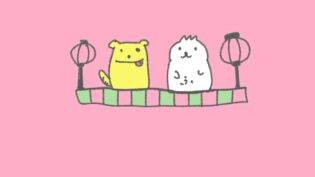3月11日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
世界初の連載開始: コラムの日
1951年、イギリスの新聞『ロンドン・アドバイザー・リテラリー・ガゼット』が、世界初のコラムの連載を始めたとされることに由来します。
Q: なぜ3月11日がコラムの日なのですか?
A: 1951年のこの日に、イギリスの新聞『ロンドン・アドバイザー・リテラリー・ガゼット』が世界で初めてコラムの連載を開始した、という情報に基づいていますが、この日付や事実関係については諸説あり、明確な記念日として広く認知されているわけではないようです。
Q: コラムとは具体的にどのような記事ですか?
A: 通常、新聞や雑誌などで、特定の執筆者が時事問題や社会風俗、身の回りの出来事などについて、比較的自由な形式で個人的な見解や感想を述べる短い文章を指します。囲み記事として定期的に掲載されることが多いのが特徴です。
西洋での初認識: パンダ発見の日
1869年のこの日、フランス人宣教師で博物学者のアルマン・ダヴィドが、中国・四川省の民家で、白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられました。これが、西洋でジャイアントパンダが知られるきっかけとなりました。

Q: なぜこの出来事が「発見」と呼ばれるのですか?
A: この日、アルマン・ダヴィド神父がパンダの毛皮を目にし、その後生体を捕獲してパリに送ったことが、西洋の学術界においてジャイアントパンダという動物の存在が初めて公式に記録・報告される契機となったためです。もちろん地元の人々には以前から知られていましたが、西洋世界にとっては未知の動物であり、学術的な「発見」とされています。
Q: アルマン・ダヴィド神父はどのような人物ですか?
A: 19世紀に中国で活動したフランス人のカトリック宣教師であり、優れた博物学者でもありました。パンダの他にも、シフゾウ(ダヴィド鹿)やゴールデンモンキーなど、多くの新種の動植物をヨーロッパに紹介し、生物学の発展に大きく貢献しました。
Q: この「発見」の後、パンダはどうなりましたか?
A: ダヴィドによる紹介以降、パンダはその愛らしい姿から世界的な人気者となりました。しかし、生息地の破壊や密猟などにより個体数が激減し、絶滅の危機に瀕しました。現在では、中国政府を中心に手厚い保護活動が進められ、絶滅危惧種から危急種へと危険度が引き下げられましたが、依然として保護が必要な動物です。
震災を忘れない: いのちの日
「災害時医療を考える会」が制定。2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災では、多くの尊い命が失われました。この震災を風化させることなく、災害への備えと命の尊さを考える日とすることが目的です。
Q: いのちの日はどのような想いで制定されましたか?
A: 東日本大震災という未曾有の大災害の記憶を風化させず、犠牲になった方々への追悼の意を示すとともに、その教訓を未来に活かすという強い想いが込められています。特に、災害時における医療の重要性や課題を再認識し、今後の防災・減災対策に繋げることを目指しています。
Q: 制定した「災害時医療を考える会」について教えてください。
A: 東日本大震災をきっかけに、災害時の医療体制や救護活動のあり方について問題意識を持つ医療関係者や市民などが集まり、設立された団体と考えられます。具体的な活動としては、震災の教訓を伝える講演会や、災害医療に関する提言、防災意識向上のための啓発活動などを行っていると推測されます。
Q: 3月11日にはどのようなことが行われていますか?
A: 政府主催の追悼式典をはじめ、全国各地で追悼行事や慰霊祭が行われます。また、学校や地域、職場などで防災訓練が実施されたり、メディアで震災関連の特集が組まれたりします。多くの人が黙祷を捧げ、犠牲者を悼み、防災への意識を新たにする一日となっています。
公衆衛生の基盤: 世界配管デー (World Plumbing Day)
世界配管評議会(World Plumbing Council, WPC)が2010年に制定した国際デーです。私たちの健康や生活環境を守る上で不可欠な、質の高い配管システムの重要性を世界的に認識し、その発展を促進することを目的としています。
Q: なぜ配管がそれほど重要なのですか?
A: 安全な飲料水の供給、衛生的な排水処理、効率的な冷暖房やガス供給など、配管システムは現代社会の公衆衛生と快適な生活を支える見えないインフラだからです。適切な配管がなければ、感染症の蔓延や水質汚染、エネルギーの無駄遣いなど、様々な問題が発生する可能性があります。
Q: 世界配管デーにはどのような活動が行われますか?
A: 世界各国の配管関連団体や企業、教育機関などが中心となり、配管技術の重要性や最新技術を紹介するセミナーや展示会、子ども向けのワークショップ、技術コンテストなどを開催しています。また、配管工という専門職の社会的役割や魅力を伝える活動も行われています。