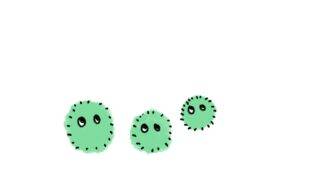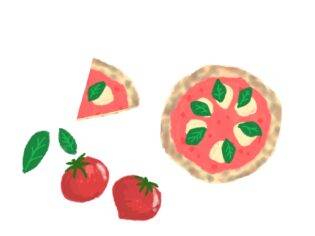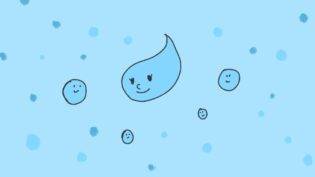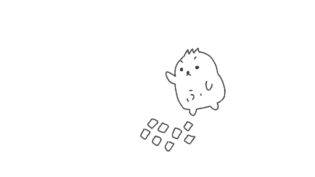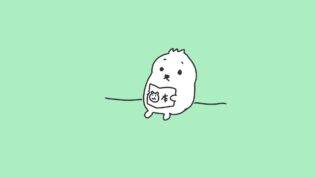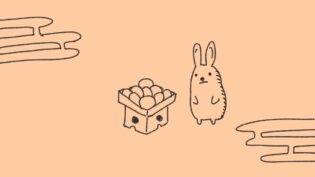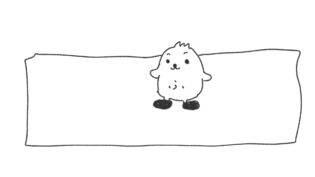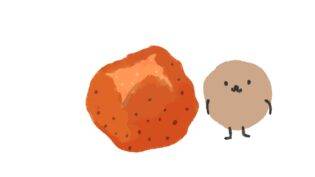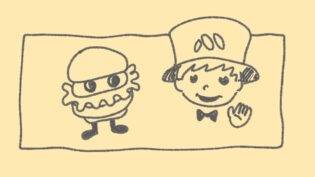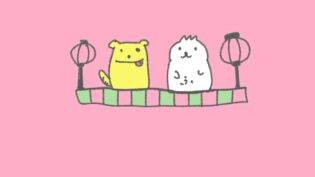3月21日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
言葉の多様性と創造性を讃える: 世界詩歌記念日 (World Poetry Day)
「国際連合教育科学文化機関」(UNESCO、ユネスコ)が1999年(平成11年)の総会で制定した国際デーです。言語の多様性を維持し、詩的な表現を通じて文化間の対話を促進することを目的としています。
Q: なぜユネスコは詩歌の記念日を制定したのですか?
A: 詩歌が人類共通の文化遺産であり、人々の創造性やアイデンティティの表現、そして異なる文化への理解を深めるための重要な手段であると認識したためです。特に、消滅の危機にある言語の保護にも詩歌が役立つと考えられています。
Q: この日には世界でどのようなことが行われていますか?
A: 各国で詩の朗読会、詩作ワークショップ、詩に関するシンポジウムや展示会、詩集の出版などが企画されます。学校教育の場で詩に親しむ活動も推奨されており、詩歌の魅力を再発見し、その力を讃える日となっています。
Q: 詩歌は現代社会においてどのような意義を持ちますか?
A: 詩歌は、言葉を通じて感情や思想を深く表現し、共感を呼び起こす力を持っています。忙しい現代社会において、立ち止まって言葉の響きや意味を味わい、内面を見つめ直す機会を与えてくれます。また、異なる価値観や文化背景を持つ人々との相互理解を促進する役割も担っています。
あらゆる差別との闘いを誓う: 国際人種差別撤廃デー (International Day for the Elimination of Racial Discrimination)
1966年(昭和41年)の国連総会で制定された国際デーの一つです。あらゆる形態の人種差別の撤廃に向けた国際社会の決意を示す日です。
Q: なぜ3月21日がこの記念日になったのですか?
A: 1960年3月21日に、南アフリカ共和国のシャープビルで、アパルトヘイト(人種隔離政策)に対する平和的なデモ行進を行っていた人々に対し、警察官が発砲し、69人が死亡するという「シャープビル虐殺事件」が発生しました。この悲劇を忘れることなく、人種差別の撤廃を訴え続けるために、この日が選ばれました。
Q: 国際人種差別撤廃デーの主な目的は何ですか?
A: 人種差別が依然として世界各地に存在している現状を認識し、その撤廃に向けて各国政府や市民社会が努力を強化することを促すのが目的です。人種、肌の色、民族、出身などによる差別や偏見をなくし、すべての人が平等に尊厳を持って生きられる社会の実現を目指します。
Q: 私たちにできることは何でしょうか?
A: まずは人種差別の問題に関心を持ち、正しい知識を学ぶことが重要です。身の回りの差別的な言動や固定観念に気づき、それに反対の声を上げること、多様な文化や価値観を尊重し、異なる背景を持つ人々と積極的に交流することも、差別をなくすための大切な一歩となります。
数字のカウントダウンから連想: 催眠術の日
催眠術をかける際によく使われる「3、2、1」というカウントダウンの掛け声から、3月21日が記念日として制定されたと言われています。

Q: この記念日は誰が制定したのですか?
A: 特定の団体が正式に制定したというよりは、主にインターネット上などで広まった、語呂合わせや連想に基づく記念日のようです。催眠術や心理学に関心のある人々の間で話題にされることがあります。
Q: 催眠術とはどのようなものですか?
A: 催眠術は、特定の誘導によって被術者をリラックスさせ、意識が変容した状態(催眠状態)に導く技術です。この状態では、暗示に対する感受性が高まるとされ、心理療法(禁煙、不安軽減など)、痛みの緩和、記憶の想起などに用いられることがあります。ただし、科学的な効果については議論もあります。
Q: 催眠術についてよくある誤解は何ですか?
A: 催眠術にかかると完全に意識を失い、術者の意のままに操られるというイメージがありますが、これは誤解です。催眠状態でも意識はあり、通常は本人が望まないことや倫理に反する暗示は受け入れません。また、誰もが簡単にかかるわけではなく、個人差があります。
日本映画に色彩をもたらした日: カラー映画の日
1951年(昭和26年)のこの日、松竹が製作・配給した国産初の長編総天然色(カラー)映画『カルメン故郷に帰る』が公開されたことを記念する日です。
Q: なぜ『カルメン故郷に帰る』が日本初のカラー映画として重要視されるのですか?
A: この作品は、日本の映画界において初めて本格的に長編劇映画全編をカラーで撮影・公開した画期的な作品だったからです。それまでの日本映画は基本的に白黒(モノクロ)であり、この映画の登場は観客に大きな驚きと感動を与え、日本のカラー映画時代の幕開けを告げる出来事となりました。
Q: 『カルメン故郷に帰る』はどのような内容の映画ですか?
A: 木下惠介監督、高峰秀子主演のコメディ映画です。東京でストリッパーとして成功した女性(カルメン)が、故郷の信州の村に派手な衣装で錦を飾り、騒動を巻き起こす物語です。美しい信州の自然風景がカラー映像で鮮やかに描かれたことも話題となりました。
Q: 当時のカラー映画技術はどのようなものでしたか?
A: 『カルメン故郷に帰る』では、日本の富士フイルムが開発した国産初のカラーフィルム「フジカラー」が使用されました。当時のカラー撮影は、技術的にも費用的にもまだハードルが高く、この映画の成功は日本の映画技術の進歩を示すものでもありました。
多様性とインクルージョンを考える: 世界ダウン症デー (World Down Syndrome Day)
世界ダウン症連合が制定し、2011年に国連総会で承認された国際デーです。ダウン症のある人々の権利や幸福、社会への完全な参加について、世界中の人々の意識を高めることを目的としています。
Q: なぜ3月21日が世界ダウン症デーなのですか?
A: ダウン症候群の多くが、通常2本である21番目の染色体が3本ある「トリソミー」によって引き起こされることから、日付を「3月21日」としています。この日付自体が、ダウン症への理解を促すシンボルとなっています。
Q: この日にはどのような啓発活動が行われますか?
A: ダウン症のある人々やその家族、支援団体などが中心となり、講演会、セミナー、写真展、啓発ウォーク、交流イベントなどを開催します。また、左右異なる靴下を履いてダウン症への支援を示す「ロック・ユア・ソックス」キャンペーンなども世界的に行われています。
Q: 私たちがこの日にできることは何ですか?
A: ダウン症についての正しい情報を知り、誤解や偏見をなくす努力をすることが大切です。SNSなどで啓発情報をシェアしたり、地域のイベントに参加したりすることも支援につながります。何よりも、ダウン症のある人々が個性豊かに、地域社会の一員として活躍できるインクルーシブな社会を目指す意識を持つことが重要です。
森の恵みと保全を考える: 国際森林デー (International Day of Forests)
2012年の国連総会で制定された国際デーです。森林の多面的な重要性(環境保全、生物多様性、気候変動緩和、人々の生活への貢献など)に対する意識を高め、森林の保全と持続可能な管理を促進することを目的としています。
Q: なぜ森林に関する国際デーが必要なのですか?
A: 森林は地球上の生命にとって不可欠な存在であり、酸素の供給、水の浄化、土壌の保全、多くの動植物の生息地提供など、計り知れない恩恵をもたらしています。しかし、世界的に森林破壊や劣化が深刻な問題となっており、その重要性を再認識し、保全に向けた行動を世界全体で強化する必要があるためです。
Q: この日にはどのような取り組みが行われますか?
A: 国連や各国政府、環境NGO、地域コミュニティなどが、植林活動、森林保全に関するセミナーやワークショップ、子ども向けの環境教育プログラム、森林に関する写真展や映画上映会などを実施します。毎年特定のテーマが設定され、森林が持つ様々な側面について理解を深めます。
6年間の思い出を刻む: ランドセルの日
ランドセルメーカーなどが加盟するランドセル工業会が制定した記念日です。日付は、小学校の修業年数である6年間にちなみ、「3+2+1=6」となることから3月21日が選ばれました。
Q: ランドセルの日の目的は何ですか?
A: 卒業シーズンを迎えるこの時期に、6年間苦楽を共にしたランドセルへの感謝の気持ちを表し、小学校生活の思い出を大切にしてもらいたいという願いが込められています。また、ランドセルという日本の文化を改めて見直す機会を提供することも目的の一つです。
Q: ランドセルはいつ頃から使われ始めたのですか?
A: ランドセルの起源は、幕末に導入された西洋式の軍隊の背嚢(はいのう、オランダ語で「ランセル」)にあるとされています。学用品を入れるための通学カバンとして学習院で採用されたのが始まりと言われ、その後、徐々に全国の小学校に普及していきました。
Q: 最近のランドセルのトレンドはありますか?
A: 従来の赤と黒だけでなく、ピンク、水色、紫、茶色、緑など、非常に多様なカラーバリエーションが登場しています。素材も軽量化が進み、デザインも刺繍やステッチ、鋲(びょう)などに工夫を凝らしたものが増えています。また、タブレット端末を収納できるスペースがあるなど、現代の学習環境に対応した機能を持つランドセルも人気です。