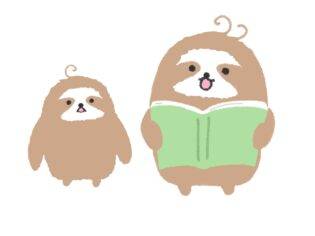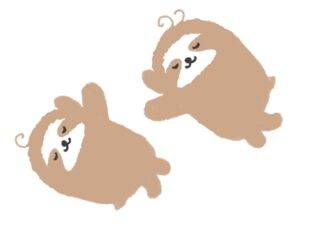6月24日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
近代UFO史の幕開け: UFOの日・空飛ぶ円盤記念日
1947年(昭和22年)のこの日、アメリカの実業家ケネス・アーノルドが自家用機で飛行中にコーヒー皿のような謎の飛行物体を目撃した。最初の目撃例となったこの日をUFO研究家たちが記念日として命名したとされる。

Q: ケネス・アーノルドが見たものは具体的にどのようなものでしたか?
A: アーノルド氏の証言によれば、ワシントン州のカスケード山脈上空で、非常に高速(時速2,700km以上と推定)で飛行する9つの銀色の物体を目撃しました。それぞれの物体は三日月形や円盤状で、水面を跳ねる石のように不規則な動きをしていたと報告されています。太陽光を反射して強く輝いていたとも述べています。
Q: なぜ「空飛ぶ円盤(Flying Saucer)」と呼ばれるようになったのですか?
A: アーノルド氏自身は物体を「円盤(ソーサー)」のようだと直接表現したわけではありませんでした。彼はその動きを「水面を跳ねるコーヒー皿(ソーサー)のようだった」と記者に説明しました。この比喩表現が報道される過程で簡略化され、「空飛ぶ円盤(Flying Saucer)」というキャッチーな言葉として広まり、以降、同様の未確認飛行物体を表す一般的な呼称となりました。
Q: この目撃事件は社会にどのような影響を与えましたか?
A: アーノルド氏の目撃情報は、当時のメディアで大きく報じられ、世界中で同様の目撃報告が相次ぐきっかけとなりました。これにより、未確認飛行物体(UFO)への関心が爆発的に高まり、UFO現象が社会的な関心事として広く認知されるようになりました。「UFO」や「空飛ぶ円盤」は、SF文化だけでなく、一般的な会話にも登場する言葉となり、現代に至るUFO研究や議論の出発点とも言える出来事でした。
音楽教育の革新: ドレミの日
1024年のこの日、イタリアの僧侶グイード・ダレッツォがドレミの音階を定めたとされる。
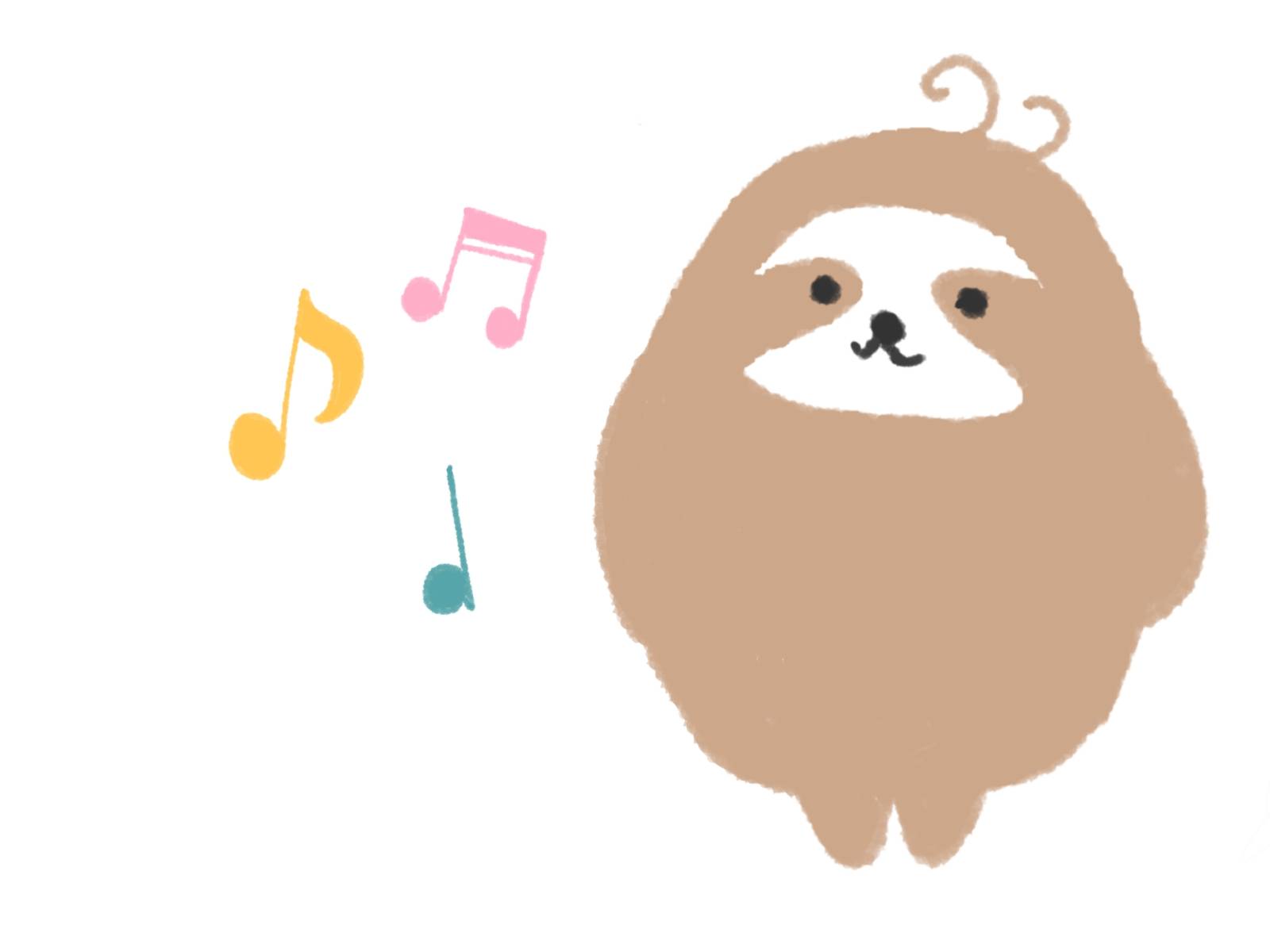
Q: グイード・ダレッツォはどのようにしてドレミの音階を定めたのですか?
A: グイードは、聖歌隊の少年たちが聖歌を覚えるのを助けるため、「聖ヨハネ賛歌」というグレゴリオ聖歌の各節の最初の音と歌詞の最初の音節を結びつけました。その歌詞が「Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum, Sancte Iohannes.」であり、各行の頭文字(Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La)が、特定の音高を示す記号(階名)として使われるようになりました。これがドレミの音階(階名唱法)の始まりです。(後にUtは発音しやすいDoに、Siが追加されました。)
Q: ドレミの音階が広まる前は、どのように音の高さを伝えていたのですか?
A: グイードの時代以前は、主に「ネウマ譜」という記譜法が使われていました。これは音の上がり下がりやリズムのニュアンスを示す記号でしたが、具体的な音高を正確に示すものではなく、旋律は主に口伝や指導者の手ぶり(カイロノミー)によって伝えられていました。そのため、新しい聖歌を覚えるのに非常に時間がかかり、正確性も低かったと言われています。
Q: グイード・ダレッツォの功績はドレミ音階だけですか?
A: いいえ、彼は音楽教育において他にも重要な貢献をしています。特に、音の高さを正確に示すために、4本の線を用いた譜線(四線譜)を考案したことは大きな功績です。これにより、音符の位置で音高が視覚的にわかるようになり、楽譜の読解と記録が格段に進歩しました。現代の五線譜の基礎を築いたとも言えます。
クレーンゲームの代名詞: UFOキャッチャーの日
株式会社セガ・インタラクティブ(現:株式会社セガ)が制定。1985年(昭和60年)から発売されているクレーンゲーム機「UFOキャッチャー」の周知目的。「UFOの日」にちなんでこの日を記念日とした。
Q: なぜセガはこの日を「UFOキャッチャーの日」に制定したのですか?
A: 自社の人気クレーンゲームブランドである「UFOキャッチャー」をさらに広く知ってもらうためです。同じ6月24日にある「UFOの日・空飛ぶ円盤記念日」にちなむことで、ユニークさと話題性を生み出し、記念日として覚えやすくすることを狙ったと考えられます。
Q: 「UFOキャッチャー」という名前の由来は何ですか?
A: アームユニットの形状が未確認飛行物体(UFO)のように見えることから名付けられました。景品を掴んで持ち上げる動きが、まるでUFOが物体を吸い上げる(キャッチする)様子に似ていることも、この名前が付けられた理由の一つです。シンプルで覚えやすく、ゲームの特徴をよく表したネーミングと言えます。
Q: UFOキャッチャーは日本のゲーム文化にどのような影響を与えましたか?
A: 「UFOキャッチャー」はクレーンゲームの代名詞となるほど普及し、ゲームセンターの定番機種として不動の地位を築きました。様々な種類の景品(ぬいぐるみ、フィギュア、雑貨など)が登場し、コレクション性や獲得する達成感が人気を集め、多くの人々に親しまれるエンターテインメントとなりました。他のメーカーからも類似のゲーム機が登場し、「プライズゲーム」というジャンルを確立する上で大きな役割を果たしました。
昭和の歌姫を偲ぶ: 林檎忌・美空ひばり忌
1989年(平成元年)のこの日に亡くなった、日本を代表する歌手・美空ひばりさんを偲ぶ日です。「林檎忌」の名称は、彼女の代表曲の一つである『リンゴ追分』にちなんでいます。
Q: なぜ「林檎忌」と呼ばれるのですか?
A: 美空ひばりさんの数多くのヒット曲の中でも、特に広く知られ、彼女の代名詞ともされる『リンゴ追分』に由来しています。彼女の業績と人々から愛されたイメージを象徴する曲名から、その命日が「林檎忌」と名付けられました。
Q: 美空ひばりはどのような歌手でしたか?
A: 「歌謡界の女王」と称され、戦後の日本を代表する国民的歌手です。幼少期から天才的な歌唱力で注目を集め、演歌、ジャズ、歌謡曲など幅広いジャンルを歌いこなし、数々のヒット曲を生み出しました。その圧倒的な表現力と存在感は、多くの人々に感動と勇気を与え、日本の音楽史に大きな足跡を残しました。
Q: この日にはどのような催しがありますか?
A: 菩提寺である横浜市の日野公園墓地には多くのファンが墓参りに訪れます。また、京都の嵐山にある「美空ひばり座」(現在は閉館)や、ゆかりの地などで、追悼イベントやフィルムコンサートなどが開催されることもあります。テレビやラジオで特集番組が組まれることも多いです。
万葉集の編者を偲ぶ: 五月雨忌・大伴家持忌
『万葉集』の編纂に深く関わったとされる奈良時代の歌人・政治家である大伴家持(おおとものやかもち)の命日とされる日です。旧暦6月24日が梅雨の時期(五月雨の季節)にあたることから「五月雨忌」とも呼ばれます。
Q: なぜ「五月雨忌」と呼ばれるのですか?
A: 大伴家持の命日とされる旧暦6月24日が、現在の暦では梅雨の時期、つまり「五月雨(さみだれ)」が降る季節にあたるため、その情景と結びつけて「五月雨忌」という雅称で呼ばれるようになりました。
Q: 大伴家持はどのような人物でしたか?
A: 奈良時代の貴族であり、優れた歌人として知られています。『万葉集』全4500首余りのうち、最も多くの歌(約470首)を残しています。越中国守などを歴任し、政治家としても活動しましたが、晩年は藤原氏との政争に巻き込まれ不遇だったとも伝えられています。『万葉集』の最終的な編纂者としても有力視されています。
Q: 万葉集とはどのような歌集ですか?
A: 日本に現存する最古の和歌集です。約4世紀半から8世紀半ばまでの約4500首の歌が収められており、天皇や貴族から、役人、防人、農民など、様々な身分の人々の歌が含まれています。内容は、恋愛、自然、生活、儀式、社会的な出来事など多岐にわたり、古代日本の人々の感情や生活を知る上で非常に貴重な資料となっています。
武将・加藤清正を祀る: 清正公の日
戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将・加藤清正(かとうきよまさ)を祀る日として、東京都港区白金台の覚林寺(清正公)や、熊本市の本妙寺などで縁日や祭礼が行われる日とされています。日付の由来については諸説あります。
Q: なぜ6月24日が清正公の日とされるのですか?
A: 覚林寺では、加藤清正の命日が旧暦の6月24日であるとして、この日に大祭が行われるためです。ただし、歴史的な記録では清正の実際の命日は慶長16年6月24日(新暦1611年8月2日)とされており、旧暦の日付を採用している形です。他の寺社でもこの日を縁日とすることがあります。
Q: 加藤清正はどのような武将でしたか?
A: 豊臣秀吉の子飼いの家臣として仕え、「賤ヶ岳の七本槍」の一人に数えられる猛将です。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)での活躍や、熊本城の築城、領内の治水・干拓事業などでも知られています。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、江戸幕府成立後は肥後熊本藩の初代藩主となりました。武勇だけでなく、築城や治世においても優れた手腕を発揮した武将として評価されています。
Q: 覚林寺や本妙寺ではどのような祭礼が行われますか?
A: 覚林寺の清正公大祭(例年5月4日・5日と、命日とされる6月24日前後)では、法要のほか、「勝守(かちまもり)」と呼ばれる菖蒲入りの御札が授与され、多くの参拝者で賑わいます。熊本市の本妙寺では、清正公の命日に合わせて「頓写会(とんしゃえ)」と呼ばれる法要や行事が行われ、こちらも多くの人々が訪れます。