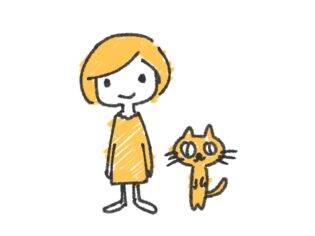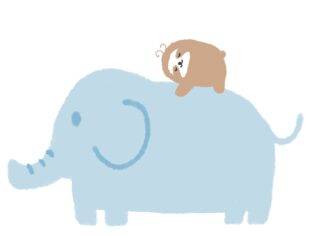11月19日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
誰もが安全なトイレを使える世界へ: 世界トイレの日 (World Toilet Day)
2013年(平成25年)7月の国連総会で制定された国際デーの一つです。世界には、安全で衛生的なトイレを利用できない人々がまだ数十億人もいるという現状を改善するため、公衆衛生の問題としてトイレの普及を国際社会全体で考え、行動を促すことを目的としています。「世界トイレデー」とも呼ばれます。

Q: 世界トイレの日は、どのような課題の解決を目指していますか?
A: 世界には、屋外での排泄を余儀なくされたり、安全でないトイレを使わざるを得なかったりする人々が多くいます。これは、コレラや赤痢などの感染症の蔓延、特に女性や女児に対する暴力のリスク増加、教育や経済活動への参加阻害など、様々な深刻な問題を引き起こしています。この記念日は、こうした衛生危機を解決し、持続可能な開発目標(SDGs)の目標6「安全な水とトイレを世界中に」の達成を目指しています。
Q: なぜ11月19日が選ばれたのですか?
A: この問題に熱心に取り組んでいたシンガポール政府の提案を受け、2001年に設立された非営利組織「世界トイレ機関(World Toilet Organization)」の設立日である11月19日が、国連の国際デーとして正式に採択されました。
Q: 私たちにできることはありますか?
A: まず、世界のトイレ事情や衛生問題について関心を持ち、学ぶことが第一歩です。関連する国際機関やNGOへの寄付や支援活動に参加したり、SNSなどを通じてこの問題の重要性を広めたりすることも有効です。また、日本の恵まれたトイレ環境に感謝し、公共トイレなどをきれいに使うことも大切です。
戦後農業の礎を築いた法律: 農協記念日
全国の農業協同組合(JA)の中央組織である一般社団法人・全国農業協同組合中央会(JA全中)などが制定。1947年(昭和22年)11月19日に、戦後の農地改革と並んで日本の農業政策の根幹となった「農業協同組合法」が公布されたことを記念しています。
Q: 農協記念日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 1947年(昭和22年)11月19日に「農業協同組合法」が公布されたことを記念しています。この法律は、日本の農業協同組合(JA)の設立と運営の法的根拠となり、戦後の農業の民主化と発展に大きな役割を果たしました。
Q: 農業協同組合法は、どのような目的で制定されたのですか?
A: 戦前の産業組合や農業会に代わり、農業者自身が協同して農業経営や生活を向上させるための自主的な組織(農業協同組合)を設立・運営できるようにすることを目的として制定されました。農業者の経済的・社会的地位の向上、農業生産力の増進、農村文化の向上などが目指されました。
Q: 農業協同組合(JA)は現在どのような活動をしていますか?
A: 組合員である農業者に対して、営農指導、農産物の共同販売、生産資材の共同購入、金融(JAバンク)、共済(JA共済)、生活用品の供給、福祉・医療など、農業経営や生活に関わる非常に幅広い事業を展開し、地域社会に貢献しています。
東海道本線電化完成の歴史: 鉄道電化の日
鉄道の電化に関する技術開発や普及促進を行う鉄道電化協会が1964年(昭和39年)に制定。1956年(昭和31年)11月19日に、東海道本線の最後の未電化区間であった米原駅~京都駅間が電化され、これにより東京駅から神戸駅(当時の電化終点)までの東海道本線全線の電化が完成したことを記念しています。
Q: 鉄道電化の日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 1956年(昭和31年)に日本の大動脈である東海道本線の全線電化が完成したという、日本の鉄道史における画期的な出来事を記念しています。
Q: 東海道本線の全線電化が完成したことで、どのような変化がありましたか?
A: それまでの蒸気機関車(SL)牽引に比べて、電気機関車や電車は高速化が可能となり、輸送時間が大幅に短縮されました。例えば、特急「つばめ」の東京~大阪間の所要時間は、電化完成により従来の8時間から7時間30分に短縮されました。また、煙が出ないため乗り心地が向上し、トンネル内の環境も改善されました。輸送能力も向上し、日本の経済成長を支える基盤となりました。
Q: 日本で最初に電化された鉄道路線はどこですか?
A: 日本で最初の鉄道電化は、1895年(明治28年)に開業した京都電気鉄道(路面電車)とされています。国鉄(JRの前身)では、1906年(明治39年)に中央本線の甲武鉄道区間(後の飯田町~中野間)で電車運転が始まったのが最初です。
「いい(11)塾(19)」で学ぶ喜びを: いい塾の日
学習塾「修猷館」(福岡県)などを運営するSHIMON GROUP(シモングループ)が制定。日付は「いい(11)塾(じゅく=19)」と読む語呂合わせから。


Q: いい塾の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 学習塾が生徒の学力向上や目標達成をサポートする重要な役割を担っていることをアピールし、学習意欲のある生徒たちを応援するとともに、より良い塾教育のあり方について考えるきっかけの日とする目的があると考えられます。
Q: なぜ11月19日が「いい塾の日」なのですか?
A: 「いい(11)塾(じゅく=19)」という覚えやすく、ポジティブなイメージの語呂合わせから、この日が選ばれました。19を「じゅく」と読ませるのがポイントです。
Q: 学習塾を選ぶ際のポイントは何ですか?
A: 子どもの学習目的(学力向上、受験対策、苦手克服など)や性格に合った指導方針・カリキュラムであるか、講師の質や指導経験はどうか、教室の雰囲気や学習環境はどうか、通塾の利便性や安全性はどうか、費用は適切かなどを総合的に判断することが大切です。体験授業などを活用して、子ども自身が納得できるかどうかも重要です。
時が育む味わい「いい(11)熟(19)成」: いい熟成ワインの日
ワインの輸入・販売などを手がける株式会社和泉屋(東京都)が制定。日付は「いい(11)じゅく(19)せい」(良い熟成)と読む語呂合わせから。
Q: いい熟成ワインの日は、どのような目的で制定されましたか?
A: ワインの中でも、適切な環境で長期間熟成させることによって複雑で深みのある味わいが生まれる「熟成ワイン(古酒、オールドヴィンテージワイン)」の魅力や価値を、より多くの人に知ってもらい、楽しんでもらうきっかけを提供することを目的としています。
Q: なぜ11月19日が「いい熟成ワインの日」なのですか?
A: 熟成によってワインが持つポテンシャルが引き出されることを「いい(11)熟成(じゅくせい=19)」という語呂合わせで表現し、この日が選ばれました。
Q: ワインはどのように熟成させるのですか?また、熟成によってどう変化しますか?
A: 瓶詰めされたワインを、温度や湿度が一定に保たれ、光が当たらない静かな環境(ワインセラーなど)で長期間保管することで熟成が進みます。熟成により、タンニン(渋み)がまろやかになり、酸味が落ち着き、果実味、酸味、タンニン、アルコールなどの要素が複雑に絡み合った、ブーケ(熟成香)と呼ばれる芳醇な香りが生まれます。全てのワインが熟成に向くわけではなく、品種や製法によって熟成期間や飲み頃は異なります。