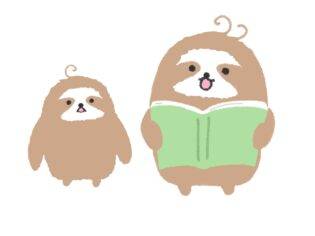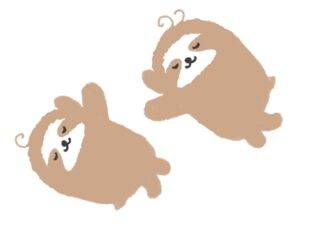6月11日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
梅雨の季節の必需品!「入梅」にちなむ日: 傘の日
日本洋傘振興協議会(JUPA)が1989年(平成元年)に制定。日付はこの日が暦の上で「梅雨入り」を意味する雑節の一つ「入梅」になることが多いことから。

Q: なぜ6月11日が「傘の日」なのですか?
A: 昔の暦(旧暦)で、梅雨入りの時期を示す雑節(季節の目安となる日)「入梅(にゅうばい)」が、現在の暦(新暦)の6月11日頃にあたることが多いため、この日が選ばれました。雨が多くなる季節に、傘の役割を再認識する日です。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: 日本洋傘振興協議会によって、傘の機能性やファッション性などをアピールし、洋傘の需要喚起と業界の発展を図ることを目的に制定されました。梅雨時期を前に、お気に入りの傘を見つけるきっかけになるかもしれません。
梅雨に備える!住まいの点検推奨日: 雨漏り点検の日
全国雨漏検査協会が1997年(平成9年)4月に制定。日付はこの日が暦の上で「梅雨入り」を意味する雑節の一つ「入梅」になることが多いことから。
Q: なぜ6月11日が「雨漏り点検の日」なのですか?
A: こちらも「傘の日」と同様に、暦の上で梅雨入りにあたる「入梅」が6月11日頃になることが多いことに由来します。本格的な梅雨のシーズンを迎える前に、家屋の雨漏りを点検し、備えることを促す日です。
Q: 雨漏りを放置するとどうなりますか?
A: 雨漏りは、天井や壁のシミ、カビの発生といった見た目の問題だけでなく、建物の構造材(柱や梁など)を腐らせたり、シロアリを呼び寄せたりする原因にもなります。放置すると建物の耐久性が低下し、修理費用も高額になる可能性があるため、早期発見・早期修繕が重要です。
日本の近代金融システムの始まり: 国立銀行設立の日
1873年(明治6年)のこの日、日本初の銀行、第一国立銀行(後の第一勧業銀行、現在のみずほ銀行)が設立された。
Q: なぜ6月11日が「国立銀行設立の日」なのですか?
A: 1873年(明治6年)の6月11日に、渋沢栄一らによって日本で最初の銀行である「第一国立銀行」が設立されたことに由来します。これは日本の近代的な金融システムの幕開けとなる出来事でした。(実際の開業は7月)
Q: なぜ「国立」銀行と呼ばれたのですか?
A: 明治政府が制定した「国立銀行条例」に基づいて設立された民間銀行だったため、「国立」という名前が付けられました。これはアメリカの「National Bank」制度を参考にしたもので、紙幣の発行権を持つなどの特権が与えられていました。第一国立銀行の後、全国に多くの国立銀行が設立されましたが、後に普通銀行へと転換していきました。
伝統的な育児用品に感謝する日: 布おむつの日
布おむつのレンタルシステムで知られる関西ダイアパーリース協同組合が制定。日付は昔から布おむつのことを襁褓(むつき)と呼んでいたことから6月で、その11日で「いい日」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ6月11日が「布おむつの日」なのですか?
A: 布おむつを昔「襁褓(むつき)」と呼んでいたことから、数字の「6(む)」=6月とし、11日を「いい日」と読む語呂合わせで、この日が選ばれました。
Q: 布おむつを使うメリットは何ですか?
A: 紙おむつと比較して、繰り返し洗って使えるため経済的で、ゴミが出ないため環境に優しいというメリットがあります。また、赤ちゃんの肌に優しい天然素材(綿など)で作られていることが多い点や、濡れた感覚が分かりやすいため、おむつ外れが早まる可能性があるとも言われています。