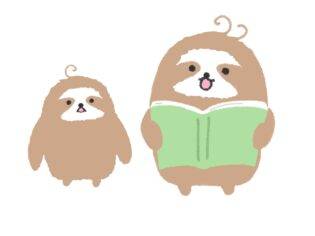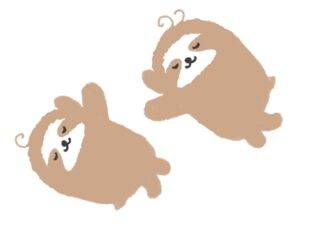6月15日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
地域金融の担い手!法律施行日: 信用金庫の日
全国信用金庫協会が制定。1951年(昭和26年)のこの日、「信用金庫法」が施行された。

Q: なぜ6月15日が「信用金庫の日」なのですか?
A: 1951年(昭和26年)の6月15日に、地域の中小企業や住民のための協同組織金融機関である「信用金庫」の根拠法となる「信用金庫法」が公布・施行されたことに由来します。
Q: 信用金庫は銀行とどう違うのですか?
A: 銀行は株式会社であり、主な取引対象に制限はありませんが、信用金庫は地域社会の相互扶助を目的とした協同組織であり、会員(地域の中小企業や住民など)の出資によって成り立っています。営業地域が限定されており、融資対象も原則として会員や地域の中小企業、住民に限られるなど、地域社会への貢献を使命としている点が大きな違いです。
チーバくんの誕生日?県誕生記念日: 千葉県民の日
1984年(昭和59年)に千葉県が制定。1873年(明治6年)のこの日、印旛県(旧 下総国の一部)と木更津県(旧 上総国・安房国)が合併し、県庁を旧両県の境界の千葉郡千葉町に設置して千葉県が誕生した。
Q: なぜ6月15日が「千葉県民の日」なのですか?
A: 1873年(明治6年)の6月15日に、それまで存在した印旛県(いんばけん)と木更津県(きさらづけん)が合併して、現在の「千葉県」が誕生したことを記念して制定されました。
Q: 千葉県ではこの日にどのようなことが行われますか?
A: 県民が郷土への理解と関心を深め、県民としての一体感を育むことを目的に、県内の公立学校が休日となるほか、県有施設(博物館、美術館など)の無料開放や割引、記念イベントなどが各地で開催されます。
合併により県域が確定した日: 栃木県民の日
1986年(昭和61年)に栃木県が制定。1873年(明治6年)のこの日、(旧)栃木県(現在の栃木県南部)と宇都宮県(現在の栃木県北部)が合併して、おおむね現在の県域と同じ栃木県が成立した。
Q: なぜ6月15日が「栃木県民の日」なのですか?
A: 千葉県と同じく、1873年(明治6年)の6月15日に、当時の栃木県(県庁:栃木町)と宇都宮県(県庁:宇都宮)が合併し、現在の県域とほぼ同じ「栃木県」(県庁:宇都宮)が誕生したことを記念して制定されました。
Q: 栃木県ではこの日にどのようなことが行われますか?
A: こちらも県民が郷土について知り、誇りと愛着を持つことを目的に、県有施設の無料開放や割引、記念行事などが実施されます。県民が一体となって祝う日として位置づけられています。
夏の便りの始まり!専用はがき発売日: 暑中見舞いの日
1950年(昭和25年)のこの日、当時の郵政省が初めて「暑中見舞用郵便葉書」を発売した。
Q: なぜ6月15日が「暑中見舞いの日」なのですか?
A: 1950年(昭和25年)の6月15日に、夏の季節の挨拶状である暑中見舞いを手軽に出せるように、当時の郵政省(現在の日本郵便)が初めて専用の「暑中見舞用郵便葉書」(くじ付き)を発売したことに由来します。
Q: 暑中見舞いはいつ頃出すのが適切ですか?
A: 暑中見舞いは、夏の暑さが厳しい時期に、相手の健康を気遣い、近況を報告するためのものです。一般的には、梅雨明け後から立秋(8月7日頃)の前までに出すのが良いとされています。立秋を過ぎたら「残暑見舞い」となります。
愛らしい鳥たちへの関心を高める日: オウムとインコの日
認定NPO法人「TSUBASA」が制定。日付は「オウム(06)インコ(15)」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ6月15日が「オウムとインコの日」なのですか?
A: 日付の数字の読み方「0(オー)6(ム)」「1(イン)5(コ)」を組み合わせて、「オウムインコ」と読むユニークな語呂合わせから、この日が記念日として制定されました。
Q: この記念日はどのような目的で制定されたのですか?
A: 飼い鳥の保護活動などを行う認定NPO法人「TSUBASA」によって制定されました。ペットとして人気の高いオウムやインコについて、その生態や適切な飼育方法、寿命が長いことなどを広く知ってもらい、飼育放棄などの問題を減らし、終生飼養への理解を深めてもらうことを目的としています。
体を温める食材!神社の祭礼にちなむ日: 生姜の日
生姜の研究・商品開発を行っている永谷園が制定。日付は石川県金沢市の波自加彌(はじかみ)神社で「はじかみ大祭」(生姜祭り)が行われる日であることから。
Q: なぜ6月15日が「生姜の日」なのですか?
A: 石川県金沢市にある波自加彌(はじかみ)神社は、日本で唯一、香辛料の神様を祀る神社として知られています。この神社で、古くから生姜(古名:はじかみ)を祀るお祭り「はじかみ大祭」(通称:生姜祭り)が毎年6月15日に行われることにちなんで制定されました。
Q: 生姜はどのような効能があると言われていますか?
A: 生姜に含まれる辛味成分(ジンゲロール、ショウガオール)には、血行を促進して体を温める効果や、殺菌作用、抗酸化作用などがあるとされています。また、吐き気を抑えたり、消化を助けたりする効果も期待されています。薬味としてだけでなく、料理の風味付け、飲み物、お菓子など、幅広く利用されています。