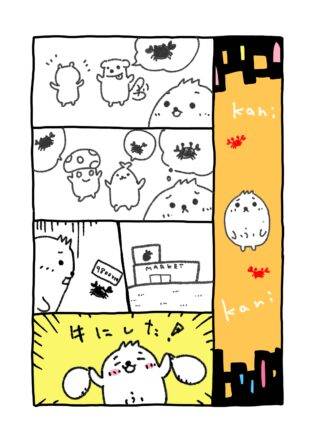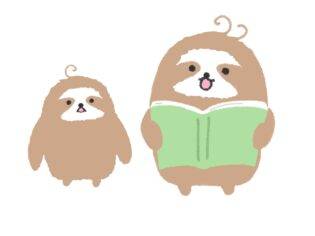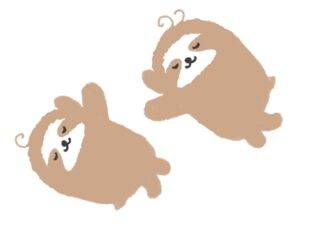6月1日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
世界中の親に感謝する国際デー: 国際親の日
2012年(平成24年)9月の国連総会で制定。国際デーの一つ。世界中の親に敬意を表する日である。また、世界中の全ての場所において、親の子どもへの無欲な献身とその関係を育むために生涯を捧げることに対して感謝を述べる日である。
Q: なぜ国連は「国際親の日」を制定したのですか?
A: 子どもの育成と保護において、親(保護者)が果たす最も重要な役割を認識し、その献身的な努力に敬意を表するために制定されました。家族の基盤である親子関係の大切さを、国際社会全体で再確認する日です。
Q: この日はどのように祝われていますか?
A: 特定の祝い方があるわけではありませんが、日頃の感謝を込めて、親にメッセージを送ったり、一緒に時間を過ごしたりする良い機会となるでしょう。また、子育て支援や家族のあり方について考えるきっかけの日でもあります。
世界の子供たちの福祉を考える日: 国際こどもの日
1925年(大正14年)8月にスイスのジュネーブで開かれた子供の福祉世界会議で制定。世界の40ヵ国余りが、6月1日を「こどもの日」としている。
Q: なぜ6月1日が「国際こどもの日」なのですか?
A: 1925年にジュネーブで開催された「子供の福祉世界会議」で、子どもの権利を守り、健やかな成長を願う日として提唱されたことが始まりです。特に旧社会主義国を中心に、多くの国でこの日が「こどもの日」として祝われています。
Q: 日本の「こどもの日」(5月5日)とは違うのですか?
A: はい、異なります。日本の「こどもの日」は国民の祝日として法律で定められていますが、6月1日の「国際こどもの日」は国際的な記念日の一つです。目的は共通していますが、由来や祝われる国が異なります。
牛乳の恵みに感謝する国際デー: 世界牛乳の日・牛乳の日
国連食糧農業機関(FAO)が2001年(平成13年)に「世界牛乳の日」を制定。これに合わせて酪農・乳業関係者で構成される日本酪農乳業協会(現:一般社団法人・Jミルク)が2007年(平成19年)にこの日を「牛乳の日」に制定した。

Q: なぜ6月1日が「世界牛乳の日」に選ばれたのですか?
A: 国連食糧農業機関(FAO)が、牛乳への関心を高め、酪農・乳業の仕事を広く知ってもらうことを目的に制定しました。日付の明確な理由は公表されていませんが、多くの国で学校が始まる時期であり、子どもたちの成長に欠かせない牛乳をアピールするのに適しているなどの理由が考えられます。
Q: 牛乳にはどのような栄養が含まれていますか?
A: 牛乳は、骨や歯を作るのに欠かせないカルシウムをはじめ、良質なたんぱく質、ビタミン(A, B2, B12など)といった、私たちの体に必要な栄養素をバランス良く含んでいます。「準完全栄養食品」とも呼ばれ、特に成長期の子どもから高齢者まで、幅広い世代にとって重要な食品です。
季節に合わせて衣類を替える習慣の日: 衣替えの日
季節の変化に応じて衣服を着替える日。

Q: なぜ6月1日が「衣替えの日」とされているのですか?
A: これは平安時代の宮中行事に由来する習慣です。当時は旧暦の4月1日と10月1日に夏装束と冬装束を入れ替えていました。明治時代以降、新暦が採用され、官公庁や学校などで6月1日に夏服へ、10月1日に冬服へ替える習慣が定着しました。
Q: 衣替えの目的は何ですか?
A: 日本の四季の変化に合わせて、気温や湿度に適した服装をすることで、快適に過ごし、健康を維持することが主な目的です。また、季節の移り変わりを感じ、生活にメリハリをつけるという意味合いもあります。衣類の整理や手入れをする良い機会でもあります。
写真文化の普及と発展を願う日: 写真の日
公益社団法人・日本写真協会が「写真の日制定委員会」において1951年(昭和26年)に制定。

Q: なぜ6月1日が「写真の日」なのですか?
A: 日本写真協会が制定した際、江戸時代の1841年(天保12年)のこの日に、日本で初めて写真が撮影されたという説(蘭学者・上野俊之丞が薩摩藩主・島津斉彬を撮影したとされる)に基づいています。ただし、この説には異論もあり、現在では明確な由来とはされていませんが、記念日としては定着しています。
Q: 写真にはどのような力がありますか?
A: 写真は、その瞬間の出来事や風景、人々の表情などを記録し、後世に伝える力を持っています。また、言葉だけでは伝えきれない感動や情報を視覚的に伝え、人々の心を動かす力も持っています。記録、報道、芸術、コミュニケーションなど、様々な分野で重要な役割を果たしています。
日本の近代気象観測の始まり: 気象記念日
1884年(明治17年)に東京気象台(現在の気象庁)が制定。1875年(明治8年)のこの日、東京・赤坂葵町に、日本初の気象台「東京気象台」が設置され、東京で気象と地震の観測が開始された。
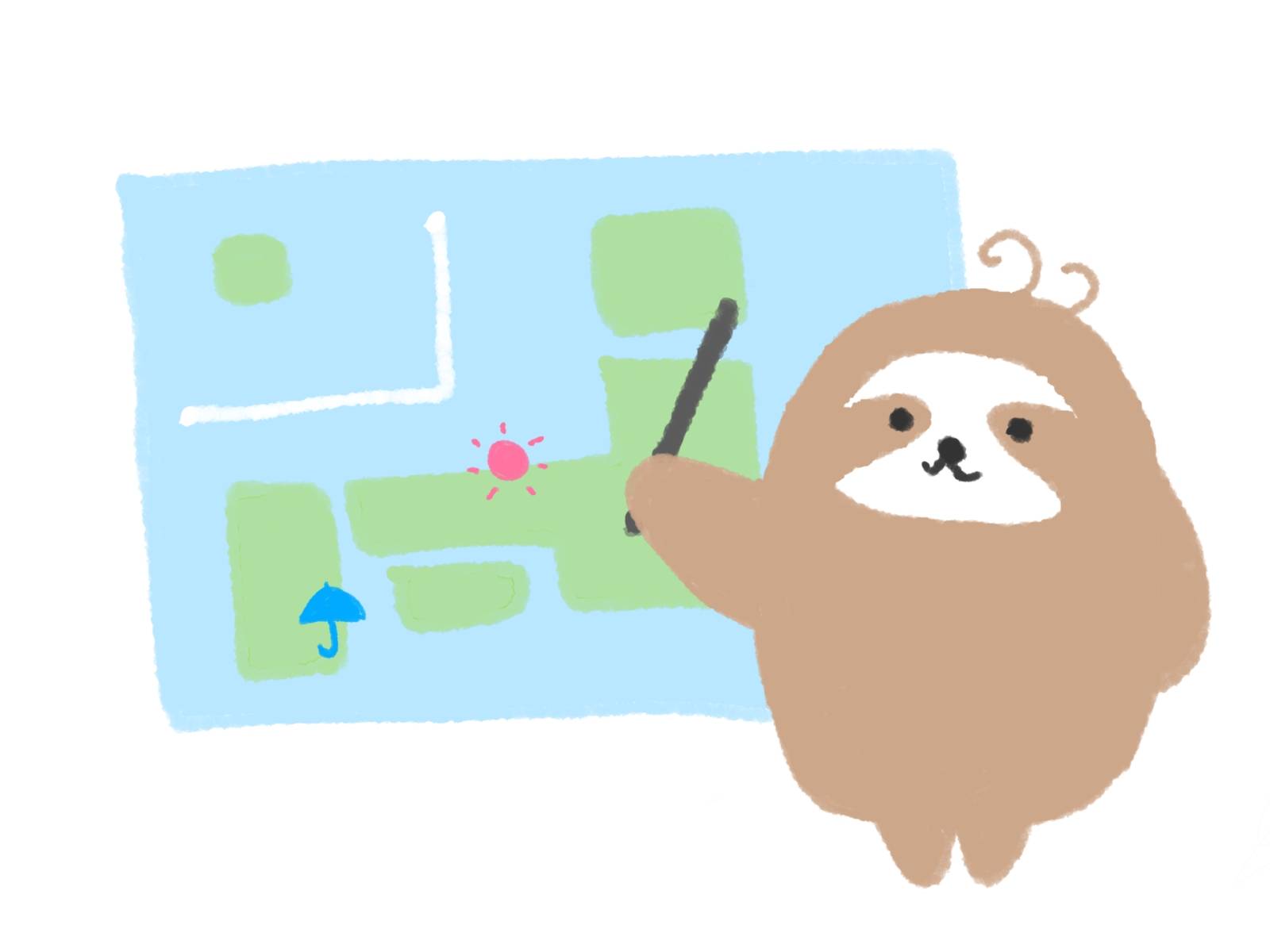
Q: なぜ6月1日が「気象記念日」なのですか?
A: 1875年(明治8年)の6月1日に、現在の気象庁の前身である「東京気象台」が業務を開始し、日本で初めて継続的な気象観測と地震観測が始まったことを記念しています。
Q: 気象観測は私たちの生活にどのように役立っていますか?
A: 日々の天気予報はもちろん、台風や大雨などの気象災害から命や財産を守るための防災情報、農業や漁業、交通機関など様々な産業活動の計画、地球温暖化などの気候変動の研究など、私たちの安全で快適な生活と社会活動を支える上で、気象観測とその情報は不可欠なものとなっています。
電波利用が国民に開放された日: 電波の日
1951年(昭和26年)に郵政省(現在の総務省)が制定。1950年(昭和25年)のこの日、電波三法(電波法・放送法・電波監理委員会設置法)が施行され、電波が一般に開放された。
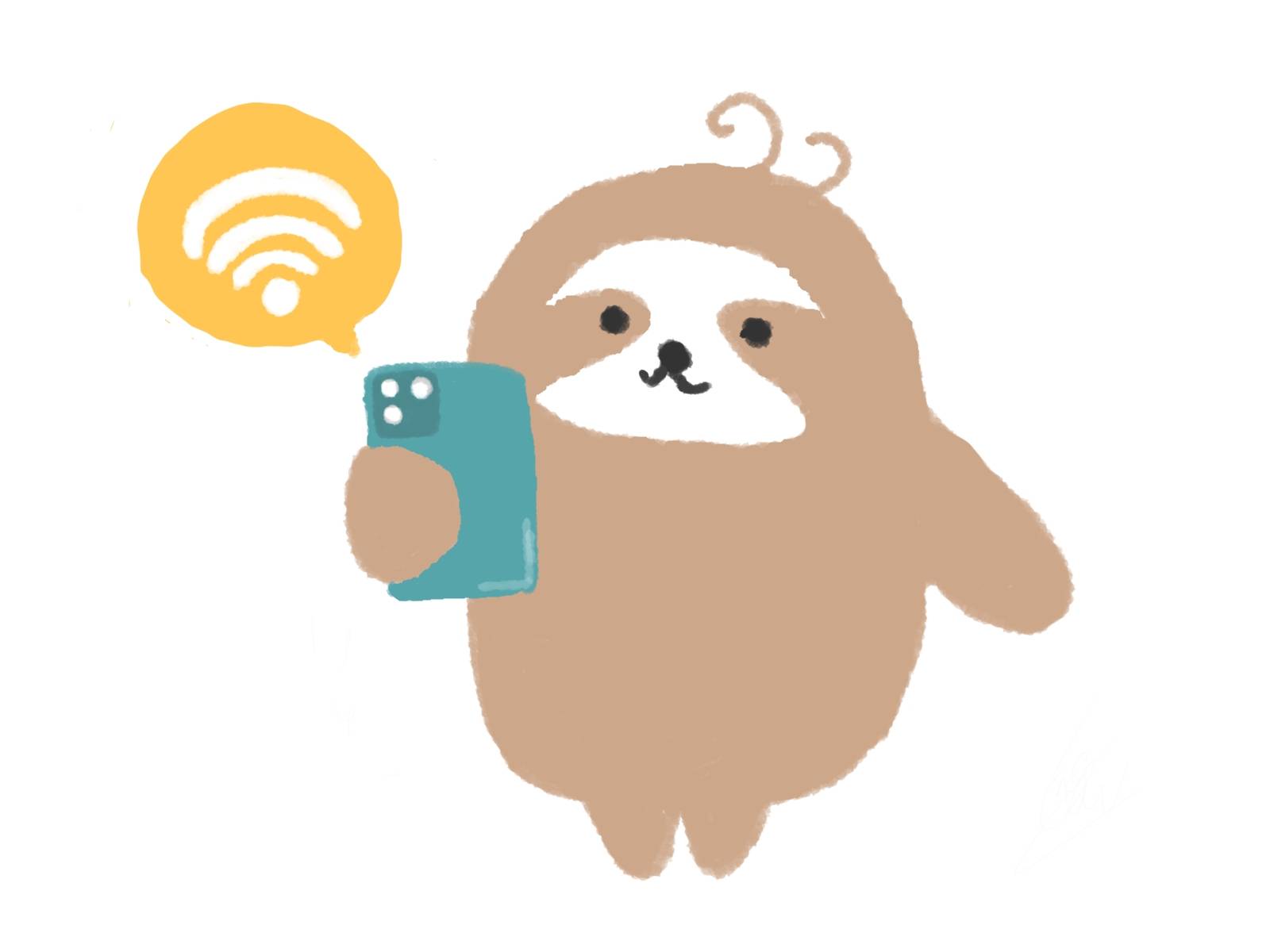
Q: なぜ6月1日が「電波の日」なのですか?
A: 1950年(昭和25年)の6月1日に、「電波法」「放送法」「電波監理委員会設置法」の電波三法が施行されたことに由来します。これにより、それまで主に政府が管理していた電波の利用が民間にも開放され、ラジオやテレビ放送、無線通信などが発展する基礎が築かれました。
Q: 電波は私たちの生活でどのように使われていますか?
A: テレビやラジオの放送、携帯電話やスマートフォンでの通信、Wi-Fi、GPS、電子レンジ、医療機器(MRIなど)、航空・船舶のレーダーや無線など、私たちの生活や社会活動のあらゆる場面で、目に見えない電波が利用されています。情報通信社会を支える基盤技術です。
噛む習慣と健康を考える日: チューインガムの日
日本チューインガム協会が1994年(平成6年)に制定。平安時代、元日と6月1日に、餅などの固いものを食べて健康と長寿を祈る「歯固め」の風習があったことに由来する。

Q: なぜ6月1日が「チューインガムの日」なのですか?
A: 平安時代には、年の始め(元日)と6月1日に、鏡餅などの固いものを食べて歯を丈夫にし、健康と長寿を願う「歯固め(はがため)」という宮中行事がありました。この「6月1日」にちなんで、噛むことと関連の深いチューインガムの記念日とされました。
Q: チューインガムを噛むことには、どのような効果がありますか?
A: 噛むことで唾液の分泌が促進され、口の中を清潔に保ち、虫歯や口臭の予防に役立ちます。また、噛むリズム運動が脳を活性化させ、集中力や記憶力を高める効果も期待されています。気分転換やストレス解消にもつながると言われています。
加賀藩から将軍家への献上品に由来する日: 氷の日
日本冷凍倉庫協会が制定。日付は江戸時代、加賀藩が将軍家に旧暦の6月1日に氷を献上し「氷室の日」として祝ったことから。
Q: なぜ6月1日が「氷の日」なのですか?
A: 江戸時代、加賀藩(現在の石川県)では、冬の間に雪を「氷室(ひむろ)」と呼ばれる貯蔵庫に保管し、夏になった旧暦の6月1日に江戸の将軍家へ献上する習わしがありました。この日を「氷室の日」と呼んでいたことにちなんで制定されました。
Q: 当時、氷はどのように運ばれたのですか?
A: 金沢から江戸まで、氷が溶けないように藁(わら)などで厳重に梱包し、昼夜兼行で飛脚がリレー方式で運びました。大変な労力を要する、貴重な贈り物でした。この氷は、夏の暑さをしのぐための貴重品として、将軍や大名たちに大変喜ばれたと言われています。
6月の誕生石を祝う日: 真珠の日
一般社団法人・日本真珠振興会が1965年(昭和40年)に制定。日付は6月の誕生石が「真珠」であることから、6月最初の6月1日を記念日としたもの。

Q: なぜ6月1日が「真珠の日」なのですか?
A: 真珠(パール)が6月の誕生石とされていることから、その月の最初の日である6月1日が記念日として選ばれました。
Q: 真珠はどのようにしてできるのですか?
A: 真珠は、アコヤガイやシロチョウガイ、クロチョウガイなどの貝の体内に、偶然または人工的に異物(核など)が入った際に、貝がその異物を自身の分泌物(真珠層)で包み込むことによって形成される生体鉱物です。幾重にも重なった真珠層が、真珠特有の美しい光沢(テリ)を生み出します。
Q: 真珠にはどのような意味が込められていますか?
A: 真珠は古くから「月のしずく」「人魚の涙」などと呼ばれ、その清純で上品な輝きから、健康、長寿、富、純潔、円満などの石言葉を持っています。冠婚葬祭などフォーマルな場面で身につけられることも多い宝石です。
清流の味覚、本格シーズン到来: 鮎の日
全国鮎(あゆ)養殖漁業組合連合会が2014年(平成26年)に制定。日付は6月1日がアユ釣りの解禁日としている地域が全国的に多く、また、アユが小売店に出そろうことからこの日が選ばれた。
Q: なぜ6月1日が「鮎の日」なのですか?
A: 日本の多くの河川で、アユ釣りが解禁されるのが6月1日頃であること、また、この時期になると天然アユや養殖アユがスーパーなどの店頭にも並び始め、本格的なアユのシーズンが始まることから、この日が記念日として制定されました。
Q: アユはどのような魚ですか?
A: アユは、日本の川を代表する魚の一つで、清流を好み、川底の石についた藻類を主食としています。その独特の香り(スイカやキュウリに例えられる)と上品な味わいから、「香魚」とも呼ばれ、初夏の味覚として珍重されています。塩焼きが定番ですが、天ぷら、甘露煮、鮎飯など様々な料理で楽しまれます。
沖縄の夏を彩るファッションの日: かりゆしウェアの日
沖縄県衣類縫製品工業組合が制定。日付は2007年(平成19年)6月1日に「かりゆしウェアを世界に広める会」が発足したことと、年中行事「衣替えの日」から6月1日としたもの。

Q: なぜ6月1日が「かりゆしウェアの日」なのですか?
A: 由来は二つあります。一つは、沖縄の夏のビジネスウェア・カジュアルウェアとして定着した「かりゆしウェア」の普及を目指す「かりゆしウェアを世界に広める会」が2007年に発足した日であること。もう一つは、本土の「衣替えの日」に合わせて、沖縄でも夏の装いであるかりゆしウェアの着用が本格化する時期であることからです。
Q: 「かりゆしウェア」とは、どのような服装ですか?
A: 沖縄の伝統的な染織物(紅型など)や自然、文化をモチーフにした柄が特徴的な、開襟シャツ(アロハシャツに似たスタイル)です。「かりゆし」とは沖縄の言葉で「めでたい」「縁起が良い」という意味があります。夏の沖縄では、ビジネスシーンや冠婚葬祭など、様々な場面で着用されています。
夏の定番飲料!収穫期と衣替えの日: 麦茶の日
1986年(昭和61年)に全国麦茶工業協同組合が制定。6月は麦茶の原料である大麦の収穫期にあたり、麦茶の季節の始りでもあることや、衣替えの日でもあることから。

Q: なぜ6月1日が「麦茶の日」なのですか?
A: 主な理由は二つあります。一つは、麦茶の原料となる大麦の収穫がピークを迎えるのが6月頃であること。もう一つは、夏服への「衣替えの日」であり、これから暑くなる季節にぴったりの飲み物である麦茶のシーズンが始まることを示すためです。
Q: 麦茶はなぜ夏によく飲まれるのですか?
A: 麦茶にはカフェインが含まれていないため、子どもからお年寄りまで安心して飲むことができます。また、体を冷やす効果があるとも言われ、香ばしい風味でさっぱりと飲めることから、夏の水分補給に適した飲み物として古くから親しまれています。ミネラル(特にカリウムや亜鉛など)も含まれており、汗で失われがちなミネラルの補給にも役立ちます。