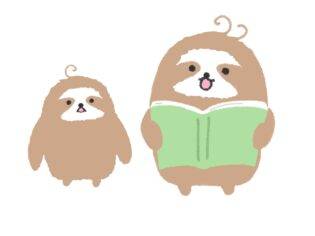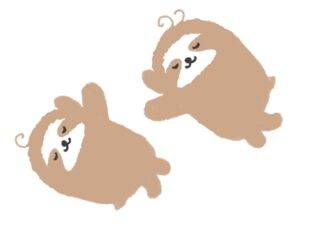6月12日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
ブラジルの風習にちなむ愛の日: 恋人の日
全国額縁組合連合会が1988年(昭和63年)に制定。ブラジル・サンパウロ地方では、女性の守護神で縁結びの神でもある聖アントニオの命日の前日の6月12日を「恋人の日」として、家族や友人、恋人同士が写真立て(フォトフレーム)に写真を入れ交換し合う風習があることから。
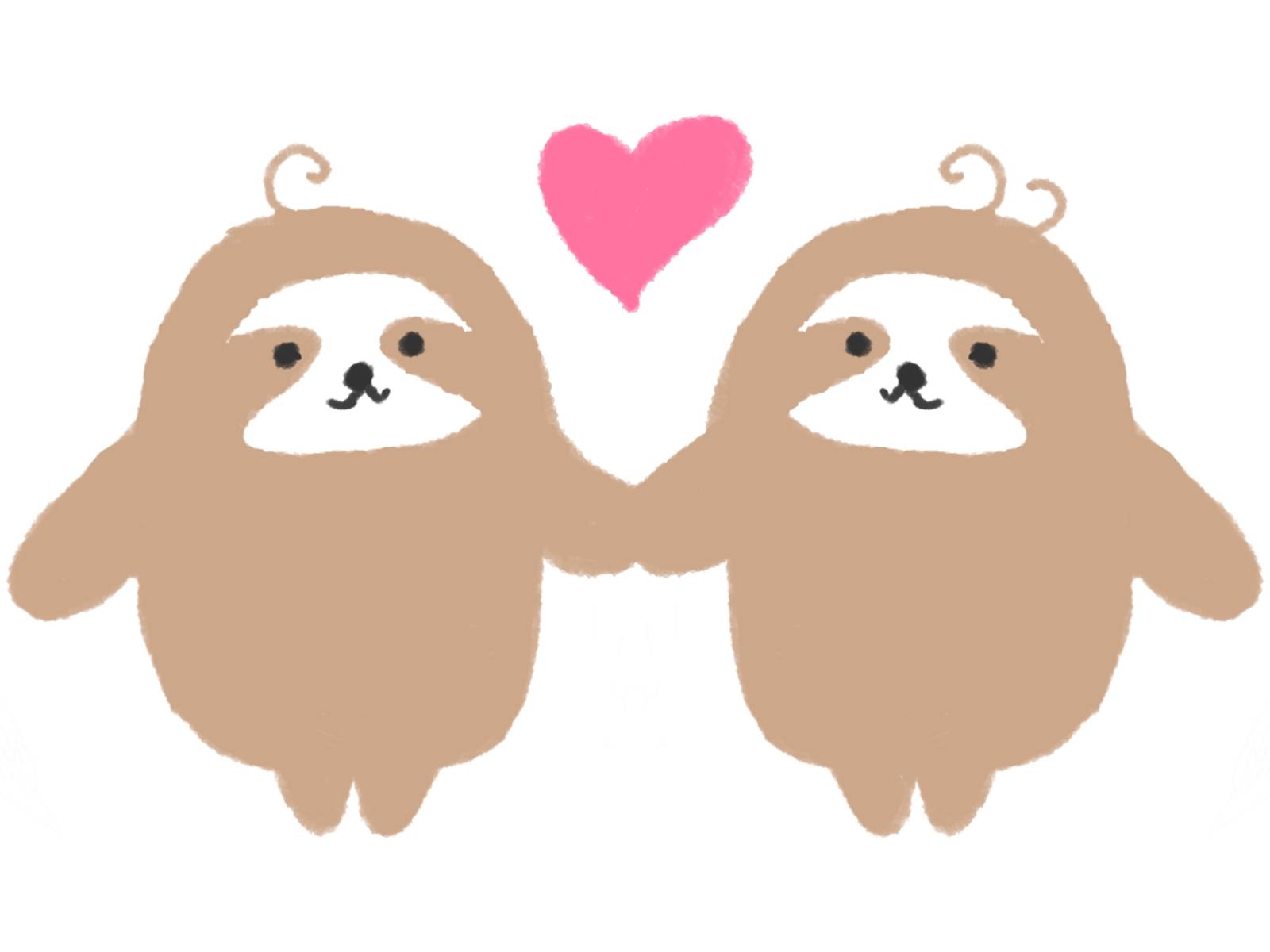
Q: なぜ日本の額縁団体がブラジルの風習にちなんだ記念日を制定したのですか?
A: ブラジルの「恋人の日」には、写真をフォトフレームに入れて贈り合うという風習があります。全国額縁組合連合会は、この素敵な習慣を日本にも広め、写真立ての需要を喚起することを目的に、この日を日本の「恋人の日」として制定しました。
Q: 聖アントニオとはどのような聖人ですか?
A: 聖アントニオ・デ・パドヴァは、13世紀のフランシスコ会の修道士で、カトリック教会で広く崇敬されている聖人の一人です。失くし物を探す際の助け手として、また縁結びや花嫁の守護聖人としても知られています。彼の命日は6月13日です。
少女が綴った希望と絶望の記録: アンネの日記の日
1942年(昭和17年)のこの日、ユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランクによって『アンネの日記』が書き始められた。
Q: なぜ6月12日が「アンネの日記の日」なのですか?
A: 第二次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れるため、オランダ・アムステルダムの隠れ家で暮らしていたユダヤ人の少女アンネ・フランクが、13歳の誕生日に贈られた日記帳に最初の日記を書き始めたのが、1942年の6月12日だったことに由来します。
Q: 『アンネの日記』はなぜ世界中で読まれているのですか?
A: この日記には、隠れ家での息詰まるような生活の中で、思春期の少女アンネが抱いた不安や希望、家族や同居人との関係、そして自身の成長などが瑞々しい感性で綴られています。過酷な状況下でも人間性を失わず、未来への希望を託した彼女の言葉は、戦争の悲劇と平和の尊さを後世に伝え、多くの人々の心を打ち続けています。
国際語の普及を願う設立記念日: エスペラントの日
日本エスペラント学会が制定。1906年(明治39年)のこの日、日本エスペラント協会が設立された。エスペラントは、ルドヴィコ・ザメンホフとその協力者たちが考案・整備した人工言語。 母語の異なる人々の間での意思伝達を目的とする。
Q: なぜ6月12日が「エスペラントの日」なのですか?
A: 1906年(明治39年)の6月12日に、日本でエスペラント語の普及と学習者の交流を目的とする「日本エスペラント協会」(現在の日本エスペラント学会の前身の一つ)が設立されたことを記念しています。
Q: エスペラントはどのような言語ですか?
A: 19世紀末にポーランドの眼科医ルドヴィコ・ザメンホフによって考案された国際補助語です。特定の民族や国家に属さず、文法が規則的で覚えやすいように設計されており、世界中の人々が母語の違いを超えて対等にコミュニケーションできることを目指しています。現在も世界中に学習者や使用者が存在します。
日本初のチャリティーイベント開催日: バザー記念日
1884年(明治17年)のこの日、鹿鳴館で第1回婦人慈善市という日本初のバザーが開催された。
Q: なぜ6月12日が「バザー記念日」なのですか?
A: 1884年(明治17年)の6月12日から3日間にわたり、東京の鹿鳴館(ろくめいかん)で、日本で初めてとされる本格的なバザー「第一回 婦人慈善市」が開催されたことに由来します。
Q: どのような目的でバザーが開催されたのですか?
A: 当時の上流階級の婦人たちが中心となり、手作りの品物や寄贈品などを販売し、その収益を病院などの慈善事業に寄付することを目的としていました。これは、女性の社会貢献活動の先駆けとも言えるイベントであり、多くの人々が集まり盛況だったと伝えられています。
本格インドカリーを日本に紹介した日: 恋と革命のインドカリーの日
1927年(昭和2年)のこの日、東京・新宿に中村屋の喫茶部(レストラン)を開設し、日本で初めて「純印度式カリー」を売り出した株式会社中村屋が制定。
Q: なぜ「恋と革命」という言葉が使われているのですか?
A: 中村屋の創業者夫妻は、イギリスからの独立運動のために日本に亡命していたインド人独立運動家ラス・ビハリ・ボースを匿い、支援しました。この記念日は、ボースが伝えた本場のカリーの味と、彼の祖国解放への情熱(革命)、そして彼を支えた中村屋夫妻の愛にちなんで名付けられました。
Q: 中村屋の「純印度式カリー」は、当時のカレーとどう違ったのですか?
A: 当時日本で一般的だったイギリス風のカレー(小麦粉でとろみをつけたもの)とは異なり、ボースが伝えたレシピに基づき、多くのスパイスを使って作られた本格的なインド式カリーでした。骨付きの鶏肉を使い、ご飯もインディカ米(長粒米)を使用するなど、本場の味を忠実に再現しようとした画期的なメニューでした。
子どもたちを過酷な労働から守る国際デー: 児童労働反対世界デー
2002年に国際労働機関(ILO)によって制定された国際デー。世界中で児童労働の問題に対する意識を高め、その撤廃に向けた取り組みを促進することが目的。
Q: なぜ児童労働の問題に取り組む必要があるのですか?
A: 世界には、貧困や紛争などの理由で、教育を受ける機会を奪われ、危険で有害な労働に従事させられている子どもたちが未だに多く存在します。児童労働は、子どもたちの健全な成長を妨げ、将来の可能性を奪う深刻な人権侵害です。この問題の解決には、国際社会全体での取り組みが必要です。
Q: この日はどのようなことが行われますか?
A: 世界各地で、児童労働の実態を知らせるキャンペーンや、問題解決に向けた議論を行う会議、啓発イベントなどが開催されます。私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、児童労働によって作られた製品を購入しないように心がけることなども、解決に向けた一歩となります。