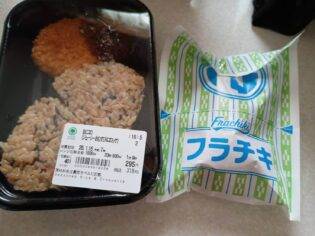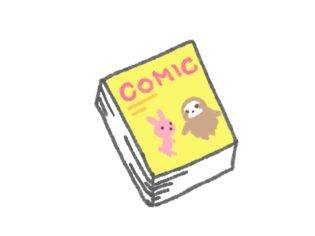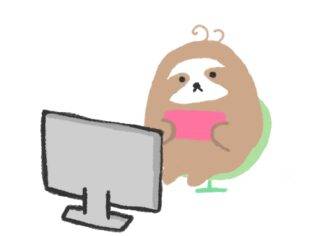7月3日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本上陸を祝う冷たいデザート: ソフトクリームの日
日本ソフトクリーム協議会が1990年(平成2年)に制定。1951年(昭和26年)のこの日、明治神宮外苑で行われた米軍主催の「アメリカ独立記念日」(7月4日)を祝うカーニバルで、ソフトクリームの模擬店を立ち上げ、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売された。

Q: なぜアメリカ独立記念日のカーニバルで販売されたのですか?
A: ソフトクリームはアメリカで生まれたデザートであり、当時まだ日本では珍しいものでした。進駐軍(米軍)が主催したアメリカ独立記念日を祝うイベントで、アメリカ文化を紹介する一環として模擬店が出され、そこで初めて一般の日本人にも提供されたため、この出来事が日本のソフトクリームの歴史の始まりとされています。
Q: ソフトクリームとアイスクリームの主な違いは何ですか?
A: 最大の違いは温度と製造工程です。ソフトクリームは、フリーザーから直接絞り出して提供されるため、-5℃から-7℃程度とアイスクリーム(通常-18℃以下で保存)より温度が高く、柔らかくなめらかな食感が特徴です。また、製造時に空気の含有量を調整することで、独特の軽い口当たりになります。
Q: 日本ソフトクリーム協議会はどのような団体ですか?
A: ソフトクリームの原料メーカーや機械メーカー、販売店などが加盟し、ソフトクリームの品質向上、衛生管理の推進、消費拡大のためのPR活動などを行っている業界団体です。ソフトクリーム文化の普及と発展を目指して活動しています。
なにわのシンボルタワー誕生: 通天閣の日
1912年(明治45年)のこの日、大阪府大阪市浪速区に通天閣が完成した。
Q: 初代通天閣はどのような建物でしたか?
A: パリのエッフェル塔(上半分)と凱旋門(下半分)を模してデザインされた、高さ約64メートルの鉄骨造りの塔でした。当時東洋一の高さを誇り、隣接していた遊園地「ルナパーク」と共に、大阪の新名所として大変な人気を集めました。内部にはエレベーターも設置されていました。
Q: 現在の通天閣は初代と同じものですか?
A: いいえ、初代通天閣は1943年(昭和18年)に火災による損傷と、戦時中の金属回収令により解体されました。現在の通天閣は、戦後の1956年(昭和31年)に地元の有志によって再建された二代目です。高さは約108メートル(避雷針含む)となり、デザインも初代とは異なりますが、大阪のシンボルとして親しまれています。
Q: 通天閣の名前の由来は何ですか?
A: 「天に通じる高い建物」という意味を込めて、明治初期の儒学者・藤沢南岳(ふじさわなんがく)によって命名されました。初代完成当時、その高さと斬新なデザインが、まさに天にも届くような印象を与えたことから付けられた名前です。
絶妙ブレンドの和風スパイス: 七味の日
株式会社向井珍味堂が2010年(平成22年)に制定。日付は「しち(7)み(3)」(七味)と読む語呂合わせから。
Q: 七味唐辛子には具体的に何が入っていますか?
A: 基本的には唐辛子を主原料とし、その他6種類の香辛料(薬味)をブレンドしたものです。代表的な材料としては、山椒、陳皮(みかんの皮)、胡麻、麻の実、けしの実、青のり、生姜などがありますが、メーカーや地域によって配合や種類は異なります。それぞれの素材の風味、辛味、香りが合わさって独特の味わいを生み出します。
Q: 七味唐辛子はいつ頃からあるのですか?
A: 江戸時代の中期(17世紀頃)、江戸・両国の薬研堀(やげんぼり)にあった「からしや徳右衛門」が、漢方薬の知識を応用して売り出したのが始まりとされています。当初は、風邪の予防などの薬効も期待されていたようです。その後、うどんやそばの薬味として人気が広まりました。
Q: 株式会社向井珍味堂はどのような会社ですか?
A: 大阪市にある香辛料メーカーで、七味唐辛子をはじめ、きな粉、ごま、わさびなど、様々な香辛料や薬味、粉類を製造・販売しています。品質にこだわった製品づくりで知られています。七味唐辛子の魅力を広めるために記念日を制定したと考えられます。
海の躍動を感じる語呂合わせ: 波の日
株式会社サイバードが制定。日付は「な(7)み(3)」(波)と読む語呂合わせから。
Q: 株式会社サイバードはどのような会社ですか?
A: モバイルコンテンツサービスやゲームの開発・提供などを主力事業とするIT企業です。サーフィン情報サイト「なみある?」などを運営していた経緯から、サーフィンをはじめとするマリンスポーツや海の魅力を多くの人に伝え、楽しんでもらうきっかけを作るために、語呂合わせで記念日を制定したと考えられます。
Q: 波にはどのような種類がありますか?
A: 波が発生する原因によって、風によって起こる「風浪(ふうろう)」、風がおさまった後も伝わる「うねり」、地震や海底火山によって起こる「津波」、船の航行によって起こる「引き波」などがあります。また、海岸近くで砕ける波を「磯波(いそなみ)」と呼んだりもします。
Q: サーフィンに適した波とはどのようなものですか?
A: 適度な高さとパワーがあり、岸に向かって規則的に、そしてある程度のスピードで崩れていく波がサーフィンに適しているとされます。風の影響が少なく、形が整った「うねり」が良い波とされることが多いです。波の質は海底の地形や風向き、潮の満ち引きなどによって大きく変化します。
元気ハツラツ!ドリンクの記念日: オロナミンCの日
大塚製薬株式会社が制定。日付は「オロナ(7)ミ(3)ンC」と読む語呂合わせから。
Q: オロナミンCはいつ発売されたのですか?
A: 1965年(昭和40年)に発売されました。発売当初は、医薬品に近いイメージを持たせるために薬局を中心に販売されていましたが、その後、自動販売機やコンビニエンスストアなどでも広く販売されるようになり、国民的な炭酸栄養ドリンクとして定着しました。
Q: オロナミンCの特徴的な成分は何ですか?
A: ビタミンCをはじめ、ビタミンB群(B2、B6)、アミノ酸、ハチミツなどが含まれています。炭酸による爽快な飲み口と、独特の甘さと風味が特徴です。「元気ハツラツ!」のキャッチフレーズと共に、手軽に栄養補給ができるドリンクとして長年親しまれています。
Q: 大塚製薬はオロナミンC以外にどのような製品で知られていますか?
A: 医療用医薬品の研究開発・製造販売を主力としながら、機能性食品・飲料(ポカリスエット、カロリーメイト、SOYJOYなど)や化粧品(ウル・オスなど)といった、独自の「ニュートラシューティカルズ関連事業」でも多くのヒット商品を生み出しています。「人々の健康維持・増進に貢献する」ことを企業理念としています。
目の潤いと健康を考える日: 涙の日
「ドライアイ研究会」が制定。日付は「な(7)み(3)だ」(涙)と読む語呂合わせから。
Q: 涙にはどのような役割があるのですか?
A: 涙は単なる水分ではなく、目の健康を守るために非常に重要な役割を担っています。主な役割として、(1)目の表面を潤し乾燥を防ぐ、(2)角膜に酸素や栄養を供給する、(3)ゴミや異物を洗い流す、(4)細菌やウイルスの感染を防ぐ(リゾチームなどの抗菌成分を含む)、(5)目の表面を滑らかにして鮮明な視界を保つ、などが挙げられます。
Q: ドライアイとはどのような状態ですか?
A: 涙の量が不足したり、涙の質が変化したりすることで、目の表面が十分に潤わなくなる病気です。目の乾き、疲れ、ゴロゴロ感、かすみ、充血、痛みなどの症状が現れます。原因としては、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、エアコンによる乾燥、コンタクトレンズの使用、加齢、特定の病気や薬の影響などが考えられます。
Q: ドライアイ研究会はどのような活動をしていますか?
A: ドライアイに関する最新の研究動向の共有、診断基準や治療法の検討、一般市民や医療従事者への情報提供や啓発活動などを行っている専門家の集まりです。ドライアイの正しい理解を広め、適切な診断と治療を促進することで、人々の目の健康を守ることを目指しています。