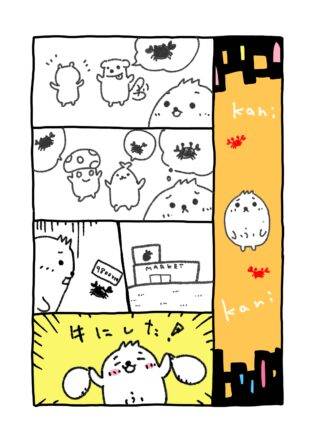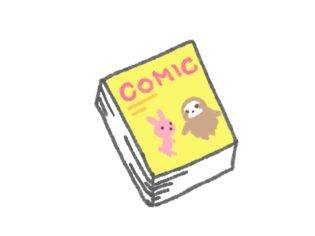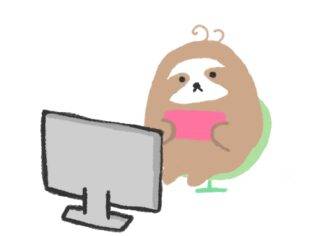7月21日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本の美しい自然を守り活かす: 自然公園の日
1957年(昭和32年)のこの日、「自然公園法」が制定された。
Q: 自然公園法とはどのような法律ですか?
A: 日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的とした法律です。この法律に基づき、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園が指定され、それぞれの景観や生態系の特性に応じた保護・管理が行われています。
Q: なぜこの法律が制定されたのですか?
A: 戦後の復興期を経て経済成長が進む中で、開発による自然景観の破壊が懸念されるようになりました。貴重な自然環境を次世代に引き継ぐため、法的な保護制度を確立する必要性が高まったことが背景にあります。
Q: 自然公園ではどのような活動ができますか?
A: 自然公園は保護だけでなく、人々が自然に親しみ、学ぶ場としての利用も目的としています。ハイキング、登山、キャンプ、自然観察、温泉利用など、自然の中で多様なレクリエーションを楽しむことができます。ただし、環境保全のためのルールを守ることが重要です。
日本が誇る三つの絶景を愛でる: 日本三景の日
日本三景観光連絡協議会が2006年(平成18年)に制定。
- 松島(宮城県)
- 天橋立(京都府)
- 宮島(広島県)
Q: なぜ7月21日が日本三景の日なのですか?
A: 日本三景という言葉を全国に広めたとされる江戸時代の儒学者・林羅山(はやしらざん)の誕生日(1583年7月21日)にちなんで制定されました。彼が著書『日本国事跡考』で松島・天橋立・宮島を「三処奇観」として紹介したことが起源とされています。
Q: 日本三景はそれぞれどのような景観ですか?
A:
- 松島: 宮城県の松島湾内に浮かぶ大小260余りの島々が織りなす多島海の景観。
- 天橋立: 京都府の宮津湾にある、全長約3.6kmの砂嘴(さし)で、約5000本の松林が続く。
- 宮島: 広島県廿日市市にある島で、海上に建つ朱塗りの大鳥居と厳島神社の社殿が象徴的。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: 長年にわたり日本の美しい景観の代表とされてきた日本三景の魅力を国内外に改めて発信し、観光振興につなげることを目的としています。
栄養豊富な高級鶏を記念する: 烏骨鶏の日
有限会社松本ファームの4社が制定。日付は烏骨鶏が1942年(昭和17年)7月21日に大分・三重・広島などの主産地で国の天然記念物として指定されたことから。
Q: なぜ烏骨鶏は国の天然記念物に指定されたのですか?
A: 皮膚、内臓、骨に至るまで黒いという特異な外見的特徴を持ち、観賞用や愛玩用、また古くから薬膳料理の材料としても珍重されてきた歴史的・学術的な価値が認められたためです。生物学的に貴重な種として保護の対象となりました。
Q: 烏骨鶏の卵にはどのような特徴がありますか?
A: 一般的な鶏卵に比べてサイズは小さいですが、卵黄の色が濃く、濃厚な味わいがあるとされています。また、DHAやEPA、ビタミン類などの栄養素が豊富に含まれていると言われ、高級食材として扱われています。
Q: この記念日はどのような目的で制定されましたか?
A: 烏骨鶏の価値や魅力を広く一般に知ってもらい、その飼育や関連商品の普及、消費拡大を図ることを目的として、烏骨鶏を扱う企業グループによって制定されました。
結婚式の感動を映像で残す文化の始まり: ウェディングビデオの日
日本綜合テレビ株式会社が制定。日付は同社が1976年(昭和51年)7月21日に設立されたことから。
Q: なぜこの会社(日本綜合テレビ)の設立日が記念日なのですか?
A: 日本綜合テレビ株式会社は、結婚式のビデオ撮影・制作サービスを早い時期から手がけ、その普及に貢献した企業のひとつです。同社の設立日を記念日とすることで、ウェディングビデオという文化の発展と、大切な日の思い出を映像で残すことの意義を伝える目的があります。
Q: ウェディングビデオはいつ頃から一般的になりましたか?
A: 1980年代以降、家庭用ビデオカメラ(カムコーダー)の普及に伴い、結婚式の様子を映像で記録することが徐々に広まりました。当初は親族や友人が撮影することも多かったですが、プロによる高品質な撮影・編集サービスへの需要が高まり、現在では多くのカップルが利用しています。
Q: ウェディングビデオにはどのような種類がありますか?
A: 当日の挙式・披露宴の様子を記録する「記録ビデオ」のほか、二人の生い立ちや馴れ初めを紹介する「プロフィールムービー」、披露宴の最後に上映する「エンドロールムービー」、結婚式前に行う「前撮りムービー」など、様々なスタイルの映像制作が行われています。
夏の読書キャンペーンを楽しむ: ナツイチの日
株式会社集英社が制定。日付は「ナ(7)ツ(2)イチ(1)」と読む語呂合わせと、キャンペーン期間中であることから。

Q: 「ナツイチ」とはどのようなキャンペーンですか?
A: 集英社文庫が毎年夏に展開している大規模な読書キャンペーンの名称です。「夏に一冊、いかがですか?」といった意味が込められており、対象となる文庫を購入するとオリジナルグッズがもらえるなどの特典があり、夏の読書を盛り上げる恒例企画となっています。
Q: なぜ「ナ(7)ツ(2)イチ(1)」の語呂合わせでこの日が選ばれたのですか?
A: キャンペーンの愛称である「ナツイチ」と日付を直接結びつけることで、覚えやすく親しみやすい記念日とするためです。夏のキャンペーン期間中であることも理由の一つです。
Q: ナツイチではどのような本がおすすめされていますか?
A: キャンペーンでは、集英社文庫の中から幅広いジャンルの作品が推薦・紹介されます。話題の新作から読み継がれる名作、夏にぴったりの爽やかな物語や冒険小説など、様々な読者の好みに合わせたラインナップが用意されることが多いです。
和装の結婚式のルーツを辿る: 神前結婚記念日
1900年(明治33年)のこの日、後の大正天皇(当時は皇太子嘉仁親王)と九条節子(後の貞明皇后)の御婚儀が、初めて宮中賢所(きゅうちゅうかしこどころ)で行われました。これが現在の「神前結婚式」の原型となったとされています。
Q: なぜこの結婚式が「神前結婚式」の始まりとされるのですか?
A: それまでの日本の結婚式は自宅で行うのが一般的でしたが、皇室が皇居内の賢所(天照大神を祀る場所)で神道の形式に則って結婚の儀式を行ったことが、国民に大きな影響を与えました。これを模範として、一般の人々の間でも神社で神前結婚式を行うスタイルが広まっていきました。
Q: 神前結婚式はどのような儀式ですか?
A: 神社の神殿において、斎主(神職)の進行のもと、修祓(しゅばつ、お祓い)、祝詞奏上(のりとそうじょう)、三献の儀(三三九度)、誓詞奏上(せいしそうじょう)、玉串拝礼(たまぐしはいれい)などの儀式を通じて、神前にて夫婦の永遠の契りを誓う、日本の伝統的な結婚式の形態です。
Q: この記念日は正式に制定されたものですか?
A: 特定の団体が公式に制定した記念日というわけではありませんが、日本の結婚式の歴史において重要な転換点となった日として、ブライダル業界などで語り継がれています。