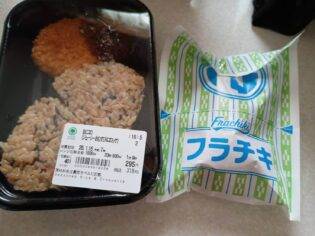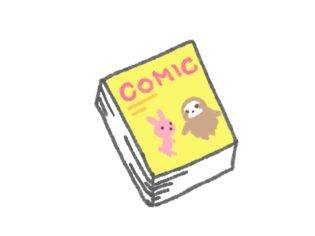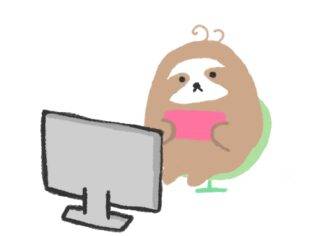7月26日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
第二次世界大戦終結への道筋を示した宣言: ポツダム宣言記念日
1945年(昭和20年)のこの日、アメリカ合衆国、中華民国、イギリスの3ヶ国の首脳が日本に無条件降伏を迫る「ポツダム宣言」をドイツ郊外のポツダムで発表しました。
Q: ポツダム宣言とは具体的にどのような内容だったのですか?
A: 連合国(米・英・中、後にソ連も参加)が日本に対して、軍隊の無条件降伏、戦争犯罪人の処罰、民主主義の確立、領土の制限などを要求した共同宣言です。日本がこれを受諾しなければ、「迅速且つ完全なる壊滅」をもたらすと警告しました。
Q: 日本はこの宣言にすぐ応じたのですか?
A: 当時の日本政府は、この宣言を「黙殺」する方針をとりました。しかし、その後広島と長崎への原子爆弾投下、ソ連の対日参戦などを経て、最終的に1945年8月14日に宣言の受諾を決定し、翌15日に終戦を国民に告げました。
Q: この宣言は戦後の日本にどのような影響を与えましたか?
A: ポツダム宣言の条項は、戦後の日本の占領政策の基本方針となり、日本国憲法の制定や軍隊の解体、民主化改革などに大きな影響を与えました。日本の戦後体制の出発点となる重要な文書です。
弘法大師が命名した景勝地: 日光の日
820年(弘仁11年)のこの日、弘法大師(空海)が日光山を命名したと伝えられています。元々は二荒山(ふたらさん)と呼ばれていましたが、二荒山に登った弘法大師がその景色に感動し、「二荒」を「にこう」と音読みし「日光山(にっこうさん)」と命名したといわれています。
Q: なぜ弘法大師が日光山を命名したと言われているのですか?
A: 伝承によれば、弘法大師(空海)が諸国を巡っていた際に二荒山(現在の男体山などを含む山々の総称)に登り、その神々しい風景に感銘を受けました。そして、観音菩薩が住むとされる伝説の山「補陀洛山(ふだらくさん)」の「ふたら」と音が似ていることから、「二荒(ふたら)」を「にこう」と読み替え、仏教的な意味合いを持つ「日光」の字を当てて「日光山」と命名したとされています。
Q: 日光はどのような場所ですか?
A: 栃木県にある地域で、日光東照宮、日光二荒山神社、輪王寺などの歴史的な建造物群(「日光の社寺」として世界遺産に登録)や、中禅寺湖、華厳の滝、男体山などの豊かな自然で知られる日本有数の観光地・景勝地です。
Q: 弘法大師(空海)とはどのような人物ですか?
A: 平安時代初期の僧侶であり、真言宗の開祖です。書道の名人(三筆の一人)としても知られ、日本各地に様々な伝説が残っています。高野山金剛峯寺を開いたことでも有名です。
日本の怪談文化を代表する歌舞伎初演: 幽霊の日
1825年(文政8年)のこの日、江戸の中村座で四代目・鶴屋南北作の歌舞伎狂言『東海道四谷怪談』が初演されました。

Q: なぜ『東海道四谷怪談』の初演日が「幽霊の日」なのですか?
A: この作品が、日本の幽霊譚(怪談)の中でも特に有名で、後世の様々な創作物に影響を与えた代表的な作品であることから、その初演日が「幽霊の日」と呼ばれるようになりました。特に、主人公お岩さんの怨霊は、日本の幽霊の典型的なイメージの一つとして定着しています。
Q: 『東海道四谷怪談』はどのような物語ですか?
A: 夫である伊右衛門に裏切られ、毒殺された女性・お岩が幽霊となって復讐を遂げるという物語です。因果応報や人間の業(ごう)といったテーマを扱い、恐ろしくも哀しいストーリーが人気を博しました。
Q: 作者の鶴屋南北とはどのような人物ですか?
A: 江戸時代後期の歌舞伎狂言作者で、四代目鶴屋南北が特に有名です。『東海道四谷怪談』のほかにも、『於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)』など、庶民のリアルな生活や愛憎劇、怪奇的な要素を取り入れた「生世話物(きぜわもの)」と呼ばれるジャンルを得意とし、多くの人気作を生み出しました。
夏の入浴の爽快さを広める語呂合わせ: 夏風呂の日
夏風呂の愛好家らが制定。日付は「な(7)つふ(2)ろ(6)」(夏風呂)と読む語呂合わせから。夏に入るお風呂の爽快さをもっと多くの人に知ってもらうことが目的。
Q: 「夏風呂の日」の由来は何ですか?
A: 日付の「726」を「な(7)つ(2)ふろ(6)」と読む語呂合わせから来ています。夏にお風呂に入ることの気持ちよさを表現した記念日です。
Q: 夏にお風呂に入るメリットは何ですか?
A: 暑い夏でも、ぬるめのお湯に浸かることで血行が促進され、夏バテ解消や疲労回復につながります。また、汗を流してさっぱりすることでリフレッシュ効果や安眠効果も期待できます。シャワーだけでなく湯船に浸かることの良さを見直すきっかけにもなります。
Q: この記念日は誰が制定したのですか?
A: 特定の企業や団体ではなく、夏にお風呂に入ることを楽しむ愛好家たちが中心となって制定したとされています。夏の入浴文化を広めたいという思いが込められています。
うなぎ風練り製品を楽しむ語呂合わせ: うな次郎の日
魚肉練り製品などを製造する一正蒲鉾株式会社が制定。日付は7月26日を0726と見立てて「う(0)な(7)じ(2)ろ(6)う」(うな次郎)と読む語呂合わせから。「うな次郎」は、うなぎの蒲焼きをイメージした魚のすり身で作った練り製品。
Q: 「うな次郎の日」はどのように決まったのですか?
A: 7月26日を数字で「0726」と表し、これを「う(0)な(7)じ(2)ろ(6)う」と読む語呂合わせに由来します。商品名をそのまま日付の語呂合わせにした、ユニークな記念日です。
Q: 「うな次郎」とはどのような商品ですか?
A: 新潟県に本社を置く一正蒲鉾株式会社が開発・販売している、魚のすり身(主にスケトウダラなど)を主原料として、見た目や食感、味をうなぎの蒲焼きに似せて作られた蒲鉾製品(魚肉練り製品)です。電子レンジなどで温めるだけで手軽にうなぎ風の味わいを楽しめます。
Q: この記念日を制定した目的は何ですか?
A: 自社製品である「うな次郎」の認知度を高め、より多くの人にその美味しさや手軽さを知ってもらうことを目的としています。特に、夏の土用の丑の日シーズンに合わせて、うなぎの代替品としてもアピールする狙いがあります。