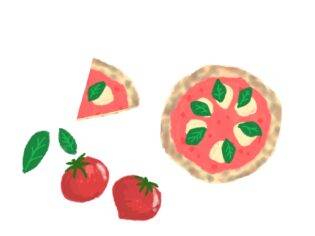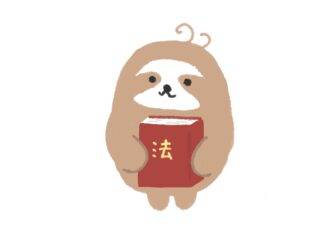9月1日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
関東大震災の教訓を忘れない、災害への備えを確認する日: 防災の日
1923年(大正12年)の9月1日午前11時58分、関東大震災が起こった日。 その経験から、震災火災に対する都市防災対策が大きく見直されました。

Q: なぜ9月1日が「防災の日」なのですか?
A: 1923年(大正12年)9月1日に発生し、10万人以上の死者・行方不明者を出した「関東大震災」の教訓を忘れないため、そして台風シーズンでもあるこの時期に、災害への備えを改めて確認するために制定されました(1960年閣議決定)。
Q: この日の目的は何ですか?
A: 地震、津波、台風、豪雨などの自然災害に対する国民の認識を深め、日頃からの備え(食料・水の備蓄、避難場所の確認、家具の固定など)や、災害発生時の適切な対応(情報収集、避難行動など)について考えるきっかけとすること、そして防災訓練などを通じて防災意識を高めることを目的としています。
Q: 「防災の日」にはどのようなことが行われますか?
A: 全国の自治体や学校、企業などで、地震や津波を想定した避難訓練、消火訓練、救助訓練などの防災訓練が一斉に行われます。また、防災に関する展示や講演会、防災グッズの点検なども推奨されています。
多様な声が電波に乗った日、民間ラジオ放送開始: 民放ラジオ放送開始記念日
1951年(昭和26年)のこの日、名古屋の中部日本放送(現:CBCラジオ)と大阪の新日本放送(現:毎日放送)が日本初の民放ラジオとして放送を開始した。
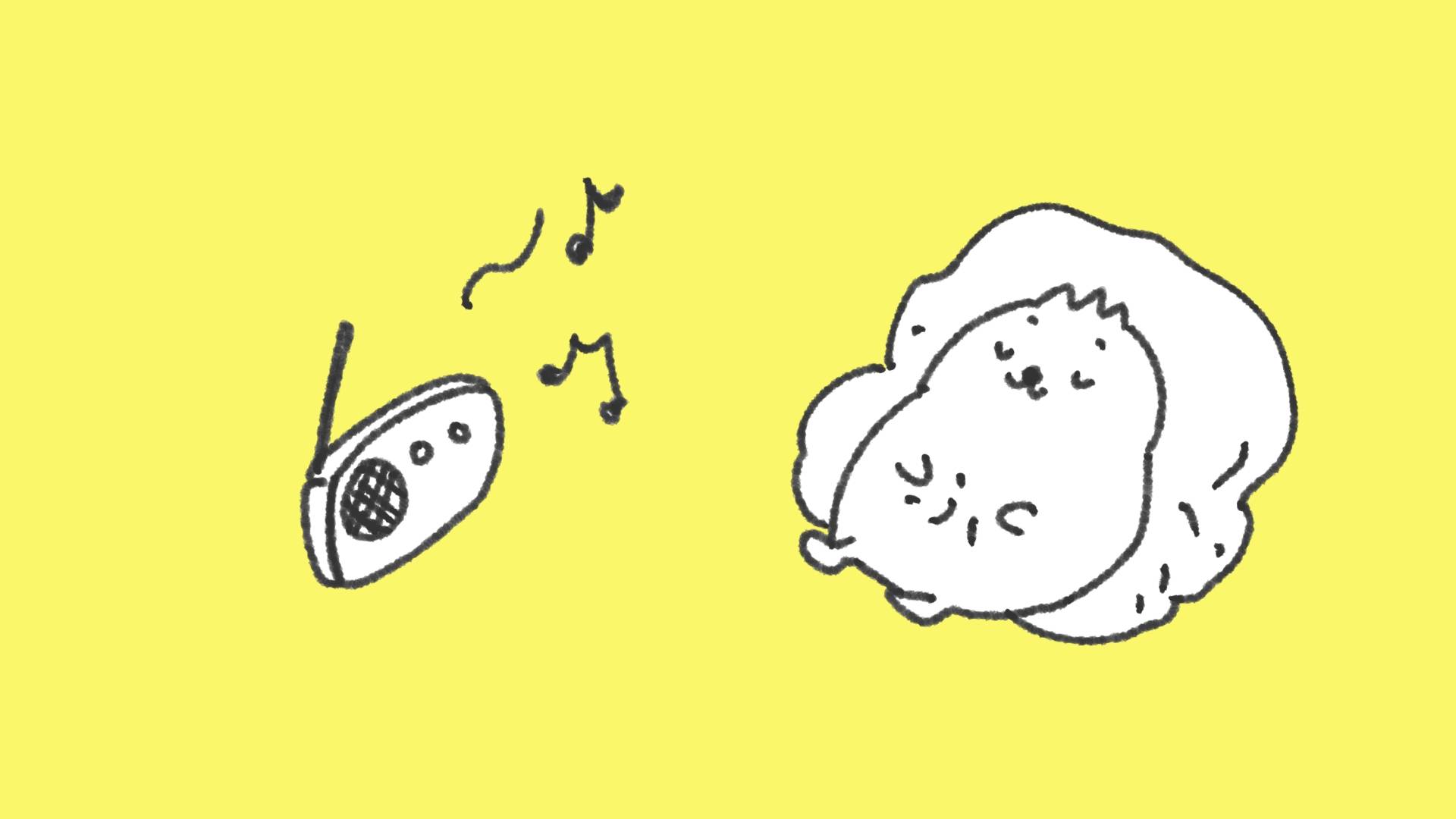
Q: なぜこの日が「民放ラジオ放送開始記念日」なのですか?
A: 1951年(昭和26年)9月1日に、名古屋の中部日本放送(CBC)と大阪の新日本放送(NJB、現在の毎日放送ラジオ・MBSラジオ)が、日本で初めてとなる民間放送によるラジオ放送を開始した歴史的な日であるためです。
Q: 民放ラジオの開始はどのような意味がありましたか?
A: それまで放送はNHK(公共放送)だけでしたが、民間企業が広告収入を財源としてラジオ放送を行うことが可能になりました。これにより、多様な番組(音楽、ドラマ、バラエティ、スポーツ中継など)が登場し、ラジオがより身近な娯楽・情報源として普及するきっかけとなりました。
Q: ラジオ放送の役割は何でしょうか?
A: 音楽やトークによる娯楽を提供するだけでなく、ニュースや交通情報、地域情報などを伝える重要なメディアです。特に、災害時には停電に強く、携帯しやすいラジオが、ライフラインに関する重要な情報源として大きな役割を果たします。
栄養満点!語呂合わせで楽しむフルーツ記念日: キウイの日
ゼスプリ インターナショナルジャパン株式会社が制定。日付は「キュー(9)イ(1)」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ9月1日が「キウイの日」なのですか?
A: 「キュー(9)イ(1)」と読む語呂合わせから、キウイフルーツの輸入・販売を手がけるゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社が制定しました。
Q: キウイフルーツにはどのような栄養がありますか?
A: ビタミンCが非常に豊富で、他にも食物繊維、カリウム、ビタミンE、葉酸、アクチニジン(タンパク質分解酵素)など、多くの栄養素を含んでいます。美肌効果、便通改善、生活習慣病予防などが期待される健康果実として人気です。
Q: キウイにはどんな種類がありますか?
A: 日本でよく見かけるのは、果肉が緑色の「グリーンキウイ」(ヘイワード種など)と、黄色い「ゴールドキウイ」です。グリーンは甘酸っぱく爽やかな味、ゴールドは甘みが強くトロピカルな風味が特徴です。最近では、果肉が赤い品種も登場しています。
南米の飲むサラダ、収穫祭にちなむ健康茶の日: マテ茶の日
日本マテ茶協会が制定。日付はマテ茶の生産国であるアルゼンチンで、その年の収穫祭が9月1日に行われることから。
Q: なぜアルゼンチンの収穫祭が「マテ茶の日」の由来なのですか?
A: マテ茶は主にアルゼンチン、ブラジル、パラグアイなど南米で生産・飲用されている伝統的なお茶です。その主要生産国であるアルゼンチンで、マテ茶の収穫を祝うお祭りが9月1日に行われることから、日本マテ茶協会がこの日を記念日として制定しました。
Q: マテ茶とはどのようなお茶ですか?
A: 南米原産のイェルバ・マテというモチノキ科の木の葉や小枝を乾燥させ、焙煎・粉砕したものです。ビタミンやミネラルが豊富で、野菜の栽培が難しい南米の一部の地域では「飲むサラダ」とも呼ばれ、健康維持に欠かせない飲み物とされています。独特の香ばしさと若干の苦味があります。
Q: 伝統的なマテ茶の飲み方は?
A: 「マテ壺(マテ)」と呼ばれるひょうたんや木製の容器に茶葉を入れ、お湯を注ぎ、「ボンビージャ」と呼ばれる金属製のストロー(先端に茶漉しがついている)で濾しながら飲みます。仲間と一つのマテ壺を回し飲みする習慣もあり、コミュニケーションツールとしての役割も持っています。
8月32日は9月1日!?ゲーム情報誌の語呂合わせ記念日: ファミ通の日
株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:カドカワ株式会社)が発行しているゲーム情報誌の『週刊ファミ通』が制定。日付は「ファ(8)ミ(3)つう(2)」(ファミ通)と読む語呂合わせから8月32日となり、これを8月31日の翌日9月1日と見立てたもの。1986年(昭和61年)6月6日、テレビゲーム専門誌『ファミコン通信』として創刊。
Q: なぜ「8月32日」を9月1日と見立てたのですか?
A: 雑誌名「ファミ通」を「ファ(8)ミ(3)つう(2)」と読む語呂合わせで「832」とし、これを日付に見立てて「8月32日」と考えました。実際には8月32日は存在しないため、8月31日の次の日、すなわち9月1日を記念日としたユニークな発想です。
Q: 『週刊ファミ通』はどのような雑誌ですか?
A: 最新のゲーム情報(新作ソフトの紹介、攻略記事、業界ニュースなど)を幅広く扱う週刊のゲーム専門誌です。特に、複数の編集者がゲームを評価する「クロスレビュー」は、ゲーム購入の参考として長年多くのゲーマーに注目されています。
Q: この記念日はどのように制定されましたか?
A: 『ファミコン通信』として創刊されてから長年にわたりゲーム業界を支えてきた同誌が、ファンへの感謝と、ゲーム文化のさらなる発展を願って制定したものです。この日には、記念イベントや読者プレゼント企画などが実施されることがあります。
言葉遊びでコミュニケーション円滑化!だじゃれの可能性を追求する日: だじゃれの日
一般社団法人・日本だじゃれ活用協会が制定。「ク(9)リエイティブかつイ(1)ンパクト」があるだじゃれは、人と人とのコミュニケーションをより豊かなものにしてくれる「無形文化遊具」であり、だじゃれが秘める無限の「吸(9)引(1)力」を活かし、生活に彩りと潤いをもたらすことで世の中に「救(9)い(1)」を届けたいとの願いが込められている。
Q: なぜ9月1日が「だじゃれの日」なのですか?
A: 一般社団法人日本だじゃれ活用協会が、「ク(9)リエイティブ・イ(1)ンパクト」「吸(9)引(1)力」「救(9)い(1)」という、だじゃれの持つ力や可能性を表す3つの言葉と日付「9月1日」を結びつけて制定しました。
Q: だじゃれにはどのような効用があると考えられていますか?
A: 単なる言葉遊びとしてだけでなく、場の雰囲気を和ませたり、会話のきっかけを作ったりするコミュニケーションツールとしての効果があります。また、言葉の音や意味に意識を向けることで、発想力や言語感覚を刺激する脳トレのような側面もあるとされています。
Q: 日本だじゃれ活用協会はどのような活動をしていますか?
A: だじゃれを使ったコミュニケーション研修、だじゃれに関するイベントの企画・開催、だじゃれを活用した地域活性化の提案などを通じて、だじゃれの社会的価値を高め、その活用を広めるための活動を行っています。
日本初のギリシャヨーグルト発売記念日: ギリシャヨーグルトの日
森永乳業株式会社が制定。日付は同社から日本初のギリシャヨーグルト「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」が発売された2011年(平成23年)9月1日から。
Q: なぜこの日が「ギリシャヨーグルトの日」なのですか?
A: 2011年9月1日に、森永乳業株式会社が日本で初めてとなるギリシャヨーグルト製品「濃密ギリシャヨーグルト パルテノ」を発売したことを記念して制定されました。
Q: ギリシャヨーグルトは普通のヨーグルトとどう違うのですか?
A: ギリシャヨーグルトは、ヨーグルトを発酵させた後、「水切り」という工程を経て作られます。これにより、水分(ホエイ)が取り除かれ、通常のヨーグルトに比べて水分が少なく、クリームチーズのように濃厚でクリーミーな食感になるのが特徴です。また、タンパク質が豊富に含まれています。
Q: 「パルテノ」はどのような商品ですか?
A: 森永乳業が独自の「3倍濃縮製法」を用いて開発した、日本におけるギリシャヨーグルトのパイオニア的ブランドです。濃厚な食感と美味しさで人気を集め、その後のギリシャヨーグルト市場の拡大に貢献しました。プレーンタイプのほか、フルーツソース付きなど様々な種類があります。
二百十日:立春から210日目、台風シーズン到来を告げる雑節
二百十日(にひゃくとおか)は、日本の暦における雑節(ざっせつ)の一つで、立春(2月4日頃)から数えて210日目にあたる日です。通常は9月1日頃になります。
Q: なぜ二百十日が特別な日とされているのですか?
A: 統計的に見て、この時期は台風が日本に襲来することが多く、また稲が開花し実る大事な時期(出穂期)と重なるため、古くから農家にとって警戒すべき「厄日」とされてきました。強風による稲への被害を特に恐れたためです。
Q: この時期に何か特別な行事はありますか?
A: 各地で風の被害を鎮め、豊作を祈るための「風祭り」や、風神を祀る行事が行われてきました。富山県の「おわら風の盆」などが有名ですが、これは二百十日の風を鎮めるための行事が起源の一つとされています。
Q: 現代において二百十日はどのような意味を持ちますか?
A: 農業技術や気象予測が進歩した現代では、かつてほどの強い警戒心は薄れていますが、依然として台風シーズン本格化の目安として意識されています。自然災害への備えを再確認するきっかけとなる日とも言えます。