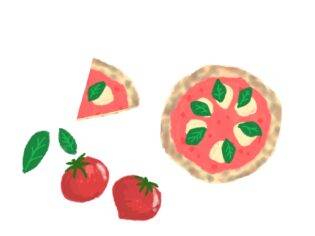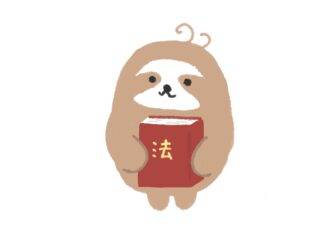9月9日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
陽数が重なる縁起の良い日、菊を愛でる五節句: 重陽の節句・菊の節句
五節句の一つ。陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なることから「重陽(ちょうよう)の節句」と呼ばれる。また、旧暦では菊が咲く季節であることから「菊の節句」とも呼ばれる。
Q: なぜ「重陽の節句」と呼ばれるのですか?
A: 古代中国の陰陽思想では、奇数は縁起の良い「陽数」とされ、その中でも最大の陽数である「9」が重なる9月9日を、非常にめでたい日と考え「重陽」と呼びました。これが日本に伝わり、五節句の一つとなりました。
Q: なぜ「菊の節句」とも呼ばれるのですか?
A: 旧暦の9月9日頃は、ちょうど菊の花が美しく咲く季節にあたります。菊は古来より薬草としても用いられ、邪気を払い長寿をもたらすと信じられていたため、この日に菊の花を観賞したり、菊の花びらを浮かべた「菊酒」を飲んだりして、不老長寿や無病息災を願う風習が生まれました。
Q: 重陽の節句には他にどのような風習がありますか?
A: 菊の露で湿らせた綿で体を拭う「菊の被せ綿(きせわた)」という風習や、秋の味覚である栗を使った「栗ご飯」を食べる習慣などがあります。また、各地で菊の品評会や展示会なども催されます。
命を救う行動を考える、語呂合わせで制定された大切な日: 救急の日
厚生省(現:厚生労働省)と消防庁が1982年(昭和57年)に制定。日付は「きゅう(9)きゅう(9)」(救急)と読む語呂合わせから。
Q: なぜ9月9日が「救急の日」なのですか?
A: 「きゅう(9)きゅう(9)」と読む語呂合わせから、厚生省(現在の厚生労働省)と消防庁によって1982年に制定されました。
Q: この日の目的は何ですか?
A: 救急業務や救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識向上を図ることを目的としています。また、応急手当(心肺蘇生法やAEDの使用法など)の知識と技術の普及も重要な目的の一つです。
Q: 「救急医療週間」とは何ですか?
A: 「救急の日」を含む一週間(日曜日から土曜日まで)は「救急医療週間」とされており、全国各地で応急手当の講習会や救急に関するイベント、講演会などが集中的に実施されます。
運命の救急? 複雑な由来を持つ占術の日: 世界占いの日
一般社団法人・日本占術協会が1999年(平成11年)に制定。日付は、下記の内容に当てはまることから。
・この日が「重陽の節句」であること。
・ノストラダムスの終末の予言の日は1999年9月9日とされていたこと、制定した1999年9月9日の数字を全部合計すると46で、46の2つの数を足すと10になり完成を物語る数であること。
・明治4年9月9日に時間の数え方を西洋式に改めたこと。
・この日が「救急の日」で占いは運命の救急であること。
Q: なぜこの日が「世界占いの日」なのですか? その由来が複雑なようですが。
A: 日本占術協会が制定したこの記念日は、複数の理由が複合的に絡み合っています。まず、この日が縁起の良い「重陽の節句」であること。次に、制定年(1999年)に話題となったノストラダムスの予言の日付と重なることや、数字の神秘的な解釈。さらに、日本の時刻制度変更の日、そして「救急の日」にちなんで「占いは運命の救急」という解釈を加えたことなどが挙げられます。
Q: 制定の目的は何でしょうか?
A: 占いや占術に対する正しい理解を広め、その文化的な価値や人々の心の支えとしての役割を社会にアピールし、占術家の社会的地位向上を目指すことなどが目的と考えられます。
Q: 占いとの上手な付き合い方はありますか?
A: 占いは、自己理解を深めたり、物事を決断する際の参考意見として活用したり、悩み相談のきっかけになったりするなど、ポジティブな側面があります。しかし、結果に一喜一憂しすぎたり、占いに依存してしまったりしないよう、客観的な視点を持って楽しむことが大切です。
ゼンマイ仕掛けでウィリー走行!ミニカーの定番記念日: チョロQの日
株式会社タカラ(現:株式会社タカラトミー)が制定。日付は「チョロQ」の「Q(キュー)」を「9」にかけて9月9日に。

Q: なぜ9月9日が「チョロQの日」なのですか?
A: 「チョロQ」の「Q」が数字の「9」に似ている(または「キュー」という読み)ことから、製造・販売元の株式会社タカラ(現在のタカラトミー)が9月9日を記念日として制定しました。
Q: チョロQはどのようなおもちゃですか?
A: 1980年に発売された、プルバックゼンマイ(後ろに引いて手を離すと走り出す)で動くミニカーです。実車をデフォルメした可愛らしいデザインと、後ろのコインホルダーにコインを挟むことでウィリー走行ができるギミックが特徴で、子どもから大人まで幅広い層に人気があります。
Q: チョロQはなぜ長く愛されているのでしょうか?
A: 手軽に遊べる楽しさ、実在する車から架空の車まで豊富な車種のラインナップによるコレクション性の高さ、そして改造パーツなどによるカスタマイズの自由度などが、世代を超えて支持される理由と考えられます。
フライドチキンの父、その誕生日を祝う日: カーネルズ・デー
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社が制定。日付はケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースの誕生日の1890年(明治23年)9月9日にちなむ。
Q: なぜこの日が「カーネルズ・デー」なのですか?
A: ケンタッキーフライドチキン(KFC)の創業者であり、お馴染みの白いスーツ姿のアイコンでもあるカーネル・ハーランド・サンダースの誕生日(1890年9月9日)を記念して、日本KFCが制定しました。
Q: カーネル・サンダースはどのようにしてKFCを成功させたのですか?
A: 彼は60代になってから、自ら開発した11種類のハーブ&スパイスを使ったフライドチキンのレシピと圧力釜による調理法を持って、アメリカ各地のレストランにその作り方を教え、売上の一部を受け取るフランチャイズビジネスを始めました。彼の情熱と粘り強い努力、そして独自のレシピがKFCを世界的なチェーンへと成長させました。
Q: カーネル・サンダースの人柄について教えてください。
A: 多くの苦労と失敗を経験しながらも、決して諦めずに夢を追い続けた人物として知られています。また、KFCの「顔」として、白いスーツと蝶ネクタイ姿で店舗を訪れ、顧客との交流を大切にしたことでも有名です。「カーネル」は名前ではなく、ケンタッキー州に貢献した人に贈られる名誉称号です。
くるくる楽しい!家庭で楽しむ寿司スタイルの記念日: 手巻き寿司の日
株式会社スギヨが制定。日付は「く(9)るく(9)る」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ9月9日が「手巻き寿司の日」なのですか?
A: 海苔でご飯と具材を「くる(9)くる(9)」と巻いて食べる様子から、この語呂合わせで株式会社スギヨが制定しました。
Q: 制定した株式会社スギヨはどのような会社ですか?
A: 石川県に本社を置く食品メーカーで、世界で初めて「カニカマ(カニ風味かまぼこ)」を開発したことで有名です。手巻き寿司の具材としても人気のカニカマとの関連も深いと言えます。
Q: 手巻き寿司の魅力は何ですか?
A: 自分の好きな具材を自由に組み合わせて、好みの太さや形で巻ける自由度の高さが魅力です。作る過程も楽しく、家族や友人が集まるパーティーメニューとしても定番です。酢飯と海苔、様々な具材を用意するだけで手軽に楽しめるのも人気の理由です。
映画館の定番スナック、鏡文字で見立てた記念日: ポップコーンの日
ジャパンフリトレー株式会社が制定。日付は、英字のポップコーン(POPCORN)の「POP」を左右を反転させた鏡文字にすると「909」に見えることから9月9日に。

Q: なぜ「POP」の鏡文字が「909」に見えるのですか?
A: アルファベットの「P」を左右反転させると数字の「9」に、真ん中の「O」はそのまま「0」に見立てるという、非常にユニークな発想です。これにより「909」とし、9月9日を記念日として、スナック菓子メーカーのジャパンフリトレー株式会社が制定しました。
Q: ポップコーンはいつ頃から食べられているのですか?
A: ポップコーンの原料となる爆裂種のトウモロコシは、数千年前の古代アメリカ大陸(現在のメキシコやペルーなど)で既に栽培され、食用にされていたと考えられています。遺跡からもポップコーンの痕跡が見つかっています。
Q: 映画館でポップコーンが定番になったのはなぜですか?
A: 1930年代のアメリカで、映画館が安価で手軽に作れるポップコーンを販売し始めたのがきっかけと言われています。映画を見ながら気軽に食べられるスナックとして人気を集め、世界中の映画館に広まりました。
生きた化石!形と活動時期にちなむ両生類の記念日: オオサンショウウオの日
京都水族館が制定。日付は、オオサンショウウオが繁殖期に入り行動が活発になる9月上旬であることと、その姿が数字の9に似ていることから9月9日としたもの。
Q: なぜ9月9日が「オオサンショウウオの日」なのですか?
A: オオサンショウウオの活動が活発になる繁殖期が9月頃であることと、体を丸めた姿や長い体が数字の「9」に見える(または重なる)ことから、京都水族館が9月9日を記念日として制定しました。
Q: オオサンショウウオはどのような生き物ですか?
A: 世界最大級の両生類で、日本の固有種です。国の特別天然記念物に指定されています。「生きた化石」とも呼ばれ、数千万年前から姿をほとんど変えずに生き続けていると考えられています。主に夜行性で、清流の上流域に生息しています。
Q: なぜ京都水族館がこの日を制定したのですか?
A: 京都水族館は、京都の鴨川水系に生息するオオサンショウウオの展示や研究、保全活動に力を入れています。この記念日を通じて、オオサンショウウオの生態や魅力、そして彼らが直面する環境問題(生息地の破壊、外来種との交雑など)について、より多くの人に関心を持ってもらうことを目的としています。