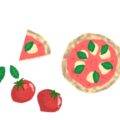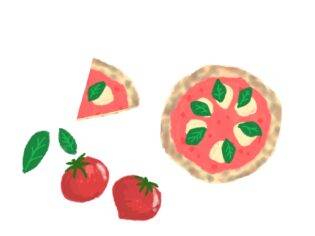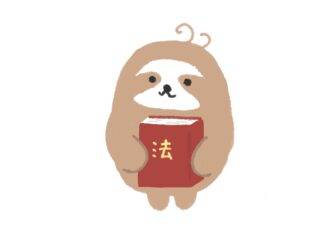9月18日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
形が由来!シャキシャキ食感のスプラウト記念日: かいわれ大根の日
日本かいわれ協会(現:日本スプラウト協会)が1986年(昭和61年)9月の会合で制定。日付は9月はこの日を制定した会合が行われた月で、18日は「8」の下に「1」で「かいわれ大根」の形(竹トンボ型)になることから。

Q: なぜ「8」の下に「1」でかいわれ大根の形になるのですか?
A: 数字の「8」をかいわれ大根の双葉(二葉)に、「1」をその下のまっすぐ伸びた茎に見立てた、ユニークな形状の語呂合わせ(見立て)です。9月は制定のための会合が開かれた月であることから、この組み合わせで9月18日が選ばれました。
Q: かいわれ大根はどのような野菜ですか?
A: 大根の種子を発芽させたスプラウト(新芽野菜)です。双葉が開き、茎が伸びた状態のもので、シャキシャキとした食感と、ピリッとした特有の辛味が特徴です。サラダのトッピング、冷奴の薬味、お刺身のつま、お味噌汁の具など、様々な料理に彩りとアクセントを加えます。
Q: かいわれ大根にはどのような栄養がありますか?
A: 発芽したばかりの新芽であるため、ビタミン類(特にビタミンC、ビタミンK、葉酸)やミネラルが比較的多く含まれています。また、辛味成分であるイソチオシアネートには、抗酸化作用や食欲増進効果などが期待されています。
沖縄の言葉と思いを未来へ繋ぐ日: しまくとぅばの日
沖縄県が「しまくとぅばの日に関する条例」により2006年(平成18年)に制定。日付は「く(9)とぅ(10)ば(8)」と読む語呂合せから。沖縄県の言葉「しまくとぅば(島言葉)」を奨励する日。
Q: なぜ9月18日が「しまくとぅばの日」なのですか?
A: 沖縄の方言で言葉を意味する「くとぅば」を、日付の「9(く)・十(とぅ)・8(ば)」と読む語呂合わせにちなんで、沖縄県が条例で制定しました。(※注: 「とぅ」は数字の「十」の沖縄方言読みに由来し、18日の「8」と合わせて「とぅば」と読んでいます。)
Q: 「しまくとぅば」とは具体的にどのような言葉ですか?
A: 沖縄県内で歴史的に使われてきた伝統的な地域言語(方言)の総称です。「島(しま)」は各地域・集落を、「言葉(くとぅば)」はその言葉を意味します。地域によって言葉は大きく異なり、沖縄本島中南部、本島北部(国頭語)、奄美、宮古、八重山など、それぞれに独自の言語・方言が存在します。
Q: なぜ「しまくとぅば」を奨励する必要があるのですか?
A: しまくとぅばは、沖縄の豊かな歴史、文化、芸能、生活様式、そして人々のアイデンティティと深く結びついた、かけがえのない文化遺産です。しかし、標準語教育の普及や社会の変化、世代間の継承の困難さなどから、日常的に使う人が減少し、消滅の危機に瀕している言葉も少なくありません。この記念日を通じて、しまくとぅばへの関心を高め、その価値を再認識し、保存・継承していくことの重要性を県内外に呼びかけています。
近代化への抵抗と悲劇、西南戦争終結の日: 西南戦争終結記念日
1877年(明治10年)9月24日に西郷隆盛が自刃し、西南戦争が終結しましたが、それ以前のこの日(9月18日)頃には、西郷軍は城山の洞窟に追い詰められ、組織的な戦闘能力をほぼ失っていました。そのため、この辺りを実質的な戦闘終結と捉える見方もあります(※公的な記念日ではありません)。
Q: 西南戦争とはどのような戦いでしたか?
A: 1877年(明治10年)に、西郷隆盛をリーダーとする鹿児島(旧薩摩藩)の士族たちが、明治新政府に対して起こした、日本国内で最後の、そして最大規模の内戦です。廃藩置県や徴兵令、秩禄処分(武士の給与廃止)など、明治政府の急進的な近代化政策に対する士族層の不満が背景にありました。
Q: なぜ西郷隆盛は新政府に反旗を翻したのですか?
A: 明治維新の功労者の一人であった西郷ですが、征韓論(朝鮮への武力行使を主張)を巡る対立で政府を去り、鹿児島で私学校を設立して士族の子弟教育にあたっていました。しかし、不平士族たちの暴発を抑えきれず、彼らに担がれる形で挙兵に至ったとされています。彼の真意については様々な解釈があります。
Q: 西南戦争の結果、日本社会はどう変わりましたか?
A: 政府軍の勝利により、士族による武力反乱の時代は完全に終焉を迎え、明治政府による中央集権体制と近代化路線が確立されました。一方で、多くの犠牲者を出した悲劇的な内戦として記憶されています。
アジア大陸への侵攻の始まり: 満州事変勃発の日(柳条湖事件)
1931年(昭和6年)9月18日夜、満州(現在の中国東北部)の奉天(現在の瀋陽)近郊の柳条湖(りゅうじょうこ)で、日本の南満州鉄道の線路が爆破される事件が発生しました。日本の関東軍はこれを中国側の仕業として、直ちに軍事行動を開始し、満州各地を占領していきました。これが満州事変の始まりです。この最初の爆破事件は「柳条湖事件」と呼ばれます。
Q: 柳条湖事件は本当に中国側の仕業だったのですか?
A: いいえ、現在では関東軍の一部参謀らが、満州での権益拡大と軍事行動開始の口実を作るために自ら計画・実行した謀略(自作自演)であったことが明らかになっています。
Q: 満州事変はその後どうなりましたか?
A: 関東軍は満州全土を占領し、翌1932年には日本の傀儡国家である「満州国」を建国しました。国際連盟はこの日本の行動を認めず、日本は国際社会から孤立を深め、1933年に国際連盟を脱退しました。満州事変は、その後の日中戦争、太平洋戦争へとつながる、日本の大陸侵攻の重要な発端となりました。
Q: この出来事を記憶する意味は何ですか?
A: 軍部の一部による暴走が、結果的に日本を破滅的な戦争へと導いた歴史の教訓として、また、戦争が引き起こす悲劇や、情報操作・謀略の危険性を考える上で、忘れてはならない重要な出来事です。